「ハンガリー公使大久保利隆が見た三国同盟」(高川邦子 著)読了 [読書]
大久保利隆は、駐ハンガリー全権公使として、欧州の現場からドイツ不利との戦況を発信し続け、大島浩駐ドイツ大使による対ソ参戦の提言を断固阻止して、大島や東条英機の不興を買って左遷された気骨の外交官。決死の思いで帰国を果たし、「ドイツは持って、あと1年から1年半」とドイツ必敗を政府中枢に説いて回った。その予言は的中した。
先に読んだ、「ヒトラーに傾倒した男――A級戦犯・大島浩の告白」は、なんとも物足りない本だったが、この大久保公使の存在を教えてくれたことは有益だった。大島がほんとうは何をやっていたのか、戦後の独白といっても何も核心には触れていないことがわかる。軍人からの成り上がり大使が外交を壟断し外交軍事情報を歪めていたことが、こちらでは活写されている。
著者は、大久保の孫にあたり、確かに見内の著述だが、NHKの登録翻訳者として活動されていて、きっちりと取材していて実証性もしっかりとしている。敗戦時に日本の外交文書の原本の多くは失われているが、当時、日本の暗号はすべて解読されていて英国などにこうした傍受された日本側の通信文書が英文で残されていた。それを著者は丹念に読み解いて、祖父らの回顧禄や関係者の証言を裏付け肉付けしていく。
興味深いのは、枢軸国ハンガリーの政治外交の現実を生々しく証言していること。ハンガリーの政治家たちが決してナチやヒトラーに追随一辺倒だったわけではなく、和平を希求し、英米と密かに通ずるなど、国民が戦争に巻き込まれることを必死に回避しようとしていた経緯が語られる。ヒトラーに翻弄され、己の無力に絶望した首相が自死を選ぶなど、それは文字通り必死の行動だった。その時、日本は「バスに乗り遅れるな」と対英米開戦という破滅の道をまっしぐらに突き進んでいたことになる。
大久保が、そういう現状を日本に伝えようと病を口実に帰国したのは、決して、命惜しさの逃避離脱ではなかった。その覚悟と行程のなまなましい現実を知ると、これまた必死の行動であることがわかる。戦中のユーラシア大陸横断の旅は、現代の日本人には想像もつかない苦難の連続だった。事実、ソ連の通行ビザが下りずにイスタンブールなどで足止めされた日本人外交官の何人かが病死したり夫婦で自殺したりしているという。
帰国を果たした大久保は、政府要人に面会し欧州の実状を説き、昭和天皇に拝謁進講しても同じことを説いたが、耳を傾ける人物はいなかった。いよいよ敗戦濃厚となったとき、東郷外務大臣に「ソ連の宣戦は必至」と進言したが、政府はそれをかえりみることなく講和の仲介をソ連に託している。
とはいえ、大久保のご進講があってこそ、昭和天皇のいわゆる「聖断」があったともいえる。歴史に「イフ」は無いと言われるが、もし、大久保が対ソ参戦を阻止していなかったら、日本は分断国家の末路を迎えていたかもしれない。
「情報」というものがいかに大事なのか。そういう視点であの戦争を見る上で貴重な証言であり、多くの人々に読んでほしいと思う。
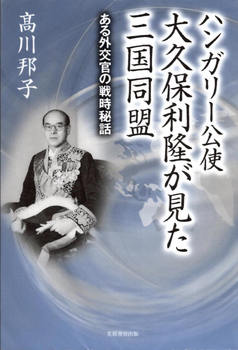
ハンガリー公使大久保利隆が見た三国同盟
ある外交官の戦時秘話
高川 邦子 (著)
芙蓉書房出版
先に読んだ、「ヒトラーに傾倒した男――A級戦犯・大島浩の告白」は、なんとも物足りない本だったが、この大久保公使の存在を教えてくれたことは有益だった。大島がほんとうは何をやっていたのか、戦後の独白といっても何も核心には触れていないことがわかる。軍人からの成り上がり大使が外交を壟断し外交軍事情報を歪めていたことが、こちらでは活写されている。
著者は、大久保の孫にあたり、確かに見内の著述だが、NHKの登録翻訳者として活動されていて、きっちりと取材していて実証性もしっかりとしている。敗戦時に日本の外交文書の原本の多くは失われているが、当時、日本の暗号はすべて解読されていて英国などにこうした傍受された日本側の通信文書が英文で残されていた。それを著者は丹念に読み解いて、祖父らの回顧禄や関係者の証言を裏付け肉付けしていく。
興味深いのは、枢軸国ハンガリーの政治外交の現実を生々しく証言していること。ハンガリーの政治家たちが決してナチやヒトラーに追随一辺倒だったわけではなく、和平を希求し、英米と密かに通ずるなど、国民が戦争に巻き込まれることを必死に回避しようとしていた経緯が語られる。ヒトラーに翻弄され、己の無力に絶望した首相が自死を選ぶなど、それは文字通り必死の行動だった。その時、日本は「バスに乗り遅れるな」と対英米開戦という破滅の道をまっしぐらに突き進んでいたことになる。
大久保が、そういう現状を日本に伝えようと病を口実に帰国したのは、決して、命惜しさの逃避離脱ではなかった。その覚悟と行程のなまなましい現実を知ると、これまた必死の行動であることがわかる。戦中のユーラシア大陸横断の旅は、現代の日本人には想像もつかない苦難の連続だった。事実、ソ連の通行ビザが下りずにイスタンブールなどで足止めされた日本人外交官の何人かが病死したり夫婦で自殺したりしているという。
帰国を果たした大久保は、政府要人に面会し欧州の実状を説き、昭和天皇に拝謁進講しても同じことを説いたが、耳を傾ける人物はいなかった。いよいよ敗戦濃厚となったとき、東郷外務大臣に「ソ連の宣戦は必至」と進言したが、政府はそれをかえりみることなく講和の仲介をソ連に託している。
とはいえ、大久保のご進講があってこそ、昭和天皇のいわゆる「聖断」があったともいえる。歴史に「イフ」は無いと言われるが、もし、大久保が対ソ参戦を阻止していなかったら、日本は分断国家の末路を迎えていたかもしれない。
「情報」というものがいかに大事なのか。そういう視点であの戦争を見る上で貴重な証言であり、多くの人々に読んでほしいと思う。
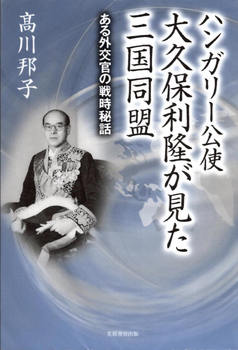
ハンガリー公使大久保利隆が見た三国同盟
ある外交官の戦時秘話
高川 邦子 (著)
芙蓉書房出版
タグ:三国同盟
ル・マルトー・サン・メートル (読響アンサンブル・シリーズ) [コンサート]
鈴木優人さんといえば、チェンバロなどの鍵盤楽器奏者にしてバッハ・コレギウム・ジャパンの首席指揮者――古楽演奏家というイメージが先行しますが、このアンサンブルシリーズでは、20年にヴィヴァルディとケージを対峙させるなどの新しいアプローチで話題を呼びました。現代音楽についても素晴らしい理解とパフォーマンスを示す若く先鋭な感受性を持つ音楽家。むしろクリエイティブな現代音楽指揮者として目の離せない存在なのかもしれません。

このシリーズ前回でも、シェーンベルクの「月に憑かれたピエロ(ピエロ・リュネール)」を披露して鮮烈な印象を与えてくれました。その鈴木さんによれば、「ピエロ・リュネールまで来たら、もう必然的にここまで来ざるを得ない」というのが、今回の「ル・マルトー・サン・メートル」というわけです。
言うまでもありません。《作曲家》ピエール・ブーレーズの代表作。
実際、ブーレーズは、「ピエロ・リュネール」に強い影響を受けたと言っているそうです。編成も、アルトのソロと小さなアンサンブルという編成も共通です。プログラムは、その編成に沿って構築されているようです。出演は、指揮者の鈴木さん、アルトの湯川亜也子さんを含めて総勢12名。
最初は、ブーレーズの「デリーヴ1」。「ル・マルトー…」よりずっと後の80年代の作品。タイトルは「漂流/変動」を意味するフランス語だそうですが、確かに繰り返しが多くて雰囲気もずっと変わらない。意外に穏やかだけれど楽器間の相互作用というの緊張感のようなものに欠ける。
二曲目は、バッハがゴルトベルク変奏曲のテーマのバス進行、最初の8音をカノンにした曲。初版譜にバッハ自身が補遺として14のカノンを書き入れていたそうです。棋譜の解読が必要で、解決譜は鈴木さんが先達のものを参考にして、学生時代に編曲したものを手直ししたもの。音列技法など前衛と呼ばれた現代音楽の厳格の論理性や遊び心を示唆する意図があるのでしょうが、聴いた印象はちょっとした「おもちゃの交響曲」的な朴訥な音色と響きで、どこか微笑ましいものでした。
三曲目は、ドビュッシー。ここでアルト歌手の湯川亜也子さんが登場します。
マラルメの詩につけた曲は、どちらかと言えばラヴェルの方が知られていますし、編成も木管と弦楽が入っていたものなのですが、あえてドビュッシーのものが歌われました。やはり、無調とは言えませんが新規な和声法とかオリエンタリズムという点でドビュッシーのほうが現代音楽への影響が大きいことは間違いありません。けっこう難解な音楽で詩が聞き取れないのでひときわ理解が難しいと感じました。そろそろ声楽曲にはテキスト訳をプロジェクタでポップアップさせることを考えてほしいです。
前半最後は、クセナキス。
「プレクト」というのは「組みひも」の意だそうですが、ただひたすら変則的なリズムと点描的な熱力学的に雑然とした音の明滅がひたすら続き、タイトルからの連想とか作曲の意図がほとんど見えてこないという印象でした。とにかくアンサンブル技術としては壮絶なほどに複雑かつ難技巧で、それを見ているのがあっけにとられるほど面白く、その見事さに舌を巻くしかありません。その一方で、音楽的にはとてつもなく平板で退屈な時間でした。
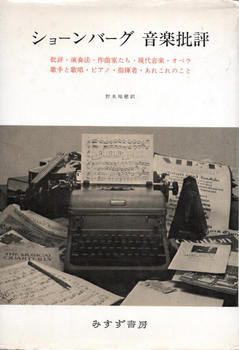
こうした音楽は、現代音楽のなかでも、かつて、特に「前衛」と呼ばれていました。
ブーレーズは、1971年にバーンスタインの辞任後の空白を埋める形でニューヨークフィルハーモニックの常任指揮者に就任しました。当時の、ショーンバーグの音楽批評にブーレーズらが主導した現代音楽運動を痛烈に皮肉ったものがあります。ショーンバーグは、その時代のニューヨークの聴衆の保守性を代弁するような批評家でした。ブーレーズが、取り入れた進取に富んだプログラムが物議をかもし、彼は転じて小さなホールでの現代音楽紹介に熱心に取り組みます。「ブーレーズの辻説法」と揶揄する一文では、皮肉たっぷりですに次のように記しています。
「ブーレーズが意見を述べている間、皆は感服して聴き入っていた。彼の言葉の一つ一つに気持ちよくついていった。そうだとも。作曲家と聴衆の間には確かに落差がある。音楽を健全な状態で将来に残そうとするならば、その亀裂をどうしても埋めなければならない。…ところが、音楽を聴くとどうか。…響きは退屈で、独創性は感じられなかった。」
さて…
休憩を経て、いよいよメインの「ル・マルトー・サン・メートル」。
これはとても素晴らしい体験でした。なるほどブーレーズというのはこういう風に知的で精緻な細密画のような美意識の音楽家だったんだと感得します。昔、FM放送か何かで聴いた記憶では、もっとごちゃごちゃしていて主張の強い騒がしい音楽というイメージがあったのですが、その頃の私には前衛音楽に対するバイアスがあったのだと思います。むしろ、静謐なたたずまいさえ感じます。音高・音価・音勢・強弱を量子化して組み合わせていく手法ですが、写実性や情感の起伏もあって美しい。打楽器によるガムランの響きとか、ギターによる琵琶のような撥弦楽器とか、東洋的なエキゾチシズムにも挑戦している。確かにシェーンベルクの点描法的手法の美学的な結実とも感じます。
こういう音楽を実際に目の当たりにする機会がこうやって訪れたのだと感慨深いものがあります。
最後に、鈴木優人さんが、先日亡くなられた一柳慧さんを偲んでのアンコール。こればもうまさに静謐さの極みのような音楽で仏教的な死生観さえ感じさせる感動的な演奏でした。
戦後の現代音楽の再演というのは、これからどんどん聴いていきたいと思いました。確かに、あの当時の実験音楽というのは、能書きばかりが先行していて聴衆と作曲者との間には深い溝が確かに存在したのだと思いますが、それが取り払われて通じ合える時代になってきたのだと思います。
素晴らしい試みでした。

読響アンサンブル・シリーズ
第35回 《鈴木優人プロデュース/ル・マルトー・サン・メートル》
2022年10月20日(木) 19:30~
トッパンホール
(P列 12番)
指揮、ピアノ、プロデュース=鈴木優人(読響指揮者/クリエイティヴ・パートナー)
アルト(メゾ・ソプラノ)=湯川亜也子
ヴァイオリン=林悠介(コンサートマスター)
ヴィオラ=鈴木康浩(ソロ・ヴィオラ)
チェロ=富岡廉太郎(首席)
フルート=片爪大輔
クラリネット=芳賀史徳
打楽器=金子泰士、西久保友広、野本洋介
ギター=大萩康司
ピアノ=大井駿
ブーレーズ:デリーヴ1
J.S.バッハ:ゴルトベルク変奏曲の主題に基づく14のカノン BWV1087(鈴木優人 編)
ドビュッシー:マラルメの3つの詩
クセナキス:プレクト
ブーレーズ:ル・マルトー・サン・メートル(主なき槌)
(アンコール)
一柳慧:インター・コンツェルト 第2楽章 静寂の彼方へ

このシリーズ前回でも、シェーンベルクの「月に憑かれたピエロ(ピエロ・リュネール)」を披露して鮮烈な印象を与えてくれました。その鈴木さんによれば、「ピエロ・リュネールまで来たら、もう必然的にここまで来ざるを得ない」というのが、今回の「ル・マルトー・サン・メートル」というわけです。
言うまでもありません。《作曲家》ピエール・ブーレーズの代表作。
実際、ブーレーズは、「ピエロ・リュネール」に強い影響を受けたと言っているそうです。編成も、アルトのソロと小さなアンサンブルという編成も共通です。プログラムは、その編成に沿って構築されているようです。出演は、指揮者の鈴木さん、アルトの湯川亜也子さんを含めて総勢12名。
最初は、ブーレーズの「デリーヴ1」。「ル・マルトー…」よりずっと後の80年代の作品。タイトルは「漂流/変動」を意味するフランス語だそうですが、確かに繰り返しが多くて雰囲気もずっと変わらない。意外に穏やかだけれど楽器間の相互作用というの緊張感のようなものに欠ける。
二曲目は、バッハがゴルトベルク変奏曲のテーマのバス進行、最初の8音をカノンにした曲。初版譜にバッハ自身が補遺として14のカノンを書き入れていたそうです。棋譜の解読が必要で、解決譜は鈴木さんが先達のものを参考にして、学生時代に編曲したものを手直ししたもの。音列技法など前衛と呼ばれた現代音楽の厳格の論理性や遊び心を示唆する意図があるのでしょうが、聴いた印象はちょっとした「おもちゃの交響曲」的な朴訥な音色と響きで、どこか微笑ましいものでした。
三曲目は、ドビュッシー。ここでアルト歌手の湯川亜也子さんが登場します。
マラルメの詩につけた曲は、どちらかと言えばラヴェルの方が知られていますし、編成も木管と弦楽が入っていたものなのですが、あえてドビュッシーのものが歌われました。やはり、無調とは言えませんが新規な和声法とかオリエンタリズムという点でドビュッシーのほうが現代音楽への影響が大きいことは間違いありません。けっこう難解な音楽で詩が聞き取れないのでひときわ理解が難しいと感じました。そろそろ声楽曲にはテキスト訳をプロジェクタでポップアップさせることを考えてほしいです。
前半最後は、クセナキス。
「プレクト」というのは「組みひも」の意だそうですが、ただひたすら変則的なリズムと点描的な熱力学的に雑然とした音の明滅がひたすら続き、タイトルからの連想とか作曲の意図がほとんど見えてこないという印象でした。とにかくアンサンブル技術としては壮絶なほどに複雑かつ難技巧で、それを見ているのがあっけにとられるほど面白く、その見事さに舌を巻くしかありません。その一方で、音楽的にはとてつもなく平板で退屈な時間でした。
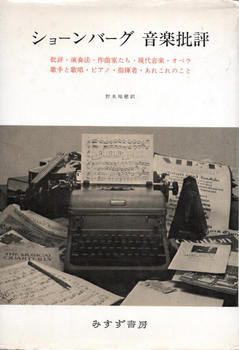
こうした音楽は、現代音楽のなかでも、かつて、特に「前衛」と呼ばれていました。
ブーレーズは、1971年にバーンスタインの辞任後の空白を埋める形でニューヨークフィルハーモニックの常任指揮者に就任しました。当時の、ショーンバーグの音楽批評にブーレーズらが主導した現代音楽運動を痛烈に皮肉ったものがあります。ショーンバーグは、その時代のニューヨークの聴衆の保守性を代弁するような批評家でした。ブーレーズが、取り入れた進取に富んだプログラムが物議をかもし、彼は転じて小さなホールでの現代音楽紹介に熱心に取り組みます。「ブーレーズの辻説法」と揶揄する一文では、皮肉たっぷりですに次のように記しています。
「ブーレーズが意見を述べている間、皆は感服して聴き入っていた。彼の言葉の一つ一つに気持ちよくついていった。そうだとも。作曲家と聴衆の間には確かに落差がある。音楽を健全な状態で将来に残そうとするならば、その亀裂をどうしても埋めなければならない。…ところが、音楽を聴くとどうか。…響きは退屈で、独創性は感じられなかった。」
さて…
休憩を経て、いよいよメインの「ル・マルトー・サン・メートル」。
これはとても素晴らしい体験でした。なるほどブーレーズというのはこういう風に知的で精緻な細密画のような美意識の音楽家だったんだと感得します。昔、FM放送か何かで聴いた記憶では、もっとごちゃごちゃしていて主張の強い騒がしい音楽というイメージがあったのですが、その頃の私には前衛音楽に対するバイアスがあったのだと思います。むしろ、静謐なたたずまいさえ感じます。音高・音価・音勢・強弱を量子化して組み合わせていく手法ですが、写実性や情感の起伏もあって美しい。打楽器によるガムランの響きとか、ギターによる琵琶のような撥弦楽器とか、東洋的なエキゾチシズムにも挑戦している。確かにシェーンベルクの点描法的手法の美学的な結実とも感じます。
こういう音楽を実際に目の当たりにする機会がこうやって訪れたのだと感慨深いものがあります。
最後に、鈴木優人さんが、先日亡くなられた一柳慧さんを偲んでのアンコール。こればもうまさに静謐さの極みのような音楽で仏教的な死生観さえ感じさせる感動的な演奏でした。
戦後の現代音楽の再演というのは、これからどんどん聴いていきたいと思いました。確かに、あの当時の実験音楽というのは、能書きばかりが先行していて聴衆と作曲者との間には深い溝が確かに存在したのだと思いますが、それが取り払われて通じ合える時代になってきたのだと思います。
素晴らしい試みでした。

読響アンサンブル・シリーズ
第35回 《鈴木優人プロデュース/ル・マルトー・サン・メートル》
2022年10月20日(木) 19:30~
トッパンホール
(P列 12番)
指揮、ピアノ、プロデュース=鈴木優人(読響指揮者/クリエイティヴ・パートナー)
アルト(メゾ・ソプラノ)=湯川亜也子
ヴァイオリン=林悠介(コンサートマスター)
ヴィオラ=鈴木康浩(ソロ・ヴィオラ)
チェロ=富岡廉太郎(首席)
フルート=片爪大輔
クラリネット=芳賀史徳
打楽器=金子泰士、西久保友広、野本洋介
ギター=大萩康司
ピアノ=大井駿
ブーレーズ:デリーヴ1
J.S.バッハ:ゴルトベルク変奏曲の主題に基づく14のカノン BWV1087(鈴木優人 編)
ドビュッシー:マラルメの3つの詩
クセナキス:プレクト
ブーレーズ:ル・マルトー・サン・メートル(主なき槌)
(アンコール)
一柳慧:インター・コンツェルト 第2楽章 静寂の彼方へ
「シューマン&ドヴォルザーク」 (芸劇ブランチコンサート) [コンサート]
たった1時間のブランチコンサート。
ですがいろいろと発見とか驚きがあって新鮮。今回はふたつのサプライズ。
最初に登場したのが、ヴァイオリニストの小林壱成さん。

小林さんは、実は今年の初めに紀尾井ホールでの「明日への扉」で聴いたばかり。「明日への扉」は、フレッシュなアーチストを紹介するシリーズでいわば若手の登竜門。コロナ禍のせいで延期が相次ぎ、ただでさえ成長著しい若手が登場したときにはもうすでに大活躍で名を知られているということが続いていました。小林さんについても、あの時点で東京交響楽団のコンサートマスターに就任してしまっていました。それで「時期外れの…」などとちょっと失礼なことを感想日記に書きました。
その小林さんが、たった半年でずいぶん貫禄がついて、驚いたのです。
雰囲気もとても落ち着いいて、成熟したロマンスあふれるシューマンを聴かせてくれたことにすっかり感服しました。もともとジュニアオーケストラで子供の頃からコンマス役を担っていたそうですから、根っからのオーケストラ演奏家なのでしょうか。地位がひとを造るということも言われますが、ほんとうに小林さんのはまりようが窺い見える急速な進境ぶりです。
続いて登場したのがチェロの笹沼 樹さん。

実は、笹沼さんもここのところよく聴いています。ただし、それはカルテット・アマービレの一員として。四重奏の中心にひときわ高くそびえる樹。目立たないわけがない。この芸劇ブランチコンサートでも、今年の初めに登場して清水さんとピアノ五重奏曲を演じています。その笹沼さん、聞くところによるとソロ活動や様々な企画をプロデュースするなど八面六臂の大活躍で大忙しなのだとか。これまた美音の心地よい、密かに情熱を燃やし恋い焦がれるようなシューマンです。
その笹沼さんと小林さんは同学年。ジュニアオーケストラでも首席同志でずっと仲良しという間柄だそうで、ステージ上のスピーチではざっくばらんな会話で、ここは一転して若やいだ雰囲気でした。
ふたつ目の驚きというのは、最後のドヴォルザークのピアノ四重奏。
これがもう、こんな魅力あふれる曲があったのかというぐらいの熱気あふれる名演だったのです。
ピアノと弦楽四重奏団との共演となる五重奏とは違って、四重奏はどうしてもにわか編成ということになって演奏機会も少ない。小林さんも笹沼さんも演奏は初めてとのこと。清水さんも「確か二回目…。でもこれっぽっちも憶えていない。」いったい誰がプログラムとして発案したのでしょう?

面白いのはヴィオラの佐々木亮さんは何度も経験しているとのこと。謹厳実直にして寡黙な佐々木さんが、あれこれ曲の要所を説明しながらのリハーサル…というのを想像して思わず吹き出してしまいます。
どう考えてもにわか仕立てのアンサンブルのはずなのに、素晴らしい熱演。音色の溶け込みも、互いの主張がぶつかり合い、あるいは呼応するような掛け合いも、美しいハーモニーやそれぞれの音色の際立ちも素晴らしい。何よりもドヴォルザークのちょっと土臭い旋律の魅力がいっぱい。寡黙なはずの佐々木さんのヴィオラが、要所要所で前へ出てきて、アンサンブル全体を結びつけ橋渡しをするように響きが浮き上がってきます。まさにヴィオラの魅力そのもの。

サロンコンサートとは対照的で、だだっ広い大ホールのステージに、せいぜいが三、四人のアンサンブル。しかも、毎回毎回、清水和音さんが集めるにわか作りの顔ぶれです。昼前のいささか安上がりのブランチコンサート。そんなカジュアルなヴェニューでこんなすごい演奏を聴けてしまってほんとうに申し訳ない…というぐらいのすごい快感でした。

芸劇ブランチコンサート
清水和音の名曲ラウンジ
第38回「シューマン&ドヴォルザーク」
2022年10月19日(水) 11:00~
東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール
(1階E列30番)
シューマン:3つのロマンス op.94
小林壱成(Vn) 清水 和音(Pf)
シューマン:幻想小曲集 op.73
笹沼 樹(vc) 清水 和音(Pf)
ドヴォルザーク:ピア四重奏曲 第2番 変ホ長調 op.87
小林壱成(Vn) 佐々木亮(Va) 笹沼 樹(vc) 清水 和音(Pf)
ですがいろいろと発見とか驚きがあって新鮮。今回はふたつのサプライズ。
最初に登場したのが、ヴァイオリニストの小林壱成さん。

小林さんは、実は今年の初めに紀尾井ホールでの「明日への扉」で聴いたばかり。「明日への扉」は、フレッシュなアーチストを紹介するシリーズでいわば若手の登竜門。コロナ禍のせいで延期が相次ぎ、ただでさえ成長著しい若手が登場したときにはもうすでに大活躍で名を知られているということが続いていました。小林さんについても、あの時点で東京交響楽団のコンサートマスターに就任してしまっていました。それで「時期外れの…」などとちょっと失礼なことを感想日記に書きました。
その小林さんが、たった半年でずいぶん貫禄がついて、驚いたのです。
雰囲気もとても落ち着いいて、成熟したロマンスあふれるシューマンを聴かせてくれたことにすっかり感服しました。もともとジュニアオーケストラで子供の頃からコンマス役を担っていたそうですから、根っからのオーケストラ演奏家なのでしょうか。地位がひとを造るということも言われますが、ほんとうに小林さんのはまりようが窺い見える急速な進境ぶりです。
続いて登場したのがチェロの笹沼 樹さん。

実は、笹沼さんもここのところよく聴いています。ただし、それはカルテット・アマービレの一員として。四重奏の中心にひときわ高くそびえる樹。目立たないわけがない。この芸劇ブランチコンサートでも、今年の初めに登場して清水さんとピアノ五重奏曲を演じています。その笹沼さん、聞くところによるとソロ活動や様々な企画をプロデュースするなど八面六臂の大活躍で大忙しなのだとか。これまた美音の心地よい、密かに情熱を燃やし恋い焦がれるようなシューマンです。
その笹沼さんと小林さんは同学年。ジュニアオーケストラでも首席同志でずっと仲良しという間柄だそうで、ステージ上のスピーチではざっくばらんな会話で、ここは一転して若やいだ雰囲気でした。
ふたつ目の驚きというのは、最後のドヴォルザークのピアノ四重奏。
これがもう、こんな魅力あふれる曲があったのかというぐらいの熱気あふれる名演だったのです。
ピアノと弦楽四重奏団との共演となる五重奏とは違って、四重奏はどうしてもにわか編成ということになって演奏機会も少ない。小林さんも笹沼さんも演奏は初めてとのこと。清水さんも「確か二回目…。でもこれっぽっちも憶えていない。」いったい誰がプログラムとして発案したのでしょう?

面白いのはヴィオラの佐々木亮さんは何度も経験しているとのこと。謹厳実直にして寡黙な佐々木さんが、あれこれ曲の要所を説明しながらのリハーサル…というのを想像して思わず吹き出してしまいます。
どう考えてもにわか仕立てのアンサンブルのはずなのに、素晴らしい熱演。音色の溶け込みも、互いの主張がぶつかり合い、あるいは呼応するような掛け合いも、美しいハーモニーやそれぞれの音色の際立ちも素晴らしい。何よりもドヴォルザークのちょっと土臭い旋律の魅力がいっぱい。寡黙なはずの佐々木さんのヴィオラが、要所要所で前へ出てきて、アンサンブル全体を結びつけ橋渡しをするように響きが浮き上がってきます。まさにヴィオラの魅力そのもの。

サロンコンサートとは対照的で、だだっ広い大ホールのステージに、せいぜいが三、四人のアンサンブル。しかも、毎回毎回、清水和音さんが集めるにわか作りの顔ぶれです。昼前のいささか安上がりのブランチコンサート。そんなカジュアルなヴェニューでこんなすごい演奏を聴けてしまってほんとうに申し訳ない…というぐらいのすごい快感でした。

芸劇ブランチコンサート
清水和音の名曲ラウンジ
第38回「シューマン&ドヴォルザーク」
2022年10月19日(水) 11:00~
東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール
(1階E列30番)
シューマン:3つのロマンス op.94
小林壱成(Vn) 清水 和音(Pf)
シューマン:幻想小曲集 op.73
笹沼 樹(vc) 清水 和音(Pf)
ドヴォルザーク:ピア四重奏曲 第2番 変ホ長調 op.87
小林壱成(Vn) 佐々木亮(Va) 笹沼 樹(vc) 清水 和音(Pf)
「ヒトラーに傾倒した男――A級戦犯・大島浩の告白」(増田 剛 著)読了 [読書]
駐独全権大使として日独伊三国同盟を主導し、戦後にA級戦犯に問われたが僅差で絞首刑を免れた大島浩。その後、恩赦で釈放されたが、茅ヶ崎に隠遁し表に出ることはなく沈黙を守ったとされていたが、その肉声の証言がカセットテープに残されていた。
この証言が公開されたのがNHKBSで放送された「BS1スペシャル」。本著は番組を提案企画したNHK記者によるもの。私もこの番組の再放送を見て興味を持ち本書を手にした。
大島が口を閉ざし続けたのは、「自分は失敗した人間であると。日本という国を誤った方向に導いた、そういう失敗した人間であるから」という自責の念があるからだという。
「国民に対してすまぬと思っている」「私なんぞは当然絞首刑になるべき人間なんだが、僕なんぞが助かっちゃってね」とも言っている。実際、昭和天皇も「死刑でなきは不思議」(「昭和天皇拝謁記」田島道治)と辛辣だった。確かに、「防共協定」締結や、独ソ不戦条約後に左遷された後にも、「日独伊三国同盟」締結に狂奔し、結果的に日米開戦に導いた責任は重い。
しかし、本書を読むと、いかにも小物感が漂う。
元陸軍大臣の息子として、陸軍で順調に出世する。ドイツびいきの父親に幼少の頃から徹底的にドイツ教育を仕込まれる。陸軍でも情報畑を歩み、大使館付武官を歴任する。そのドイツ語の会話能力は抜きん出ていて、そのドイツの文化・歴史への造詣ぶりはしばしばドイツ人自身以上で、ナチスの成り上がりの貴族趣味をくすぐってその懐中に深く潜り込む。
得てしてこういう語学などの異才で重用されて組織を誤った方向へ導く人物は、古今東西、官民問わずにいるものだ。軍部が次第に政治を壟断し、松岡洋右のような成り上がりのポピュリストが官僚を保守的な抵抗勢力と見なして直情径行に走り喝采を浴びる。ドイツ軍優勢と言いつのる直電情報は、「バスに乗り遅れるな」との風潮を煽り、対英米参戦反対の声を封じ込むことに利用された。
そういう戦前の危うい政治統治の時流に乗っただけの男。歴史の檜舞台の表裏に立つことに舞い上がっていた男。
テープの肉声も、殊勝な口ぶりにもかかわらず、いまだにヒトラーに心酔しきったままであることを隠そうともしていない。ヒトラーとの親密な交流や、外交の舞台である社交界の華やかさを懐かしむ。そういう場でともに活躍した華族出身の夫人とは、集成仲睦まじかったというが、そういうまっとうさがかえって小物感を助長する。
TVでは、割愛省略された情報も多少は補完されている。例えば、長期の総力戦となっった場合の日本敗北必至を説いた「秋丸機関」報告書の存在。あるいは、大島に抵抗したハンガリー公使大久保利隆の手記が伝える「在欧大公使会議」での対決とその後の左遷人事。しかし、文字にしてみると、TVの伝える情報というものがいかに印象過多で実質情報が薄いかという実感がわく。本にするのだったら、もっと深く掘り下げてほしかった。TVと書物では役割が違う。
安倍政権以来の、安易な反官僚的な風潮に乗った、いわゆる《官邸主導》というものに対する警戒心を国民はもっと持っていてよいのではないかというのが、この内容希薄な書物の読後感となった。

ヒトラーに傾倒した男
A級戦犯・大島浩の告白
NHKBS1スペシャル取材班 増田 剛 著
論創社
この証言が公開されたのがNHKBSで放送された「BS1スペシャル」。本著は番組を提案企画したNHK記者によるもの。私もこの番組の再放送を見て興味を持ち本書を手にした。
大島が口を閉ざし続けたのは、「自分は失敗した人間であると。日本という国を誤った方向に導いた、そういう失敗した人間であるから」という自責の念があるからだという。
「国民に対してすまぬと思っている」「私なんぞは当然絞首刑になるべき人間なんだが、僕なんぞが助かっちゃってね」とも言っている。実際、昭和天皇も「死刑でなきは不思議」(「昭和天皇拝謁記」田島道治)と辛辣だった。確かに、「防共協定」締結や、独ソ不戦条約後に左遷された後にも、「日独伊三国同盟」締結に狂奔し、結果的に日米開戦に導いた責任は重い。
しかし、本書を読むと、いかにも小物感が漂う。
元陸軍大臣の息子として、陸軍で順調に出世する。ドイツびいきの父親に幼少の頃から徹底的にドイツ教育を仕込まれる。陸軍でも情報畑を歩み、大使館付武官を歴任する。そのドイツ語の会話能力は抜きん出ていて、そのドイツの文化・歴史への造詣ぶりはしばしばドイツ人自身以上で、ナチスの成り上がりの貴族趣味をくすぐってその懐中に深く潜り込む。
得てしてこういう語学などの異才で重用されて組織を誤った方向へ導く人物は、古今東西、官民問わずにいるものだ。軍部が次第に政治を壟断し、松岡洋右のような成り上がりのポピュリストが官僚を保守的な抵抗勢力と見なして直情径行に走り喝采を浴びる。ドイツ軍優勢と言いつのる直電情報は、「バスに乗り遅れるな」との風潮を煽り、対英米参戦反対の声を封じ込むことに利用された。
そういう戦前の危うい政治統治の時流に乗っただけの男。歴史の檜舞台の表裏に立つことに舞い上がっていた男。
テープの肉声も、殊勝な口ぶりにもかかわらず、いまだにヒトラーに心酔しきったままであることを隠そうともしていない。ヒトラーとの親密な交流や、外交の舞台である社交界の華やかさを懐かしむ。そういう場でともに活躍した華族出身の夫人とは、集成仲睦まじかったというが、そういうまっとうさがかえって小物感を助長する。
TVでは、割愛省略された情報も多少は補完されている。例えば、長期の総力戦となっった場合の日本敗北必至を説いた「秋丸機関」報告書の存在。あるいは、大島に抵抗したハンガリー公使大久保利隆の手記が伝える「在欧大公使会議」での対決とその後の左遷人事。しかし、文字にしてみると、TVの伝える情報というものがいかに印象過多で実質情報が薄いかという実感がわく。本にするのだったら、もっと深く掘り下げてほしかった。TVと書物では役割が違う。
安倍政権以来の、安易な反官僚的な風潮に乗った、いわゆる《官邸主導》というものに対する警戒心を国民はもっと持っていてよいのではないかというのが、この内容希薄な書物の読後感となった。

ヒトラーに傾倒した男
A級戦犯・大島浩の告白
NHKBS1スペシャル取材班 増田 剛 著
論創社
タグ:大島浩
サロンコンサートの終焉 (アートスペース・オー) [コンサート]
10年以上通い続けてきた、町田市の小さなサロンコンサート。その歴史はさらに古くてもう30年以上になります。そのサロンコンサートが今年で最後を迎えます。

小さなコンサートというのは、他にもあることはあります。けれども、いかにも手作りで、これほど内外のトップ奏者の演奏を親しい距離感で楽しめるというのは、なかなか他に思い当たりません。演奏後のサイン会はほとんど演奏者との立ち話ともなります。思い出深いのは、アキロン・クァルテットのコンサート後の小パーティ。軽い食事を取りながらの交流はまさにサロン。通訳もいたのにずっと手持ち無沙汰。ほとんどの人が、直接、英語で演奏者と談笑していたからです。
ようやくコロナ禍の規制緩和で再開したものの、オーナーの大橋さんが今年を最後として引退したいとのことで、この4回ほどはサンクスコンサートとして、旧来の常連だった演奏家の出演が続きます。
今回はその3回目。
本来は、前橋汀子さんも出演の予定でしたが、体調不良とのことで直前になってキャンセルとなったことはほんとうに残念でした。急遽、代演となったのは小林美恵さん。日本人として初めてロン・テイボー国際コンクールで優勝された実力者。
そして、日本の音楽界の重鎮、チェロの堤剛さん。ピアノは、共演者としてトップアーティストたちから絶大な信頼を得ている津田裕也さん。

プログラムは、オール・ベートーヴェン。前半は、ヴァイオリンとチェロのそれぞれのソナタ。――やはり素晴らしかったのは最後の「大公トリオ」。
ピアノトリオというのは、こうしたサロンコンサートでの黄金メニューという気がします。それぞれの楽器と演奏者の個性がむき出しになってぶつかり合う。間近なだけに、楽器の音色、演奏者の呼吸や覇気のようなものが直接耳を刺す。特にこのサロンはデッドな音空間なのでそういう露出が時には過度で残酷にさえ感じます。接近しているので、当然に方向感覚や立体感覚が研ぎ澄まされてきますが、それ以上に音や情感のエネルギーが聴き手の身体に直接に作用する。その近接感覚がすごい。

小林さんの楽器は、ストラディヴァリウス「ナド=クーレンカンプ」(1734年製、所有は昭和音楽大学)。
かつてゲオルク・クーレンカンプが使用したもの。ほかのヴァイオリンに比べて構造が一ミリほど大きく作られているそうで、ナチスに反抗し続けたクーレンカンプの愛器らしい骨太で頑固なところがあるような気がするのは、あながち気のせいではなさそうです。前半ではそういう音の重たさで少し足元がふらつくようなところがありましたが、堤さんとの合奏になってそれが見違えるほどに、艶やかな色気をいっぱいに含んで歌い出しました。

一方で、堤さんの楽器は、1733年製モンタニャーナ。
こうやって目の前で鳴りわたる響きを聴いてみて、あらためてその剛毅な音色を堪能しました。モンタニャーナもクレモナの制作者でストラディバリの兄弟弟子。この楽器は特にいかり肩で横幅が広い。そのぶん、雄渾で深い音が出る。これがまさに堤剛さんの個性と合一化しています。堤さんは、この楽器をアイザック・スターンさんに紹介してもらってビバリーヒルズのある収集家から手に入れたそうです。この楽器が思うように音を出してくれるようになったのは、入手から3年ほど弾き込んでからのことだったとか。
ご一緒したUNICORNさんとは、ひとしきり弓のことが話題になりました。楽器本体と違って、弓は比較的近代のものが使われます。特に演奏家が求めて入手したがるのは、19世紀のフランス製。この頃、奏法と楽器の近代的改造が進みそれにふさわしい弓が必要になったのです。UNICORNさんによれば、最近はアメリカが優秀な製作者を輩出し、素材はブラジル製の木材が最適なのだとか。
実際、堤さんの弓は、日本人の手になるもの。素材はフェルナンブーコというブラジル原産の木。製作者は、植木繁さんといってドイツやフランスの工房で経験を積んだ楽器製作者。パリ時代はベルギーの名バイオリニスト、グリュミオーから楽器の調整を任されていたほどの名匠だそうで、堤さんのお父さんの代からの縁なのだそうです。大ぶりのモンタニャーナには「強い弓が必要」――そういう重量感のある、まさに、剛弓。堤さんにとって、楽器が分身なら、この弓は右腕。「日本の弓で、しかも新しいものだ」と説明するとみんな驚かれるのだそうです。
こうしたことは、コンサートの後で知ったことですが、ほんとうにことごとく実感します。そういう実感は、サロンコンサートならではの距離感がもたらした貴重な体験だと思うのです。

津田さんのピアノは、サロン備え付けのヤマハの小さめのコンサートグランド。この楽器でも容赦なく弾かれると小さなサロンでは耳をつんざくような音になります。津田さんは、部屋の音響とアンサンブルとのバランスが見事。こういう室内楽の名手としては、やはりこのサロンで何度か聴いた小菅優さんを思い浮かべます。オーナーの大橋さんによれば「いつもはクールな津田さんが、決して名器とは言えないここのヤマハで熱く燃えた」――まさにそういう演奏でした。
感動的だったのは、まだ顔のほてりが収まらない堤さんのアンコールの紹介スピーチ。「大橋さんのここでのサロンコンサートは、まさに歴史を作った」――そう褒め称えておられました。桐朋学園大学の学長を長く務め、サントリーホール館長でもあり、内外の多くのトップアーティストを育て、迎えてきた堤さんの熱い言葉でした。

Thanks Concert IV-III
Piano Trio
小林美恵(Vn)、堤 剛(Vc)、津田 裕也(P)
2022年10月9日(土) 16:00
東京・町田 アートスペース・オー
L.V.ベートーヴェン:
ヴァイオリン・ソナタ第5番 ヘ長調 作品24「春」
チェロ・ソナタ第3番 イ長調 作品69
(アンコール)
ピアノ三重奏曲 第4番『街の歌』から、第2楽章アダージョ
小さなコンサートというのは、他にもあることはあります。けれども、いかにも手作りで、これほど内外のトップ奏者の演奏を親しい距離感で楽しめるというのは、なかなか他に思い当たりません。演奏後のサイン会はほとんど演奏者との立ち話ともなります。思い出深いのは、アキロン・クァルテットのコンサート後の小パーティ。軽い食事を取りながらの交流はまさにサロン。通訳もいたのにずっと手持ち無沙汰。ほとんどの人が、直接、英語で演奏者と談笑していたからです。
ようやくコロナ禍の規制緩和で再開したものの、オーナーの大橋さんが今年を最後として引退したいとのことで、この4回ほどはサンクスコンサートとして、旧来の常連だった演奏家の出演が続きます。
今回はその3回目。
本来は、前橋汀子さんも出演の予定でしたが、体調不良とのことで直前になってキャンセルとなったことはほんとうに残念でした。急遽、代演となったのは小林美恵さん。日本人として初めてロン・テイボー国際コンクールで優勝された実力者。
そして、日本の音楽界の重鎮、チェロの堤剛さん。ピアノは、共演者としてトップアーティストたちから絶大な信頼を得ている津田裕也さん。
プログラムは、オール・ベートーヴェン。前半は、ヴァイオリンとチェロのそれぞれのソナタ。――やはり素晴らしかったのは最後の「大公トリオ」。
ピアノトリオというのは、こうしたサロンコンサートでの黄金メニューという気がします。それぞれの楽器と演奏者の個性がむき出しになってぶつかり合う。間近なだけに、楽器の音色、演奏者の呼吸や覇気のようなものが直接耳を刺す。特にこのサロンはデッドな音空間なのでそういう露出が時には過度で残酷にさえ感じます。接近しているので、当然に方向感覚や立体感覚が研ぎ澄まされてきますが、それ以上に音や情感のエネルギーが聴き手の身体に直接に作用する。その近接感覚がすごい。

小林さんの楽器は、ストラディヴァリウス「ナド=クーレンカンプ」(1734年製、所有は昭和音楽大学)。
かつてゲオルク・クーレンカンプが使用したもの。ほかのヴァイオリンに比べて構造が一ミリほど大きく作られているそうで、ナチスに反抗し続けたクーレンカンプの愛器らしい骨太で頑固なところがあるような気がするのは、あながち気のせいではなさそうです。前半ではそういう音の重たさで少し足元がふらつくようなところがありましたが、堤さんとの合奏になってそれが見違えるほどに、艶やかな色気をいっぱいに含んで歌い出しました。

一方で、堤さんの楽器は、1733年製モンタニャーナ。
こうやって目の前で鳴りわたる響きを聴いてみて、あらためてその剛毅な音色を堪能しました。モンタニャーナもクレモナの制作者でストラディバリの兄弟弟子。この楽器は特にいかり肩で横幅が広い。そのぶん、雄渾で深い音が出る。これがまさに堤剛さんの個性と合一化しています。堤さんは、この楽器をアイザック・スターンさんに紹介してもらってビバリーヒルズのある収集家から手に入れたそうです。この楽器が思うように音を出してくれるようになったのは、入手から3年ほど弾き込んでからのことだったとか。
ご一緒したUNICORNさんとは、ひとしきり弓のことが話題になりました。楽器本体と違って、弓は比較的近代のものが使われます。特に演奏家が求めて入手したがるのは、19世紀のフランス製。この頃、奏法と楽器の近代的改造が進みそれにふさわしい弓が必要になったのです。UNICORNさんによれば、最近はアメリカが優秀な製作者を輩出し、素材はブラジル製の木材が最適なのだとか。
実際、堤さんの弓は、日本人の手になるもの。素材はフェルナンブーコというブラジル原産の木。製作者は、植木繁さんといってドイツやフランスの工房で経験を積んだ楽器製作者。パリ時代はベルギーの名バイオリニスト、グリュミオーから楽器の調整を任されていたほどの名匠だそうで、堤さんのお父さんの代からの縁なのだそうです。大ぶりのモンタニャーナには「強い弓が必要」――そういう重量感のある、まさに、剛弓。堤さんにとって、楽器が分身なら、この弓は右腕。「日本の弓で、しかも新しいものだ」と説明するとみんな驚かれるのだそうです。
こうしたことは、コンサートの後で知ったことですが、ほんとうにことごとく実感します。そういう実感は、サロンコンサートならではの距離感がもたらした貴重な体験だと思うのです。

津田さんのピアノは、サロン備え付けのヤマハの小さめのコンサートグランド。この楽器でも容赦なく弾かれると小さなサロンでは耳をつんざくような音になります。津田さんは、部屋の音響とアンサンブルとのバランスが見事。こういう室内楽の名手としては、やはりこのサロンで何度か聴いた小菅優さんを思い浮かべます。オーナーの大橋さんによれば「いつもはクールな津田さんが、決して名器とは言えないここのヤマハで熱く燃えた」――まさにそういう演奏でした。
感動的だったのは、まだ顔のほてりが収まらない堤さんのアンコールの紹介スピーチ。「大橋さんのここでのサロンコンサートは、まさに歴史を作った」――そう褒め称えておられました。桐朋学園大学の学長を長く務め、サントリーホール館長でもあり、内外の多くのトップアーティストを育て、迎えてきた堤さんの熱い言葉でした。
Thanks Concert IV-III
Piano Trio
小林美恵(Vn)、堤 剛(Vc)、津田 裕也(P)
2022年10月9日(土) 16:00
東京・町田 アートスペース・オー
L.V.ベートーヴェン:
ヴァイオリン・ソナタ第5番 ヘ長調 作品24「春」
チェロ・ソナタ第3番 イ長調 作品69
(アンコール)
ピアノ三重奏曲 第4番『街の歌』から、第2楽章アダージョ
「ジュリオ・チェーザレ」 (新国立劇場) [コンサート]
こんな素晴らしいプロダクションが日本に居ながらにして楽しめるなんて。ヘンデルのバロック・オペラを堪能しました。面白くて面白くて、4時間半の長丁場もあっという間。お尻は痛くなりましたけど…。
演出は、ロラン・ペリー。もともとは2011年にパリ・オペラ座で初演されたもの。まずは、博物館の古代文明収蔵庫で繰り広げられる古代の歴史劇という巧妙な舞台が目を引きます。

かといって現代などへの置き換えということではなく、物語そのものはあくまでもシーザーとクレオパトラ。衣装もローマ時代のエジプト。原作をいささかも損なわない。実に、巧妙な演出です。
もうひとつの魅力はジェンダーフリー。
バロック・オペラの時代、その花形はカストラート。それは去勢された男性歌手のこと。カストラートは歌舞伎の女形同様に、その技を磨きに磨き、音楽的にも、肉体的にも、技術的にも最高の歌手。その高音域で人々を魅了する。歴史的には、市民社会の人権意識の伸長とともに当然に衰退し絶滅してしまう。それを現代のジェンダーフリーで再現する。英雄シーザー(初演カストラート)はソプラノ、女王クレオパトラもソプラノ(初演も同じ)、トロメーオ(初演カストラート)はカウンターテナーという具合。
その効果は、もちろん原作にある高い声域で歌われるアリアの華麗さ、軽妙さの魅力。ハイトーン・ボイスはいつの時代だって魅力なのです。そして、交錯するジェンダーが平等にやりとりする不思議な魅力。英雄と女王は、恋のかけひきを繰り広げるけど、同時に、政敵との覇権争い、陰謀への復讐でも共闘する。オペラ・セリアであっても決して深刻で陰惨にならないのがジェンダーフリーの絶大な効果。だからバロック・オペラは、エンターテイメント。ファンタジーやユーモアでも楽しませてくれます。
《博物館の収納庫》には現代のリアリズムが写し出されていて、それだけに史劇のファンタジーが引き立ち、歴史への想像力をかき立てるのです。

第二幕で、クレオパトラが色仕掛けでシーザーを籠絡される場面も、ロココ調の衣装に変わっていて、バロック時代の宮廷風の衣装の美女のバンダに合わせて、ルーブル美術館の名画の巨大な額縁に入ったり、周囲を巡ったりのアリアがなんとも色っぽい。
この場面で特に引き立つのが、ダ・カーポ・アリア。歌手の技量を披露するために、同じ旋律を繰り返し、繰り返し聴かせる。そこに変幻自在の変化をつけるのが歌手の聴かせどころだったわけですが、それを舞台狭しとくるくると周り巡り、演技の動的変化を視覚的にみせながらの歌唱が、この舞台と演出のもうひとつの巧妙な仕掛けになっているのです。
クレオパトラの森谷真理は圧倒的なヒロイン。ほとんどタイトルロール。とにかく出ずっぱり歌いっぱなしの全3幕で歌えば歌うほどに声の量感と艶が増していく。第一幕の超エロチックな衣装からして、とにかく体当たり的な歌唱。

同じくらい体当たりなのが、トロメーオの藤木大地。もはや、古楽復古のカウンターテナーのアカデミズムの衣など脱ぎ捨てて、それこそ半裸に姿をさらしてまでの歌唱と演技には目を瞠るほど。クレオパトラとの対峙は、シリアスなエンターテイメントがあふれています。

シーザーのマリアンネ・ベアーテ・キーランドには、中性的な魅力がいっぱい。英雄につきものの汗臭さはこれっぽっちも無くて、とても格調があって清廉でハンサム。ズボン役とはまたちがったローマ時代のレリーフの裸像のような魅力を感じます。彼女の出演は、コロナ禍で2年半延期となった不幸がかえって呼び込んだ僥倖なのだそうです。

出色だったのは、クレオパトラの侍従ニレーノ役の村松稔之。これもまた両性具有の美少年、あるいは、いたずら好きの妖精パック。美声とスリムな容姿と、巧まざる身体能力を駆使した演技は最高に楽しいものでした。

ポンペーオの寡婦コルネーリアの加納悦子、コルネーリアの息子セストの金子美香も、新国立常連の実力派。単なる脇役ということではなくしっかりとした存在感のある持ち場を見せてくれたのも、今回の公演の楽しさ。
視点をピットに移すと、これまた、東フィルの古楽スタイルの演奏の変身ぶりにびっくりするやら、感心するやら。ここまで古楽スタイルに徹した演奏が可能だなんて想像もしていませんでした。ミラノ・スカラ座など世界の歌劇場オーケストラはこうした演奏スタイルの早変わりで、はるか先を行っていると思っていましたが、まさか、東フィルがそれをやってのけるとは。第1幕での、勇壮なホルンのソロ(ナチュラルホルンではなくてピストン付でしたが)は見事でした。もちろんエキストラも入っているのでしょうが、舞台上のロココ調の女性バンダもそうですが、個別のクレジットがないのでわかりません。そのことがかえって残念です。
指揮者のリナルド・アレッサンドリーニは、音楽をすべて把握してコントロールしきっていました。ダ・カーポ・アリアの最後を告げるリタルダンドとフェルマータはいかにもバロック。ピットはどこまで浅く引き上げられていたのかわかりませんが、ステージ上で演奏されるヘンデルの合奏協奏曲を聴いているような響きと渋いガット弦のような音色で魅了します。東フィルから、バロック音楽の魅力を引き出したのは、当然に彼の力量でしょう。

最後は、死んだはずの敵役のトロメーオもアッキラもそろっての、お定まりの祝勝の大団円。客席にとっても大いに気持ちの上がる大団円でした。
(写真は新国立劇場のHPから拝借しました)

新国立劇場
クロード・ドビュッシー 「ペレアスとメリザンド」
2022年10月5日 17:00
東京・初台 新国立劇場 オペラハウス
(1階5列16番)
指揮:リナルド・アレッサンドリーニ
演出・衣裳:ロラン・ペリー
美術:シャンタル・トマ
照明:ジョエル・アダム
ドラマトゥルク:アガテ・メリナン
演出補:ローリー・フェルドマン
舞台監督:髙橋尚史
ジュリオ・チェーザレ:マリアンネ・ベアーテ・キーランド
クーリオ:駒田敏章
コルネーリア:加納悦子
セスト:金子美香
クレオパトラ:森谷真理
トロメーオ:藤木大地
アキッラ:ヴィタリ・ユシュマノフ
ニレーノ:村松稔之
合唱指揮:冨平恭平
合唱:新国立劇場合唱団
管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団
演出は、ロラン・ペリー。もともとは2011年にパリ・オペラ座で初演されたもの。まずは、博物館の古代文明収蔵庫で繰り広げられる古代の歴史劇という巧妙な舞台が目を引きます。

かといって現代などへの置き換えということではなく、物語そのものはあくまでもシーザーとクレオパトラ。衣装もローマ時代のエジプト。原作をいささかも損なわない。実に、巧妙な演出です。
もうひとつの魅力はジェンダーフリー。
バロック・オペラの時代、その花形はカストラート。それは去勢された男性歌手のこと。カストラートは歌舞伎の女形同様に、その技を磨きに磨き、音楽的にも、肉体的にも、技術的にも最高の歌手。その高音域で人々を魅了する。歴史的には、市民社会の人権意識の伸長とともに当然に衰退し絶滅してしまう。それを現代のジェンダーフリーで再現する。英雄シーザー(初演カストラート)はソプラノ、女王クレオパトラもソプラノ(初演も同じ)、トロメーオ(初演カストラート)はカウンターテナーという具合。
その効果は、もちろん原作にある高い声域で歌われるアリアの華麗さ、軽妙さの魅力。ハイトーン・ボイスはいつの時代だって魅力なのです。そして、交錯するジェンダーが平等にやりとりする不思議な魅力。英雄と女王は、恋のかけひきを繰り広げるけど、同時に、政敵との覇権争い、陰謀への復讐でも共闘する。オペラ・セリアであっても決して深刻で陰惨にならないのがジェンダーフリーの絶大な効果。だからバロック・オペラは、エンターテイメント。ファンタジーやユーモアでも楽しませてくれます。
《博物館の収納庫》には現代のリアリズムが写し出されていて、それだけに史劇のファンタジーが引き立ち、歴史への想像力をかき立てるのです。

第二幕で、クレオパトラが色仕掛けでシーザーを籠絡される場面も、ロココ調の衣装に変わっていて、バロック時代の宮廷風の衣装の美女のバンダに合わせて、ルーブル美術館の名画の巨大な額縁に入ったり、周囲を巡ったりのアリアがなんとも色っぽい。
この場面で特に引き立つのが、ダ・カーポ・アリア。歌手の技量を披露するために、同じ旋律を繰り返し、繰り返し聴かせる。そこに変幻自在の変化をつけるのが歌手の聴かせどころだったわけですが、それを舞台狭しとくるくると周り巡り、演技の動的変化を視覚的にみせながらの歌唱が、この舞台と演出のもうひとつの巧妙な仕掛けになっているのです。
クレオパトラの森谷真理は圧倒的なヒロイン。ほとんどタイトルロール。とにかく出ずっぱり歌いっぱなしの全3幕で歌えば歌うほどに声の量感と艶が増していく。第一幕の超エロチックな衣装からして、とにかく体当たり的な歌唱。

同じくらい体当たりなのが、トロメーオの藤木大地。もはや、古楽復古のカウンターテナーのアカデミズムの衣など脱ぎ捨てて、それこそ半裸に姿をさらしてまでの歌唱と演技には目を瞠るほど。クレオパトラとの対峙は、シリアスなエンターテイメントがあふれています。

シーザーのマリアンネ・ベアーテ・キーランドには、中性的な魅力がいっぱい。英雄につきものの汗臭さはこれっぽっちも無くて、とても格調があって清廉でハンサム。ズボン役とはまたちがったローマ時代のレリーフの裸像のような魅力を感じます。彼女の出演は、コロナ禍で2年半延期となった不幸がかえって呼び込んだ僥倖なのだそうです。

出色だったのは、クレオパトラの侍従ニレーノ役の村松稔之。これもまた両性具有の美少年、あるいは、いたずら好きの妖精パック。美声とスリムな容姿と、巧まざる身体能力を駆使した演技は最高に楽しいものでした。

ポンペーオの寡婦コルネーリアの加納悦子、コルネーリアの息子セストの金子美香も、新国立常連の実力派。単なる脇役ということではなくしっかりとした存在感のある持ち場を見せてくれたのも、今回の公演の楽しさ。
視点をピットに移すと、これまた、東フィルの古楽スタイルの演奏の変身ぶりにびっくりするやら、感心するやら。ここまで古楽スタイルに徹した演奏が可能だなんて想像もしていませんでした。ミラノ・スカラ座など世界の歌劇場オーケストラはこうした演奏スタイルの早変わりで、はるか先を行っていると思っていましたが、まさか、東フィルがそれをやってのけるとは。第1幕での、勇壮なホルンのソロ(ナチュラルホルンではなくてピストン付でしたが)は見事でした。もちろんエキストラも入っているのでしょうが、舞台上のロココ調の女性バンダもそうですが、個別のクレジットがないのでわかりません。そのことがかえって残念です。
指揮者のリナルド・アレッサンドリーニは、音楽をすべて把握してコントロールしきっていました。ダ・カーポ・アリアの最後を告げるリタルダンドとフェルマータはいかにもバロック。ピットはどこまで浅く引き上げられていたのかわかりませんが、ステージ上で演奏されるヘンデルの合奏協奏曲を聴いているような響きと渋いガット弦のような音色で魅了します。東フィルから、バロック音楽の魅力を引き出したのは、当然に彼の力量でしょう。

最後は、死んだはずの敵役のトロメーオもアッキラもそろっての、お定まりの祝勝の大団円。客席にとっても大いに気持ちの上がる大団円でした。
(写真は新国立劇場のHPから拝借しました)

新国立劇場
クロード・ドビュッシー 「ペレアスとメリザンド」
2022年10月5日 17:00
東京・初台 新国立劇場 オペラハウス
(1階5列16番)
指揮:リナルド・アレッサンドリーニ
演出・衣裳:ロラン・ペリー
美術:シャンタル・トマ
照明:ジョエル・アダム
ドラマトゥルク:アガテ・メリナン
演出補:ローリー・フェルドマン
舞台監督:髙橋尚史
ジュリオ・チェーザレ:マリアンネ・ベアーテ・キーランド
クーリオ:駒田敏章
コルネーリア:加納悦子
セスト:金子美香
クレオパトラ:森谷真理
トロメーオ:藤木大地
アキッラ:ヴィタリ・ユシュマノフ
ニレーノ:村松稔之
合唱指揮:冨平恭平
合唱:新国立劇場合唱団
管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団
「帰りたい」(カミーラ・シャムジー 著)読了 [読書]
イギリスのパキスタン系移民のふたつの対照的な家族が、互いに交錯するなかで悲劇的な結末を迎える。一方は、父親がアフガンのテロリストとされて監視と差別のなかで生きづらい毎日を送るインテリの姉とその双子の妹弟。一方は、富裕な白人を妻として移民社会を裏切ることで内務大臣にまで登り詰めた男とその息子。日本人の私たちには想像もつかない状況のなかで物語は舞台を大きく広げて展開し、衝撃のラストを迎える。
作者は、パキスタンのカラチ生まれ。米国ハミルトン大学創作科卒業後、マサチューセッツ州立大学でファインアート修士号を取得。作家デビュー後、英国に移住し英国籍を取得している。本作は七作目で2017年のブッカー賞最終候補、翌年には女性小説賞を受賞している。
物語は、章を分けて登場人物のそれぞれの一人称で語り継がれていく。視点が変わることで、次第に真実が明らかになり、同時に、複雑な移民社会の感情の行き違いも見えてくる。物語の始まりは、アメリカ東岸の大学へ研究生として出発する空港で、散々なチェックを受けて予定のフライトに乗り遅れるシーンから始まる。この日常的で既視感のある情景に胚胎する苛立ち、諦めかけた怒りのようなものが、大きな伏線となって次第に肥大していく。実際、この空港検査の屈辱は作者自身の実体験であり、この小説を書くきっかけとなったという。
そういう静かだが、どこかまがまがしさをはらむ日常的な始まりから、次第にギリシャ悲劇的な壮大な歴史劇へと拡大していくダイナミックスも見事。
日本人の私たちの肌感覚では、その深層はすぐには伝わってこないのだが、それでもこの小説の構成の巧みさに導かれて、今のイギリスの移民問題、ムスリムへの偏見と差別などのシリアスな実情が見えてくる。
イギリスの俗語や、ムスリムの慣習や独特な言葉などには具体的で丁寧な注がつけてある。訳者は、直接、作者と丁寧なやりとりを重ねたということで、翻訳はとてもこなれていて、しかも、適切な注に助けられイギリスの肌感覚も少しずつ身についてくる。翻訳として出色の仕事。

帰りたい
カミーラ・シャムジー 著
金原端人・安納令奈 訳
白水社
(原書)
Home Fire
Kamila Shamsie
Bloomsbury Publishing PLC
作者は、パキスタンのカラチ生まれ。米国ハミルトン大学創作科卒業後、マサチューセッツ州立大学でファインアート修士号を取得。作家デビュー後、英国に移住し英国籍を取得している。本作は七作目で2017年のブッカー賞最終候補、翌年には女性小説賞を受賞している。
物語は、章を分けて登場人物のそれぞれの一人称で語り継がれていく。視点が変わることで、次第に真実が明らかになり、同時に、複雑な移民社会の感情の行き違いも見えてくる。物語の始まりは、アメリカ東岸の大学へ研究生として出発する空港で、散々なチェックを受けて予定のフライトに乗り遅れるシーンから始まる。この日常的で既視感のある情景に胚胎する苛立ち、諦めかけた怒りのようなものが、大きな伏線となって次第に肥大していく。実際、この空港検査の屈辱は作者自身の実体験であり、この小説を書くきっかけとなったという。
そういう静かだが、どこかまがまがしさをはらむ日常的な始まりから、次第にギリシャ悲劇的な壮大な歴史劇へと拡大していくダイナミックスも見事。
日本人の私たちの肌感覚では、その深層はすぐには伝わってこないのだが、それでもこの小説の構成の巧みさに導かれて、今のイギリスの移民問題、ムスリムへの偏見と差別などのシリアスな実情が見えてくる。
イギリスの俗語や、ムスリムの慣習や独特な言葉などには具体的で丁寧な注がつけてある。訳者は、直接、作者と丁寧なやりとりを重ねたということで、翻訳はとてもこなれていて、しかも、適切な注に助けられイギリスの肌感覚も少しずつ身についてくる。翻訳として出色の仕事。

帰りたい
カミーラ・シャムジー 著
金原端人・安納令奈 訳
白水社
(原書)
Home Fire
Kamila Shamsie
Bloomsbury Publishing PLC



