絵画カバー専用音響パネル (サウンドスフィア特注) [オーディオ]
私のお茶の間オーディオは、ごく平凡なリビングルームをリスニングルームと兼用させています。
そのために、向かって左手にダイニングスペースがあって、空間がぽっかり空いていてアコースティックが左右非対称です。右側にはオーディオラックもあるし、隅にはTVセットまであって、どうも音の響きの重心が右に寄りがちに感じてしまう。センター音像をきっちり中央に合わせても、どこか右手から左に向かっているように感じてしまうのです。

(before)
そのことの一つの要因が、左手の壁にかけている日本画の額縁にあることは、以前に椀方さんのご指摘でわかっています。やや下向きにかかっていたものを壁面にできるだけ平行にすることで驚くほどの改善がありました。
とはいえ、額縁の平面の存在はそのままですから、一次反射の影響は避けられません。そのことが以前からどうにも気になっていました。外してしまえばいいわけですが、そこはお茶の間オーディオ――リビングとしての生活空間はそのままにしたい。何よりもこの絵は、亡き母の手になるものですからこだわりもあるわけです。
そこでちょっとした実験をしてみました。音楽鑑賞中だけタオルなどをかけてみて額縁を覆ってみたのです。この効果はすぐに感じられました。かなり左手の響きを感じるようになり、ステージの幅が左に拡がった感覚があります。
その効果を確認したところで、コスモプロジェクトに吸音パネル「サウンドスフィア」の特注品を発注しました。以前、TVの液晶画面を覆うものを発注したことがあり、そのTVカバーは、アルテのピラミッドと併用して今も使用し続けています。ピラミッドを使ったのは吸音の平面パネルだけでは、いまひとつ自然な拡がりが不足していたからです。
今回も、平面パネルではなく新たに商品ラインに加わったピラミッド型のパネルにしてみました。最近の物価高騰もあってだいぶコストは上昇していましたが、事前の試験で効果を認めている以上は、躊躇できませんでした。
一ヶ月ほどして、ものが届きました。

さっそく掛けてみると…
サイズや掛け具合もぴったりで問題ありません。TV用の平面パネルに較べると思ったより重く感じますが耐荷重は事前にチェックしていて、実際に掛けてみても不安もなく問題ありません。
まだ初印象というところですが、聴いてみると期待以上に効果がありました。思ったよりピラミッドの高さが低く平面に近いと感じたのですが、効果はてきめんのようでピラミッドにしてよかったと感じています。絵を掛けている左壁側に不足していたステージが拡がったのは期待通りです。さらに低域が充実したと感じられたのは望外の成果でちょっと驚きました。
低音の不足感というのは、部屋の形状サイズからくる定在波(長波長の節)のせいだと思い込んでいました。実際、後方右隅の低域量感はリスポジよりも多くて、テストCDとスマホアプリで簡単に測定もどきのことをやってみると、51Hzのテスト信号でリスポジより右手コーナーのほうがおよそ5dB高い。つまり、50近辺の音の吹きだまりが確かに存在しています。逆にリスポジでは、そこが谷になっています。それは聴感と一致しているのです。
それが今回の絵画カバーで、リスポジでの低音が聴感上けっこうかさ上げされて明瞭になったような気がするのです。どうもリスポジでの帯域バランスというのは定在波だけが原因ではないようです。則壁の一次反射がかなり影響しているようです。部屋形状にもよりますが、前後の壁はスピーカーの設置位置やリスポジとの距離で影響しますが、同じように側壁やそこに置いてある家具などによる一次反射の影響を大きく受けているのではないでしょうか。それが低音にもかなり効いている…ということを感じてちょっと驚いています。

(after)
リビング兼用で、壁にかけた絵画にもこだわりがある――そういう方には、この掛け外しができる専用音響パネルはおすすめです。
そのために、向かって左手にダイニングスペースがあって、空間がぽっかり空いていてアコースティックが左右非対称です。右側にはオーディオラックもあるし、隅にはTVセットまであって、どうも音の響きの重心が右に寄りがちに感じてしまう。センター音像をきっちり中央に合わせても、どこか右手から左に向かっているように感じてしまうのです。
(before)
そのことの一つの要因が、左手の壁にかけている日本画の額縁にあることは、以前に椀方さんのご指摘でわかっています。やや下向きにかかっていたものを壁面にできるだけ平行にすることで驚くほどの改善がありました。
とはいえ、額縁の平面の存在はそのままですから、一次反射の影響は避けられません。そのことが以前からどうにも気になっていました。外してしまえばいいわけですが、そこはお茶の間オーディオ――リビングとしての生活空間はそのままにしたい。何よりもこの絵は、亡き母の手になるものですからこだわりもあるわけです。
そこでちょっとした実験をしてみました。音楽鑑賞中だけタオルなどをかけてみて額縁を覆ってみたのです。この効果はすぐに感じられました。かなり左手の響きを感じるようになり、ステージの幅が左に拡がった感覚があります。
その効果を確認したところで、コスモプロジェクトに吸音パネル「サウンドスフィア」の特注品を発注しました。以前、TVの液晶画面を覆うものを発注したことがあり、そのTVカバーは、アルテのピラミッドと併用して今も使用し続けています。ピラミッドを使ったのは吸音の平面パネルだけでは、いまひとつ自然な拡がりが不足していたからです。
今回も、平面パネルではなく新たに商品ラインに加わったピラミッド型のパネルにしてみました。最近の物価高騰もあってだいぶコストは上昇していましたが、事前の試験で効果を認めている以上は、躊躇できませんでした。
一ヶ月ほどして、ものが届きました。
さっそく掛けてみると…
サイズや掛け具合もぴったりで問題ありません。TV用の平面パネルに較べると思ったより重く感じますが耐荷重は事前にチェックしていて、実際に掛けてみても不安もなく問題ありません。
まだ初印象というところですが、聴いてみると期待以上に効果がありました。思ったよりピラミッドの高さが低く平面に近いと感じたのですが、効果はてきめんのようでピラミッドにしてよかったと感じています。絵を掛けている左壁側に不足していたステージが拡がったのは期待通りです。さらに低域が充実したと感じられたのは望外の成果でちょっと驚きました。
低音の不足感というのは、部屋の形状サイズからくる定在波(長波長の節)のせいだと思い込んでいました。実際、後方右隅の低域量感はリスポジよりも多くて、テストCDとスマホアプリで簡単に測定もどきのことをやってみると、51Hzのテスト信号でリスポジより右手コーナーのほうがおよそ5dB高い。つまり、50近辺の音の吹きだまりが確かに存在しています。逆にリスポジでは、そこが谷になっています。それは聴感と一致しているのです。
それが今回の絵画カバーで、リスポジでの低音が聴感上けっこうかさ上げされて明瞭になったような気がするのです。どうもリスポジでの帯域バランスというのは定在波だけが原因ではないようです。則壁の一次反射がかなり影響しているようです。部屋形状にもよりますが、前後の壁はスピーカーの設置位置やリスポジとの距離で影響しますが、同じように側壁やそこに置いてある家具などによる一次反射の影響を大きく受けているのではないでしょうか。それが低音にもかなり効いている…ということを感じてちょっと驚いています。
(after)
リビング兼用で、壁にかけた絵画にもこだわりがある――そういう方には、この掛け外しができる専用音響パネルはおすすめです。
春の祭典 (新国立劇場バレエ団) [コンサート]
久しぶりに新国立劇場のバレエに足を運んだ。
バレエというよりダンスということで、いずれもモダンな振り付けによる創作ダンス。

第2部の「春の祭典」が面白かった。
一貫して男女のデュオによって踊られる。原作やベジャール版のような生贄の乙女と原始的祝祭と儀典の群舞ということではなく、男女ふたりの肉体の絡みあう造形の妙味とそこから引き出される融合のエネルギーと愛の変転のドラマを雄弁に表現するというもの。
4手のピアノ連弾は、無駄がそぎ落とされて打楽器的なリズムが強調されていて、デュオダンスによりふさわしいシンプルでダイナミックな音楽になっていた。

舞台はとてもシンプル。ステージの平面が最大限に使用されて、後方に2台のピアノが向かい合って配置される。最後の悲劇的な結末を暗示する仕掛けが秀逸だった。
この日のダンサーは、ファースト・ソリストの池田理沙子とゲストの中川賢。ふたりとも清新さにあふれていて演技もフレッシュ。複雑な肉体の立体的な造形も見事で難しい体型も安定して決めていた。
ピアノは、若手とベテランの組み合わせ。個人的には、以前にリスト編ベートーヴェン交響曲のシリーズですっかり虜にされた後藤泉がお目当てだったが、ぴったりと息の合った連弾でこの曲の変拍子と打撃的なリズムの饗宴を大いに楽しんだ。それぞれがPAで補強されていたようだ。舞台上の形状から、ラインアレイスピーカーとサブウーファーを組み合わせたYAMAHAのDXL1Kのように見えたが詳細はわからない。舞台最奥なので音量に不足感が否めず、せっかくPAを使うのならもっと厚めに補強してほしかった。

第1部は、ドビュッシーの「牧神の午後」に振り付けたもの。「春の祭典」とともに初演時のニジンスキーのスキャンダラスな振り付けのエピソードが想起されるが、男性ダンサーだけによる群舞で、いたって平凡で退屈した。恐らく立体的な組み合わせで新奇な造形を狙うという点で第一部の「春の祭典」の二番煎じなのだろうが、ストーリー性に乏しく退屈した。
音響も、純然たるPAによるもので第2部との対比比較で期待したが、新作の序部導入の音楽もドビュッシーも単純な音響構成に終始していた。映画やディスコの音響のめざましい効果をなぜ取り入れないのだろう。最近では音量面はもちろん多チャンネルに効果や、生音からは得にくいPAならではの音響効果が可能になっているはず。二十世紀以前の作曲家の作品をただ録音で流すだけではだめだ。ダンスのクリエイティビティを高めるような音響プロデュースの才能を発掘し参画させることが、こうしたモダンダンスの魅力には必須なのではないか。

新国立劇場バレエ団
春の祭典
2022年11月26日(土)14:00
東京・初台 新国立劇場中劇場
(1階15列20番)
第1部『半獣神の午後』
【演出・振付】平山素子
【音楽】クロード・ドビュッシー、笠松泰洋
【照明デザイン】森 規幸
福田圭吾
渡邊峻郁、木下嘉人
宇賀大将、小野寺 雄、福田紘也
石山 蓮、太田寛仁、小川尚宏、上中佑樹、菊岡優舞、樋口 響、
山田悠貴、渡邊拓朗、渡部義紀
第2部『春の祭典』40分)
【演出・振付・美術原案】平山素子
【共同振付】柳本雅寛
【音楽】イーゴリ・ストラヴィンスキー
【照明デザイン】小笠原 純
【美術作品協力】渡辺晃一(作品《On An Earth》より)
池田理沙子、中川 賢(ゲストダンサー)
【演奏(2台ピアノ連弾)】後藤 泉、松木詩奈
バレエというよりダンスということで、いずれもモダンな振り付けによる創作ダンス。

第2部の「春の祭典」が面白かった。
一貫して男女のデュオによって踊られる。原作やベジャール版のような生贄の乙女と原始的祝祭と儀典の群舞ということではなく、男女ふたりの肉体の絡みあう造形の妙味とそこから引き出される融合のエネルギーと愛の変転のドラマを雄弁に表現するというもの。
4手のピアノ連弾は、無駄がそぎ落とされて打楽器的なリズムが強調されていて、デュオダンスによりふさわしいシンプルでダイナミックな音楽になっていた。
舞台はとてもシンプル。ステージの平面が最大限に使用されて、後方に2台のピアノが向かい合って配置される。最後の悲劇的な結末を暗示する仕掛けが秀逸だった。
この日のダンサーは、ファースト・ソリストの池田理沙子とゲストの中川賢。ふたりとも清新さにあふれていて演技もフレッシュ。複雑な肉体の立体的な造形も見事で難しい体型も安定して決めていた。
ピアノは、若手とベテランの組み合わせ。個人的には、以前にリスト編ベートーヴェン交響曲のシリーズですっかり虜にされた後藤泉がお目当てだったが、ぴったりと息の合った連弾でこの曲の変拍子と打撃的なリズムの饗宴を大いに楽しんだ。それぞれがPAで補強されていたようだ。舞台上の形状から、ラインアレイスピーカーとサブウーファーを組み合わせたYAMAHAのDXL1Kのように見えたが詳細はわからない。舞台最奥なので音量に不足感が否めず、せっかくPAを使うのならもっと厚めに補強してほしかった。

第1部は、ドビュッシーの「牧神の午後」に振り付けたもの。「春の祭典」とともに初演時のニジンスキーのスキャンダラスな振り付けのエピソードが想起されるが、男性ダンサーだけによる群舞で、いたって平凡で退屈した。恐らく立体的な組み合わせで新奇な造形を狙うという点で第一部の「春の祭典」の二番煎じなのだろうが、ストーリー性に乏しく退屈した。
音響も、純然たるPAによるもので第2部との対比比較で期待したが、新作の序部導入の音楽もドビュッシーも単純な音響構成に終始していた。映画やディスコの音響のめざましい効果をなぜ取り入れないのだろう。最近では音量面はもちろん多チャンネルに効果や、生音からは得にくいPAならではの音響効果が可能になっているはず。二十世紀以前の作曲家の作品をただ録音で流すだけではだめだ。ダンスのクリエイティビティを高めるような音響プロデュースの才能を発掘し参画させることが、こうしたモダンダンスの魅力には必須なのではないか。

新国立劇場バレエ団
春の祭典
2022年11月26日(土)14:00
東京・初台 新国立劇場中劇場
(1階15列20番)
第1部『半獣神の午後』
【演出・振付】平山素子
【音楽】クロード・ドビュッシー、笠松泰洋
【照明デザイン】森 規幸
福田圭吾
渡邊峻郁、木下嘉人
宇賀大将、小野寺 雄、福田紘也
石山 蓮、太田寛仁、小川尚宏、上中佑樹、菊岡優舞、樋口 響、
山田悠貴、渡邊拓朗、渡部義紀
第2部『春の祭典』40分)
【演出・振付・美術原案】平山素子
【共同振付】柳本雅寛
【音楽】イーゴリ・ストラヴィンスキー
【照明デザイン】小笠原 純
【美術作品協力】渡辺晃一(作品《On An Earth》より)
池田理沙子、中川 賢(ゲストダンサー)
【演奏(2台ピアノ連弾)】後藤 泉、松木詩奈
「音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む」(川原 繁人 著)読了 [読書]
音声学の入門書。
著者はとにかく音声学に誘おうとあれこれと手をつくす。そういうことの常套手段が子供をダシにすることというのは古今東西万事に共通する。その企みが成功しているのかどうかはわからないが、この本がかなりの話題を集めているらしいことは確かのようだ。
それでは「音声学」とは何だろうか。
「音声学」とは、言ってみれば、あの発音記号を思い浮かべればよい。英語の学習などでお世話になったあの[ ]に囲まれた音声を表す記号のこと。音声学会が制定する国際音声記号(IPA)は、たいへんな数に上ることを本書で初めて知った。
そういう音声記号の基本になっているのが「調音」で、人間の発声器官を使って音声を発すること、あるいはその声音のこと。これも顔の断面図がおなじみだが、今やそれがMRIで直接観察されていることも本書で知った。
著者はどうやらこういう調音音声学が専門らしく、本書はこういう調音の話題に終始し過ぎるきらいがある。「ママ」([m])「パパ」([p」)とかいった両唇音が幼児語に多いなど、ある意味で常識的な話題ばかりで字数を尽くす。子供に人気のカピチュウの可愛いネーミングにそれが多いといった話しで気を引くが、幼児的な音の取り違えや順番の逆転現象などは音韻論だとして踏み込まない。あるいはTVの警察捜査ドラマの声紋などでおなじみの音響音声学や、言語音声を聴くという聴取、認識、理解という幼児の言語成育にも重要な関わりのある聴覚音声学や音響心理学にもほとんど触れていない。
調音音声学の範囲に限定されると、せっかく音声学に興味を持っても、そこからどう広げていくかの展望や科学的な進路が見えてこない。巻末のゴスペラーズの北山陽一との対談も、その意味で歌手や俳優のボイストレーニングの本質に迫るような力に乏しいと感じてしまう。
子供の話題で誘ってエントリーさせても、それで本当に科学的なマインドが育つのか大いに疑問を感じる。

音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む
―プリチュワからカピチュウ、おっけーぐるぐるまで―
川原 繁人 (著)
朝日出版社
著者はとにかく音声学に誘おうとあれこれと手をつくす。そういうことの常套手段が子供をダシにすることというのは古今東西万事に共通する。その企みが成功しているのかどうかはわからないが、この本がかなりの話題を集めているらしいことは確かのようだ。
それでは「音声学」とは何だろうか。
「音声学」とは、言ってみれば、あの発音記号を思い浮かべればよい。英語の学習などでお世話になったあの[ ]に囲まれた音声を表す記号のこと。音声学会が制定する国際音声記号(IPA)は、たいへんな数に上ることを本書で初めて知った。
そういう音声記号の基本になっているのが「調音」で、人間の発声器官を使って音声を発すること、あるいはその声音のこと。これも顔の断面図がおなじみだが、今やそれがMRIで直接観察されていることも本書で知った。
著者はどうやらこういう調音音声学が専門らしく、本書はこういう調音の話題に終始し過ぎるきらいがある。「ママ」([m])「パパ」([p」)とかいった両唇音が幼児語に多いなど、ある意味で常識的な話題ばかりで字数を尽くす。子供に人気のカピチュウの可愛いネーミングにそれが多いといった話しで気を引くが、幼児的な音の取り違えや順番の逆転現象などは音韻論だとして踏み込まない。あるいはTVの警察捜査ドラマの声紋などでおなじみの音響音声学や、言語音声を聴くという聴取、認識、理解という幼児の言語成育にも重要な関わりのある聴覚音声学や音響心理学にもほとんど触れていない。
調音音声学の範囲に限定されると、せっかく音声学に興味を持っても、そこからどう広げていくかの展望や科学的な進路が見えてこない。巻末のゴスペラーズの北山陽一との対談も、その意味で歌手や俳優のボイストレーニングの本質に迫るような力に乏しいと感じてしまう。
子供の話題で誘ってエントリーさせても、それで本当に科学的なマインドが育つのか大いに疑問を感じる。

音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む
―プリチュワからカピチュウ、おっけーぐるぐるまで―
川原 繁人 (著)
朝日出版社
ヴィクトリア・ムローヴァ ヴァイオリン・リサイタル [コンサート]
ピリオド仕様のガダニーニとモダン仕様のストラディヴァリウスのそれぞれの名器を堪能した。
ムローヴァは、ここのところ来日のたびにこうしたピリオドとモダンの弾き分けを披露しているようだ。ピリオドは古楽の演奏、モダンは近現代、あるいは、ロマン派以降であっても同時代のオリジナル楽器で演奏する――そういう弾き分けがだんだんと浸透してきて私たちを楽しませてくれる。

けれども、この日のムローヴァは、そこからもう一歩踏み込んだ演奏だったのだと思う。それはとてもフィジカルな挑戦であって、音楽の楽しみ、感動というものを峻厳かつ深遠に掘り下げるような演奏だった。
ピアノのビートソンも、ムローヴァの楽器に合わせてフォルテピアノとモダンのスタインウェイを弾き分ける。フォルテピアノは、1820年製作の6オクターヴ、ウィーンアクションのオリジナル。

前半の一曲目、4番のソナタが始まると、ガダニーニとフォルテピアノの音量と音色がとても調和していて、古典的が均整美がまずひときわ胸を打つ。モダン同志のデュオだと主役の取り合いになりがちで、あるいは、その逆にピアノが遠慮して活きてこないことが多い。それが、ピリオドだと音が溶け合いすばらしいバランス。
7番は、4つの楽章の全てがピアノだけで開始される。そのことがなぜかフォルテピアノだと鮮烈に印象づけられる。これもまたピリオドならではの対等のバランスが生む効果なのだろうか。それだけでなくそれぞれの楽器の音のコントラストが引き立ってくる。剣の鋭い切っ先が切り結ぶような、あるいは、名書家の雄渾な運筆が躍動するようなベートーヴェンの勇壮なハ短調。とてもピリオド演奏とは思えない力強さがあって、しかも、音の強弱や濃淡、勢い、運びが墨書のように引き立つ。

休憩時にはピアノが交代するが、後半の開演直前までフォルテピアノはステージ右隅に蓋を開けたままで展示されていた。ホールの粋な計らいといえる。もともとこのホールは、開演時以外は写真撮影はOK。会場係員は、ちょっと距離を置いて待機しているだけ。多くの聴衆が興味深げに楽器をのぞき込み写真に収めていた。
後半は、モダン楽器。
最初の武満ではっとさせられた。ドビュッシーの影響が濃厚な若い武満のピアニズムに続いて深々とヴィヴラートをかけた叙情味あふれるヴァイオリンが現れる。こうしたロングフレーズにムローヴァは、いかにもモダンらしいたっぷりととしたヴィヴラートをかける。モダンならではのパルシブな運弓や浮遊するようなフラジオレットと対比されて、いかにも日本的な湿り気たっぷりの叙情を込めた息の長いフレージングは鮮烈。
そこには、ピリオドとモダンの境界、混交を感じてしまう。いわば、ピリオドとモダンの奏法の汽水域のようなものだ。そのことは、続けて演奏されたペルトにも流れ込んでいく。清澄な古楽的な協和音に満ちた世界が次第に色彩を帯びてきて、魂がぶつかり合い、きしみ合うようなモダニズムの厳しい触感の世界が混じり合う。ピリオドを聴いた直後だからこそ感じ取りやすくなった、音のコラージュの美学なのかもしれない。
最後のシューベルトでは、ストラディヴァリウスの華麗な音色に覚醒される思いがした。ここに至ってフルカラーの世界で、シューベルトの歌とその技巧的なヴァリエーションの世界が艶やかに躍動する。
普通に考えるなら、シューベルトの方がピリオドになじみやすい。ムローヴァは、あえてベートーヴェンと逆転させることで、互いの美点を際立たせている。ベートーヴェンでは、表現力の幅が広いモダンだと労なくして通り過ぎてしまいがちな本質が見逃されがち。スリムで敏捷性に富むピリオド奏法で、筋肉質で贅肉のない引き締まったベートーヴェンが鮮やかだった。一方のシューベルトでは、ガット弦で得た奏法によって実にフレッシュなモダンボウの裁きで聴き手をわくわくさせてくれた。
だから、このプログラムは、ベートーヴェンとシューベルトがリバーシブル。ピリオド奏法を一段と掘り下げ、その奏法で得たものをまたモダンでの演奏にフィードバックする。聴き手にとっても、そうした奏法の交換によってフレッシュな感覚が研ぎ澄まされてくる。ピリオドが作曲と同時代の楽器での再現という、アカデミックな視点からもっと純粋で自由な音楽探求にまで踏み込んできた。
ムローヴァの進化・深化はとどまるところを知らない。

ヴィクトリア・ムローヴァ ヴァイオリン・リサイタル
2022年11月20日(日) 15:00
東京・築地 浜離宮朝日ホール
(1階10列9番)
ヴィクトリア・ムローヴァ(ヴァイオリン)
ガダニーニ(ガット弦)/ストラディヴァリウス「ジュールズ・フォーク」
アラスデア・ビートソン
フォルテピアノ/ヨハン・ゲオルグ・グレーバー製作(インスブルック1820年)
ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第4番 イ短調 Op.23
ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第7番 ハ短調 Op.30-2
(ピリオド楽器)
武満徹:妖精の距離 ヴァイオリンとピアノのための
ペルト:フラトレス
シューベルト:ヴァイオリンとピアノのためのロンド ロ短調 D895
(モダン楽器)
(アンコール)
ベートーヴェン:スプリング・ソナタから第二楽章
ムローヴァは、ここのところ来日のたびにこうしたピリオドとモダンの弾き分けを披露しているようだ。ピリオドは古楽の演奏、モダンは近現代、あるいは、ロマン派以降であっても同時代のオリジナル楽器で演奏する――そういう弾き分けがだんだんと浸透してきて私たちを楽しませてくれる。

けれども、この日のムローヴァは、そこからもう一歩踏み込んだ演奏だったのだと思う。それはとてもフィジカルな挑戦であって、音楽の楽しみ、感動というものを峻厳かつ深遠に掘り下げるような演奏だった。
ピアノのビートソンも、ムローヴァの楽器に合わせてフォルテピアノとモダンのスタインウェイを弾き分ける。フォルテピアノは、1820年製作の6オクターヴ、ウィーンアクションのオリジナル。
前半の一曲目、4番のソナタが始まると、ガダニーニとフォルテピアノの音量と音色がとても調和していて、古典的が均整美がまずひときわ胸を打つ。モダン同志のデュオだと主役の取り合いになりがちで、あるいは、その逆にピアノが遠慮して活きてこないことが多い。それが、ピリオドだと音が溶け合いすばらしいバランス。
7番は、4つの楽章の全てがピアノだけで開始される。そのことがなぜかフォルテピアノだと鮮烈に印象づけられる。これもまたピリオドならではの対等のバランスが生む効果なのだろうか。それだけでなくそれぞれの楽器の音のコントラストが引き立ってくる。剣の鋭い切っ先が切り結ぶような、あるいは、名書家の雄渾な運筆が躍動するようなベートーヴェンの勇壮なハ短調。とてもピリオド演奏とは思えない力強さがあって、しかも、音の強弱や濃淡、勢い、運びが墨書のように引き立つ。

休憩時にはピアノが交代するが、後半の開演直前までフォルテピアノはステージ右隅に蓋を開けたままで展示されていた。ホールの粋な計らいといえる。もともとこのホールは、開演時以外は写真撮影はOK。会場係員は、ちょっと距離を置いて待機しているだけ。多くの聴衆が興味深げに楽器をのぞき込み写真に収めていた。
後半は、モダン楽器。
最初の武満ではっとさせられた。ドビュッシーの影響が濃厚な若い武満のピアニズムに続いて深々とヴィヴラートをかけた叙情味あふれるヴァイオリンが現れる。こうしたロングフレーズにムローヴァは、いかにもモダンらしいたっぷりととしたヴィヴラートをかける。モダンならではのパルシブな運弓や浮遊するようなフラジオレットと対比されて、いかにも日本的な湿り気たっぷりの叙情を込めた息の長いフレージングは鮮烈。
そこには、ピリオドとモダンの境界、混交を感じてしまう。いわば、ピリオドとモダンの奏法の汽水域のようなものだ。そのことは、続けて演奏されたペルトにも流れ込んでいく。清澄な古楽的な協和音に満ちた世界が次第に色彩を帯びてきて、魂がぶつかり合い、きしみ合うようなモダニズムの厳しい触感の世界が混じり合う。ピリオドを聴いた直後だからこそ感じ取りやすくなった、音のコラージュの美学なのかもしれない。
最後のシューベルトでは、ストラディヴァリウスの華麗な音色に覚醒される思いがした。ここに至ってフルカラーの世界で、シューベルトの歌とその技巧的なヴァリエーションの世界が艶やかに躍動する。
普通に考えるなら、シューベルトの方がピリオドになじみやすい。ムローヴァは、あえてベートーヴェンと逆転させることで、互いの美点を際立たせている。ベートーヴェンでは、表現力の幅が広いモダンだと労なくして通り過ぎてしまいがちな本質が見逃されがち。スリムで敏捷性に富むピリオド奏法で、筋肉質で贅肉のない引き締まったベートーヴェンが鮮やかだった。一方のシューベルトでは、ガット弦で得た奏法によって実にフレッシュなモダンボウの裁きで聴き手をわくわくさせてくれた。
だから、このプログラムは、ベートーヴェンとシューベルトがリバーシブル。ピリオド奏法を一段と掘り下げ、その奏法で得たものをまたモダンでの演奏にフィードバックする。聴き手にとっても、そうした奏法の交換によってフレッシュな感覚が研ぎ澄まされてくる。ピリオドが作曲と同時代の楽器での再現という、アカデミックな視点からもっと純粋で自由な音楽探求にまで踏み込んできた。
ムローヴァの進化・深化はとどまるところを知らない。

ヴィクトリア・ムローヴァ ヴァイオリン・リサイタル
2022年11月20日(日) 15:00
東京・築地 浜離宮朝日ホール
(1階10列9番)
ヴィクトリア・ムローヴァ(ヴァイオリン)
ガダニーニ(ガット弦)/ストラディヴァリウス「ジュールズ・フォーク」
アラスデア・ビートソン
フォルテピアノ/ヨハン・ゲオルグ・グレーバー製作(インスブルック1820年)
ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第4番 イ短調 Op.23
ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第7番 ハ短調 Op.30-2
(ピリオド楽器)
武満徹:妖精の距離 ヴァイオリンとピアノのための
ペルト:フラトレス
シューベルト:ヴァイオリンとピアノのためのロンド ロ短調 D895
(モダン楽器)
(アンコール)
ベートーヴェン:スプリング・ソナタから第二楽章
イゴール・レヴィットのベートーヴェン [コンサート]
レヴィットは聴いたことがありませんでした。たまたま見たチラシがどうしても気になってチケットを購入したのです。ベートーヴェンのソナタということでは、いま一番の注目のピアニストと知ったのはその後のことです。だから聴く前の頭の中は白紙のままでした。

まずはその指先の自在なコントロールに舌を巻いてしまいます。速くて軽やかで鍵盤に吸い付くように触れながらかけめぐる。自分の意志に従わせて、できないことは何もないと言わんばかり。しかも、決して《のりをこえず(「従心所欲不踰矩」)》 …という感覚。既成のベートーヴェンを壊すという新奇に発したわけではなく、己の自在な奏法を駆使して新たな造形を探っているという感覚です。
プログラムは、作品49のふたつの小ソナタも含めて比較的初期の作品を前半に配置し、後半を中期作品に焦点を移して《熱情》ソナタでクライマックスに至る。あたりまえの組み立てのようでいて、聴いていると壮麗な階梯を歩み登っていくような見事な構成のプログラムであるように思えてきます。ステップのひとつひとつの作品に新しい発見があってしかもそこには確かな上昇感覚をともなう。そういうプログラムビルダーとしての手腕にも舌を巻いてしまうのです。
最初の5番のソナタは、ベートーヴェンのハ短調。そういう出発点がそもそも意味深であるわけだけれど、野心にあふれた若さの発露は、一貫して上昇音型が支配的で、むしろ快活で叙情味もある。レヴィットの演奏も、そのスタートはいたって譜面に忠実だと感じます。
次の作品49のふたつは、ウィーン古典派の貴族的な日常情緒にあふれた2楽章形式の可憐な連作。レヴィットのタッチは、ここでも自在で軽やかなのですが、タッチや細やかなペダリングを弾き分けて繊細な色彩の綾があふれていてどこまでも聞き飽きない。最後のメヌエットから聴き慣れた七重奏曲のフレーズが聞こえてきて、思わずはっとさせておいて、そして小粋に終わる。

後半の22番のソナタが意表をつくものでした。
前半の作品49と同じ2楽章の小ソナタ。休憩をまたがってそういう連続性を保ち、しかも、第一楽章は〈テンポ・デ・メヌエット〉といかにもウィーン古典派の伝統を引き継ぐかのよう。ところが、いきなり細かい三連符の連続からこの曲の破調ぶりが展開されていく。振り返れば、前半の初期作品に秘められたベートーヴェンの創造希求がただならぬものだったと後になって気づかせる。この辺りからレヴィットのタッチにも加速度がつき始める。曲の終盤の音型やその粒立ち、響きの異形ぶりに目が醒める思いでした。
そうやって階段を登りつめる上昇気流に乗ったかのような《熱情》ソナタが圧巻でした。
もはや秘密の箱の蓋は開けられた。だから、冒頭の密やかな響きの序奏のなかに、こんなことでは済まないだろうという予感をまざまざと感じてしまっている。そこから始まるドラマの展開から、まるでレヴィットは周囲構わずスロットルを吹き上げるような鮮烈さです。もはやもう誰も止められない。その中に指先の技巧のめくるめく多様性は息もつかせぬもので、しかも、そのタッチは決して浅くなく低音弦も存分に深く沈み込む。圧倒的な快速《熱情》でした。
ベートーヴェンに何か精神性だとか、悲劇や実存だとか、そういう19世紀的な巨匠性を求めているわけではない演奏です。まだまだ何かやれると言わんばかり。いずれはこの指先でピリオド楽器やフォルテピアノでも弾いてほしいとも思いました。

確かに目の離せないピアニスト。また聴きたいと思わせるピアニスト。来年のシリーズⅢ、Ⅳのプログラムを眺めて、いったいどんな意表をつく企みが隠されているのだろうと感じ入ってしまいます。特にⅣの最後の3つのソナタは、いったいどう弾くというのでしょうか。

イゴール・レヴィット
ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ・サイクル・イン・ジャパン II
2022年11月19日(土)14:00
東京・四谷 紀尾井ホール
(1階 9列6番)
ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ
第5番ハ短調 op.10-1
第19番ト短調 op.49-1
第20番ト長調 op.49-2
第22番ヘ長調 op.54
第23番ヘ短調 op.57《熱情》
(アンコール)
シューマン:子供の情景op.15より第13曲「詩人のお話」

まずはその指先の自在なコントロールに舌を巻いてしまいます。速くて軽やかで鍵盤に吸い付くように触れながらかけめぐる。自分の意志に従わせて、できないことは何もないと言わんばかり。しかも、決して《のりをこえず(「従心所欲不踰矩」)》 …という感覚。既成のベートーヴェンを壊すという新奇に発したわけではなく、己の自在な奏法を駆使して新たな造形を探っているという感覚です。
プログラムは、作品49のふたつの小ソナタも含めて比較的初期の作品を前半に配置し、後半を中期作品に焦点を移して《熱情》ソナタでクライマックスに至る。あたりまえの組み立てのようでいて、聴いていると壮麗な階梯を歩み登っていくような見事な構成のプログラムであるように思えてきます。ステップのひとつひとつの作品に新しい発見があってしかもそこには確かな上昇感覚をともなう。そういうプログラムビルダーとしての手腕にも舌を巻いてしまうのです。
最初の5番のソナタは、ベートーヴェンのハ短調。そういう出発点がそもそも意味深であるわけだけれど、野心にあふれた若さの発露は、一貫して上昇音型が支配的で、むしろ快活で叙情味もある。レヴィットの演奏も、そのスタートはいたって譜面に忠実だと感じます。
次の作品49のふたつは、ウィーン古典派の貴族的な日常情緒にあふれた2楽章形式の可憐な連作。レヴィットのタッチは、ここでも自在で軽やかなのですが、タッチや細やかなペダリングを弾き分けて繊細な色彩の綾があふれていてどこまでも聞き飽きない。最後のメヌエットから聴き慣れた七重奏曲のフレーズが聞こえてきて、思わずはっとさせておいて、そして小粋に終わる。
後半の22番のソナタが意表をつくものでした。
前半の作品49と同じ2楽章の小ソナタ。休憩をまたがってそういう連続性を保ち、しかも、第一楽章は〈テンポ・デ・メヌエット〉といかにもウィーン古典派の伝統を引き継ぐかのよう。ところが、いきなり細かい三連符の連続からこの曲の破調ぶりが展開されていく。振り返れば、前半の初期作品に秘められたベートーヴェンの創造希求がただならぬものだったと後になって気づかせる。この辺りからレヴィットのタッチにも加速度がつき始める。曲の終盤の音型やその粒立ち、響きの異形ぶりに目が醒める思いでした。
そうやって階段を登りつめる上昇気流に乗ったかのような《熱情》ソナタが圧巻でした。
もはや秘密の箱の蓋は開けられた。だから、冒頭の密やかな響きの序奏のなかに、こんなことでは済まないだろうという予感をまざまざと感じてしまっている。そこから始まるドラマの展開から、まるでレヴィットは周囲構わずスロットルを吹き上げるような鮮烈さです。もはやもう誰も止められない。その中に指先の技巧のめくるめく多様性は息もつかせぬもので、しかも、そのタッチは決して浅くなく低音弦も存分に深く沈み込む。圧倒的な快速《熱情》でした。
ベートーヴェンに何か精神性だとか、悲劇や実存だとか、そういう19世紀的な巨匠性を求めているわけではない演奏です。まだまだ何かやれると言わんばかり。いずれはこの指先でピリオド楽器やフォルテピアノでも弾いてほしいとも思いました。

確かに目の離せないピアニスト。また聴きたいと思わせるピアニスト。来年のシリーズⅢ、Ⅳのプログラムを眺めて、いったいどんな意表をつく企みが隠されているのだろうと感じ入ってしまいます。特にⅣの最後の3つのソナタは、いったいどう弾くというのでしょうか。

イゴール・レヴィット
ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ・サイクル・イン・ジャパン II
2022年11月19日(土)14:00
東京・四谷 紀尾井ホール
(1階 9列6番)
ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ
第5番ハ短調 op.10-1
第19番ト短調 op.49-1
第20番ト長調 op.49-2
第22番ヘ長調 op.54
第23番ヘ短調 op.57《熱情》
(アンコール)
シューマン:子供の情景op.15より第13曲「詩人のお話」
タグ:イゴール・レヴィット
豆粒水準器 [オーディオ]
豆粒水準器でカートリッジの水平を根気よく追い込んでみました。

小さいのでシェルの上にちゃんと乗るし、自重は1gもありません。レコード盤面に落とした状態できちんと水平を確認ができます。

これで高さを合わせ直し、アーム軸方向の左右の傾きも厳格に調整しなおしました。従来はアームの水平は目視、左右の傾きはDL-103の白線に直角曲げ尺で合わせてました。加齢で目も怪しくなってきたし、レコード盤に乗せた状態での調整ではありませんでした。

水平、特に左右の傾きを追い込むと、やっぱり音が良くなった気がする。高音の粗さとか曖昧さが取れてすっと美しく伸びやかになる感じ。ノイズも静かになった気がする。
フェイスブックのオーディオのコミュで、このことを投稿したら、S字アームやJ字アームでは、レスト位置とレコード盤面に落とした状態では、左右の傾きが変わるというコメントをもらった。ストレートアームではそうならないのだそうだ。そんなことってあるのかな?って、理屈がぜんぜんわからないけど、その人はすごく自信ありげなコメント。どうなんでしょう。
いずれにせよ、実際にレコード盤面に乗せて確認することと、シビアな水準器合わせにしたことで、気持ちはだんぜんすっきりします。
小さいのでシェルの上にちゃんと乗るし、自重は1gもありません。レコード盤面に落とした状態できちんと水平を確認ができます。
これで高さを合わせ直し、アーム軸方向の左右の傾きも厳格に調整しなおしました。従来はアームの水平は目視、左右の傾きはDL-103の白線に直角曲げ尺で合わせてました。加齢で目も怪しくなってきたし、レコード盤に乗せた状態での調整ではありませんでした。
水平、特に左右の傾きを追い込むと、やっぱり音が良くなった気がする。高音の粗さとか曖昧さが取れてすっと美しく伸びやかになる感じ。ノイズも静かになった気がする。
フェイスブックのオーディオのコミュで、このことを投稿したら、S字アームやJ字アームでは、レスト位置とレコード盤面に落とした状態では、左右の傾きが変わるというコメントをもらった。ストレートアームではそうならないのだそうだ。そんなことってあるのかな?って、理屈がぜんぜんわからないけど、その人はすごく自信ありげなコメント。どうなんでしょう。
いずれにせよ、実際にレコード盤面に乗せて確認することと、シビアな水準器合わせにしたことで、気持ちはだんぜんすっきりします。
タグ:アナログプレーヤー
「ボリス・ゴドゥノフ」 (新国立劇場オペラ) [コンサート]
エグいオペラ。実にエグい。部分的にはえげつないと言えるほど。
何がエグいって、一番エグかったのが、ボリスの息子フョードル。
といっても歌手のことではない。黙役を演じた女優ユスティナ・ヴァシレフスカのこと。この演出ではフョードルと聖愚者を同一のものとして扱う。原作では、皇位継承に耐えない病弱の息子となっているが、このプロダクションでは重度の脳障害者。その障害者ぶりが真に迫っていて恐ろしいほど。
聖愚者というのは、佯狂者(ようきょうしゃ)とも訳されるが、正教会独特の聖人のことで、ボロをまとって人々の辱めを受けながら市井を放浪する聖人のこと。純真な心でものごとの真実や核心を見透す言辞を遠慮容赦なく発する。最高権力者にとってはその忌憚のない言辞が啓示ともなる。
息子が脳障害者というのは、大江健三郎の小説「個人的な体験」を思い浮かべるが、親としてのボリスのみならず、オペラ全体を見る聴衆にとっても心理的な負担となって重くのしかかる。この演出は決して史劇ではなく、物語を心象風景に遷し変えて人間の心の奥底に隠れたものを掘り下げていく心理劇になっている。ボリスは、先帝の幼い皇子ドミトリー暗殺の嫌疑を自ら抱え込み、子殺しの幻影が執拗につきまとい、皇位の正統性の不安に苛まれる孤独な権力者は、やがて自ら破滅していく。
そういうボリスの脅迫観念は敵役をことさらに酷薄残虐にし、側近の面従腹背におびえる不信はあっけないまでの裏切りとなって実現する。をことさらに酷薄残虐なものにする。辺境の居酒屋の場面は、ドミトリー皇子を僭称するグリゴリーの残虐性の発露という、これまたえげつない結末になる。そのえげつなさは、終幕には壮絶な殺戮場面となって倍加されていく。こうした場面の連続に客席は凍りつき、幕間の拍手を思わず忘れてしまうほど。
権力の正統性喪失後の大動乱、動乱収拾のための専制に付和雷同する民衆、権力に寄生する成り上がりども、側近政治と裏切り、酷薄残虐な支配階級とそれに仕返しする復讐報復の狂乱、支配層に取り入り暴虐の限りを尽くす傭兵たち。こうした黒々とした群像が忌まわしいまでに舞台上にあふれかえる。それが、ロシアという国の人格の真理であり、その投影であるかのように。まさにムソルグスキーの世界だ。
今のご時勢だから、どうしても現実のロシアを重ね合わせてしまう。こんなあからさまなプロダクションは今の欧米では無理で、日本でしか上演できないのかもしれない。ロシア人歌手が早くからキャンセルとなったのは無理もないような気さえする。来られなくなったのではなく、来なかったのではないか。
急遽代役としてたてられた歌手はいずれも期待を大きく上回った。タイトル役のギド・イェンティンスは、ワグナー歌手としてさすがの歌唱と演技。シュイスキー公爵役のアーノルド・ベズイエンはオランダ人だが、面従腹背の策謀家を歌って貫禄を示した。僧侶ビーメン役のゴデルジ・ジャネリーゼもジョージア出身だが、演技ばかりでなく、ロシアン・バスの音楽的魅力をふんだんに堪能させてくれた。
衣装も想像力に富んだもので、この演出を単なる読み替えものにしていない。幼児の大きな頭部、傭兵のオオカミなどの被り物、特に甲冑の醸し出す象徴性はアイデアとして素晴らしい。照明も演出や舞台に寄り添ったもので際立っていたし、心理を象徴させる装置もアクティブで見事。ただし、席が3列目と事実上の最前列だったせいかノイズがかなり耳についたのは残念。デジタル技術の性質上避けられないのか、投射映像が遅れてしまうそのズレも気になって仕方がなかった。
期待通りとはいかなかったのは、ピットのオーケストラ。
総監督の大野和士が自ら手勢の都響を指揮するのだから悪かろうはずもなく、大野の気配りの行き届いた力演なのだが、とにかく音量に乏しい。せっかく代役の歌手陣が期待以上に頑張ったのだからもったいない。
ウィーン国立歌劇場で聴いたときも最前列近くだったが、重厚かつ壮大な音響で全身が包まれ恍惚となるほどだった。バスチューバや銅鑼など低音楽器が大活躍するプロローグのみならず、要所要所で深々とした音色がロシアの漆黒の夜や民衆の嘆きを導き出し、ぶ厚い合唱や懊悩に満ちたルネ・パペの歌唱を深く彩っていた。ロシア歌劇はやっぱり低音の魅力。そういうウィーン・フィルと較べるべくもないと言ってしまえば身も蓋もないが、本当にそうなのか。確かに池松宏以下6台のコントラバスが入っていたのだけど、どうもピット内が寡兵との印象が拭えない。それがコロナ感染対策のせいだったとしたら、残念至極というしかない。

新国立劇場 開場25周年記念公演
モデスト・ムソルグスキー 「ボリス・ゴドゥノフ」
2022年11月17日(木) 19:00
東京・初台 新国立劇場
(1階 3列27番)
【指 揮】大野和士
【演 出】マリウシュ・トレリンスキ
【美 術】ボリス・クドルチカ
【衣 裳】ヴォイチェフ・ジエジッツ
【照 明】マルク・ハインツ
【映 像】バルテック・マシス
【ドラマトゥルク】マルチン・チェコ
【振 付】マチコ・プルサク
【ヘアメイクデザイン】ヴァルデマル・ポクロムスキ
【舞台監督】髙橋尚史
【ボリス・ゴドゥノフ】ギド・イェンティンス
【フョードル】小泉詠子
【クセニア】九嶋香奈枝
【乳母】金子美香
【ヴァシリー・シュイスキー公】アーノルド・ベズイエン
【アンドレイ・シチェルカーロフ】秋谷直之
【ピーメン】ゴデルジ・ジャネリーゼ
【グリゴリー・オトレピエフ(偽ドミトリー)】工藤和真
【ヴァルラーム】河野鉄平
【ミサイール】青地英幸
【女主人】清水華澄
【聖愚者の声】清水徹太郎
【ニキーティチ/役人】駒田敏章
【ミチューハ】大塚博章
【侍従】濱松孝行
【フョードル/聖愚者(黙役)ユスティナ・ヴァシレフスカ
【合唱指揮】冨平恭平
【合 唱】新国立劇場合唱団
【児童合唱】TOKYO FM 少年合唱団
【管弦楽】東京都交響楽団
共同制作:ポーランド国立歌劇場
何がエグいって、一番エグかったのが、ボリスの息子フョードル。
といっても歌手のことではない。黙役を演じた女優ユスティナ・ヴァシレフスカのこと。この演出ではフョードルと聖愚者を同一のものとして扱う。原作では、皇位継承に耐えない病弱の息子となっているが、このプロダクションでは重度の脳障害者。その障害者ぶりが真に迫っていて恐ろしいほど。
聖愚者というのは、佯狂者(ようきょうしゃ)とも訳されるが、正教会独特の聖人のことで、ボロをまとって人々の辱めを受けながら市井を放浪する聖人のこと。純真な心でものごとの真実や核心を見透す言辞を遠慮容赦なく発する。最高権力者にとってはその忌憚のない言辞が啓示ともなる。
息子が脳障害者というのは、大江健三郎の小説「個人的な体験」を思い浮かべるが、親としてのボリスのみならず、オペラ全体を見る聴衆にとっても心理的な負担となって重くのしかかる。この演出は決して史劇ではなく、物語を心象風景に遷し変えて人間の心の奥底に隠れたものを掘り下げていく心理劇になっている。ボリスは、先帝の幼い皇子ドミトリー暗殺の嫌疑を自ら抱え込み、子殺しの幻影が執拗につきまとい、皇位の正統性の不安に苛まれる孤独な権力者は、やがて自ら破滅していく。
そういうボリスの脅迫観念は敵役をことさらに酷薄残虐にし、側近の面従腹背におびえる不信はあっけないまでの裏切りとなって実現する。をことさらに酷薄残虐なものにする。辺境の居酒屋の場面は、ドミトリー皇子を僭称するグリゴリーの残虐性の発露という、これまたえげつない結末になる。そのえげつなさは、終幕には壮絶な殺戮場面となって倍加されていく。こうした場面の連続に客席は凍りつき、幕間の拍手を思わず忘れてしまうほど。
権力の正統性喪失後の大動乱、動乱収拾のための専制に付和雷同する民衆、権力に寄生する成り上がりども、側近政治と裏切り、酷薄残虐な支配階級とそれに仕返しする復讐報復の狂乱、支配層に取り入り暴虐の限りを尽くす傭兵たち。こうした黒々とした群像が忌まわしいまでに舞台上にあふれかえる。それが、ロシアという国の人格の真理であり、その投影であるかのように。まさにムソルグスキーの世界だ。
今のご時勢だから、どうしても現実のロシアを重ね合わせてしまう。こんなあからさまなプロダクションは今の欧米では無理で、日本でしか上演できないのかもしれない。ロシア人歌手が早くからキャンセルとなったのは無理もないような気さえする。来られなくなったのではなく、来なかったのではないか。
急遽代役としてたてられた歌手はいずれも期待を大きく上回った。タイトル役のギド・イェンティンスは、ワグナー歌手としてさすがの歌唱と演技。シュイスキー公爵役のアーノルド・ベズイエンはオランダ人だが、面従腹背の策謀家を歌って貫禄を示した。僧侶ビーメン役のゴデルジ・ジャネリーゼもジョージア出身だが、演技ばかりでなく、ロシアン・バスの音楽的魅力をふんだんに堪能させてくれた。
衣装も想像力に富んだもので、この演出を単なる読み替えものにしていない。幼児の大きな頭部、傭兵のオオカミなどの被り物、特に甲冑の醸し出す象徴性はアイデアとして素晴らしい。照明も演出や舞台に寄り添ったもので際立っていたし、心理を象徴させる装置もアクティブで見事。ただし、席が3列目と事実上の最前列だったせいかノイズがかなり耳についたのは残念。デジタル技術の性質上避けられないのか、投射映像が遅れてしまうそのズレも気になって仕方がなかった。
期待通りとはいかなかったのは、ピットのオーケストラ。
総監督の大野和士が自ら手勢の都響を指揮するのだから悪かろうはずもなく、大野の気配りの行き届いた力演なのだが、とにかく音量に乏しい。せっかく代役の歌手陣が期待以上に頑張ったのだからもったいない。
ウィーン国立歌劇場で聴いたときも最前列近くだったが、重厚かつ壮大な音響で全身が包まれ恍惚となるほどだった。バスチューバや銅鑼など低音楽器が大活躍するプロローグのみならず、要所要所で深々とした音色がロシアの漆黒の夜や民衆の嘆きを導き出し、ぶ厚い合唱や懊悩に満ちたルネ・パペの歌唱を深く彩っていた。ロシア歌劇はやっぱり低音の魅力。そういうウィーン・フィルと較べるべくもないと言ってしまえば身も蓋もないが、本当にそうなのか。確かに池松宏以下6台のコントラバスが入っていたのだけど、どうもピット内が寡兵との印象が拭えない。それがコロナ感染対策のせいだったとしたら、残念至極というしかない。

新国立劇場 開場25周年記念公演
モデスト・ムソルグスキー 「ボリス・ゴドゥノフ」
2022年11月17日(木) 19:00
東京・初台 新国立劇場
(1階 3列27番)
【指 揮】大野和士
【演 出】マリウシュ・トレリンスキ
【美 術】ボリス・クドルチカ
【衣 裳】ヴォイチェフ・ジエジッツ
【照 明】マルク・ハインツ
【映 像】バルテック・マシス
【ドラマトゥルク】マルチン・チェコ
【振 付】マチコ・プルサク
【ヘアメイクデザイン】ヴァルデマル・ポクロムスキ
【舞台監督】髙橋尚史
【ボリス・ゴドゥノフ】ギド・イェンティンス
【フョードル】小泉詠子
【クセニア】九嶋香奈枝
【乳母】金子美香
【ヴァシリー・シュイスキー公】アーノルド・ベズイエン
【アンドレイ・シチェルカーロフ】秋谷直之
【ピーメン】ゴデルジ・ジャネリーゼ
【グリゴリー・オトレピエフ(偽ドミトリー)】工藤和真
【ヴァルラーム】河野鉄平
【ミサイール】青地英幸
【女主人】清水華澄
【聖愚者の声】清水徹太郎
【ニキーティチ/役人】駒田敏章
【ミチューハ】大塚博章
【侍従】濱松孝行
【フョードル/聖愚者(黙役)ユスティナ・ヴァシレフスカ
【合唱指揮】冨平恭平
【合 唱】新国立劇場合唱団
【児童合唱】TOKYO FM 少年合唱団
【管弦楽】東京都交響楽団
共同制作:ポーランド国立歌劇場
快音レコード!持ち寄りオフ会〈後編〉 (横浜のMさん邸訪問記 その2) [オーディオ]
横浜のMさんを訪問しての「快音レコード!持ち寄りオフ会」で、Mさんがかけてくれたレコード再生にUNICORNさんがまさかのダメ出し(!?)というお話しの続きです。
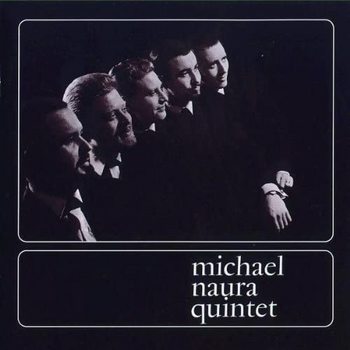
UNICORNさん曰く「これは再発盤だね。あの時代のヨーロッパオリジナル盤の音は、もっと艶やかな音のはず!」
ただでさえこのアナログ盤は入手難のレア盤。このディスクが後々の再発盤だったことは図星だったようでMさんが悔しがること悔しがること…。オリジナル盤ともなるとン十万円だそうで、…というよりもそもそも出物がなかったのだと嘆くことしきり。それにしても話しがトリヴィアルでついていけない(笑)。これよりもさらに良い音っていったいどんな音?という思いでした。

そのUNICORNさんが持参されたレコード。
こういうシンプルなものが、このシステムでは本領発揮。ダイナ・ショアのヴォーカルにくつろいだ色気があってとても艶めかしい。でもクラシック派の私にとっては若きプレヴィンのピアノがちょっと気になるところ。UNICORNさんも同じような感覚だったらしく、その気配を感じ取ったMさんが立ち上がります。
アクティブイコライザーを駆使して、盤ごとに一枚一枚音を聴きながら微妙に帯域バランスを調整していくと、わずかな調整で音のディテールが変わっていきます。その変化にも驚きますが、みるみるうちに音色のピントのようなものが絞り込まれていくことになお驚かされます。盤の音を聴くだけでなく、持参したレコードの持ち主の意見や、場合によってはその表情を読み取りながら調整していく。その知識、感性、技能の素晴らしさ。のみならず、茶事の亭主の《おもてなし》の神髄とも言うべき、ホストの心配りには感服させられてしまいます。

そういうボーカルとピアノ、あるいはアメリカンとヨーロピアンの録音の音色や空間の捉え方の違いといったことが、帯域の微妙なバランスの合わせ方で浮かび上がってくるということは、エヴァンス率いるピアノトリオと北欧の美神とが出会ったこのディスクでも同じ。まさに「降っても晴れても」という感じ。

これも、いかにも女性ボーカルに通じたLotus Rootsさんらしい選択。濃度のある声音はかなり中性的。これもまたとてもシンプルで、しかもアコースティック。社会派シンガーソングライターらしい毅然とした芯の強さには色気というものは無縁ですが、歌手との距離をとても近寄せて親しみを感じさせるサウンドです。

いたちょうさんのお得意の中本マリ。最近仕入れた中古盤だそうですが、東芝EMIのプロユースシリーズ。東芝の「不良社員」こと行方洋一氏の仕掛けた高音質シリーズですが、その音の凄みにはMさんも舌を巻いたご様子。この頃の日本のオーディオ界の元気の良さをしのばせる…そんな団塊世代の感慨にふけっている場合じゃないと思ったほど。

やはりいたちょうさんお得意の中森明菜。これも45回転の華が満開という感じでキレキレのパーカッション。これには、今度はMさんが「センターボーカルが奥に引っ込む録音が残念」とダメ出し。Mさんによると、80年代の録音のある種の流行だったのだそうです。

その意味で対象的なのが、始めにMさんがかけてくれた南沙織。これを聴いたUNICORNさんが「南沙織ってこんなにいい声だったの?」と思わぬことを口走ります。南沙織といえば我が世代にとっては青春そのもの。学生時代からジャズ一辺倒だったUNICORNさんの世間からのズレように一同爆笑。たまらずMさんが我らがシンシアのディープなウンチクをひとくさり。Mさんは学生時代に、学園祭のコンサートでPAを担当しその縁でデビュー間もない彼女に相当密着していたそうです。オーディオキャリアはその頃からのことで筋金入りなのです。

こうなるとクラシック派の私もいろいろ気になってきます。これもMさんが最初にかけてくれたディスク。
ここでもMさんのトーンコントロールの冴えが光ります。みるみるうちに音色が私好みになっていく。ライブの空気感がすーっと沸き立ってきます。ハタから見るとクラシック派というのは、いわゆるピラミッド型の抑えた高域を好むというように見られるようですが、本来はまったく逆なのです。
面白かったのは、定位とか立体感覚の違い。Mさんは、デュプレとバレンボイムが泣き別れだと仰ったのですが、聴かせていただくとけっこう二人は中央に寄り添うように定位します。ただし、リスニングポジションをあえてセンターから外すと音像がスピーカー中央から外れてしまいます。どうやらMさんは、このシステムではあえてそういう音像の焦点合わせに頓着していない。それがこのマッキンの存在価値ではない、と言わんばかり。というのも以前に別の部屋で聴かせていただいたパラゴンでは見事なまでの3D空間だったからです。

私も、始めのころにはセンターポジションにこだわっていましたが、いろいろ聴かせていただくうちに、だんだんとツボのようなものが別にあると感じてきました。センターにこだわるあまり後ろに下がると、背後のワインセラーのガラスが反射面となって中低域をぼかしてしまいます。分厚いガラスは触ってみても大音量にもびくともしませんが、一次反射面になって位相が交差してしまうのでしょう。
そのことに気がついて、センターへのこだわりを捨てて前方のかなり右寄りのソファーに移動しました。かなり右スピーカー正面に近くなり定位が崩れてしまいますが、むしろここの音がおいしい。鮮度が高く、かつ、濃厚な音色の旨味があります。気に入って後半はずっとここで聴いていました。後でMさんにその話しをすると、Mさんにとっては、実はそのソファーがスイートスポットなんだとか。何だか拍子抜けしてしまいました(笑)。

オフ会を終えて、中華街に繰り出して、懇親会。ここでも、オーディオとか歌謡界の変遷とか、いろいろな話題に花が咲きました。ちょっとここでは書き切れないほど中身の濃いオフ会で、勉強にもなりましたし、また、それ以上に仲間がこうして集えることの楽しさがぎゅうぎゅうに詰まった一日だったのです。
(終わり)
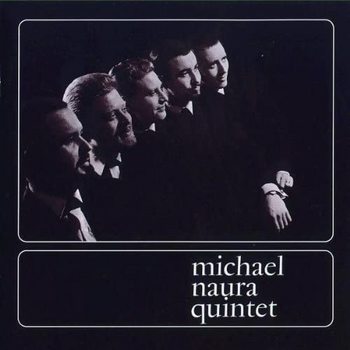
UNICORNさん曰く「これは再発盤だね。あの時代のヨーロッパオリジナル盤の音は、もっと艶やかな音のはず!」
ただでさえこのアナログ盤は入手難のレア盤。このディスクが後々の再発盤だったことは図星だったようでMさんが悔しがること悔しがること…。オリジナル盤ともなるとン十万円だそうで、…というよりもそもそも出物がなかったのだと嘆くことしきり。それにしても話しがトリヴィアルでついていけない(笑)。これよりもさらに良い音っていったいどんな音?という思いでした。

そのUNICORNさんが持参されたレコード。
こういうシンプルなものが、このシステムでは本領発揮。ダイナ・ショアのヴォーカルにくつろいだ色気があってとても艶めかしい。でもクラシック派の私にとっては若きプレヴィンのピアノがちょっと気になるところ。UNICORNさんも同じような感覚だったらしく、その気配を感じ取ったMさんが立ち上がります。
アクティブイコライザーを駆使して、盤ごとに一枚一枚音を聴きながら微妙に帯域バランスを調整していくと、わずかな調整で音のディテールが変わっていきます。その変化にも驚きますが、みるみるうちに音色のピントのようなものが絞り込まれていくことになお驚かされます。盤の音を聴くだけでなく、持参したレコードの持ち主の意見や、場合によってはその表情を読み取りながら調整していく。その知識、感性、技能の素晴らしさ。のみならず、茶事の亭主の《おもてなし》の神髄とも言うべき、ホストの心配りには感服させられてしまいます。

そういうボーカルとピアノ、あるいはアメリカンとヨーロピアンの録音の音色や空間の捉え方の違いといったことが、帯域の微妙なバランスの合わせ方で浮かび上がってくるということは、エヴァンス率いるピアノトリオと北欧の美神とが出会ったこのディスクでも同じ。まさに「降っても晴れても」という感じ。

これも、いかにも女性ボーカルに通じたLotus Rootsさんらしい選択。濃度のある声音はかなり中性的。これもまたとてもシンプルで、しかもアコースティック。社会派シンガーソングライターらしい毅然とした芯の強さには色気というものは無縁ですが、歌手との距離をとても近寄せて親しみを感じさせるサウンドです。

いたちょうさんのお得意の中本マリ。最近仕入れた中古盤だそうですが、東芝EMIのプロユースシリーズ。東芝の「不良社員」こと行方洋一氏の仕掛けた高音質シリーズですが、その音の凄みにはMさんも舌を巻いたご様子。この頃の日本のオーディオ界の元気の良さをしのばせる…そんな団塊世代の感慨にふけっている場合じゃないと思ったほど。

やはりいたちょうさんお得意の中森明菜。これも45回転の華が満開という感じでキレキレのパーカッション。これには、今度はMさんが「センターボーカルが奥に引っ込む録音が残念」とダメ出し。Mさんによると、80年代の録音のある種の流行だったのだそうです。

その意味で対象的なのが、始めにMさんがかけてくれた南沙織。これを聴いたUNICORNさんが「南沙織ってこんなにいい声だったの?」と思わぬことを口走ります。南沙織といえば我が世代にとっては青春そのもの。学生時代からジャズ一辺倒だったUNICORNさんの世間からのズレように一同爆笑。たまらずMさんが我らがシンシアのディープなウンチクをひとくさり。Mさんは学生時代に、学園祭のコンサートでPAを担当しその縁でデビュー間もない彼女に相当密着していたそうです。オーディオキャリアはその頃からのことで筋金入りなのです。

こうなるとクラシック派の私もいろいろ気になってきます。これもMさんが最初にかけてくれたディスク。
ここでもMさんのトーンコントロールの冴えが光ります。みるみるうちに音色が私好みになっていく。ライブの空気感がすーっと沸き立ってきます。ハタから見るとクラシック派というのは、いわゆるピラミッド型の抑えた高域を好むというように見られるようですが、本来はまったく逆なのです。
面白かったのは、定位とか立体感覚の違い。Mさんは、デュプレとバレンボイムが泣き別れだと仰ったのですが、聴かせていただくとけっこう二人は中央に寄り添うように定位します。ただし、リスニングポジションをあえてセンターから外すと音像がスピーカー中央から外れてしまいます。どうやらMさんは、このシステムではあえてそういう音像の焦点合わせに頓着していない。それがこのマッキンの存在価値ではない、と言わんばかり。というのも以前に別の部屋で聴かせていただいたパラゴンでは見事なまでの3D空間だったからです。
私も、始めのころにはセンターポジションにこだわっていましたが、いろいろ聴かせていただくうちに、だんだんとツボのようなものが別にあると感じてきました。センターにこだわるあまり後ろに下がると、背後のワインセラーのガラスが反射面となって中低域をぼかしてしまいます。分厚いガラスは触ってみても大音量にもびくともしませんが、一次反射面になって位相が交差してしまうのでしょう。
そのことに気がついて、センターへのこだわりを捨てて前方のかなり右寄りのソファーに移動しました。かなり右スピーカー正面に近くなり定位が崩れてしまいますが、むしろここの音がおいしい。鮮度が高く、かつ、濃厚な音色の旨味があります。気に入って後半はずっとここで聴いていました。後でMさんにその話しをすると、Mさんにとっては、実はそのソファーがスイートスポットなんだとか。何だか拍子抜けしてしまいました(笑)。
オフ会を終えて、中華街に繰り出して、懇親会。ここでも、オーディオとか歌謡界の変遷とか、いろいろな話題に花が咲きました。ちょっとここでは書き切れないほど中身の濃いオフ会で、勉強にもなりましたし、また、それ以上に仲間がこうして集えることの楽しさがぎゅうぎゅうに詰まった一日だったのです。
(終わり)
快音レコード!持ち寄りオフ会〈前編〉 (横浜のMさん邸訪問記 その1) [オーディオ]
ほんとうに久しぶりの訪問でした。
ひょんなことからメッセージのやりとりが始まって、しばらくご無沙汰をしてしまった横浜のMさんの会心の音をお聴かせくださいとお願いしたら快諾。それでは「快音レコード!持ち寄りオフ会」をやりましょうというご提案になりました。これが、マニアックななかにも賑やかで実に楽しい会になりました。
地下鉄・元町中華街の駅で待ち合わせ。集まったのは、Lotus Rootsさん、いたちょうさん、UNICORNさん、それと私を加えて四人。それぞれが思い思いのLPレコードを持って集合です。

Mさんのサロンルームは大きくて広い。その一角にマッキントッシュの巨大なスピーカーとパワーアンプを中心にしたシステムが大きな外窓の前に構えています。弩級システムですが、それが部屋の傍らに納まっています。スピーカーは背丈を超えるツィタータワーですが、それを超える天井の高さがあって堂々としていてしかも余裕のあるセッティング。

プレーヤーシステムは、最新の光カートリッジとテクニクスのDDターンテーブルを特注の黒檀のケースに納めています。その贅沢さには圧倒されますが、鏡面仕上げの美しい木目を見るとその美麗で優雅な姿に不思議と心が和みます。
光電型カートリッジというのは昔からあったのですが、昨今の光センサー素子や発光ダイオードの技術的躍進もあって最近になって脚光を浴びているようです。原理は変わっておらず、赤外線LEDの光をカンチレバーに直結した遮光板を通して受光センサーが受ける。遮光板の振動によって光の強度が変わる。受けたその光の強弱に応じて、センサー(光ダイオード)が発電するというもの。デジタルと混同誤解されがちですが、まったくのアナログです。
通常のMM型やMC型は電磁誘導を原理としていて、振動の速度変化に応じて発電する《速度型》ですが、光電式は針先の変位(無信号時の位置からのずれ)に比例して起電力を生じる《変位型》です。原理が違うのでレコードに刻まれた溝に対する周波数特性が違ってきて、全く別のフォノイコライザーが必要になります。このことも光カートリッジが普及しなかったひとつの要因になりました。
速度型のカートリッジの出力電圧の周波数特性をフラットにするには、針先の振動速度の周波数特性がフラット(等速度録音)になるようにすればいいわけです。ところが等速度にすると高域の振幅は極めて小さくなりノイズに埋もれてしまうし、低域では逆に大きくなり過ぎてカートリッジが耐えられない。そこで高域と低域は、変位を周波数に関係なく一定(等変位録音)にすればよい。これがRIAAを始めとする録音再生規格の原理になっています。つまり、録音特性は1kHzを中心として等速度と等変位の折衷になっているというわけです。
というわけで、RIAAは速度型に真ん中(1KHz)を合わせた規格なわけですが、変位型の光カートリッジは立場が逆転してしまいます。それで別の特別なフォノアンプが必要になってしまうわけです。

一方、スピーカーの方ですが、こちらにはアクティブ・イコライザー・ユニットが付属しています。かなり独特のユニット構成を持った巨大なスピーカーシステムなので部屋の影響も大きいということでシステムの一部としてイコライザーが入っているのだそうです。といっても特殊なものではないようで、5ポイント(70Hz、150Hz、300Hz、600Hz、1.2kHz)でそれぞれをブースト/カットするというものだそうです。

改めてMさんのシステム構成をご紹介すると、光カートリッジ→専用イコライザーアンプ→マランツ#7(ライン入力)→マッキントッシュパワーアンプ→アクティブイコライザー→マッキントッシュ(XRT26)スピーカー、ということになります。
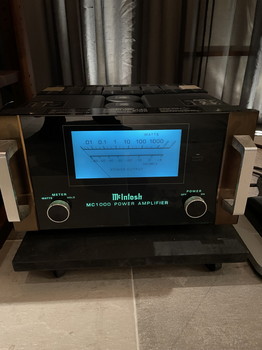
まずは邂逅を祝して乾杯。
互いの自己紹介や近況報告などをしているうちに話しが盛り上がり、いささか年寄りじみた病気自慢まで始まってしまいなかなか試聴ステージに進みません(笑)。ようやく思い出したように、せっかく持ち寄ったのだから聴きましょうということになりました。ところが誰もが遠慮して譲り合い。そこはやはりご主人からということで、Mさんが笑いながら「それでは模範演技ということで失礼いたします」と。いつもながら、どこまでも謙虚なMさんらしい。
持ち出したのは、どれもがレジェンド的名盤・名録音。
その再生音には圧倒されます。
かなりの音量ですが、いわゆる爆音ではありません。アコースティックな生演奏と同じでリスニングポジションで、平均で80dB台。ピークでも100dBを超えることはありません。それでいて、音が抜けるように鮮明で明快。低域も音程やリズムが明瞭でくぐもらず、立ち上がり立ち下がりのスピードが速い。リズムセクションも大迫力で、床は石造りのしっかりしたものでびくともしないのに、振動が身体にじかに伝わってくる。目も醒めるようなスーパーサウンドです。
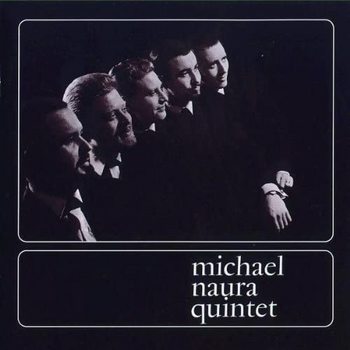
このディスクには、思わずのけぞるほどの衝撃を受けました。。
いかにもヨーロ・ジャズともいうべき、クリーンな空間表現と個々の楽器の鮮烈で生々しい音像はとても60年代初めの録音とは思えません。特にアルトサックスの肉感はたまりません。リズムセクションの刻むビートもリアルで渋い光沢の甲冑のような重量感があります。
…ところが、ジャズ通のUNICORNさんから意外なダメ出しが…!!
(続く)
ひょんなことからメッセージのやりとりが始まって、しばらくご無沙汰をしてしまった横浜のMさんの会心の音をお聴かせくださいとお願いしたら快諾。それでは「快音レコード!持ち寄りオフ会」をやりましょうというご提案になりました。これが、マニアックななかにも賑やかで実に楽しい会になりました。
地下鉄・元町中華街の駅で待ち合わせ。集まったのは、Lotus Rootsさん、いたちょうさん、UNICORNさん、それと私を加えて四人。それぞれが思い思いのLPレコードを持って集合です。
Mさんのサロンルームは大きくて広い。その一角にマッキントッシュの巨大なスピーカーとパワーアンプを中心にしたシステムが大きな外窓の前に構えています。弩級システムですが、それが部屋の傍らに納まっています。スピーカーは背丈を超えるツィタータワーですが、それを超える天井の高さがあって堂々としていてしかも余裕のあるセッティング。
プレーヤーシステムは、最新の光カートリッジとテクニクスのDDターンテーブルを特注の黒檀のケースに納めています。その贅沢さには圧倒されますが、鏡面仕上げの美しい木目を見るとその美麗で優雅な姿に不思議と心が和みます。
光電型カートリッジというのは昔からあったのですが、昨今の光センサー素子や発光ダイオードの技術的躍進もあって最近になって脚光を浴びているようです。原理は変わっておらず、赤外線LEDの光をカンチレバーに直結した遮光板を通して受光センサーが受ける。遮光板の振動によって光の強度が変わる。受けたその光の強弱に応じて、センサー(光ダイオード)が発電するというもの。デジタルと混同誤解されがちですが、まったくのアナログです。
通常のMM型やMC型は電磁誘導を原理としていて、振動の速度変化に応じて発電する《速度型》ですが、光電式は針先の変位(無信号時の位置からのずれ)に比例して起電力を生じる《変位型》です。原理が違うのでレコードに刻まれた溝に対する周波数特性が違ってきて、全く別のフォノイコライザーが必要になります。このことも光カートリッジが普及しなかったひとつの要因になりました。
速度型のカートリッジの出力電圧の周波数特性をフラットにするには、針先の振動速度の周波数特性がフラット(等速度録音)になるようにすればいいわけです。ところが等速度にすると高域の振幅は極めて小さくなりノイズに埋もれてしまうし、低域では逆に大きくなり過ぎてカートリッジが耐えられない。そこで高域と低域は、変位を周波数に関係なく一定(等変位録音)にすればよい。これがRIAAを始めとする録音再生規格の原理になっています。つまり、録音特性は1kHzを中心として等速度と等変位の折衷になっているというわけです。
というわけで、RIAAは速度型に真ん中(1KHz)を合わせた規格なわけですが、変位型の光カートリッジは立場が逆転してしまいます。それで別の特別なフォノアンプが必要になってしまうわけです。
一方、スピーカーの方ですが、こちらにはアクティブ・イコライザー・ユニットが付属しています。かなり独特のユニット構成を持った巨大なスピーカーシステムなので部屋の影響も大きいということでシステムの一部としてイコライザーが入っているのだそうです。といっても特殊なものではないようで、5ポイント(70Hz、150Hz、300Hz、600Hz、1.2kHz)でそれぞれをブースト/カットするというものだそうです。

改めてMさんのシステム構成をご紹介すると、光カートリッジ→専用イコライザーアンプ→マランツ#7(ライン入力)→マッキントッシュパワーアンプ→アクティブイコライザー→マッキントッシュ(XRT26)スピーカー、ということになります。
まずは邂逅を祝して乾杯。
互いの自己紹介や近況報告などをしているうちに話しが盛り上がり、いささか年寄りじみた病気自慢まで始まってしまいなかなか試聴ステージに進みません(笑)。ようやく思い出したように、せっかく持ち寄ったのだから聴きましょうということになりました。ところが誰もが遠慮して譲り合い。そこはやはりご主人からということで、Mさんが笑いながら「それでは模範演技ということで失礼いたします」と。いつもながら、どこまでも謙虚なMさんらしい。
持ち出したのは、どれもがレジェンド的名盤・名録音。
その再生音には圧倒されます。
かなりの音量ですが、いわゆる爆音ではありません。アコースティックな生演奏と同じでリスニングポジションで、平均で80dB台。ピークでも100dBを超えることはありません。それでいて、音が抜けるように鮮明で明快。低域も音程やリズムが明瞭でくぐもらず、立ち上がり立ち下がりのスピードが速い。リズムセクションも大迫力で、床は石造りのしっかりしたものでびくともしないのに、振動が身体にじかに伝わってくる。目も醒めるようなスーパーサウンドです。
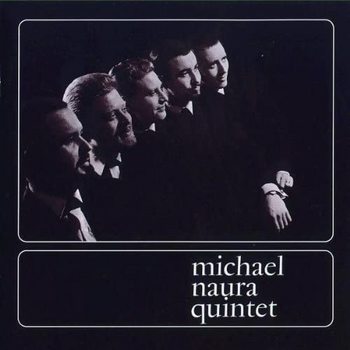
このディスクには、思わずのけぞるほどの衝撃を受けました。。
いかにもヨーロ・ジャズともいうべき、クリーンな空間表現と個々の楽器の鮮烈で生々しい音像はとても60年代初めの録音とは思えません。特にアルトサックスの肉感はたまりません。リズムセクションの刻むビートもリアルで渋い光沢の甲冑のような重量感があります。
…ところが、ジャズ通のUNICORNさんから意外なダメ出しが…!!
(続く)
古典美とエスプリ (堀正文・清水和音-名曲リサイタル・サロン) [コンサート]
芸劇ブランチコンサートにはふたつのシリーズがあって、一方は清水和音さんがコーディネートする「名曲ラウンジ」、そしてこちらが八塩圭子さん司会の「名曲リサイタル・サロン」。どちらも若手中心でそれを清水さんなどのベテランがさりげなく支えるという感じ。特に「清水和音の名曲ラウンジ」は、清水さんとそのお弟子さんが多く出演します。

ところがこの日は、日本の音楽界の重鎮ともいうべき堀さんの登場。長くN響のコンマスを務め、現在は、桐朋学園大学の主任教授。桐朋学園の前身である「子供のための音楽教室」の出身の清水さんより、一回り上の大先輩ということになります。堀さんとのリサイタルパートナーとしては、清水さんが新進気鋭の頃から起用だそうです。以来、40年近く各地で公演を重ねられてきたのだとか。堀さんは寡黙な音楽家で知られ、この日も清水さんの饒舌ぶりは相変わらずなのですが、ここかしこに大先輩への気遣いがあるところがいつもとは違います。
1時間きっかりのプログラムは、ヴァイオリン・ソナタの名曲がふたつ。新人のよく取り上げる曲ですし、よく知られた名曲ということではまるでクラシックにはふだん馴染みのない地方の小都市での公演のような鉄壁の演目。大ベテランの堀さんの技巧の安定感ということもあって、正直言ってあまり緊張感もなく聴き始めたのです。
スプリング・ソナタは、小春日和の陽光あふれる穏やかな昼前にはとてもふさわしい。この曲を聴いていると、ただもうそれだけで幸せな気分になります。とはいえ近年の演奏には、もっとベートーヴェン的な野心とか先鋭さを求めるものも多くなっています。一方で、あくまでもヴァイオリンの美音を載せた多幸感そのものを追求する若手やベテランも少なくない。そんなことが、いろいろと頭をよぎります。
ところが、ずっと聴いていると、堀さんと清水さんの演奏にはどこかそういう二分類的なところが皆無だと感じてきて、ふと不思議な気がしてきます。中庸とか均衡とか、ましてやどっちつかずの凡庸ということでは決してない。ベートーヴェンのこの曲の魅力がすべて織り込まれていて、それがじわじわと滲み出てくるような味わい深さを感じます。
そのことは二曲目のフランクのソナタではっきりとしてきます。
若手もベテランもこぞって取り上げる名曲中の名曲ですが、デュオということでは存外に難しい。インタープレー的なところが随所にあって、それは単なる掛け合いというよりは、一方が誘い出し、もう一方が呼応するようなあうんの呼吸もある。そのことは冒頭のピアノの音型の繰り返しに誘い出されるヴァイオリンの主題提示から早くも始まります。だからデュオとしてよほど互いの息づかいや感情の起伏が合っていないと難しいのです。
フランクの古典的形式感は、もちろんベートーヴェンの追求を規範としていますが、それを循環形式という形でより堅固な均整美にまで高めています。それと同時にあふれるようなロマンチシズムが随所にあって、そういう相反するふたつの要素をバランスさせることだけでも、ふたりの息がぴたりと合っている必要がある。ルバートやアッチェランドが行き過ぎると、形式美のみならずふたりの均衡まで崩れてしまうし、それを安全に合わせようとすればドラマが消えてしまう。
堀さんの演奏は、とても折り目正しくて正統的。音符の長さ、アーティキュレーションが実に明快。音色もクリアで濃密でありながら余計なものが全くまとわりついてきません。淡々とした地味な演奏でいるように見えて、随所で強弱をつけテンポを揺らしていて繊細な陰影に満ちています。第二楽章の終結部のクレッシェンドとアッチェランドも品位を保ちながら、しかも素晴らしい盛り上がりで、思わず拍手を入れたくなるほど。
ふたりはまったく目を合わせることもないのですが、コミュニケーションは絶対的で驚くほど安定しています。堀さんの行き届いた起伏に合わせて清水さんのピアノにも自由でなおかつ懐の深い遊びがあります。こんなに安らかで、しかも、気持ちがのびやかなフランクは、まるで初めて聴いたかのよう。いろいろな発見があって感慨深いものがあります。
だから聴き終わっても、余韻が強く残ります。気持ちのなかで、聴き慣れた曲のはずなのにあれやこれやと思いがめぐってしまうことに戸惑うほど。家に帰ってから、LPやらCDを取り出して、あの巨匠はどうだったのかとか、好きでよく聴く演奏家、あるいは評判の若手とかの新しい録音はどこがどうだったのかしらと、しばらくは頭の整理がつきませんでした。
おいしいパンケーキとかベルギーワッフルは、焼きたてのシンプルなプレーンに限る…そんな子供っぽい連想しか思い浮かびませんが、フランクというのはそういう作曲家だったのかもしれません。

芸劇ブランチコンサート
名曲リサイタル・サロン
第21回 堀 正文
2022年11月9日(水) 11:00~
東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール
(1階M列20番)
堀正文(ヴァイオリン)
清水和音(ピアノ)
八塩圭子(ナビゲーター)
ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ 第5番 へ長調 「春」 op.24
フランク:ヴァイオリン・ソナタ イ長調

ところがこの日は、日本の音楽界の重鎮ともいうべき堀さんの登場。長くN響のコンマスを務め、現在は、桐朋学園大学の主任教授。桐朋学園の前身である「子供のための音楽教室」の出身の清水さんより、一回り上の大先輩ということになります。堀さんとのリサイタルパートナーとしては、清水さんが新進気鋭の頃から起用だそうです。以来、40年近く各地で公演を重ねられてきたのだとか。堀さんは寡黙な音楽家で知られ、この日も清水さんの饒舌ぶりは相変わらずなのですが、ここかしこに大先輩への気遣いがあるところがいつもとは違います。
1時間きっかりのプログラムは、ヴァイオリン・ソナタの名曲がふたつ。新人のよく取り上げる曲ですし、よく知られた名曲ということではまるでクラシックにはふだん馴染みのない地方の小都市での公演のような鉄壁の演目。大ベテランの堀さんの技巧の安定感ということもあって、正直言ってあまり緊張感もなく聴き始めたのです。
スプリング・ソナタは、小春日和の陽光あふれる穏やかな昼前にはとてもふさわしい。この曲を聴いていると、ただもうそれだけで幸せな気分になります。とはいえ近年の演奏には、もっとベートーヴェン的な野心とか先鋭さを求めるものも多くなっています。一方で、あくまでもヴァイオリンの美音を載せた多幸感そのものを追求する若手やベテランも少なくない。そんなことが、いろいろと頭をよぎります。
ところが、ずっと聴いていると、堀さんと清水さんの演奏にはどこかそういう二分類的なところが皆無だと感じてきて、ふと不思議な気がしてきます。中庸とか均衡とか、ましてやどっちつかずの凡庸ということでは決してない。ベートーヴェンのこの曲の魅力がすべて織り込まれていて、それがじわじわと滲み出てくるような味わい深さを感じます。
そのことは二曲目のフランクのソナタではっきりとしてきます。
若手もベテランもこぞって取り上げる名曲中の名曲ですが、デュオということでは存外に難しい。インタープレー的なところが随所にあって、それは単なる掛け合いというよりは、一方が誘い出し、もう一方が呼応するようなあうんの呼吸もある。そのことは冒頭のピアノの音型の繰り返しに誘い出されるヴァイオリンの主題提示から早くも始まります。だからデュオとしてよほど互いの息づかいや感情の起伏が合っていないと難しいのです。
フランクの古典的形式感は、もちろんベートーヴェンの追求を規範としていますが、それを循環形式という形でより堅固な均整美にまで高めています。それと同時にあふれるようなロマンチシズムが随所にあって、そういう相反するふたつの要素をバランスさせることだけでも、ふたりの息がぴたりと合っている必要がある。ルバートやアッチェランドが行き過ぎると、形式美のみならずふたりの均衡まで崩れてしまうし、それを安全に合わせようとすればドラマが消えてしまう。
堀さんの演奏は、とても折り目正しくて正統的。音符の長さ、アーティキュレーションが実に明快。音色もクリアで濃密でありながら余計なものが全くまとわりついてきません。淡々とした地味な演奏でいるように見えて、随所で強弱をつけテンポを揺らしていて繊細な陰影に満ちています。第二楽章の終結部のクレッシェンドとアッチェランドも品位を保ちながら、しかも素晴らしい盛り上がりで、思わず拍手を入れたくなるほど。
ふたりはまったく目を合わせることもないのですが、コミュニケーションは絶対的で驚くほど安定しています。堀さんの行き届いた起伏に合わせて清水さんのピアノにも自由でなおかつ懐の深い遊びがあります。こんなに安らかで、しかも、気持ちがのびやかなフランクは、まるで初めて聴いたかのよう。いろいろな発見があって感慨深いものがあります。
だから聴き終わっても、余韻が強く残ります。気持ちのなかで、聴き慣れた曲のはずなのにあれやこれやと思いがめぐってしまうことに戸惑うほど。家に帰ってから、LPやらCDを取り出して、あの巨匠はどうだったのかとか、好きでよく聴く演奏家、あるいは評判の若手とかの新しい録音はどこがどうだったのかしらと、しばらくは頭の整理がつきませんでした。
おいしいパンケーキとかベルギーワッフルは、焼きたてのシンプルなプレーンに限る…そんな子供っぽい連想しか思い浮かびませんが、フランクというのはそういう作曲家だったのかもしれません。

芸劇ブランチコンサート
名曲リサイタル・サロン
第21回 堀 正文
2022年11月9日(水) 11:00~
東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール
(1階M列20番)
堀正文(ヴァイオリン)
清水和音(ピアノ)
八塩圭子(ナビゲーター)
ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ 第5番 へ長調 「春」 op.24
フランク:ヴァイオリン・ソナタ イ長調



