「日本の建築」(隈 研吾 著)読了 [読書]
隈研吾といえば、今の日本人の建築家のなかでおそらく最も多忙な人だろう。本書は、そのひとが八年かけて書いたという。

日本の建築が、西欧の様式建築やモダニズム建築と出会って150年。それ以来の建築家たちの覚醒、葛藤や迷い、自己矛盾、変節を、忖度なく、徹底的に読み解いた日本現代建築史。
その思考思索の決着のように自身の建築へと帰着する。隈研吾の建築は、木材などの自然素材を多用し、居丈高なタテの巨大な柱が無い。和のモダニズム…とでも呼んでよいような、そういう隈の設計思想を理解するうえでも格好の書。
.jpg)
著者である自身は、巻末の「おわりに」で、『従来の日本建築史の退屈は、二項対立にあると感じた』と書いている。
しかし、本書の面白さは《二項対立》にある。
よくも、まあ、これだけの対立項目があるかと感心するほどに多面的で様々な対立が建築の歴史にあるのかと、もうそれだけで面白く、ハラハラ、ドキドキの連続だ。退屈するどころではない。
日本の現代建築の始まりに必ず登場するのが《桂離宮》と「モダニズム建築の巨匠」ブルーノ・タウト。しかし、そこにはタウトと、鉄とコンクリートを多用したシンプルでキレのある形態を全面に押し出してタウトを時代遅れとしてモダニズムの主役から引きずり落とした「フォルマリズム」のコルビジェらとの対立があるという。タウトは、その桂離宮を大礼賛した一方で、それと対比させるように日光東照宮をこきおろしたことはよく知られているが、そこには質実・清貧主義vs権威的様式主義の二項対立があったという。
…という具合で、のっけから二項対立の連鎖。反ファシズムvs反アメリカ、弥生vs縄文、西の大陸的合理性vs東の武士的合理性、関東の大きさvs関西の小ささ、北欧的後進性vs西欧的産業社会、土俗的民衆vs権力と権威、鉄とコンクリートvs木材、柱vs壁、製材木材vs丸太、数理的工業規格vsあいまいな和建築の身体単位、垂直vs水平、デカルト空間vs斜め線、西洋流「大きな構造設計」vs日本の「小さな構造設計」…等々。
数え切れないほどの《二項対立》があるが、そうした対立項を明らかにして、戦争や冷戦などの政治対立、経済成長やその停滞、自然災害や環境破壊などと、どう建築家たちが向き合い、迷い悩み、内外面で反目し合ったかを解き明かしているからこそ、本書は面白い。二項対立は退屈だと最後っ屁のように言い放った隈自身こそ矛盾だらけだ。
建築家は、得てして饒舌だし理屈っぽい。しかし、本書を読むと、なぜそうなのかということもわかるような気がしてくる。建築というものは、人間の衣食住という生活万端に関わる根本だ。だからこそ、人間臭く奥が深い。
隈の文筆の才にも感歎させられた。

日本の建築
隈 研吾 (著)
岩波新書 新赤版 1995
2023/11/29

日本の建築が、西欧の様式建築やモダニズム建築と出会って150年。それ以来の建築家たちの覚醒、葛藤や迷い、自己矛盾、変節を、忖度なく、徹底的に読み解いた日本現代建築史。
その思考思索の決着のように自身の建築へと帰着する。隈研吾の建築は、木材などの自然素材を多用し、居丈高なタテの巨大な柱が無い。和のモダニズム…とでも呼んでよいような、そういう隈の設計思想を理解するうえでも格好の書。
.jpg)
著者である自身は、巻末の「おわりに」で、『従来の日本建築史の退屈は、二項対立にあると感じた』と書いている。
しかし、本書の面白さは《二項対立》にある。
よくも、まあ、これだけの対立項目があるかと感心するほどに多面的で様々な対立が建築の歴史にあるのかと、もうそれだけで面白く、ハラハラ、ドキドキの連続だ。退屈するどころではない。
日本の現代建築の始まりに必ず登場するのが《桂離宮》と「モダニズム建築の巨匠」ブルーノ・タウト。しかし、そこにはタウトと、鉄とコンクリートを多用したシンプルでキレのある形態を全面に押し出してタウトを時代遅れとしてモダニズムの主役から引きずり落とした「フォルマリズム」のコルビジェらとの対立があるという。タウトは、その桂離宮を大礼賛した一方で、それと対比させるように日光東照宮をこきおろしたことはよく知られているが、そこには質実・清貧主義vs権威的様式主義の二項対立があったという。
…という具合で、のっけから二項対立の連鎖。反ファシズムvs反アメリカ、弥生vs縄文、西の大陸的合理性vs東の武士的合理性、関東の大きさvs関西の小ささ、北欧的後進性vs西欧的産業社会、土俗的民衆vs権力と権威、鉄とコンクリートvs木材、柱vs壁、製材木材vs丸太、数理的工業規格vsあいまいな和建築の身体単位、垂直vs水平、デカルト空間vs斜め線、西洋流「大きな構造設計」vs日本の「小さな構造設計」…等々。
数え切れないほどの《二項対立》があるが、そうした対立項を明らかにして、戦争や冷戦などの政治対立、経済成長やその停滞、自然災害や環境破壊などと、どう建築家たちが向き合い、迷い悩み、内外面で反目し合ったかを解き明かしているからこそ、本書は面白い。二項対立は退屈だと最後っ屁のように言い放った隈自身こそ矛盾だらけだ。
建築家は、得てして饒舌だし理屈っぽい。しかし、本書を読むと、なぜそうなのかということもわかるような気がしてくる。建築というものは、人間の衣食住という生活万端に関わる根本だ。だからこそ、人間臭く奥が深い。
隈の文筆の才にも感歎させられた。

日本の建築
隈 研吾 (著)
岩波新書 新赤版 1995
2023/11/29
「言語の力」(ビオリカ・マリアン 著)読了 [読書]
複数の言語を話すことで、人間の脳は変わる。認知や思考に大きな影響を与えコミュニケーションの能力が拡大し、果ては認知症のリスクも減らすという。
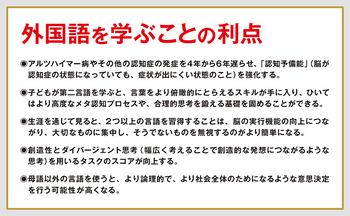
意外に思うかもしれないが、全世界に暮らす人の過半数がバイリンガルかマルチリンガルだという。全世界的に見ると、複数の言語を話す人は、例外ではなくむしろ普通の存在だ。
そして、外国語を習得することはさほど難しくない。
個人的な話しだけれど、昔、東大生は他の大学よりも帰国子女や留学体験者が格段に多いと教わった。そのことを教えてくれたのは東大教養学部のフランス文学の教授だった。調査の結果は学外秘とされていた。公表すると世の中の教育熱心な親たちがパニックになるだろうと懸念したからだそうだ。もう40年も昔の話しだけれど。
著者は、米国ノースウェスタン大学のコミュニケーション科学の教授。自らもルーマニア語を母語とするマルチリンガル。ロシア語はほぼ母語と同等、もちろん英語も話す。その他、様々な言語の研究に携わってきた。そうした立場と、自らの研究・調査結果から、マルチリンガルは良いことだらけだという。
そもそも脳は、それぞれの言語を別々に処理しているわけではない。聴覚、視覚といった知覚や認知も、記憶、思考など様々に連携するネットワークになっていて、言語によってその連携に違いは無いという。
つまり、人間の脳はひとつのオーケストラ。
同じオーケストラが、ベートーヴェンもブラームスでも、どんな曲でも演奏できる。曲によって楽団員が違うわけでも、楽器を持ち替えるわけでもない。それでまるで別の曲、ちがう音響を奏でる。
これも個人的な話しだけれど、会社の先輩で帰国子女で英語が堪能なバイリンガルがいた。通訳をしながら、日本語でメモを取り、それと同時に相手の英語でのひそひそ話しまで聴き取っていた。ひとつの脳でいくらでもこなせる。
言語は、人格を作るし文化や習慣も違ってくる。色や形などの認知までも言語によって変わってくる。だから、マルチリンガルは違った文化に対し寛容で、様々な感受性、表現の違いや表情や言葉の裏表への理解や思いやりが高まる。寛容度が上がり、他者を受け入れやすくなるという。だから、本人の幸福度も高まり、社会の分断リスクを低めて、世界はより平和になる。
米国国務省のレポートによると、日本語は最も難しい言語だそうだ。英語話者にとって習得するまでに要する時間が最長のカテゴリーに属する。単一性の高い民族で、島国という地勢もあってモノリンガルがあたりまえと思っている。
著者の紹介する言語学的、脳科学的な事例は、身近で、しかも、かなりショッキングな話しも多い。
読むと、きっとひとつでも外国語を学ぼうという気になるに違いありません。著者の調査によると、言語習得には幼児からの教育である必要はなく、高齢になっても学習に要する時間はさほど変わらないそうですから。

言語の力
「思考・価値観・感情」なぜ新しい言語を持つと世界が変わるのか?
ビオリカ・マリアン 著
今井むつみ 監訳・解説
桜田直美 訳
KADOKAWA
2023年12月21日 初版発行
The Power of Language
Viorica Marian
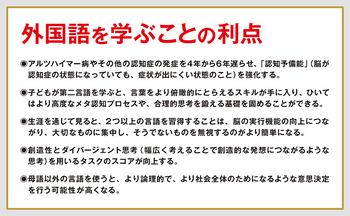
意外に思うかもしれないが、全世界に暮らす人の過半数がバイリンガルかマルチリンガルだという。全世界的に見ると、複数の言語を話す人は、例外ではなくむしろ普通の存在だ。
そして、外国語を習得することはさほど難しくない。
個人的な話しだけれど、昔、東大生は他の大学よりも帰国子女や留学体験者が格段に多いと教わった。そのことを教えてくれたのは東大教養学部のフランス文学の教授だった。調査の結果は学外秘とされていた。公表すると世の中の教育熱心な親たちがパニックになるだろうと懸念したからだそうだ。もう40年も昔の話しだけれど。
著者は、米国ノースウェスタン大学のコミュニケーション科学の教授。自らもルーマニア語を母語とするマルチリンガル。ロシア語はほぼ母語と同等、もちろん英語も話す。その他、様々な言語の研究に携わってきた。そうした立場と、自らの研究・調査結果から、マルチリンガルは良いことだらけだという。
そもそも脳は、それぞれの言語を別々に処理しているわけではない。聴覚、視覚といった知覚や認知も、記憶、思考など様々に連携するネットワークになっていて、言語によってその連携に違いは無いという。
つまり、人間の脳はひとつのオーケストラ。
同じオーケストラが、ベートーヴェンもブラームスでも、どんな曲でも演奏できる。曲によって楽団員が違うわけでも、楽器を持ち替えるわけでもない。それでまるで別の曲、ちがう音響を奏でる。
これも個人的な話しだけれど、会社の先輩で帰国子女で英語が堪能なバイリンガルがいた。通訳をしながら、日本語でメモを取り、それと同時に相手の英語でのひそひそ話しまで聴き取っていた。ひとつの脳でいくらでもこなせる。
言語は、人格を作るし文化や習慣も違ってくる。色や形などの認知までも言語によって変わってくる。だから、マルチリンガルは違った文化に対し寛容で、様々な感受性、表現の違いや表情や言葉の裏表への理解や思いやりが高まる。寛容度が上がり、他者を受け入れやすくなるという。だから、本人の幸福度も高まり、社会の分断リスクを低めて、世界はより平和になる。
米国国務省のレポートによると、日本語は最も難しい言語だそうだ。英語話者にとって習得するまでに要する時間が最長のカテゴリーに属する。単一性の高い民族で、島国という地勢もあってモノリンガルがあたりまえと思っている。
著者の紹介する言語学的、脳科学的な事例は、身近で、しかも、かなりショッキングな話しも多い。
読むと、きっとひとつでも外国語を学ぼうという気になるに違いありません。著者の調査によると、言語習得には幼児からの教育である必要はなく、高齢になっても学習に要する時間はさほど変わらないそうですから。

言語の力
「思考・価値観・感情」なぜ新しい言語を持つと世界が変わるのか?
ビオリカ・マリアン 著
今井むつみ 監訳・解説
桜田直美 訳
KADOKAWA
2023年12月21日 初版発行
The Power of Language
Viorica Marian
世にもあいまいなことばの秘密 [読書]
日本語はあいまいな言語だとよく言われる。
「世にもあいまいなことば(=日本語)・の秘密」という題名を一見して、日本語という言語のもつ特有のあいまいさを言語学的に解明しようという本だと思い、手にしてみた。

ところが読み始めてみるとそうではない。
「世にもあいまいな・ことばの秘密」ということで、(ことば=あいまい)という意味。表現にはあいまいさがつきまとうが、それは日本語に限ったことではない。そういうことばのあいまいさ(=複数の解釈が可能)を回避するための実用書みたいな本でした。
ことばといっても、日常の日本語。言語学といった難しい本ではなく、ごくごく身の回りの会話とか、メールやSNSでのやりとり、ニュースの見出しなどのお話し。例文もごく簡単なものだから、親しみやすいし、わかりやすい。
でも笑ってすませるわけにもいかない。
メールやSNSなど、短文のやりとりばかりの昨今。こんな短いことばでも誤解のすき間だらけとびっくり。短文だからこそ言葉を選び、磨いてみよう。

世にもあいまいなことばの秘密
川添愛著
ちくまプリマー新書442
2023年12月10日 初版第一刷発行
「世にもあいまいなことば(=日本語)・の秘密」という題名を一見して、日本語という言語のもつ特有のあいまいさを言語学的に解明しようという本だと思い、手にしてみた。

ところが読み始めてみるとそうではない。
「世にもあいまいな・ことばの秘密」ということで、(ことば=あいまい)という意味。表現にはあいまいさがつきまとうが、それは日本語に限ったことではない。そういうことばのあいまいさ(=複数の解釈が可能)を回避するための実用書みたいな本でした。
ことばといっても、日常の日本語。言語学といった難しい本ではなく、ごくごく身の回りの会話とか、メールやSNSでのやりとり、ニュースの見出しなどのお話し。例文もごく簡単なものだから、親しみやすいし、わかりやすい。
でも笑ってすませるわけにもいかない。
メールやSNSなど、短文のやりとりばかりの昨今。こんな短いことばでも誤解のすき間だらけとびっくり。短文だからこそ言葉を選び、磨いてみよう。

世にもあいまいなことばの秘密
川添愛著
ちくまプリマー新書442
2023年12月10日 初版第一刷発行
「謎の平安前期」(榎村 寛之 (著)読了 [読書]
平安時代は400年も続いた。桓武天皇が平安京に遷都してから藤原道長が摂政関白太政大臣の頂点に立つまでには約200年の時が流れている。私たちは平安時代といっても、前半の200年のことは何も知らない。
本書は、そのあまり知られていない「平安前期」を深掘りして再考してみようというもの。
著者によれば、平安時代の歴史があまり知られていないのは仕方のないこと。そもそも、この時代になって正規の歴史書(「正史」)というものが書かれなくなった。王朝交代を繰り返す中国と違って、政権交代の正統性を謳うための前史を編纂する必要が無くなった。唐も滅び、新羅も渤海も滅び、大陸や朝鮮半島との行き来も途絶え外交不在だから記録するほどのこともない。平安時代というのは、そういうユルい時代。教科書で習うのは、「古今和歌集」や「源氏物語」「枕草子」のことばかりになる。
ところが、その平安前期が、なかなかに面白い。ぼんやりと、奈良時代に完成した律令国家の衰退が平安時代だ…などと思い込んでいると、「ボーっと生きてんじゃねーよ!」と叱られそう。
著者は、古代史研究家。特に、伊勢神宮または賀茂神社に巫女として奉仕した未婚の内親王(天皇の皇女)に詳しい。平安前期の歴史を、天皇家の女系を中心にジェンダーの視点から見直し再評価しようというのが本書。
桓武天皇が完成させた律令国家は、あくまでも中国の統治体制のコピペ。それを日本の現実に合わせていくのが平安前期。それは建前先行の大きな政府から、地方重視の小さな政府へと実利的な改革が重ねられた時代。むしろ国は豊かになり、平安京は未曾有の繁栄を誇る本格的な都市となる。
建前から現実へ移行していくにつれて、王家のあり方も変わっていく。皇族皇統とそれを支援する有力豪族による「護送船団方式」から、やがて、門閥貴族が外戚として血統を支配していく「摂関政治」へと変質し身分も固定化していく。皇統直系の身位であるべき皇后とか、それに仕える女官という建前が薄まっていき、天皇の寝所に侍する女はすべからく女御や更衣となって政治とは無縁の『女御・更衣あまたさぶらひける…』後宮を形成していく。政治の実権は、皇子の母系となる摂関家や幼い天皇に譲位した太上天皇(上皇)が握ることになる。
つまり正式の官位もあり活躍していた女性たちは次第に表舞台から排除され、政治はもっぱら殿方たちの専管事項となっていくというわけ。
天皇血統の皇后がいなくなれば、女性天皇の可能性も無くなる。皇女たちは、もっと悲惨で、行き場を失う。その多くは未婚のまま。巫女として神に仕えるという形で天皇家を守る斎王というのもそこから生まれるが、京を離れ遠く伊勢に下る本人たちやそれに付き添う女たちの立場は微妙だろう。そこから六条御息所のような生霊、死霊の祟りへの恐怖物語も生ずる。
政治統治の公用語である漢文も使いこなした皇后とそれを取り巻く女官たちの教養は、やがては女御に付く女房へとどんどんと下級へと沈下していくことに。一方で、外交不在の時代になって外国語としての漢文(中国語)はどんどんと形式化・形骸化し、活き活きとした文化は口語表音文字としての仮名文字が担うことになっていくというわけです。
こうした女御、あるいはそれに仕える名も無き女房たちは、ある種の文化サロンを主催し、それを通じて天皇やその側近たちに直接まみえることもできた。紀貫之などの下級貴族といえども和歌などの文化活動を通じて権力の頂点の知己を得る機会があったというのがこの時代の宮廷文化であり、政治の実態だったというわけです。地方の風物事情も知悉する下級貴族は紀行文学も生み出し、京のことしか知らない宮廷とその周辺にもてはやされる。
とにかく目からウロコの連続で、なるほどと面白い。
…が、ちょっと読みにくく、後半になればなるほど重たい。個人名が多く、家系、血統などが複雑だし、テーマが前後錯綜し繰り返しも多いので、読み進めるのはちょっと根気が必要。後半は、重複も多いのでもどかしい。もう少し流れや主題を整理して、読みやすくわかりやすいものにして欲しかった。

謎の平安前期
―桓武天皇から『源氏物語』誕生までの200年
榎村 寛之 (著)
中公新書 2783
2023/12/25 発行
本書は、そのあまり知られていない「平安前期」を深掘りして再考してみようというもの。
著者によれば、平安時代の歴史があまり知られていないのは仕方のないこと。そもそも、この時代になって正規の歴史書(「正史」)というものが書かれなくなった。王朝交代を繰り返す中国と違って、政権交代の正統性を謳うための前史を編纂する必要が無くなった。唐も滅び、新羅も渤海も滅び、大陸や朝鮮半島との行き来も途絶え外交不在だから記録するほどのこともない。平安時代というのは、そういうユルい時代。教科書で習うのは、「古今和歌集」や「源氏物語」「枕草子」のことばかりになる。
ところが、その平安前期が、なかなかに面白い。ぼんやりと、奈良時代に完成した律令国家の衰退が平安時代だ…などと思い込んでいると、「ボーっと生きてんじゃねーよ!」と叱られそう。
著者は、古代史研究家。特に、伊勢神宮または賀茂神社に巫女として奉仕した未婚の内親王(天皇の皇女)に詳しい。平安前期の歴史を、天皇家の女系を中心にジェンダーの視点から見直し再評価しようというのが本書。
桓武天皇が完成させた律令国家は、あくまでも中国の統治体制のコピペ。それを日本の現実に合わせていくのが平安前期。それは建前先行の大きな政府から、地方重視の小さな政府へと実利的な改革が重ねられた時代。むしろ国は豊かになり、平安京は未曾有の繁栄を誇る本格的な都市となる。
建前から現実へ移行していくにつれて、王家のあり方も変わっていく。皇族皇統とそれを支援する有力豪族による「護送船団方式」から、やがて、門閥貴族が外戚として血統を支配していく「摂関政治」へと変質し身分も固定化していく。皇統直系の身位であるべき皇后とか、それに仕える女官という建前が薄まっていき、天皇の寝所に侍する女はすべからく女御や更衣となって政治とは無縁の『女御・更衣あまたさぶらひける…』後宮を形成していく。政治の実権は、皇子の母系となる摂関家や幼い天皇に譲位した太上天皇(上皇)が握ることになる。
つまり正式の官位もあり活躍していた女性たちは次第に表舞台から排除され、政治はもっぱら殿方たちの専管事項となっていくというわけ。
天皇血統の皇后がいなくなれば、女性天皇の可能性も無くなる。皇女たちは、もっと悲惨で、行き場を失う。その多くは未婚のまま。巫女として神に仕えるという形で天皇家を守る斎王というのもそこから生まれるが、京を離れ遠く伊勢に下る本人たちやそれに付き添う女たちの立場は微妙だろう。そこから六条御息所のような生霊、死霊の祟りへの恐怖物語も生ずる。
政治統治の公用語である漢文も使いこなした皇后とそれを取り巻く女官たちの教養は、やがては女御に付く女房へとどんどんと下級へと沈下していくことに。一方で、外交不在の時代になって外国語としての漢文(中国語)はどんどんと形式化・形骸化し、活き活きとした文化は口語表音文字としての仮名文字が担うことになっていくというわけです。
こうした女御、あるいはそれに仕える名も無き女房たちは、ある種の文化サロンを主催し、それを通じて天皇やその側近たちに直接まみえることもできた。紀貫之などの下級貴族といえども和歌などの文化活動を通じて権力の頂点の知己を得る機会があったというのがこの時代の宮廷文化であり、政治の実態だったというわけです。地方の風物事情も知悉する下級貴族は紀行文学も生み出し、京のことしか知らない宮廷とその周辺にもてはやされる。
とにかく目からウロコの連続で、なるほどと面白い。
…が、ちょっと読みにくく、後半になればなるほど重たい。個人名が多く、家系、血統などが複雑だし、テーマが前後錯綜し繰り返しも多いので、読み進めるのはちょっと根気が必要。後半は、重複も多いのでもどかしい。もう少し流れや主題を整理して、読みやすくわかりやすいものにして欲しかった。

謎の平安前期
―桓武天皇から『源氏物語』誕生までの200年
榎村 寛之 (著)
中公新書 2783
2023/12/25 発行
「世界を、こんなふうに見てごらん」(日高敏隆 著)読了 [読書]
真面目なようでいて、ちょっと不真面目なエッセイ。
本人はいたって真面目なつもりなのか、やっぱり、意図してちょっと不真面目さを装っているのかは不明。語り口は、科学者とは思えないほどにやさしくて、後進の若手に語っているというよりは、童心を失わない子供に語りかけているような口ぶり。ひらがなが多くて字面は白っぽくて200ページもない薄い文庫本だ。
緩くて、自然で、それでいてとても深い。
読んでいるととてもわかったような気分になってくる。気が楽になってくる。肩の力が抜けてくる。――でも、ちっともわかったような気もしない。何ともふんわりとした後味と、気を抜けないという気持ちが、うま味のようなものになって後を引く。
ようは、ものごとをじっと観察して、なに、なぜ、なんだろうと考えてみよう。そういう子どものような「なぜ」を誰も止めてはいけないし、止めることもできない。純真な疑問と、それをつきつめていく好奇心をいつまでも持っていようよということを、とかくしゃちほこばって言いたがる大人たちに言い聞かせているようなところもある。
著者が、東大の理学部の学生時代に、科学は「なぜ」を問うてはいけないと言われたそうだ。「どのように(How)」はよいが、「なぜ(Why)」はダメ。リンゴが下に落ちるのはなぜか?――万有引力があるからだ。でも、なぜ、万有引力があるのか、とは聞いちゃいけない。それはカミサマが出てくる話になってしまう。「なぜ」にこだわるなら京大へ行け…と。
でも、「なぜ」だろうと考えて、じっと見ることでこそ、いろいろなことが見えてくる。型にはまらない、自由な「なぜ?」が大切だという。
イリュージョンという話しが面白かった。
人間に見えるものは、人間が見るイリュージョンだという。モンシロチョウの雄は、雌に向かってまっしぐらにいく。人間には雄と雌の区別はつかないのになぜだろう?フェロモンは発しているからだと言うひともいた。けれども、モンシロチョウの羽は、紫外線の反射が雄と雌では違うということがわかった。モンシロチョウからすれば雌は真っ黒に見える。人間だって、人によっては、あるいは時代によっては、ものの見方が変わる。「真実」は永遠不変ではない。
アゲハチョウのサナギは、木や葉に合わせて色を変える。いわゆる保護色が。ではどのようにして色を合わせるのだろう?当然、周囲の色に合わせるのだろうと考えられていた。でも観察してみるとそうではない。なぜだろう?と追求していくと、止まっている枝の太さとか、色だけではないいろいろな要因が複雑に絡んでいて色が決まるということがわかった。
高山に生息するある種のハチを、実験観察のために飼育したらすぐに全部死んでしまう。なぜだろう?と何度も試行錯誤を繰り返したら、昼と夜とで飼育温度を変える必要があることがわかった。飼育は、恒温ですることが生物学の決まりだった。でも、高山では昼夜の寒暖差が大きい。「決まり」の通りにすれば死んでしまう。
違う種類のハチは、何キロも遠くの雄も引きつけるという。そういうデータがあって定説になっていた。そんな遠くまでフェロモンが届くはずがないのに「なぜだろう?」と思って調べてみたら、ハチの行動範囲が広くたまたま雌の近くに通りかかったハチが雌に引きつけられただけだった。近づかない限りはフェロモンに引き寄せられるわけではない。
そんな事例の数々が、けっこう面白い。
イリュージョンだと思えば、気が楽だ。科学は真実を明らかにするなどと、肩を怒らせて思い込まないほうがよい。イマジネーションも大事だ。科学だとかの権威に縛られることはない。とても自由だ。なぜならば、いつも「なぜだろう?」と純粋な疑問を持ち続けているから。
本当は、科学といっても、いろいろな考え方がある。難しく言えば、帰納法と演繹法の違いもある。著者の言わんとしていることは、ニュートン以来の運動力学的な厳密な因果論の発想が『科学』として規範であり続けたこと。物理学こそ科学だという、《物理学帝国主義》への批判だ。動物学は科学じゃないと言われたこともあるという。今や、文学部に所属していた心理学も、医学や薬学、化学、情報学などを総合的に駆使しての《脳科学》になっている。
科学的思考を何でもかんでも否定しているわけではない。著者はそんなことを言っているわけではない。そこのところは誤解しないほうがよい。

世界を、こんなふうに見てごらん
日高敏隆
集英社文庫
本人はいたって真面目なつもりなのか、やっぱり、意図してちょっと不真面目さを装っているのかは不明。語り口は、科学者とは思えないほどにやさしくて、後進の若手に語っているというよりは、童心を失わない子供に語りかけているような口ぶり。ひらがなが多くて字面は白っぽくて200ページもない薄い文庫本だ。
緩くて、自然で、それでいてとても深い。
読んでいるととてもわかったような気分になってくる。気が楽になってくる。肩の力が抜けてくる。――でも、ちっともわかったような気もしない。何ともふんわりとした後味と、気を抜けないという気持ちが、うま味のようなものになって後を引く。
ようは、ものごとをじっと観察して、なに、なぜ、なんだろうと考えてみよう。そういう子どものような「なぜ」を誰も止めてはいけないし、止めることもできない。純真な疑問と、それをつきつめていく好奇心をいつまでも持っていようよということを、とかくしゃちほこばって言いたがる大人たちに言い聞かせているようなところもある。
著者が、東大の理学部の学生時代に、科学は「なぜ」を問うてはいけないと言われたそうだ。「どのように(How)」はよいが、「なぜ(Why)」はダメ。リンゴが下に落ちるのはなぜか?――万有引力があるからだ。でも、なぜ、万有引力があるのか、とは聞いちゃいけない。それはカミサマが出てくる話になってしまう。「なぜ」にこだわるなら京大へ行け…と。
でも、「なぜ」だろうと考えて、じっと見ることでこそ、いろいろなことが見えてくる。型にはまらない、自由な「なぜ?」が大切だという。
イリュージョンという話しが面白かった。
人間に見えるものは、人間が見るイリュージョンだという。モンシロチョウの雄は、雌に向かってまっしぐらにいく。人間には雄と雌の区別はつかないのになぜだろう?フェロモンは発しているからだと言うひともいた。けれども、モンシロチョウの羽は、紫外線の反射が雄と雌では違うということがわかった。モンシロチョウからすれば雌は真っ黒に見える。人間だって、人によっては、あるいは時代によっては、ものの見方が変わる。「真実」は永遠不変ではない。
アゲハチョウのサナギは、木や葉に合わせて色を変える。いわゆる保護色が。ではどのようにして色を合わせるのだろう?当然、周囲の色に合わせるのだろうと考えられていた。でも観察してみるとそうではない。なぜだろう?と追求していくと、止まっている枝の太さとか、色だけではないいろいろな要因が複雑に絡んでいて色が決まるということがわかった。
高山に生息するある種のハチを、実験観察のために飼育したらすぐに全部死んでしまう。なぜだろう?と何度も試行錯誤を繰り返したら、昼と夜とで飼育温度を変える必要があることがわかった。飼育は、恒温ですることが生物学の決まりだった。でも、高山では昼夜の寒暖差が大きい。「決まり」の通りにすれば死んでしまう。
違う種類のハチは、何キロも遠くの雄も引きつけるという。そういうデータがあって定説になっていた。そんな遠くまでフェロモンが届くはずがないのに「なぜだろう?」と思って調べてみたら、ハチの行動範囲が広くたまたま雌の近くに通りかかったハチが雌に引きつけられただけだった。近づかない限りはフェロモンに引き寄せられるわけではない。
そんな事例の数々が、けっこう面白い。
イリュージョンだと思えば、気が楽だ。科学は真実を明らかにするなどと、肩を怒らせて思い込まないほうがよい。イマジネーションも大事だ。科学だとかの権威に縛られることはない。とても自由だ。なぜならば、いつも「なぜだろう?」と純粋な疑問を持ち続けているから。
本当は、科学といっても、いろいろな考え方がある。難しく言えば、帰納法と演繹法の違いもある。著者の言わんとしていることは、ニュートン以来の運動力学的な厳密な因果論の発想が『科学』として規範であり続けたこと。物理学こそ科学だという、《物理学帝国主義》への批判だ。動物学は科学じゃないと言われたこともあるという。今や、文学部に所属していた心理学も、医学や薬学、化学、情報学などを総合的に駆使しての《脳科学》になっている。
科学的思考を何でもかんでも否定しているわけではない。著者はそんなことを言っているわけではない。そこのところは誤解しないほうがよい。

世界を、こんなふうに見てごらん
日高敏隆
集英社文庫
「台湾の半世紀」(若林正丈 著)読了 [読書]
台湾研究の大家である著者が、自らの研究人生を振り返り、その道筋をたどった研究史。
そういう研究者の自分史が、とりもなおさず台湾研究の成り立ちでもあり、同時に台湾の戦後史を臨場感たっぷりに描き出している。なぜならば、著者以前には台湾研究という地域研究そのものが存在していなかったから。そして、それは同時に、「台湾人」としてのアイデンティティの確立までの物語そのものだからだ。つまりは、冷戦構造と二つの中国の対峙に翻弄されながらも、自らののアイデンティティの確立と民主化を主体的に模索してきた台湾の人々の試練の戦後史そのもの。著者の研究人生が、台湾の人々との関わりを通じて、それを活き活きと描いている。
著者が、東大の教養学部(国際関係論)を卒業し大学院修士課程に進学したのが1972年のこと。それはまさに田中角栄首相(当時)の電撃訪中が実現し、日中共同声明が宣せられた年。
日中国交正常化が実現したと言われる一方で、それは台湾の切り捨てでもあった。特別永住者の資格を持ついわゆる在日華僑の台湾人は、国籍の変更を半ば強いられ、「中華民国」国籍を維持しても「台湾住民」だった痕跡は抹消されてしまう。
「二つの中国」の否定は、何も大陸だけではなかった。中国内戦後に台湾に逃げ込んだ蒋介石の国民党は台湾のみを統治していたが、中国共産党が「ひとつの中国」を主張したことの裏返しで、台湾に中国全体を代表する正統政府が存在するという虚構を維持した。それが国民党の一党独裁の根拠となり、民主的手続きをとることのない永年議員が存在し、政府議会とは別に、肩書きと既得権だけの「台湾省」が存在する。住民の意思はまったく政治には反映されなかった。
著者は、台湾研究を志しても社会学の間借りのような形で在籍するしかなかった。地域研究や国際関係論、あるいは文学研究であれ、「中国」はあっても「台湾」は事実上存在しない。大学院時代、著者はよく同僚らから「いつ大陸侵攻するのか?」とからかわれたという。つまり、台湾研究ではなく「中国」研究への鞍替えのことだ。
結局、著者は東大教養学部の助教授職を得るが、それはあくまでも「外国語」教員というもの。それでも東大教授の肩書きはものを言ったという。それがなかった時には、台湾の新聞や雑誌を定期購読するカネも無かったからだ。台湾で選挙があれば出かけていき、直接、オポジション(非国民党の運動家)の事務所などに取材する。そうしたことを通じて、台湾の社会や政治の現実に通暁し、台湾の人々のメンタリティへの洞察を深めていく。
台湾は、戦前は日本の統治、戦後は大陸から逃げ込んできた国民党や軍人という外省人の支配を受ける。「犬が去って豚が来た」というわけだ。民主化とは、取りも直さず住民自身による統治ということ。つまり、「台湾の台湾化」ということ。そのためには、内戦継続という虚構を剥ぎ取り、憲法や法制の改訂が必要だった。「台湾独立」がタブーであることは、実は、台湾の国民党にとっては、大陸の共産党以上のものだった。それを地道に成し遂げて言ったのが、単なるお飾りのイエスマンと思われていた李登輝の巧みで粘り強い改革路線だったというわけだ。
日本台湾学会設立に尽力したのも著者。旗揚げの最終段階で、それを小さなコラムの形で報じたのが朝日新聞。「学術研究が政治対立に巻き込まれるのは不幸なこと」――巧みなレトリックに隠された《警告》《恫喝》には戦りつを覚える。つまりは「雉も鳴かずば打たれまい」ということ。朝日新聞の立ち位置ということにはゾッとさせられる。
最初は、地味な研究人生の自分史のような語り口に、正直なところちょっとしらける気分もあったが、読み進むにつれてぐいぐいと引き込まれてしまった。民主主義というのは、単なる手続きの形式的な正統性の争いではない。住民のアイデンティティそのもの。住民こそが主体であることの確信があってこそ、実現し維持されるということを、台湾政治の歴史から強いメッセージとなって伝わってくる。きな臭い軍事的な恫喝ばかりが台湾問題の本質では決してない。そのことを切実に実感する。

台湾の半世紀 ――民主化と台湾化の現場
若林 正丈 (著)
筑摩選書
2023年12月15日初版第一刷
そういう研究者の自分史が、とりもなおさず台湾研究の成り立ちでもあり、同時に台湾の戦後史を臨場感たっぷりに描き出している。なぜならば、著者以前には台湾研究という地域研究そのものが存在していなかったから。そして、それは同時に、「台湾人」としてのアイデンティティの確立までの物語そのものだからだ。つまりは、冷戦構造と二つの中国の対峙に翻弄されながらも、自らののアイデンティティの確立と民主化を主体的に模索してきた台湾の人々の試練の戦後史そのもの。著者の研究人生が、台湾の人々との関わりを通じて、それを活き活きと描いている。
著者が、東大の教養学部(国際関係論)を卒業し大学院修士課程に進学したのが1972年のこと。それはまさに田中角栄首相(当時)の電撃訪中が実現し、日中共同声明が宣せられた年。
日中国交正常化が実現したと言われる一方で、それは台湾の切り捨てでもあった。特別永住者の資格を持ついわゆる在日華僑の台湾人は、国籍の変更を半ば強いられ、「中華民国」国籍を維持しても「台湾住民」だった痕跡は抹消されてしまう。
「二つの中国」の否定は、何も大陸だけではなかった。中国内戦後に台湾に逃げ込んだ蒋介石の国民党は台湾のみを統治していたが、中国共産党が「ひとつの中国」を主張したことの裏返しで、台湾に中国全体を代表する正統政府が存在するという虚構を維持した。それが国民党の一党独裁の根拠となり、民主的手続きをとることのない永年議員が存在し、政府議会とは別に、肩書きと既得権だけの「台湾省」が存在する。住民の意思はまったく政治には反映されなかった。
著者は、台湾研究を志しても社会学の間借りのような形で在籍するしかなかった。地域研究や国際関係論、あるいは文学研究であれ、「中国」はあっても「台湾」は事実上存在しない。大学院時代、著者はよく同僚らから「いつ大陸侵攻するのか?」とからかわれたという。つまり、台湾研究ではなく「中国」研究への鞍替えのことだ。
結局、著者は東大教養学部の助教授職を得るが、それはあくまでも「外国語」教員というもの。それでも東大教授の肩書きはものを言ったという。それがなかった時には、台湾の新聞や雑誌を定期購読するカネも無かったからだ。台湾で選挙があれば出かけていき、直接、オポジション(非国民党の運動家)の事務所などに取材する。そうしたことを通じて、台湾の社会や政治の現実に通暁し、台湾の人々のメンタリティへの洞察を深めていく。
台湾は、戦前は日本の統治、戦後は大陸から逃げ込んできた国民党や軍人という外省人の支配を受ける。「犬が去って豚が来た」というわけだ。民主化とは、取りも直さず住民自身による統治ということ。つまり、「台湾の台湾化」ということ。そのためには、内戦継続という虚構を剥ぎ取り、憲法や法制の改訂が必要だった。「台湾独立」がタブーであることは、実は、台湾の国民党にとっては、大陸の共産党以上のものだった。それを地道に成し遂げて言ったのが、単なるお飾りのイエスマンと思われていた李登輝の巧みで粘り強い改革路線だったというわけだ。
日本台湾学会設立に尽力したのも著者。旗揚げの最終段階で、それを小さなコラムの形で報じたのが朝日新聞。「学術研究が政治対立に巻き込まれるのは不幸なこと」――巧みなレトリックに隠された《警告》《恫喝》には戦りつを覚える。つまりは「雉も鳴かずば打たれまい」ということ。朝日新聞の立ち位置ということにはゾッとさせられる。
最初は、地味な研究人生の自分史のような語り口に、正直なところちょっとしらける気分もあったが、読み進むにつれてぐいぐいと引き込まれてしまった。民主主義というのは、単なる手続きの形式的な正統性の争いではない。住民のアイデンティティそのもの。住民こそが主体であることの確信があってこそ、実現し維持されるということを、台湾政治の歴史から強いメッセージとなって伝わってくる。きな臭い軍事的な恫喝ばかりが台湾問題の本質では決してない。そのことを切実に実感する。

台湾の半世紀 ――民主化と台湾化の現場
若林 正丈 (著)
筑摩選書
2023年12月15日初版第一刷
「ロスチャイルドの女たち」(ナタリー・リヴィングストン 著)読了 [読書]
ロスチャイルドといえば金持ちの代名詞とも言うべき家系で、知らぬものはいない。
ヨーロッパの政治や経済を大きく動かしてきた一族の毀誉褒貶の歴史は、当然のことながら多くが語られてきたが、その血統と閨閥に連なる女性たちのことはまったく語られることがなかった。
本著は、ロスチャイルドの女たちが書いた日記や手紙や論文などを発掘し丹念につなぎ合わせて、いわばヨーロッパ近現代の歴史の意外で興味深い実相を見事に浮き彫りにしている。
実に面白い。
そもそもロスチャイルド家は、フランクフルトのゲットー(ユダヤ人隔離居住区)の勤勉だけが取り柄のような家族から始まった。「ロスチャイルド」は、ゲットーの住居の通称「赤い盾(ロートシルト)」に由来する。古銭業から出発して、やがて宮廷貴族への両替・貸付で取り入り銀行業へと成り上がっていく。始祖母グートレは長寿だったが、ユダヤ人の居住が自由になり、一族が巨万の富を築いてもゲットーの家を離れなかった。
その勃興を支え家計を取り仕切った偉大な母グートレに遺されたのは、棲む家だけ。糟糠の妻であろうと、女には一切遺産を相続させず、死後に経営に口をだすこともまかりならないというのが夫の遺言であり、これがロスチャイルド家の家訓となる。家財と会社は、長男のみに継承させる。婚姻は、厳格にユダヤ人名家かもしくは一族に限られ、政略で決められる。そのためには従兄弟や叔父姪などの近親婚も厭わない。それもこれも、家系の結束を固め資産の分散を防ぐため。女は家具か道具のように見なされた。
そうした男尊女卑は当時の社会常識でもあった。それに対する女たちの鬱屈や不満、抵抗と反抗、反逆を心中に抱えながらも、進取の気性はとどまるところを知らない。期待通りにヨーロッパ各地に拡がる一族のかすがい役を果たし、社交界では政財界に強力な人脈を築き、夫の政治的野心を後押しして選挙基盤を築いていく。男たちは反ユダヤ主義を克服し国会議員の地位や貴族の称号を得るが、それを実現させたのは女たちの力だった。
ヴィクトリア朝の絶世期を迎え、社会的にも進取の気風に溢れていたイギリス社会で、女たちが積極的に推進したのは一族のためだけではない。選挙権の拡大、特に女性参政権にも積極的な論陣を張る。さらには、貧困対策や公衆衛生面にも取り組み、同性愛者への法的差別撤廃をも主張している。
女たちが後押ししたのは、祖地パレスチナにユダヤ国家を建設するというシオニズム運動。
本来、ロスチャイルド家を始めとするユダヤ系保守層は、近代国家への同化を推進する立場だったから、イスラエル国家建設を目指すシオニズムには反対だった。しかし、ロシアでの19世紀末以来のポグロム(ユダヤ人迫害)の激化背景にシオニズム支援へと転換させ、ついには最後の砦だった外務大臣バルフォア伯爵の同意を勝ち取ったのも女の力だった。バルフォアの公開書簡は、ダブルスタンダードの矛盾をはらみながらも、ヒットラー政権の成立で行き場を失い命を落としたユダヤ人への同情が募るとともに、ついには外交公約と見なされていく。
さすがに、スーパーリッチの女たちの活力、行動力はスケールが違う。
彼女たちの活躍、足跡をたどっていくと、ヨーロッパの近現代の歴史が、型どおりの教科書的なものとはまるで違って見えてきて、生々しく血の通ったものに感じられてくる。反抗や反逆、対立はあっても、親族同士の暖かい愛情あふれた絆は、やはり、女性だからこそのもの。しかも、戦争や人種・性差別など今に通じるテーマがちりばめられていて、とても今日的。
残念なのは翻訳。
ただでさえ登場人物が多く、その日記や手紙の片言隻句を頻繁に引用し、イギリス人好みのひねった書き方で読みにくいのに、それを工夫もなく直訳するので読みにくいことこの上ない。人名索引も欲しかった。何とか我慢して読み進めることができたのは、とにかく内容が面白いからに他ならない。
ぜひおすすめしたい。

ロスチャイルドの女たち
ナタリー・リヴィングストン (著), 古屋 美登里 (翻訳)
亜紀書房
2023年11月4日 初版
THE WOMEN OF ROTHSCHILD by Ntalie Livingstone
The Untold Story of the World's Most Famous Dynasty
ヨーロッパの政治や経済を大きく動かしてきた一族の毀誉褒貶の歴史は、当然のことながら多くが語られてきたが、その血統と閨閥に連なる女性たちのことはまったく語られることがなかった。
本著は、ロスチャイルドの女たちが書いた日記や手紙や論文などを発掘し丹念につなぎ合わせて、いわばヨーロッパ近現代の歴史の意外で興味深い実相を見事に浮き彫りにしている。
実に面白い。
そもそもロスチャイルド家は、フランクフルトのゲットー(ユダヤ人隔離居住区)の勤勉だけが取り柄のような家族から始まった。「ロスチャイルド」は、ゲットーの住居の通称「赤い盾(ロートシルト)」に由来する。古銭業から出発して、やがて宮廷貴族への両替・貸付で取り入り銀行業へと成り上がっていく。始祖母グートレは長寿だったが、ユダヤ人の居住が自由になり、一族が巨万の富を築いてもゲットーの家を離れなかった。
その勃興を支え家計を取り仕切った偉大な母グートレに遺されたのは、棲む家だけ。糟糠の妻であろうと、女には一切遺産を相続させず、死後に経営に口をだすこともまかりならないというのが夫の遺言であり、これがロスチャイルド家の家訓となる。家財と会社は、長男のみに継承させる。婚姻は、厳格にユダヤ人名家かもしくは一族に限られ、政略で決められる。そのためには従兄弟や叔父姪などの近親婚も厭わない。それもこれも、家系の結束を固め資産の分散を防ぐため。女は家具か道具のように見なされた。
そうした男尊女卑は当時の社会常識でもあった。それに対する女たちの鬱屈や不満、抵抗と反抗、反逆を心中に抱えながらも、進取の気性はとどまるところを知らない。期待通りにヨーロッパ各地に拡がる一族のかすがい役を果たし、社交界では政財界に強力な人脈を築き、夫の政治的野心を後押しして選挙基盤を築いていく。男たちは反ユダヤ主義を克服し国会議員の地位や貴族の称号を得るが、それを実現させたのは女たちの力だった。
ヴィクトリア朝の絶世期を迎え、社会的にも進取の気風に溢れていたイギリス社会で、女たちが積極的に推進したのは一族のためだけではない。選挙権の拡大、特に女性参政権にも積極的な論陣を張る。さらには、貧困対策や公衆衛生面にも取り組み、同性愛者への法的差別撤廃をも主張している。
女たちが後押ししたのは、祖地パレスチナにユダヤ国家を建設するというシオニズム運動。
本来、ロスチャイルド家を始めとするユダヤ系保守層は、近代国家への同化を推進する立場だったから、イスラエル国家建設を目指すシオニズムには反対だった。しかし、ロシアでの19世紀末以来のポグロム(ユダヤ人迫害)の激化背景にシオニズム支援へと転換させ、ついには最後の砦だった外務大臣バルフォア伯爵の同意を勝ち取ったのも女の力だった。バルフォアの公開書簡は、ダブルスタンダードの矛盾をはらみながらも、ヒットラー政権の成立で行き場を失い命を落としたユダヤ人への同情が募るとともに、ついには外交公約と見なされていく。
さすがに、スーパーリッチの女たちの活力、行動力はスケールが違う。
彼女たちの活躍、足跡をたどっていくと、ヨーロッパの近現代の歴史が、型どおりの教科書的なものとはまるで違って見えてきて、生々しく血の通ったものに感じられてくる。反抗や反逆、対立はあっても、親族同士の暖かい愛情あふれた絆は、やはり、女性だからこそのもの。しかも、戦争や人種・性差別など今に通じるテーマがちりばめられていて、とても今日的。
残念なのは翻訳。
ただでさえ登場人物が多く、その日記や手紙の片言隻句を頻繁に引用し、イギリス人好みのひねった書き方で読みにくいのに、それを工夫もなく直訳するので読みにくいことこの上ない。人名索引も欲しかった。何とか我慢して読み進めることができたのは、とにかく内容が面白いからに他ならない。
ぜひおすすめしたい。

ロスチャイルドの女たち
ナタリー・リヴィングストン (著), 古屋 美登里 (翻訳)
亜紀書房
2023年11月4日 初版
THE WOMEN OF ROTHSCHILD by Ntalie Livingstone
The Untold Story of the World's Most Famous Dynasty
「日本のクラシック音楽は歪んでいる」(森本 恭正 著)読了 [読書]
日本の西洋音楽受容を一刀両断。日本のクラシック音楽ファンをすべて敵に回すような論調は、SNSで言うところの「釣り」手法、あるいは「炎上」商法とでも言うべきでしょうか。
そういう私も、ネットで話題になっているのを見て、まんまと釣り上げられて手にしてみたクチ。ただし、この著者には、10年前に同じ光文社新書で「西洋音楽論」という良著があって、作曲家・指揮者としてヨーロッパで活動してきた自身が西洋音楽の本質に覚醒していく経験を率直に語っていて、優れて啓蒙的なものでした。
というわけで、まずは著者の言い分を勝手に要約してみると次のようなものだと受け止めました。
批判1 戦前・戦後を通じて権威的存在だった井口基成が技術主義の元凶
批判2 明治の音楽教育は、本質を欠いた表面的な西洋音楽移植による機械論
批判3 明治政府の西洋音楽導入は、伝統邦楽の否定と軍事教育
批判4 日本人はダウンビート体質 アップビートを理解しない
批判5 西洋音楽は暴力的で平和志向の邦楽と相容れない
批判6 西洋音楽は階級社会的で資本主義・拡大主義
批判7 吉田秀和は、戦中内務省検閲に関わった権威主義者
批判8 楽譜に表記されていない音楽を再現発想する素養の欠如
批判9 日本人はフレージングが不得手(歌えない)
批判10 日本人の演奏は四角四面でスウィングがない
批判11 日本人は絶対音感偏重で相対音感が身についていない
批判12 コピーや既存知識ベースを組み合わせた最適解では創造はできない
多くは、かなり以前から言い古されてきたこと。著者自身、前著の使い回しというところもある。21世紀の現代、世界的に活躍する日本人作曲家、演奏家も多い。日本的な音楽伝統や美意識についての理解や共感も高まってきていて、日本文化に対する異国趣味一辺倒の好奇趣味的な視線はもはやほとんどない。それは決して著者の言うような西洋音楽(文化)の侵略支配とはいえないとも思います。その意味でも、著者の偽悪的な口調は、いささか時代錯誤なのではないでしょうか。
とはいえ、的確な指摘は多々ある。書きようによっては、クラシック音楽入門あるいは再入門として面白く読めるところも豊富にあったはず。学術的なささいな間違いで揚げ足をとられたり、吉田秀和批判などに拒否感を抱かれてしまうのは、編集部のそそのかしに安易にのってしまった著者の不徳の致すところというべきなのかもしれません。
もったいない。

日本のクラシック音楽は歪んでいる
12の批判的考察
森本 恭正 (著)
光文社新書
そういう私も、ネットで話題になっているのを見て、まんまと釣り上げられて手にしてみたクチ。ただし、この著者には、10年前に同じ光文社新書で「西洋音楽論」という良著があって、作曲家・指揮者としてヨーロッパで活動してきた自身が西洋音楽の本質に覚醒していく経験を率直に語っていて、優れて啓蒙的なものでした。
というわけで、まずは著者の言い分を勝手に要約してみると次のようなものだと受け止めました。
批判1 戦前・戦後を通じて権威的存在だった井口基成が技術主義の元凶
批判2 明治の音楽教育は、本質を欠いた表面的な西洋音楽移植による機械論
批判3 明治政府の西洋音楽導入は、伝統邦楽の否定と軍事教育
批判4 日本人はダウンビート体質 アップビートを理解しない
批判5 西洋音楽は暴力的で平和志向の邦楽と相容れない
批判6 西洋音楽は階級社会的で資本主義・拡大主義
批判7 吉田秀和は、戦中内務省検閲に関わった権威主義者
批判8 楽譜に表記されていない音楽を再現発想する素養の欠如
批判9 日本人はフレージングが不得手(歌えない)
批判10 日本人の演奏は四角四面でスウィングがない
批判11 日本人は絶対音感偏重で相対音感が身についていない
批判12 コピーや既存知識ベースを組み合わせた最適解では創造はできない
多くは、かなり以前から言い古されてきたこと。著者自身、前著の使い回しというところもある。21世紀の現代、世界的に活躍する日本人作曲家、演奏家も多い。日本的な音楽伝統や美意識についての理解や共感も高まってきていて、日本文化に対する異国趣味一辺倒の好奇趣味的な視線はもはやほとんどない。それは決して著者の言うような西洋音楽(文化)の侵略支配とはいえないとも思います。その意味でも、著者の偽悪的な口調は、いささか時代錯誤なのではないでしょうか。
とはいえ、的確な指摘は多々ある。書きようによっては、クラシック音楽入門あるいは再入門として面白く読めるところも豊富にあったはず。学術的なささいな間違いで揚げ足をとられたり、吉田秀和批判などに拒否感を抱かれてしまうのは、編集部のそそのかしに安易にのってしまった著者の不徳の致すところというべきなのかもしれません。
もったいない。

日本のクラシック音楽は歪んでいる
12の批判的考察
森本 恭正 (著)
光文社新書
タグ:森本 恭正
「新 古事記」(村田喜代子 著)読了 [読書]
作者がふと手にした、原爆開発の手記がもとになっています。
巻末の「謝辞」によると、その手記は、科学者の夫と共にニューメキシコ辺境に暮らした女性が記したもの。夫が勤めるロスアラモスの研究施設が原爆開発のためのものとは知らぬままに2年の歳月が過ぎた。新婚の彼女は、世界と隔絶した岩山の台地で両親に住所を知らせることもできず、夫の仕事の内容も教えられないままに家事と子育てに明け暮れたという。
マンハッタン計画。科学技術の軍事利用、それに加担する科学者たち。
そうした科学者たちの痛切な悔恨。原爆開発を強く提唱し、開発に関わった科学者の大半がホロコーストの恐怖から逃れたユダヤ人科学者たちだったこと。人種差別。日系移民迫害やそれを煽りたてるNYタイムズなどマスコミの執拗な日本人蔑視キャンペーン。ユダヤ人たちの成就は、その意図とは異なって、日本人の頭上で閃光となってすべてを焼き尽くすことになります。
そうした重たいテーマが、さりげない女性たちの日常のなかから薄明かりに照らし出されるように浮かび上がってきます。
集められた科学者はみな若い。だからロスアラモスは新婚さんだらけで、入所後のニューカップルも加わって、ちょっとした出産ラッシュになります。軍が警備する研究施設には大きな産院棟が増設される。
「あたし」は、そんなカップルのひとり。幼なじみの恋人についてきて、親にも知らせることができないままに、辺境の地で式をあげ、やがて身ごもる。柵の外にある動物病院の受付係を勤めているが、研究員が連れてきたペットで大忙し。最初はストレスで病んでいた愛犬たちも、繁殖期を迎えるとやがて人間と同じように出産ラッシュとなって殺到する。
新しい生命の誕生と大量破壊兵器の開発。「あたし」の日常は一見平和のようでいて、静かに湧き上がってくる不安と恐怖がある。時にはくぐもるような原因不明の怒りのようなものがこみ上げて来さえもする。ヒットラーが自殺を遂げ、ルーズベルトが脳卒中で死んでも、日本との戦争は続いている。
「あたし」は、自分が日系移民ではないけれども日本の血をひいていているということを夫に打ち明けた。リンカーン大統領の時に咸臨丸でアメリカにやってきた水夫の孫にあたる。…幼なじみの夫は、押し黙ったままだけど驚く様子もない。
ある日、研究員はこぞって行列を成して機材を積み込んだトラックで遠方を目指して出発する。その家族たちは、隊列が向かった方向とは違う遠望の効く山の頂点を目指す。そこで輝かしい閃光を見るためだ。
「あたし」の夫だけは、隊列には加わろうとせずそれに背を向けるようにして家にこもる。身ごもっていた「あたし」は、その夫とふたりで部屋のなかでひっそりと身を潜める。
ユダヤ人の聖典「タナハ」(旧約聖書)「創世記」では、神がまず「光あれ」と言う。すると光が現れ、闇とを分けた。それが天地創造の第一日の朝となる。
「わたし」の祖先の国の神話は、それとはだいぶ違う。背中合わせで決して顔を合わせないというほどに、とても対照的。
女神のイザナミの「成なり成なりて、成なり合あはざるところ」を、男神のイザナギの「成り成りて成り余あまれるところ」で「刺し塞たぎ」て、国を生み成す。…それが「古事記」の国生みの物語。
作者は、この小説の表題のいわれをひと言も語っていません。
でも、もともと作者は、胚胎というありふれている生の営みの、えも知れぬ不思議に、並々ならぬ関心をもって小説を書きつづってきたところもあります。それは、皮肉たっぷりのユーモアにあふれているけど、どこかに生命のぬくもりを感じさせます。今の私たちは、そういう辛辣な矛盾から逃れられないところに生きています。
この作家の傑作かもしれない。

新 古事記
村田喜代子
講談社
2023年8月8日 第一刷
初出(「新「古事記」an impossible story) 「群像」連載 2022年~23年
巻末の「謝辞」によると、その手記は、科学者の夫と共にニューメキシコ辺境に暮らした女性が記したもの。夫が勤めるロスアラモスの研究施設が原爆開発のためのものとは知らぬままに2年の歳月が過ぎた。新婚の彼女は、世界と隔絶した岩山の台地で両親に住所を知らせることもできず、夫の仕事の内容も教えられないままに家事と子育てに明け暮れたという。
マンハッタン計画。科学技術の軍事利用、それに加担する科学者たち。
そうした科学者たちの痛切な悔恨。原爆開発を強く提唱し、開発に関わった科学者の大半がホロコーストの恐怖から逃れたユダヤ人科学者たちだったこと。人種差別。日系移民迫害やそれを煽りたてるNYタイムズなどマスコミの執拗な日本人蔑視キャンペーン。ユダヤ人たちの成就は、その意図とは異なって、日本人の頭上で閃光となってすべてを焼き尽くすことになります。
そうした重たいテーマが、さりげない女性たちの日常のなかから薄明かりに照らし出されるように浮かび上がってきます。
集められた科学者はみな若い。だからロスアラモスは新婚さんだらけで、入所後のニューカップルも加わって、ちょっとした出産ラッシュになります。軍が警備する研究施設には大きな産院棟が増設される。
「あたし」は、そんなカップルのひとり。幼なじみの恋人についてきて、親にも知らせることができないままに、辺境の地で式をあげ、やがて身ごもる。柵の外にある動物病院の受付係を勤めているが、研究員が連れてきたペットで大忙し。最初はストレスで病んでいた愛犬たちも、繁殖期を迎えるとやがて人間と同じように出産ラッシュとなって殺到する。
新しい生命の誕生と大量破壊兵器の開発。「あたし」の日常は一見平和のようでいて、静かに湧き上がってくる不安と恐怖がある。時にはくぐもるような原因不明の怒りのようなものがこみ上げて来さえもする。ヒットラーが自殺を遂げ、ルーズベルトが脳卒中で死んでも、日本との戦争は続いている。
「あたし」は、自分が日系移民ではないけれども日本の血をひいていているということを夫に打ち明けた。リンカーン大統領の時に咸臨丸でアメリカにやってきた水夫の孫にあたる。…幼なじみの夫は、押し黙ったままだけど驚く様子もない。
ある日、研究員はこぞって行列を成して機材を積み込んだトラックで遠方を目指して出発する。その家族たちは、隊列が向かった方向とは違う遠望の効く山の頂点を目指す。そこで輝かしい閃光を見るためだ。
「あたし」の夫だけは、隊列には加わろうとせずそれに背を向けるようにして家にこもる。身ごもっていた「あたし」は、その夫とふたりで部屋のなかでひっそりと身を潜める。
ユダヤ人の聖典「タナハ」(旧約聖書)「創世記」では、神がまず「光あれ」と言う。すると光が現れ、闇とを分けた。それが天地創造の第一日の朝となる。
「わたし」の祖先の国の神話は、それとはだいぶ違う。背中合わせで決して顔を合わせないというほどに、とても対照的。
女神のイザナミの「成なり成なりて、成なり合あはざるところ」を、男神のイザナギの「成り成りて成り余あまれるところ」で「刺し塞たぎ」て、国を生み成す。…それが「古事記」の国生みの物語。
作者は、この小説の表題のいわれをひと言も語っていません。
でも、もともと作者は、胚胎というありふれている生の営みの、えも知れぬ不思議に、並々ならぬ関心をもって小説を書きつづってきたところもあります。それは、皮肉たっぷりのユーモアにあふれているけど、どこかに生命のぬくもりを感じさせます。今の私たちは、そういう辛辣な矛盾から逃れられないところに生きています。
この作家の傑作かもしれない。

新 古事記
村田喜代子
講談社
2023年8月8日 第一刷
初出(「新「古事記」an impossible story) 「群像」連載 2022年~23年
「未完のファシズム」(片山 杜秀 著)読了 [読書]
論旨はいたって明解。
エリート軍人たちは、始めから米英と戦争すれば国家滅亡に至ると知っていた。けれども、軍人の分をわきまえれば「負ける」「戦わない」と表立っては言えない。本音は負けるとわかっていても、表向きは勝てると言っていただけ…というのです。
*『統帥綱領』『戦闘綱要』を執筆した小畑敏四郎:
なるべく短期で決着する戦争をすればいい、それ以外は負けるからやれない
*満州事変を引き起こした張本人の石原莞爾:
日満経済ブロックに閉じこもり、どんなに挑発されようが大戦争はやらない
*『戦陣訓』の陰の執筆者で東条英機のブレーン役の中柴末純:
やる前から負けるとは言えないから、精神力で勝ててしまえることにしよう

いずれにせよ、米英のような「持てる国」に対して「持たざる国」である日本が戦争を挑めば必ず負ける。そう表立って言うわけにはいかない。火力・火砲で制圧するという装備戦力重視の戦術論は主張できないので、表向きは短期決戦・包囲殲滅や歩兵の練度・精神力で勝機をつかむ戦術論をひたすら押し通したというわけです。
そうした「皇道派」を一掃した「統制派」は、「持てる国」を目指して国家総動員体制によって経済力で米英に追いつこうという遠大な国家数十年の計を描いた。満州の資源と市場に霊感を得た石原莞爾がその代表だったというわけです。「統制」は、軍制の統制ばかりではなく、暗にソ連の計画経済をモデルとした統制経済の構築も目指していた。これが革新官僚たちに継承されて戦後の高成長を実現したというわけです。
しかし、そうした精神主義は誇大妄想となって世界を敵に回す大戦争に踏み込んでしまう。確かに真珠湾や南方作戦など当初の短期決戦には勝利し、死を恐れぬ日本軍兵士の突進力は恐れられたが、米軍は圧倒的な物量で確実に押し返していく。バンザイを叫んで突進してくる痩せこけた猿の群れは、銃口の先の格好の標的となって滅多打ちにされる…少なくともそういうキャンペーンが米国内で流布された。
大正期のエリート軍人が日露戦争を見る目は実に醒めていて、兵士を犠牲にするばかりの攻略は、「持たざる国」だからやむを得なかっただけであって、あんな時代遅れの戦争はもう二度とやれないと考えていた。その一方で、大国ロシア陸軍を相手に勝利した小国・日本の奮闘を見た欧米各国が、一時は本気で精神主義の歩兵戦重視に傾いたという指摘は興味深い。英独仏の軍事大国といえども、《寡を以って衆を制す》的な短期決戦・包囲殲滅戦への魅力に血湧き肉躍るものがあって、大いに勘違いしてしまうところがあったというわけです。
昭和史とかアジア・太平洋戦争の政治史としては、むしろ、トンデモ本なのかもしれませんが、軍事オタクにとってはたまらなく面白く、思わずフンフンとのめり込んでしまうオブナイ本と言えるでしょう。

未完のファシズム―「持たざる国」日本の運命
片山 杜秀 (著)
新潮選書
エリート軍人たちは、始めから米英と戦争すれば国家滅亡に至ると知っていた。けれども、軍人の分をわきまえれば「負ける」「戦わない」と表立っては言えない。本音は負けるとわかっていても、表向きは勝てると言っていただけ…というのです。
*『統帥綱領』『戦闘綱要』を執筆した小畑敏四郎:
なるべく短期で決着する戦争をすればいい、それ以外は負けるからやれない
*満州事変を引き起こした張本人の石原莞爾:
日満経済ブロックに閉じこもり、どんなに挑発されようが大戦争はやらない
*『戦陣訓』の陰の執筆者で東条英機のブレーン役の中柴末純:
やる前から負けるとは言えないから、精神力で勝ててしまえることにしよう

いずれにせよ、米英のような「持てる国」に対して「持たざる国」である日本が戦争を挑めば必ず負ける。そう表立って言うわけにはいかない。火力・火砲で制圧するという装備戦力重視の戦術論は主張できないので、表向きは短期決戦・包囲殲滅や歩兵の練度・精神力で勝機をつかむ戦術論をひたすら押し通したというわけです。
そうした「皇道派」を一掃した「統制派」は、「持てる国」を目指して国家総動員体制によって経済力で米英に追いつこうという遠大な国家数十年の計を描いた。満州の資源と市場に霊感を得た石原莞爾がその代表だったというわけです。「統制」は、軍制の統制ばかりではなく、暗にソ連の計画経済をモデルとした統制経済の構築も目指していた。これが革新官僚たちに継承されて戦後の高成長を実現したというわけです。
しかし、そうした精神主義は誇大妄想となって世界を敵に回す大戦争に踏み込んでしまう。確かに真珠湾や南方作戦など当初の短期決戦には勝利し、死を恐れぬ日本軍兵士の突進力は恐れられたが、米軍は圧倒的な物量で確実に押し返していく。バンザイを叫んで突進してくる痩せこけた猿の群れは、銃口の先の格好の標的となって滅多打ちにされる…少なくともそういうキャンペーンが米国内で流布された。
大正期のエリート軍人が日露戦争を見る目は実に醒めていて、兵士を犠牲にするばかりの攻略は、「持たざる国」だからやむを得なかっただけであって、あんな時代遅れの戦争はもう二度とやれないと考えていた。その一方で、大国ロシア陸軍を相手に勝利した小国・日本の奮闘を見た欧米各国が、一時は本気で精神主義の歩兵戦重視に傾いたという指摘は興味深い。英独仏の軍事大国といえども、《寡を以って衆を制す》的な短期決戦・包囲殲滅戦への魅力に血湧き肉躍るものがあって、大いに勘違いしてしまうところがあったというわけです。
昭和史とかアジア・太平洋戦争の政治史としては、むしろ、トンデモ本なのかもしれませんが、軍事オタクにとってはたまらなく面白く、思わずフンフンとのめり込んでしまうオブナイ本と言えるでしょう。

未完のファシズム―「持たざる国」日本の運命
片山 杜秀 (著)
新潮選書
タグ:片山杜秀



