将軍の世紀 下巻(山内 昌之 著) 読了 [読書]
下巻は、ほぼすべてが幕末に費やされている。
今までの幕末維新の歴史観はすべて倒幕側からのもの。本書はあくまでも標題の通りで将軍、すなわち江戸幕府側からの視点で書かれている。そのことが本書の独創的なところで、とても面白い。
下巻を読み通して、つくづく思うのは江戸幕府は内側から自壊したのだということ。滅ぼしたのは徳川御三家。その源泉であり中核となったのが水戸藩の斉昭。その実子である一橋慶喜が「大政奉還」という形で幕を引くことになる。
水戸が伝統的に背負っていたのは、藩主血統の正統性とその自戒から生まれた「水戸学」。その真髄は、儒学的な日本の社会秩序の精神的な権力体系。皇統に絶対的支配の頂点を求める「尊皇」思想のこと。この水戸学を狂信的な「攘夷」と結びつけたのが斉昭だった。
それは、第12代家斉の時代から始まった幕藩体制の弛緩とロシアなどの外国船の度重なる侵犯という社会背景によって、熱烈な反幕運動となって日本国中に浸透していくことになる。その否定の論理は過激化し、同時に強烈な保守の抵抗勢力を生み、互いに相容れない対立・分裂の危機を深めていく精神構造を胚胎していた。
家斉時代の反動としての家慶時代は、天保改革で幕を開ける。それは苛烈な緊縮・禁制に終始し、結局は幕府内部の改革には結びつかず挫折する。それほど幕内の既得権益は岩盤だった。そこに登場したのが「逆説の政治家」斉昭。
しかし「賢君」と期待された斉昭は、世間一般では人気が高かったが、その声望にふさわしい内実がともなわない。自らの「尊皇攘夷」が、将軍の人格を否定しその大権を干犯することに気がつかない。幕閣やその中核を成す親藩・譜代の大名たちは、斉昭の空疎なアジテーションを嫌いぬいた。幕政が混迷を深めるその一方で、足元の水戸藩も泥沼の派閥抗争に陥っていく。
こうした「尊皇攘夷」の狂気がもたらす対立・分裂の構造は、何も徳川幕府に限らない。薩長を中心とする外様の国持大名でも同じことになった。幕府も有力外様も、こうした血で血を洗う内部抗争で人材を消耗していく。幕府内の抗争はついに「安政の大獄」を生み、「桜田門外の変」で大局を喪失する。井伊直弼を闇討ちにしたのは水戸藩の脱藩浪士だった。幕府内に残されたのは、政治のリアリズムと実務には長けた人材だけで、大局を動かす人材は消失した。慶喜は斉昭の実子として生まれついたゆえに嫌われ続け、その不運が一生つきまとうことになる。
「攘夷」や「公武合体」を旗印に慶喜の周辺に輪を成した、会津の容保、桑名の定敬の兄弟も水戸徳川家の直系であり、彼らが頼みにした尾張藩慶勝も母方を通じて水戸につながっている。その血は、すなわち、そのまま水戸学「尊皇攘夷」のシンパということになる。こうした御三家、親藩譜代たちも、慶喜の醒めたリアリズムの足かせになるばかりで、結局は、薩摩のマキャベリズムの前に屈することになる。
本当に最後の将軍と言えるのは第14代の家茂だったのかもしれない。吉宗以来の紀伊徳川血統による血の入れ替えを図ったわけだが、何しろ家茂は若すぎた。心身ともに健全で見識もあり世情にも明るい青年政治家で幕閣からの敬愛も深かったが、結局は、その誠実な真情も幕末の政治的混沌には抗しきれない。長州征討の途上で虚しく夭折したのは政治に翻弄され続けた精神的抑圧がもたらした悲劇というしかない。
実際、家茂には「攘夷」論の愚を明瞭に見通す眼力があった。「世界の大勢は、和親を結び互いに富強を図る習いに変わったのに、日本だけは一向に外交に関わらないというのでは『卑怯退縮』であり、国のかたちも威信もかえって立たない」と喝破していた。孝明天皇が、一貫して佐幕の立場を貫いたのはこうした家茂の誠実さだった。孝明天皇は暗愚ではなかったが、あまりに世間知らずで朝廷をめぐる陰謀を統御できなかった。その「攘夷」は、むしろ無知ゆえの「ゼノフォビア(外国人恐怖)」であって、終始、家茂を悩ませた。「攘夷」の狂気がさっぱりと消え失せたのは孝明天皇崩御の瞬間だったいえる。日本国中がようやく冷静を取り戻すことになる。
「大政奉還」を果断に実行したのは慶喜の功績といえるが、「将軍辞職」は何も最後の土壇場に浮上したわけではないという。家茂も深刻に考えていた。表明寸前で幕閣に抵抗されて挫折している。薩摩の武力倒幕論に対して、建白による平和革命を説いたのが土佐藩だった。大政奉還の建白を思いついたのは、高知の漢方医・今井順青だったそうだ。それを坂本龍馬が後藤象二郎に伝え、山内容堂が諒承する。著者は、容堂の律儀さを称賛してやまない。慶喜の名誉は、容堂によって与えられたものであり、滅びゆく武家社会最後の道徳観の発露だったとさえ言う。
とにかく長大な幕末史を語って倦むことがない「下巻」だが、慶喜の時代はそのほんのわずかな紙数に過ぎない。実際、慶喜が将軍職にあったのは1年にわずかに満たない。この間、江戸城にすらも入ったことがない。しかし、一橋慶喜とその行動は家茂時代にはむしろ家茂以上に言及されている。なんといっても徳川幕府終焉をもたらしたのは、水戸の副将軍・斉昭とその子・慶喜だったのだから。
著者によれば、慶喜の犯した取り返しのつかない錯誤は、薩長の挑発に乗って鳥羽伏見の戦端を開いたことだという。薩長の武力倒幕は幕末維新の最大の汚点だが、それは島津久光の病による統制喪失のせいもあったという。せっかくの大政奉還にもかかわらず、慶喜がかえって戦乱を招いたことになっのは不幸なことだったと著者は惜しむ。
いずれにせよ、もはや将軍の世紀は終わっていて、戊辰戦争以後は章外のこととなる。
壮大かつ詳細を究める幕末史として「下巻」だけでも大変に読み応えがあった。
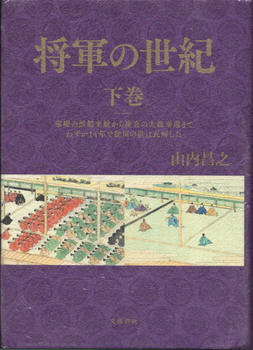
将軍の世紀 下巻
パクス・トクガワナを築いた家康の戦略から遊王・家斉の爛熟まで
山内 昌之 (著)
文藝春秋
2023年4月新刊
今までの幕末維新の歴史観はすべて倒幕側からのもの。本書はあくまでも標題の通りで将軍、すなわち江戸幕府側からの視点で書かれている。そのことが本書の独創的なところで、とても面白い。
下巻を読み通して、つくづく思うのは江戸幕府は内側から自壊したのだということ。滅ぼしたのは徳川御三家。その源泉であり中核となったのが水戸藩の斉昭。その実子である一橋慶喜が「大政奉還」という形で幕を引くことになる。
水戸が伝統的に背負っていたのは、藩主血統の正統性とその自戒から生まれた「水戸学」。その真髄は、儒学的な日本の社会秩序の精神的な権力体系。皇統に絶対的支配の頂点を求める「尊皇」思想のこと。この水戸学を狂信的な「攘夷」と結びつけたのが斉昭だった。
それは、第12代家斉の時代から始まった幕藩体制の弛緩とロシアなどの外国船の度重なる侵犯という社会背景によって、熱烈な反幕運動となって日本国中に浸透していくことになる。その否定の論理は過激化し、同時に強烈な保守の抵抗勢力を生み、互いに相容れない対立・分裂の危機を深めていく精神構造を胚胎していた。
家斉時代の反動としての家慶時代は、天保改革で幕を開ける。それは苛烈な緊縮・禁制に終始し、結局は幕府内部の改革には結びつかず挫折する。それほど幕内の既得権益は岩盤だった。そこに登場したのが「逆説の政治家」斉昭。
しかし「賢君」と期待された斉昭は、世間一般では人気が高かったが、その声望にふさわしい内実がともなわない。自らの「尊皇攘夷」が、将軍の人格を否定しその大権を干犯することに気がつかない。幕閣やその中核を成す親藩・譜代の大名たちは、斉昭の空疎なアジテーションを嫌いぬいた。幕政が混迷を深めるその一方で、足元の水戸藩も泥沼の派閥抗争に陥っていく。
こうした「尊皇攘夷」の狂気がもたらす対立・分裂の構造は、何も徳川幕府に限らない。薩長を中心とする外様の国持大名でも同じことになった。幕府も有力外様も、こうした血で血を洗う内部抗争で人材を消耗していく。幕府内の抗争はついに「安政の大獄」を生み、「桜田門外の変」で大局を喪失する。井伊直弼を闇討ちにしたのは水戸藩の脱藩浪士だった。幕府内に残されたのは、政治のリアリズムと実務には長けた人材だけで、大局を動かす人材は消失した。慶喜は斉昭の実子として生まれついたゆえに嫌われ続け、その不運が一生つきまとうことになる。
「攘夷」や「公武合体」を旗印に慶喜の周辺に輪を成した、会津の容保、桑名の定敬の兄弟も水戸徳川家の直系であり、彼らが頼みにした尾張藩慶勝も母方を通じて水戸につながっている。その血は、すなわち、そのまま水戸学「尊皇攘夷」のシンパということになる。こうした御三家、親藩譜代たちも、慶喜の醒めたリアリズムの足かせになるばかりで、結局は、薩摩のマキャベリズムの前に屈することになる。
本当に最後の将軍と言えるのは第14代の家茂だったのかもしれない。吉宗以来の紀伊徳川血統による血の入れ替えを図ったわけだが、何しろ家茂は若すぎた。心身ともに健全で見識もあり世情にも明るい青年政治家で幕閣からの敬愛も深かったが、結局は、その誠実な真情も幕末の政治的混沌には抗しきれない。長州征討の途上で虚しく夭折したのは政治に翻弄され続けた精神的抑圧がもたらした悲劇というしかない。
実際、家茂には「攘夷」論の愚を明瞭に見通す眼力があった。「世界の大勢は、和親を結び互いに富強を図る習いに変わったのに、日本だけは一向に外交に関わらないというのでは『卑怯退縮』であり、国のかたちも威信もかえって立たない」と喝破していた。孝明天皇が、一貫して佐幕の立場を貫いたのはこうした家茂の誠実さだった。孝明天皇は暗愚ではなかったが、あまりに世間知らずで朝廷をめぐる陰謀を統御できなかった。その「攘夷」は、むしろ無知ゆえの「ゼノフォビア(外国人恐怖)」であって、終始、家茂を悩ませた。「攘夷」の狂気がさっぱりと消え失せたのは孝明天皇崩御の瞬間だったいえる。日本国中がようやく冷静を取り戻すことになる。
「大政奉還」を果断に実行したのは慶喜の功績といえるが、「将軍辞職」は何も最後の土壇場に浮上したわけではないという。家茂も深刻に考えていた。表明寸前で幕閣に抵抗されて挫折している。薩摩の武力倒幕論に対して、建白による平和革命を説いたのが土佐藩だった。大政奉還の建白を思いついたのは、高知の漢方医・今井順青だったそうだ。それを坂本龍馬が後藤象二郎に伝え、山内容堂が諒承する。著者は、容堂の律儀さを称賛してやまない。慶喜の名誉は、容堂によって与えられたものであり、滅びゆく武家社会最後の道徳観の発露だったとさえ言う。
とにかく長大な幕末史を語って倦むことがない「下巻」だが、慶喜の時代はそのほんのわずかな紙数に過ぎない。実際、慶喜が将軍職にあったのは1年にわずかに満たない。この間、江戸城にすらも入ったことがない。しかし、一橋慶喜とその行動は家茂時代にはむしろ家茂以上に言及されている。なんといっても徳川幕府終焉をもたらしたのは、水戸の副将軍・斉昭とその子・慶喜だったのだから。
著者によれば、慶喜の犯した取り返しのつかない錯誤は、薩長の挑発に乗って鳥羽伏見の戦端を開いたことだという。薩長の武力倒幕は幕末維新の最大の汚点だが、それは島津久光の病による統制喪失のせいもあったという。せっかくの大政奉還にもかかわらず、慶喜がかえって戦乱を招いたことになっのは不幸なことだったと著者は惜しむ。
いずれにせよ、もはや将軍の世紀は終わっていて、戊辰戦争以後は章外のこととなる。
壮大かつ詳細を究める幕末史として「下巻」だけでも大変に読み応えがあった。
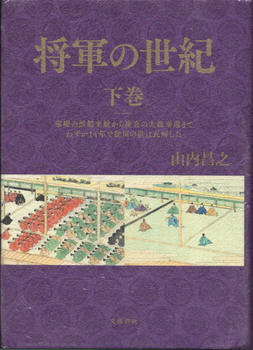
将軍の世紀 下巻
パクス・トクガワナを築いた家康の戦略から遊王・家斉の爛熟まで
山内 昌之 (著)
文藝春秋
2023年4月新刊




コメント 0