日下紗矢子リーダーによる室内合奏団 (読響アンサンブルシリーズ) [コンサート]
読響のメンバーによる室内楽プロジェクト。いろいろなリーダーの下で様々な編成での企画のアンサンブルシリーズです。
企画そのものにもちろん各リーダーのアイデアが盛り込まれるだけでなく、普段は指揮者のキャラクターに隠れがちなリーダーの統率の個性が浮かび上がってくるところもあります。
今回は、日下紗矢子さんの個性が存分に発揮されました。
日下さんはほっそりとしなやかな姿態のヴァイオリニスト――その暖かな笑顔にもかかわらず、その音楽は、けっこう強面。そのリーダーシップから引き出される引き締まったアンサンブルは峻厳にして直截。そのことは、ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団の第一コンサートマスターとしてエッシェンバッハの絶大な信頼を得ていることからもわかりますし、リーダーを務める同楽団メンバーによる室内管弦楽団の演奏からも感じ取れます。
ハイドンの若い交響曲で始まり、間に二十世紀の弦楽合奏曲をはさんで、ハイドン中期の交響曲で締めるというプログラム。ハイドンの選曲もさることながら、その間に入る弦楽アンサンブルの選曲もいかにも日下さんらしい。
ハイドンの記念すべき交響曲第一作。20代半ばの若きハイドンの瑞々しい感性とともに、その彼がまず規範としたイタリア的な輝かしい陽光溢れる音楽になっています。ナチュラルホルンなどの管楽器の音色の純朴さが、弦楽器だけの第二楽章の色艶とのコントラストから浮かび上がらせているところも、日下さんらしい。
プログラムの核心は、やはり、二曲目のヤナーチェク。
もともとは弦楽四重奏曲の名曲ですが、先日、紀尾井ホールで聴いたリチャード・トネッティの編曲版。トルストイのドロドロの不倫小説をそのままに音楽化したもので、クァルテットで聴いても、痛切かつ懊悩と破局へと連なる緊張みなぎるテンションの高い音楽で、これを6-4-4-3-2の大きめの弦楽五部で演奏されるので相当に手強い音楽です。プレトークで司会者が、「スル・ポンティチェロの奇怪な音もアンサンブルでやるときれいになるますね」と口を滑らせると、日下さんは「そうですか?じゃあ、本番ではもっともっと汚い音になるように全力でやりましょう」と斬り返されタジタジ(笑)。

後半のシュレーカーは、日下さんのお好みの作曲家だそうです。
シェーンベルクの「グレの歌」などの初演も行った人でワイマール時代にはR.シュトラウスに次いで人気のあった現役オペラ作曲家で、ベルリン高等音楽学校の校長にまでなった音楽家。ユダヤの血もひいていたことからナチにその地位を追われ、直後に脳梗塞で倒れたことで戦争を生きながらえることがかないませんでした。そのせいでなかなかメジャーとして取り上げられませんが、もしかしたらこれからぐんぐんと知られるようになるかもしれない――聴いてみるとなかなかの曲でした。
最後のハイドンも、いかにも日下さんらしい選曲。
エステルハージ宮廷楽長の地位の束縛を脱しようとしていた時期。「イギリス交響曲」と「パリ交響曲」の狭間で無名のために取り上げられることが少ないのですが、開かれた市民社会へと向き合い始めた自由さが充溢。最後の楽章のシンコペーションの心地よいグルーヴ感がその証しです。
アンサンブルは、短期間で仕上げた粗さも感じましたが、ある意味では日下さんらしいリーダーシップのクリスプな味わいと、読響の名手たちによる早生のフレッシュ感が逆にとてもすがすがしく感じられました。

読響アンサンブル・シリーズ
第38回 《日下紗矢子リーダーによる室内合奏団》
2023年7月28日(金) 19:30~
トッパンホール
(M列 14番)
ヴァイオリン/リーダー=日下紗矢子(読響特別客演コンサートマスター)
岸本萌乃加(次席)荒川以津美、井上雅美、
大澤理菜子、小形響、鎌田成光、武田桃子、寺井馨、山田耕司
ヴィオラ=三浦克之、長岡晶子、長倉寛、森口恭子
チェロ=遠藤真理(読響ソロ・チェロ)、木村隆哉、室野良史
コントラバス=石川滋(読響ソロ・コントラバス)、小金丸章斗
フルート=佐藤友美
オーボエ=山本楓、多田敦美(客演)
ファゴット=吉田将(読響首席)、岩佐雅美
ホルン=松坂隼(読響隼)、伴野涼介
ハイドン:交響曲第1番 ニ長調
ヤナーチェク:弦楽四重奏曲第1番「クロイツェル・ソナタ」(弦楽合奏版)
シュレーカー:弦楽オーケストラのためのスケルツォ
ハイドン:交響曲第80番 二短調
企画そのものにもちろん各リーダーのアイデアが盛り込まれるだけでなく、普段は指揮者のキャラクターに隠れがちなリーダーの統率の個性が浮かび上がってくるところもあります。
今回は、日下紗矢子さんの個性が存分に発揮されました。
日下さんはほっそりとしなやかな姿態のヴァイオリニスト――その暖かな笑顔にもかかわらず、その音楽は、けっこう強面。そのリーダーシップから引き出される引き締まったアンサンブルは峻厳にして直截。そのことは、ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団の第一コンサートマスターとしてエッシェンバッハの絶大な信頼を得ていることからもわかりますし、リーダーを務める同楽団メンバーによる室内管弦楽団の演奏からも感じ取れます。
ハイドンの若い交響曲で始まり、間に二十世紀の弦楽合奏曲をはさんで、ハイドン中期の交響曲で締めるというプログラム。ハイドンの選曲もさることながら、その間に入る弦楽アンサンブルの選曲もいかにも日下さんらしい。
ハイドンの記念すべき交響曲第一作。20代半ばの若きハイドンの瑞々しい感性とともに、その彼がまず規範としたイタリア的な輝かしい陽光溢れる音楽になっています。ナチュラルホルンなどの管楽器の音色の純朴さが、弦楽器だけの第二楽章の色艶とのコントラストから浮かび上がらせているところも、日下さんらしい。
プログラムの核心は、やはり、二曲目のヤナーチェク。
もともとは弦楽四重奏曲の名曲ですが、先日、紀尾井ホールで聴いたリチャード・トネッティの編曲版。トルストイのドロドロの不倫小説をそのままに音楽化したもので、クァルテットで聴いても、痛切かつ懊悩と破局へと連なる緊張みなぎるテンションの高い音楽で、これを6-4-4-3-2の大きめの弦楽五部で演奏されるので相当に手強い音楽です。プレトークで司会者が、「スル・ポンティチェロの奇怪な音もアンサンブルでやるときれいになるますね」と口を滑らせると、日下さんは「そうですか?じゃあ、本番ではもっともっと汚い音になるように全力でやりましょう」と斬り返されタジタジ(笑)。
後半のシュレーカーは、日下さんのお好みの作曲家だそうです。
シェーンベルクの「グレの歌」などの初演も行った人でワイマール時代にはR.シュトラウスに次いで人気のあった現役オペラ作曲家で、ベルリン高等音楽学校の校長にまでなった音楽家。ユダヤの血もひいていたことからナチにその地位を追われ、直後に脳梗塞で倒れたことで戦争を生きながらえることがかないませんでした。そのせいでなかなかメジャーとして取り上げられませんが、もしかしたらこれからぐんぐんと知られるようになるかもしれない――聴いてみるとなかなかの曲でした。
最後のハイドンも、いかにも日下さんらしい選曲。
エステルハージ宮廷楽長の地位の束縛を脱しようとしていた時期。「イギリス交響曲」と「パリ交響曲」の狭間で無名のために取り上げられることが少ないのですが、開かれた市民社会へと向き合い始めた自由さが充溢。最後の楽章のシンコペーションの心地よいグルーヴ感がその証しです。
アンサンブルは、短期間で仕上げた粗さも感じましたが、ある意味では日下さんらしいリーダーシップのクリスプな味わいと、読響の名手たちによる早生のフレッシュ感が逆にとてもすがすがしく感じられました。

読響アンサンブル・シリーズ
第38回 《日下紗矢子リーダーによる室内合奏団》
2023年7月28日(金) 19:30~
トッパンホール
(M列 14番)
ヴァイオリン/リーダー=日下紗矢子(読響特別客演コンサートマスター)
岸本萌乃加(次席)荒川以津美、井上雅美、
大澤理菜子、小形響、鎌田成光、武田桃子、寺井馨、山田耕司
ヴィオラ=三浦克之、長岡晶子、長倉寛、森口恭子
チェロ=遠藤真理(読響ソロ・チェロ)、木村隆哉、室野良史
コントラバス=石川滋(読響ソロ・コントラバス)、小金丸章斗
フルート=佐藤友美
オーボエ=山本楓、多田敦美(客演)
ファゴット=吉田将(読響首席)、岩佐雅美
ホルン=松坂隼(読響隼)、伴野涼介
ハイドン:交響曲第1番 ニ長調
ヤナーチェク:弦楽四重奏曲第1番「クロイツェル・ソナタ」(弦楽合奏版)
シュレーカー:弦楽オーケストラのためのスケルツォ
ハイドン:交響曲第80番 二短調
シングルMFPCのお披露目 [オーディオ]
新しいMFPCのお披露目をしました。
導入して2ヶ月近く経ち、セッティングの周辺の見極めなど落ち着いたので聴いていただきました。

新しいMFPCは、何とミニデスクPCたった1台という構成です。別に隠すつもりはありませんが、DACとのUSBケーブルが従来使用の短いものがベストだったのでラック裏に押し込めてしまったというわけです。

従来は、ミニデスクを中心に5台構成でした。ミニデスクにRoon Core、Controller、Bufferとネットワーク経由で分散処理をさせ、RoonBridgeを経由してDiretta Target PCに送り込むという構成。
これが1台のシングルPCで、むしろ、音が良いというわけですから痛快。このPCは、従来、Roon Coreに使用していたミニデスク(i9 2.8GHz)をそのまま転用しましたのでハードの追加費用はゼロです。省スペースの効果で、ラック内に余裕が生じ、このことも音質アップに一役買ったことも思わぬ効果。
初めは roon + HQPlayer + NAA という構成でしたが、Bridge PC 導入時に、まず HQPlayer は卒業。Diretta導入時には、機能的に重複するNAAともおさらば。Diretta導入による音質アップはダントツでした。PC1台に戻って、そのDirettaも不要というのですからネットワークレスの効果は絶大です。
これが実現できたのは、Windowsのプロセスカットをさらに徹底したことによるそうです。これに貢献したのがChatGPTだというからそういう時代なのでしょうね。カットする順番の精緻を極めることで、それまではカットできなかったものも可能になる。その知恵をAIが見つけてくる。最後にはカットのバッチのコマンドラインまで書いてくれるというのですから驚きです。

さて、その新MFPCのお披露目の比較試聴です…
比較は、CD、PC。DAC以下アンプ、スピーカーはまったく同じというガチンコ対決。CDとそのディスクからリッピングしたファイル再生です。アナログがある音源ソフトは、リファレンスとしてまずアナログ再生を聴いていただき、その上での比較です。
機材の構成はざっと以下の通り。
GRANDIOSO K1 (CD player/USB DAC)
金田式DCプリアンプ(バッテリー駆動+出川式 LCM 電源 Phono-EQ 内蔵)
〃 パワーアンプ( 〃 〃 )
PSD T-4 (パワーアンプ直結 2wayマルチドラブ)
(参考-アナログ系)
YAMAHA GT2000X
ViV Laboratory Rigid Float
DENON DL103改

Mさんは、自らギターも弾く音楽ファン。マンション住まいなので2千枚以上のCDの収納に悩んでおられましたので、私のファイルオーディオに目をつけられました。それがシングル体制になったことを聞きつけいよいよ導入に本気になったそうです。
半信半疑だったMさんも、聴いた途端にCDよりも音が良いことに驚かれたようです。ご感想をお聞きすると、やはり楽器をやられている人は鋭い。空間の左右の広がりと前後の深度、バックスの定位の安定感と実在感、コーラスの息づかいや声の質感のリアルさなどがびっくりするほど違うという。こんな音も入っていたのかという発見が続出する…。私は、クラシック音楽派なので、ロック・ポップ系に造詣の深いMさんのお言葉は力強い。
翌日は、板倉さんにも聴いていただきました。
板倉さんのご感想を聞くと、やっぱり板倉さんはボーカルフェチ(笑)だなぁと痛感しました。聴いているところが私やMさんのようなインストフェチとちょっと違う。
最初のE.クラプトン("Tears in Heaven")では、クラプトンのボーカルが少し薄めで芯が弱くなると言うのです。これは多少、私やMさんも感じていたことなのですが、これは弱音の解像度の高さと空間表現の深化とのトレードオフのようなもので、いままで聴いてきたCD再生のコントラストのほうに親しみを感じてしまうからです。
ファイル再生だけでしたが、私が自分で課題と思っている女性ボーカルの検定もお願いしました。中森明菜の(「セカンドラブ」)でお褒めいただいたのはうれしかったですね。竹内まりやのセルフカバー(「元気を出して」)のエンディング・リフレインのバックコーラスが鮮やかと評されてうれしくて天にも昇る心地。コーラスから薬師丸ひろ子や山下達郎の声が鮮度明瞭に聴き取れて心が華やぐのです。竹内まりやもまだまだ若々しかった。
アナログをまず聴いてもらうという狙いもうまくはまってくれました。
従来は、デジタル再生をいろいろ聴き較べて、最後にアナログディスクを回すと、「なぁんだ、やっぱりオリジナルのアナログ再生が一番だね」となるのがオチでしたが、新・MFPC は、デジタルの情報量の多さとアナログのエネルギッシュな濃密さとのいいとこ取り。特に、太田裕美(「青春のしおり」)の声の強さと濃度の高さがアナログと遜色ありません。この《自己満足》をご納得いただけたことも何よりでした。
導入して2ヶ月近く経ち、セッティングの周辺の見極めなど落ち着いたので聴いていただきました。
新しいMFPCは、何とミニデスクPCたった1台という構成です。別に隠すつもりはありませんが、DACとのUSBケーブルが従来使用の短いものがベストだったのでラック裏に押し込めてしまったというわけです。
従来は、ミニデスクを中心に5台構成でした。ミニデスクにRoon Core、Controller、Bufferとネットワーク経由で分散処理をさせ、RoonBridgeを経由してDiretta Target PCに送り込むという構成。
これが1台のシングルPCで、むしろ、音が良いというわけですから痛快。このPCは、従来、Roon Coreに使用していたミニデスク(i9 2.8GHz)をそのまま転用しましたのでハードの追加費用はゼロです。省スペースの効果で、ラック内に余裕が生じ、このことも音質アップに一役買ったことも思わぬ効果。
初めは roon + HQPlayer + NAA という構成でしたが、Bridge PC 導入時に、まず HQPlayer は卒業。Diretta導入時には、機能的に重複するNAAともおさらば。Diretta導入による音質アップはダントツでした。PC1台に戻って、そのDirettaも不要というのですからネットワークレスの効果は絶大です。
これが実現できたのは、Windowsのプロセスカットをさらに徹底したことによるそうです。これに貢献したのがChatGPTだというからそういう時代なのでしょうね。カットする順番の精緻を極めることで、それまではカットできなかったものも可能になる。その知恵をAIが見つけてくる。最後にはカットのバッチのコマンドラインまで書いてくれるというのですから驚きです。
さて、その新MFPCのお披露目の比較試聴です…
比較は、CD、PC。DAC以下アンプ、スピーカーはまったく同じというガチンコ対決。CDとそのディスクからリッピングしたファイル再生です。アナログがある音源ソフトは、リファレンスとしてまずアナログ再生を聴いていただき、その上での比較です。
機材の構成はざっと以下の通り。
GRANDIOSO K1 (CD player/USB DAC)
金田式DCプリアンプ(バッテリー駆動+出川式 LCM 電源 Phono-EQ 内蔵)
〃 パワーアンプ( 〃 〃 )
PSD T-4 (パワーアンプ直結 2wayマルチドラブ)
(参考-アナログ系)
YAMAHA GT2000X
ViV Laboratory Rigid Float
DENON DL103改
Mさんは、自らギターも弾く音楽ファン。マンション住まいなので2千枚以上のCDの収納に悩んでおられましたので、私のファイルオーディオに目をつけられました。それがシングル体制になったことを聞きつけいよいよ導入に本気になったそうです。
半信半疑だったMさんも、聴いた途端にCDよりも音が良いことに驚かれたようです。ご感想をお聞きすると、やはり楽器をやられている人は鋭い。空間の左右の広がりと前後の深度、バックスの定位の安定感と実在感、コーラスの息づかいや声の質感のリアルさなどがびっくりするほど違うという。こんな音も入っていたのかという発見が続出する…。私は、クラシック音楽派なので、ロック・ポップ系に造詣の深いMさんのお言葉は力強い。
翌日は、板倉さんにも聴いていただきました。
板倉さんのご感想を聞くと、やっぱり板倉さんはボーカルフェチ(笑)だなぁと痛感しました。聴いているところが私やMさんのようなインストフェチとちょっと違う。
最初のE.クラプトン("Tears in Heaven")では、クラプトンのボーカルが少し薄めで芯が弱くなると言うのです。これは多少、私やMさんも感じていたことなのですが、これは弱音の解像度の高さと空間表現の深化とのトレードオフのようなもので、いままで聴いてきたCD再生のコントラストのほうに親しみを感じてしまうからです。
ファイル再生だけでしたが、私が自分で課題と思っている女性ボーカルの検定もお願いしました。中森明菜の(「セカンドラブ」)でお褒めいただいたのはうれしかったですね。竹内まりやのセルフカバー(「元気を出して」)のエンディング・リフレインのバックコーラスが鮮やかと評されてうれしくて天にも昇る心地。コーラスから薬師丸ひろ子や山下達郎の声が鮮度明瞭に聴き取れて心が華やぐのです。竹内まりやもまだまだ若々しかった。
アナログをまず聴いてもらうという狙いもうまくはまってくれました。
従来は、デジタル再生をいろいろ聴き較べて、最後にアナログディスクを回すと、「なぁんだ、やっぱりオリジナルのアナログ再生が一番だね」となるのがオチでしたが、新・MFPC は、デジタルの情報量の多さとアナログのエネルギッシュな濃密さとのいいとこ取り。特に、太田裕美(「青春のしおり」)の声の強さと濃度の高さがアナログと遜色ありません。この《自己満足》をご納得いただけたことも何よりでした。
タグ:MFPC
「蘇我氏四代」(遠山美都男 著)読了 [読書]
私たちの世代までは、蘇我氏は専横のままに政治を壟断し王権を簒奪しようとした極悪人で、大化の改新で中大兄皇子と中臣鎌足に誅せられたのも当然というように教えられてきた。
著者は、そういう蘇我氏四代に不当に課せられた汚名の虚偽を暴き、えん罪を晴らしていく。曰く、蘇我氏は葛城氏の正統を受け継ぐ群臣筆頭の家柄であり、蝦夷も入鹿も王権の意に忠実に従い為政に精励した忠臣だったと説く。
蘇我氏の歴史的評価見直しが、古代史研究の大きな転機であったことは間違いなさそうだ。王位というものが有力豪族の間でどのような位置づけだったのか、後継指名のあり方をめぐっての争いを通じて古代王権の確立に至った経緯が近年ずいぶんと明らかになってきた。王の在所、政権の執政所は、背景となる有力豪族によって左右されていたが、集権の象徴としての王都建設が政策の主眼となって争点ともなっていく。
「書紀」や「古事記」などのテキストを批判的に解読し、その記述の齟齬や矛盾を丹念に読み解いていく手法はとても丁寧だが、読者にとってはいささか退屈で難渋の連続。
文献学的な手法で読み解いても、正史というものは編纂にあたっては政治的な価値観に左右されているわけだから、本来は、後世の私たちがそれをどのようなバイアスで読み取ったかとかいったことが問題であって、必ずしも歴史的な事実の探求たり得ない。えん罪を晴らしたところで真犯人や新事実は現れてこない。本書にはそういうもどかしさがある。
「臣、罪を知らず」というのは、入鹿の断末魔の叫びだったが、では、入鹿は誰かにはめられたのか。それにしても、大王面前の公式行事の最中の血生臭いクーデターはあまりにも異様である。その犯人と真の動機が解明されないのでは、それまで耐えて読んできた長文が何だったのかという欲求不満がつのる。
結末の欲求不満に加えて、厩戸皇子(聖徳太子)の血統がなぜにこれほどまでに排除されたのかという謎も深まるばかり。
歴史に勧善懲悪はあり得ないというのはあたりまえの時代。そのことを定着させたことに著者は貢献したことは間違いないが、その先がほしい。古代史には、まだまだ謎が多い。

蘇我氏四代 臣、罪を知らず
遠山美都男 (著)
ミネルヴァ書房 (ミネルヴァ日本評伝選)
2006年初版
著者は、そういう蘇我氏四代に不当に課せられた汚名の虚偽を暴き、えん罪を晴らしていく。曰く、蘇我氏は葛城氏の正統を受け継ぐ群臣筆頭の家柄であり、蝦夷も入鹿も王権の意に忠実に従い為政に精励した忠臣だったと説く。
蘇我氏の歴史的評価見直しが、古代史研究の大きな転機であったことは間違いなさそうだ。王位というものが有力豪族の間でどのような位置づけだったのか、後継指名のあり方をめぐっての争いを通じて古代王権の確立に至った経緯が近年ずいぶんと明らかになってきた。王の在所、政権の執政所は、背景となる有力豪族によって左右されていたが、集権の象徴としての王都建設が政策の主眼となって争点ともなっていく。
「書紀」や「古事記」などのテキストを批判的に解読し、その記述の齟齬や矛盾を丹念に読み解いていく手法はとても丁寧だが、読者にとってはいささか退屈で難渋の連続。
文献学的な手法で読み解いても、正史というものは編纂にあたっては政治的な価値観に左右されているわけだから、本来は、後世の私たちがそれをどのようなバイアスで読み取ったかとかいったことが問題であって、必ずしも歴史的な事実の探求たり得ない。えん罪を晴らしたところで真犯人や新事実は現れてこない。本書にはそういうもどかしさがある。
「臣、罪を知らず」というのは、入鹿の断末魔の叫びだったが、では、入鹿は誰かにはめられたのか。それにしても、大王面前の公式行事の最中の血生臭いクーデターはあまりにも異様である。その犯人と真の動機が解明されないのでは、それまで耐えて読んできた長文が何だったのかという欲求不満がつのる。
結末の欲求不満に加えて、厩戸皇子(聖徳太子)の血統がなぜにこれほどまでに排除されたのかという謎も深まるばかり。
歴史に勧善懲悪はあり得ないというのはあたりまえの時代。そのことを定着させたことに著者は貢献したことは間違いないが、その先がほしい。古代史には、まだまだ謎が多い。

蘇我氏四代 臣、罪を知らず
遠山美都男 (著)
ミネルヴァ書房 (ミネルヴァ日本評伝選)
2006年初版
タグ:蘇我氏四代
伝統をモダンへ (紀尾井ホール室内管・定期演奏会) [コンサート]
しばらくは興奮が収まらなかった。
頭がほてってしまって、その音楽についていったい何からどう書きとめたらよいのやら考えがまとまらなかったほど。トネッティは、以前から期待していたけれど、コロナ禍で来日が延期になってしまい、その思いが募るばかりだった。なにしろ、あのバッハ弾きのアンジェラ・ヒューイットが、コンチェルトの録音に指名したのがトネッティとオーストラリア室内管。バッハと新大陸の――しかも、南北の両半球にまたがる二つの大陸の――音楽家との結びつきの不思議さがあったから。

プログラムからもそういう不思議な飛躍感が予見されていた。
前半・後半ともに二十世紀と古典派、200年を隔たりをもって作曲された曲をペアリングした二部形式。
しかも、いずれも(チェロを除いて)全員が立って演奏する。現代曲は、ヴァイオリンのソロを伴った弦楽だけの合奏。ハイドンとモーツァルトでは、管楽器群も全員が立奏。おそらくこれは楽団初めてのことではないか。現代曲は二十世紀型配置で、古典の二曲は両翼対向型。曲間でいちいち交代するが、譜面台を第二ヴァイオリンとヴィオラで交換するだけなので簡単といえば簡単だが、その狙いと効果は歴然。
トネッティは、弾き振り。ソロでは中央に立つが時おり弓を高く振って全体をリードする。武満だけはコンサートマスターを玉井菜採に任せているが、ソロはトネッティが兼ねる。そのことは古典派の二曲でも同じ。むしろ指揮振りの身振りはかえって大きい。
そういう不思議な態様と編成の効果は、絶大。一曲目から、その音楽的効果に唖然ともしたし、思わず腰が浮いてしまうほど高揚した。
「オラヴァ」というのは、ポーランドとスロヴァキアの国境にある地域名だとのことで、そのオラヴァ地方の民俗音楽を土台としているのだとか。同じ音型を執拗に繰り返し、変形していく。弦楽器のキレのよいリズムで変拍子の変則的なアクセントを繰り返されるとどんどんと高揚していく。この切り口での第一曲ですっかり客席が覚醒していしまっている。
後半の武満の「ノスタルジア」は、これとはむしろ対照的。映画監督のアンドレイ・タルコフスキーの追悼として作曲されたものだが、ほとんど拍節のない水の流れや霧が立ちこめるような世界。細分化された合奏とフラジオレットの倍音が立ち昇る水の世界。映画「ノスタルジア」は、ロシア人作曲家がイタリアを彷徨いながら亡命を決意していくというストーリー。ほとんど台詞はなく詩的な映像の連続だが、確かに泉水や流水など水の場面が多い。そういう彷徨の流れに幻影のように故郷のロシアの風景が茫洋と映し出される。――まさにそういう音楽。ここでのトネッティはヴァイオリン奏者としての実力を鮮烈なまでに発揮する。そのことにも少なからず驚きを覚える。
続けて演奏されたバッハも、救済と昇華の心情をとらえて胸を打つ。ここでの篠崎友美のヴィオラの伴奏アルペジオが素晴らしかった。

この二十世紀音楽の持つ本質的なグルーヴが触発するハイドンとモーツァルトがこれまた清新にして溌剌。
ハイドンは、不思議とカラヤンの演奏を想起させる。奏法としてはカラヤン流のベルベットの上品で光沢のある流麗な質感とはまるで対照的なのに、細やかな意匠を織り込んだ豊穣な響きは共通しているからなのかもしれない。
何と言ってもジュピター交響曲が圧巻だった。ここでも細やかなフレージングに自発的かつ集合的なグルーヴ感覚があふれていて、そこにトネッティが仕掛けた巨大で息の長いクレッシェンドとアッチェランドが最後のフーガートで爆発的なクライマックスを作り上げる。沸き立つような生の賛歌は、劇的な大団円となって会場を一体化させるような高揚感があった。

まずもって喝采は、紀尾井ホール室内管の誇る弦楽器パートに送られるべきだろうが、管楽器群のみずみずしい若い感覚が印象的。ここにも明らかに立奏の効果がある。小さな身体を大きく動かすファゴットの福士マリ子の内声のしなやかなグルーヴは秀逸だったし、亀井良信、芳賀史徳がそろって古楽器風の黄楊(つげ)材の楽器を使用していて木管群の響きの直進性を高めていて若々しさを誇示していた。そして何と言っても賞賛したいのは、リズムセクション。佐藤玲伊奈、古田俊博のトランペットは光輝そのものでピッチも伸びやかで正確。久一忠之のティンパニは思い切りがよくて常にオーケストラのグルーヴの中心にいた。
トネッティには、もう一度と言わず何度でもここに戻ってきてほしい。

紀尾井ホール室内管弦楽団
第1355回定期演奏会
2023年7月15日(土)14:00
東京・四ッ谷 紀尾井ホール
(2階C席2列13番)
指揮・ヴァイオリン:リチャード・トネッティ
コンサートマスター:玉井菜採
紀尾井ホール室内管弦楽団
キラル:オラヴァ
ハイドン:交響曲第104番ニ長調 Hob.I:104《ロンドン》
武満徹:ノスタルジア~アンドレイ・タルコフスキーの追憶に
+バッハ・コラール前奏曲《われ汝に呼ばわる、主イエス・キリストよ》BWV639
モーツァルト: 交響曲第41番ハ長調 K.551《ジュピター》
頭がほてってしまって、その音楽についていったい何からどう書きとめたらよいのやら考えがまとまらなかったほど。トネッティは、以前から期待していたけれど、コロナ禍で来日が延期になってしまい、その思いが募るばかりだった。なにしろ、あのバッハ弾きのアンジェラ・ヒューイットが、コンチェルトの録音に指名したのがトネッティとオーストラリア室内管。バッハと新大陸の――しかも、南北の両半球にまたがる二つの大陸の――音楽家との結びつきの不思議さがあったから。
プログラムからもそういう不思議な飛躍感が予見されていた。
前半・後半ともに二十世紀と古典派、200年を隔たりをもって作曲された曲をペアリングした二部形式。
しかも、いずれも(チェロを除いて)全員が立って演奏する。現代曲は、ヴァイオリンのソロを伴った弦楽だけの合奏。ハイドンとモーツァルトでは、管楽器群も全員が立奏。おそらくこれは楽団初めてのことではないか。現代曲は二十世紀型配置で、古典の二曲は両翼対向型。曲間でいちいち交代するが、譜面台を第二ヴァイオリンとヴィオラで交換するだけなので簡単といえば簡単だが、その狙いと効果は歴然。
トネッティは、弾き振り。ソロでは中央に立つが時おり弓を高く振って全体をリードする。武満だけはコンサートマスターを玉井菜採に任せているが、ソロはトネッティが兼ねる。そのことは古典派の二曲でも同じ。むしろ指揮振りの身振りはかえって大きい。
そういう不思議な態様と編成の効果は、絶大。一曲目から、その音楽的効果に唖然ともしたし、思わず腰が浮いてしまうほど高揚した。
「オラヴァ」というのは、ポーランドとスロヴァキアの国境にある地域名だとのことで、そのオラヴァ地方の民俗音楽を土台としているのだとか。同じ音型を執拗に繰り返し、変形していく。弦楽器のキレのよいリズムで変拍子の変則的なアクセントを繰り返されるとどんどんと高揚していく。この切り口での第一曲ですっかり客席が覚醒していしまっている。
後半の武満の「ノスタルジア」は、これとはむしろ対照的。映画監督のアンドレイ・タルコフスキーの追悼として作曲されたものだが、ほとんど拍節のない水の流れや霧が立ちこめるような世界。細分化された合奏とフラジオレットの倍音が立ち昇る水の世界。映画「ノスタルジア」は、ロシア人作曲家がイタリアを彷徨いながら亡命を決意していくというストーリー。ほとんど台詞はなく詩的な映像の連続だが、確かに泉水や流水など水の場面が多い。そういう彷徨の流れに幻影のように故郷のロシアの風景が茫洋と映し出される。――まさにそういう音楽。ここでのトネッティはヴァイオリン奏者としての実力を鮮烈なまでに発揮する。そのことにも少なからず驚きを覚える。
続けて演奏されたバッハも、救済と昇華の心情をとらえて胸を打つ。ここでの篠崎友美のヴィオラの伴奏アルペジオが素晴らしかった。
この二十世紀音楽の持つ本質的なグルーヴが触発するハイドンとモーツァルトがこれまた清新にして溌剌。
ハイドンは、不思議とカラヤンの演奏を想起させる。奏法としてはカラヤン流のベルベットの上品で光沢のある流麗な質感とはまるで対照的なのに、細やかな意匠を織り込んだ豊穣な響きは共通しているからなのかもしれない。
何と言ってもジュピター交響曲が圧巻だった。ここでも細やかなフレージングに自発的かつ集合的なグルーヴ感覚があふれていて、そこにトネッティが仕掛けた巨大で息の長いクレッシェンドとアッチェランドが最後のフーガートで爆発的なクライマックスを作り上げる。沸き立つような生の賛歌は、劇的な大団円となって会場を一体化させるような高揚感があった。

まずもって喝采は、紀尾井ホール室内管の誇る弦楽器パートに送られるべきだろうが、管楽器群のみずみずしい若い感覚が印象的。ここにも明らかに立奏の効果がある。小さな身体を大きく動かすファゴットの福士マリ子の内声のしなやかなグルーヴは秀逸だったし、亀井良信、芳賀史徳がそろって古楽器風の黄楊(つげ)材の楽器を使用していて木管群の響きの直進性を高めていて若々しさを誇示していた。そして何と言っても賞賛したいのは、リズムセクション。佐藤玲伊奈、古田俊博のトランペットは光輝そのものでピッチも伸びやかで正確。久一忠之のティンパニは思い切りがよくて常にオーケストラのグルーヴの中心にいた。
トネッティには、もう一度と言わず何度でもここに戻ってきてほしい。

紀尾井ホール室内管弦楽団
第1355回定期演奏会
2023年7月15日(土)14:00
東京・四ッ谷 紀尾井ホール
(2階C席2列13番)
指揮・ヴァイオリン:リチャード・トネッティ
コンサートマスター:玉井菜採
紀尾井ホール室内管弦楽団
キラル:オラヴァ
ハイドン:交響曲第104番ニ長調 Hob.I:104《ロンドン》
武満徹:ノスタルジア~アンドレイ・タルコフスキーの追憶に
+バッハ・コラール前奏曲《われ汝に呼ばわる、主イエス・キリストよ》BWV639
モーツァルト: 交響曲第41番ハ長調 K.551《ジュピター》
ブロードウッドが誘う時代の旅(川口成彦@紀尾井レジデント・シリーズ第2回) [コンサート]
川口成彦さんのフォルテピアノによる紀尾井レジデント・シリーズ第2回。
第1回は、1890年製のエラールでムソルグスキー「展覧会の絵」を弾いてみせて度肝を抜いた川口さん。
ピリオド楽器演奏というのは、作曲年代と同時期の楽器による演奏ということに意義があります。そう考えてみると、《展覧会の絵》が作曲されたのは1874年だから実のところエラールで弾くことは、まさに「ピリオド」ということであって何の不思議もありません。超絶技巧の大男がモダンピアノで大音響で弾く《展覧会の絵》というのは、ある意味では20世紀のヴィルトゥオーソへの熱狂が作った虚像。曲が秘めていたものをモダン楽器が引き出したという面もあるけれど、失ったものも少なくないかもしれないのです。
今回の川口さんは、そういう楽器の持つ、時代と地域を自在に飛翔してしまう自由や解放感ということで、またまた聴くものの度肝を抜いてしまいました。
今回使用されたのは、1800年頃に製作されたジョン・ブロードウッド・&サンのフォルテピアノ。

19世紀初頭のブロードウッドといえば、まさにモーツァルトとかベートーヴェンの時代の楽器。
ピアノという楽器は、産業革命以降の社会が生んだ楽器で、中西欧の市民社会と密接な工業製品。木工家具を作る名匠たちの工芸技術と、巨大な鋳鉄フレームと高純度炭素鋼のワイヤーという最先端の工業技術のマリアージュ。それだけに、時代の変遷と技術の進化とともにどんどんと変貌していきます。
だから、とても自由。――『同時代』ということにさえこだわることがありません。
プログラムの前半は、イベリアの音楽。
川口さんは、スペインが大好きなのだそうです。古楽器を学ぶためにオランダに留学し、ショパン国際ピリオド楽器コンクールで第2位に入賞する前に、青少年のためのスペイン音楽ピアノコンクールで最優秀スペイン音楽グランプリを受賞、 ローマ・フォルテピアノ国際コンクールでも優勝しています。もともとはラテンが大好き。
最初はファリャ。20世紀初頭のパリで活躍したスペインの作曲家でドビュッシーとも親交を結んだ。ドビュッシーをプレイエルやエラールで弾くというのは何度か聴いたことがありますが、ブロードウッドというのは不思議。ところが聴いてみると、その軽やかさと響きの純度の高さがぴったり。
ファンダンゴは、イベリア発祥の舞曲。19世紀初頭にはヨーロッパ中で大流行。すぐにフラメンコを想起させる情熱的でリズムの高揚感あふれる舞曲。D.スカルラッティなどチェンバロで聴くといささか騒がしく聞こえてしまうのですが、ブロードウッド・ピアノで聴くと見事なまでに優雅で、それでいて南国の陽気なラテン気質がみなぎっていて聴き手の気持ちも華やぎます。それはそのまま、アルベニスの《タンゴ》に引き継がれるのです。
ここで《ラ・ムジカ・コッラーナ》のメンバーが登場。
古楽器の弦五部のアンサンブル。コントラバスではなくてヴィオローネを生で聴くのはたぶん初めて。ここからは、バロックから、古典派、ロマン派初期までには確かな存在だった、室内楽としてのピアノ協奏曲というものの再発見の旅。
前半のイベリアと後半のピアノ協奏曲との橋渡しになっているのが、ポルトガル人セイシャスとスペイン人パロミノの協奏曲。パロミノは、ポルトガル王室で活躍しますが、この協奏曲は晩年を過ごしたカナリヤ諸島のラス・パルマスで作曲されたのだとか。モーツァルトやバッハと同時代の二人の作曲家の協奏曲は、西欧名画で見るようなちょっとレースや重めのサテンなどの服装ではなくて、なぜか20世紀初頭の真っ白なスーツで軽やかに演奏しているようなリゾート感覚あふれる楽団が思い浮かんできます。

後半は、再び川口さんのソロで開始ですが、最初はアメリカのフォークソングで有名な《朝日のあたる家》の変奏曲。ドイツの現代作曲家シュナイダーが書いたものですが、モーツァルト生誕250周年の記念に作曲されたのだとか。モーツァルトの様式とちょっと気鬱な雰囲気と原曲とが見事に調和するのは、やはりフォルテピアノの雰囲気の効果かもしれません。そのまま、ラヴェルの《亡き王女のためのパヴァーヌ》に引き継がれるという運びが鮮やか。ポツポツと切れがちな伴奏アルペッジョは、フォルテピアノならではのもので、管弦楽やモダンピアノからはなかなか引き出せなかった古雅な素朴感が見事。孤独な雰囲気のアリアは、前曲から引き継いだもので、まさにフレンチ・クォーターのけだるい叙情そのもの。
モーツァルトのピアノ協奏曲は、もちろんこの夜の主役。いや、主役というより基準となる模範演奏、プログラムの「おへそ」みたいなものでしょうか。弦楽四重奏でも演奏できるというこの曲こそ、作曲年代と同時期の楽器による演奏というピリオドそのものだからです。モダンだといささか粗野に響く冒頭の三度和音もとてもすがすがしいスタートに様変わり。三拍子主体の舞曲的なこの曲は、この室内楽的な演奏スタイル以外には考えられないと思えるほど。
このモーツァルトがあるからこそ、時代も地理も自在に飛翔するフォルテピアノという楽器の大らかなキャラクターが闊達に響いて心のなかに何の抵抗もなくすっと浸透してくるのです。
最後は、イギリスの新古典主義的なリーの《小協奏曲》でしめくくり。これは、イギリスらしいエスプリの効いた美しい音楽でした。
アンコールには、滝廉太郎まで登場。素敵な小旅行でした。

紀尾井レジデント・シリーズ Ⅱ
川口成彦(フォルテピアノ)(第2回)
2023年7月7日(水) 19:00
東京・四ッ谷 紀尾井ホール
(1階6列8番)
川口成彦(フォルテピアノ)
使用楽器:ジョン・ブロードウッド・&サン(1800年頃 太田垣至 修復)
[共演]La Musica Collanaメンバー(ピリオド楽器による弦楽5名)
丸山韶(第1ヴァイオリン)
廣海史帆(第2ヴァイオリン
佐々木梨花(ヴィオラ)
島根朋史(チェロ)
諸岡典経(ヴィオローネ)
ファリャ:ドビュッシーの墓のための讃歌 G.57(1920)
マルティ:ファンダンゴと変奏 ニ短調(19世紀初期?)
アルベニス/ゴドフスキ編:タンゴ ニ長調 op.165-2[ソロ]
セイシャス:協奏曲イ長調(18世紀前半)
パロミノ:協奏曲ト長調(1785)
シュナイダー:ニューオーリンズのモーツァルト~『朝日のあたる家』による変奏曲(2006)
ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ[ソロ]
モーツァルト:ピアノ協奏曲第11番ヘ長調 K.413 (387a)[作曲者によるピアノと弦楽四重奏版](1783)
リー:小協奏曲(1934)
(アンコール)
グラナドス:12のスペイン舞曲より第5番「アンダルーサ」
瀧廉太郎:2つのピアノ小品よりメヌエット ロ短調
パロミロ:協奏曲 ト長調より第3楽章抜粋
第1回は、1890年製のエラールでムソルグスキー「展覧会の絵」を弾いてみせて度肝を抜いた川口さん。
ピリオド楽器演奏というのは、作曲年代と同時期の楽器による演奏ということに意義があります。そう考えてみると、《展覧会の絵》が作曲されたのは1874年だから実のところエラールで弾くことは、まさに「ピリオド」ということであって何の不思議もありません。超絶技巧の大男がモダンピアノで大音響で弾く《展覧会の絵》というのは、ある意味では20世紀のヴィルトゥオーソへの熱狂が作った虚像。曲が秘めていたものをモダン楽器が引き出したという面もあるけれど、失ったものも少なくないかもしれないのです。
今回の川口さんは、そういう楽器の持つ、時代と地域を自在に飛翔してしまう自由や解放感ということで、またまた聴くものの度肝を抜いてしまいました。
今回使用されたのは、1800年頃に製作されたジョン・ブロードウッド・&サンのフォルテピアノ。

19世紀初頭のブロードウッドといえば、まさにモーツァルトとかベートーヴェンの時代の楽器。
ピアノという楽器は、産業革命以降の社会が生んだ楽器で、中西欧の市民社会と密接な工業製品。木工家具を作る名匠たちの工芸技術と、巨大な鋳鉄フレームと高純度炭素鋼のワイヤーという最先端の工業技術のマリアージュ。それだけに、時代の変遷と技術の進化とともにどんどんと変貌していきます。
だから、とても自由。――『同時代』ということにさえこだわることがありません。
プログラムの前半は、イベリアの音楽。
川口さんは、スペインが大好きなのだそうです。古楽器を学ぶためにオランダに留学し、ショパン国際ピリオド楽器コンクールで第2位に入賞する前に、青少年のためのスペイン音楽ピアノコンクールで最優秀スペイン音楽グランプリを受賞、 ローマ・フォルテピアノ国際コンクールでも優勝しています。もともとはラテンが大好き。
最初はファリャ。20世紀初頭のパリで活躍したスペインの作曲家でドビュッシーとも親交を結んだ。ドビュッシーをプレイエルやエラールで弾くというのは何度か聴いたことがありますが、ブロードウッドというのは不思議。ところが聴いてみると、その軽やかさと響きの純度の高さがぴったり。
ファンダンゴは、イベリア発祥の舞曲。19世紀初頭にはヨーロッパ中で大流行。すぐにフラメンコを想起させる情熱的でリズムの高揚感あふれる舞曲。D.スカルラッティなどチェンバロで聴くといささか騒がしく聞こえてしまうのですが、ブロードウッド・ピアノで聴くと見事なまでに優雅で、それでいて南国の陽気なラテン気質がみなぎっていて聴き手の気持ちも華やぎます。それはそのまま、アルベニスの《タンゴ》に引き継がれるのです。
ここで《ラ・ムジカ・コッラーナ》のメンバーが登場。
古楽器の弦五部のアンサンブル。コントラバスではなくてヴィオローネを生で聴くのはたぶん初めて。ここからは、バロックから、古典派、ロマン派初期までには確かな存在だった、室内楽としてのピアノ協奏曲というものの再発見の旅。
前半のイベリアと後半のピアノ協奏曲との橋渡しになっているのが、ポルトガル人セイシャスとスペイン人パロミノの協奏曲。パロミノは、ポルトガル王室で活躍しますが、この協奏曲は晩年を過ごしたカナリヤ諸島のラス・パルマスで作曲されたのだとか。モーツァルトやバッハと同時代の二人の作曲家の協奏曲は、西欧名画で見るようなちょっとレースや重めのサテンなどの服装ではなくて、なぜか20世紀初頭の真っ白なスーツで軽やかに演奏しているようなリゾート感覚あふれる楽団が思い浮かんできます。

後半は、再び川口さんのソロで開始ですが、最初はアメリカのフォークソングで有名な《朝日のあたる家》の変奏曲。ドイツの現代作曲家シュナイダーが書いたものですが、モーツァルト生誕250周年の記念に作曲されたのだとか。モーツァルトの様式とちょっと気鬱な雰囲気と原曲とが見事に調和するのは、やはりフォルテピアノの雰囲気の効果かもしれません。そのまま、ラヴェルの《亡き王女のためのパヴァーヌ》に引き継がれるという運びが鮮やか。ポツポツと切れがちな伴奏アルペッジョは、フォルテピアノならではのもので、管弦楽やモダンピアノからはなかなか引き出せなかった古雅な素朴感が見事。孤独な雰囲気のアリアは、前曲から引き継いだもので、まさにフレンチ・クォーターのけだるい叙情そのもの。
モーツァルトのピアノ協奏曲は、もちろんこの夜の主役。いや、主役というより基準となる模範演奏、プログラムの「おへそ」みたいなものでしょうか。弦楽四重奏でも演奏できるというこの曲こそ、作曲年代と同時期の楽器による演奏というピリオドそのものだからです。モダンだといささか粗野に響く冒頭の三度和音もとてもすがすがしいスタートに様変わり。三拍子主体の舞曲的なこの曲は、この室内楽的な演奏スタイル以外には考えられないと思えるほど。
このモーツァルトがあるからこそ、時代も地理も自在に飛翔するフォルテピアノという楽器の大らかなキャラクターが闊達に響いて心のなかに何の抵抗もなくすっと浸透してくるのです。
最後は、イギリスの新古典主義的なリーの《小協奏曲》でしめくくり。これは、イギリスらしいエスプリの効いた美しい音楽でした。
アンコールには、滝廉太郎まで登場。素敵な小旅行でした。

紀尾井レジデント・シリーズ Ⅱ
川口成彦(フォルテピアノ)(第2回)
2023年7月7日(水) 19:00
東京・四ッ谷 紀尾井ホール
(1階6列8番)
川口成彦(フォルテピアノ)
使用楽器:ジョン・ブロードウッド・&サン(1800年頃 太田垣至 修復)
[共演]La Musica Collanaメンバー(ピリオド楽器による弦楽5名)
丸山韶(第1ヴァイオリン)
廣海史帆(第2ヴァイオリン
佐々木梨花(ヴィオラ)
島根朋史(チェロ)
諸岡典経(ヴィオローネ)
ファリャ:ドビュッシーの墓のための讃歌 G.57(1920)
マルティ:ファンダンゴと変奏 ニ短調(19世紀初期?)
アルベニス/ゴドフスキ編:タンゴ ニ長調 op.165-2[ソロ]
セイシャス:協奏曲イ長調(18世紀前半)
パロミノ:協奏曲ト長調(1785)
シュナイダー:ニューオーリンズのモーツァルト~『朝日のあたる家』による変奏曲(2006)
ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ[ソロ]
モーツァルト:ピアノ協奏曲第11番ヘ長調 K.413 (387a)[作曲者によるピアノと弦楽四重奏版](1783)
リー:小協奏曲(1934)
(アンコール)
グラナドス:12のスペイン舞曲より第5番「アンダルーサ」
瀧廉太郎:2つのピアノ小品よりメヌエット ロ短調
パロミロ:協奏曲 ト長調より第3楽章抜粋
「ウクライナ戦争」(小泉 悠 著)読了 [読書]
著者も述べている通り、終わりの見えない現在進行中のこの戦争を追っている限りでは限界もある。けれども、もはやあり得ないと言われていた国家対国家の大戦争が現実には起こっているという衝撃は大きく、誰しもが「なぜ?」という疑問を持っているはず。本書は、そういう衝撃的疑問に十分答えている。
まずは開戦に至るまでの経緯と開戦前夜を第1章と第2章で解き明かす。続いて第3章と第4章では開戦直後から、戦争が長期化の様相を確実にした昨年の夏頃までの経過をつぶさに追っていく。ここらあたりはとても読み応えがある。
プーチンは、国家対国家の大戦争を起こす意図はなかったし、今でもそういう戦争
をしているという自覚もないのではないか。この点で、ウクライナ侵攻がKGB出身のプーチン好みの、内通者とごく一部の精鋭で数日のうちにゼレンスキー政権を転覆する計画だったということを活写する。それがあっけなく挫折し、同時に侵攻したウクライナ南部と東部でやむなく地域紛争の形で継続せざるを得ない状況に陥っているという分析は鋭い。
プーチンの誤算は、謀略の内実があまりにもずさんだったこと。
しかもゼレンスキー政権が思わぬ抵抗力を見せた。ウクライナは、誰もが予想しないほどに果敢に抵抗し、緒戦の反撃に成功した。ゼレンスキーが背中を見せなかったことで戦争遂行について国民の絶大な支持を受け、古典的な国民戦争の様相を現したことだ。その挫折は、現代的な情報戦やハイテク戦力の底が知れていたことを露呈し、結局は、戦闘員だけでなく市民をも無差別に巻き込む死屍累々たる残虐な古典的大戦争の軍隊の本質がむき出しになってしまう。
しかし、それでもプーチンは国家対国家の戦争になっていることを認めない。
自分たちの失敗を糊塗し、地位を守ろうとする将軍たちは、他に戦いようがないからある限りの古典的な重火器を動員して物量でウクライナを押しに押そうとするが、それはもはや前進は放棄した侵攻地域確保の戦いに過ぎない。ミサイルや無人機攻撃などは、平時の地図情報のみだから大型インフラや市街地の攻撃しかできない。緒戦の失敗で近代化の表層が剥がれ落ちたら、第二次世界大戦以来のロシア国軍の古い地層しか残っていなかったということがであって、プーチンの政治的意図と戦争遂行のメカニズムとの間には、第三者からは憶測のしようがないギャップがある。
今後の問題は、核の行使とNATO軍との直接の交戦といった戦争のエスカレーションだ。
このことに著者は、どちらかといえば楽観的だ。核は使えないということで、米欧露は共通しているというのだ。たとえ戦術核であっても使ったら最後、人類誰もが予想もつかない様相にまで一気にエスカレートしていく。そういう恐怖を共有する。核は使えないから抑止力として機能する。
しかし、そういう核兵器観もまさに冷戦時代までの古典的思考ではないのか?
本書は、昨年9月時点での著述であることを断っている。ドイツやアメリカが主力戦車の供与を表明したのは今年2023年に入ってから。その後は、主力戦闘機や長射程ミサイルの供与などウクライナ支援の武器供与姿勢はどんどんと高度化していっている。
6月末のいまのこの瞬間まで、こうして供与された主力戦力が本来の戦闘力を発揮したとの兆候は薄い。やはり、こうした供与武器はゲームチェンジャーたり得ないのか?あるいはオペレーターの訓練等準備不足で本格的反抗が始まっていないのか。世界は固唾をのんでいるわけだが、この本ではそういう点で著者本来の軍事オタクとしての分析が及んでいない。
そこがとてももどかしい。
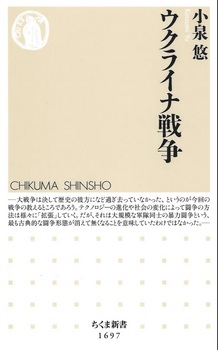
ウクライナ戦争
小泉 悠
ちくま新書(1967)
筑摩書房
2022年12月10日新刊
まずは開戦に至るまでの経緯と開戦前夜を第1章と第2章で解き明かす。続いて第3章と第4章では開戦直後から、戦争が長期化の様相を確実にした昨年の夏頃までの経過をつぶさに追っていく。ここらあたりはとても読み応えがある。
プーチンは、国家対国家の大戦争を起こす意図はなかったし、今でもそういう戦争
をしているという自覚もないのではないか。この点で、ウクライナ侵攻がKGB出身のプーチン好みの、内通者とごく一部の精鋭で数日のうちにゼレンスキー政権を転覆する計画だったということを活写する。それがあっけなく挫折し、同時に侵攻したウクライナ南部と東部でやむなく地域紛争の形で継続せざるを得ない状況に陥っているという分析は鋭い。
プーチンの誤算は、謀略の内実があまりにもずさんだったこと。
しかもゼレンスキー政権が思わぬ抵抗力を見せた。ウクライナは、誰もが予想しないほどに果敢に抵抗し、緒戦の反撃に成功した。ゼレンスキーが背中を見せなかったことで戦争遂行について国民の絶大な支持を受け、古典的な国民戦争の様相を現したことだ。その挫折は、現代的な情報戦やハイテク戦力の底が知れていたことを露呈し、結局は、戦闘員だけでなく市民をも無差別に巻き込む死屍累々たる残虐な古典的大戦争の軍隊の本質がむき出しになってしまう。
しかし、それでもプーチンは国家対国家の戦争になっていることを認めない。
自分たちの失敗を糊塗し、地位を守ろうとする将軍たちは、他に戦いようがないからある限りの古典的な重火器を動員して物量でウクライナを押しに押そうとするが、それはもはや前進は放棄した侵攻地域確保の戦いに過ぎない。ミサイルや無人機攻撃などは、平時の地図情報のみだから大型インフラや市街地の攻撃しかできない。緒戦の失敗で近代化の表層が剥がれ落ちたら、第二次世界大戦以来のロシア国軍の古い地層しか残っていなかったということがであって、プーチンの政治的意図と戦争遂行のメカニズムとの間には、第三者からは憶測のしようがないギャップがある。
今後の問題は、核の行使とNATO軍との直接の交戦といった戦争のエスカレーションだ。
このことに著者は、どちらかといえば楽観的だ。核は使えないということで、米欧露は共通しているというのだ。たとえ戦術核であっても使ったら最後、人類誰もが予想もつかない様相にまで一気にエスカレートしていく。そういう恐怖を共有する。核は使えないから抑止力として機能する。
しかし、そういう核兵器観もまさに冷戦時代までの古典的思考ではないのか?
本書は、昨年9月時点での著述であることを断っている。ドイツやアメリカが主力戦車の供与を表明したのは今年2023年に入ってから。その後は、主力戦闘機や長射程ミサイルの供与などウクライナ支援の武器供与姿勢はどんどんと高度化していっている。
6月末のいまのこの瞬間まで、こうして供与された主力戦力が本来の戦闘力を発揮したとの兆候は薄い。やはり、こうした供与武器はゲームチェンジャーたり得ないのか?あるいはオペレーターの訓練等準備不足で本格的反抗が始まっていないのか。世界は固唾をのんでいるわけだが、この本ではそういう点で著者本来の軍事オタクとしての分析が及んでいない。
そこがとてももどかしい。
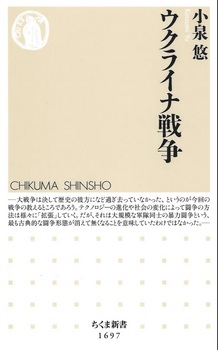
ウクライナ戦争
小泉 悠
ちくま新書(1967)
筑摩書房
2022年12月10日新刊



