西洋近代の鏡 (西洋美術館特別展記念コンサート) [コンサート]
東京・春・音楽祭のミュージアムコンサートの会場のひとつだった西洋美術館講堂でのコンサートが復活した。

西洋美術館はコロナ禍と改修工事で長く閉館していたが、昨春にリニューアルオープンした。すっきりした前庭から眺めてみると、コルビジェの美術館とその弟子である前川圀雄の東京文化会館が向き合う形になっていることに改めて気づきます。それが上野公園を横切るように貫く道の両側で対峙していて、まるで合わせ鏡のようにとてもよく調和しています。
ここでのコンサートは、美術館の特別企画展のテーマとのコラボになっていて、プレトークのような形で学芸員の講話があって、しかも、コンサートチケットで企画展も常設展も鑑賞できて、とてもお得。講堂はちょうどその企画展の入り口に向かい側にあります。

特別企画展は、「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」ちょっと長いテーマだけど、要は、今年で65年目となる国立西洋美術館のそもそもの成り立ちを振り返り、自問するというもの。この美術館では初めてとなる現代美術――すなわち、今の日本で実験的な制作活動をしていアーティストたちの作品展。

15分足らずの講話は、この企画展の意図を説明するだけのものでしたが、改めてこの美術館の成立を知って面白かった。
この美術館は、そもそも戦後にフランスから返還された「松方コレクション」を収蔵するために建てられたもの。「松方コレクション」は、松方正義の子息・幸次郎が蒐集した印象派を中心とする一連の美術品。幸次郎は、川崎造船所(現・川崎重工業)の初代社長。大恐慌で造船所が破綻したため美術品はほとんど処分されたが、国外にあったものは散逸を免れた。軍国主義の台頭と戦争によって行き場を失ったコレクションはそのまま海外に留め置かれフランス政府によって接収されたが、戦後になって寄贈返還されることになった。
幸次郎は、日本のアーティストは西洋近代美術を範としながら油絵などを描いているが、その西洋美術を目の当たりにしたことがないままにいることは不幸だと嘆き、そういう規範となる優れた西洋美術の蒐集を思い立ったという。西洋美術館を建設するにあたっては民間の寄付が募られた。その際に、大口の寄付者には見返りとして著名アーティストの作品をプレゼントしようということになった。今の「ふるさと納税」みたいなこと。
この提案に対して、当初、美術家たちは抵抗した。それを一変させてのが、洋画家の安井曾太郎の発言だったそうだ。
「このコレクションが戻ってきて、一番恩恵を受けるのは誰か。われわれ美術家ではないか」
今回の企画展は、そういう西洋美術館の成立を改めて自問するというわけです。美術館こそ、その現代に生きる美術館にとって恩恵を与える存在であったのかという反問だというわけです。

コンサートは、武満徹の作品と、彼にとって規範となった近代フランスの作曲家ドビュッシーの作品。
こういうテーマと、フルート、ハープ、ヴィオラという構成の作品をごく親密な空間で間近に接するという機会は希ですので矢も楯もたまらず足を運びました。
「海へ」は、アルトフルートとギターのために作曲され、それがオーケストラ伴奏を伴う版へと編曲され、さらに、最終的にこのハープとの二重奏版である「Ⅲ」へと改編されました。一連の「水」をテーマとした曲のひとつ。
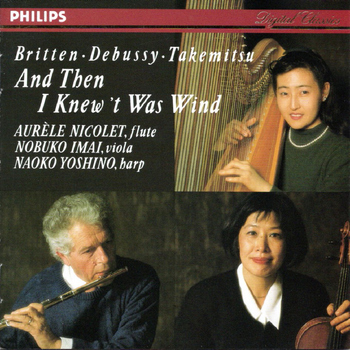
武満の葬式の弔辞で、海外友人代表のピーター・グリリは、次のように語ったそうです。
「武満こそ、西も東もない音楽の海を泳いでいた一頭の鯨ではなかったか」
二曲目の、「エア」は、武満最後の作品。武満を尊敬し、無二の親友でもあったオーレル・ニコレの70歳の誕生日プレゼントとして贈られたもの。その奏法は、フランス近代音楽の主役ともなったフルートに、日本の尺八を思わせる様々な特殊奏法を垣間見ることができました。
三曲目は、ドビュッシーのソナタ。
最後の「そして、それが風であることを知った」は、明らかにそのドビュッシーへのオマージュ。
ニコレは、武満について次のように語っています。
「…彼はフランスとの関係が強くて、はじめはドビュッシーのような作曲家だという印象を受けました。日本の能にあるような孤独な音楽を目指しておられて、そこがドビュッシーに似ているのです。」
「…“自然を大切にする”作曲家で、その点ドビュッシーが《海》や《夜想曲》を書いたのと共通しています。」
武満は、ドビュッシー、ラベル、メシアンから深い影響を受け、西洋近代音楽が崩壊する瞬間というべき《前衛》の時代に奮闘し、日本音楽への回帰と西洋音楽への揺り戻しとの間で行き交いながら、自らの「夢」の宇宙へと飛翔していった作曲家だったといえると思います。
東フィル首席の斉藤和志さんのアルト・フルート独奏の音色や、間近で聴く田原綾子さんのヴィオラの音色は出色。特に、ベテランの木村茉莉のハープには酔いしれました。ハープという楽器は、遠くのステージや、録音などではなかなかその音色と響きのバランスを体感することは難しく、こうやって2、3メートルの至近で聴くハープこそその本質なんだと痛感させられました。

ミュージアム・コンサート
「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」展 記念コンサート vol.1
2024年3月19日(火)11:00
東京・上野 国立西洋美術館 講堂
お話:新藤 淳(国立西洋美術館 主任研究員)
斎藤和志(フルート)、田原綾子(ヴィオラ)、木村茉莉(ハープ)
武満 徹:
海へⅢ
エア
ドビュッシー:
フルート、ヴィオラ、ハープのためのソナタ
武満 徹:
そして、それが風であることを知った
西洋美術館はコロナ禍と改修工事で長く閉館していたが、昨春にリニューアルオープンした。すっきりした前庭から眺めてみると、コルビジェの美術館とその弟子である前川圀雄の東京文化会館が向き合う形になっていることに改めて気づきます。それが上野公園を横切るように貫く道の両側で対峙していて、まるで合わせ鏡のようにとてもよく調和しています。
ここでのコンサートは、美術館の特別企画展のテーマとのコラボになっていて、プレトークのような形で学芸員の講話があって、しかも、コンサートチケットで企画展も常設展も鑑賞できて、とてもお得。講堂はちょうどその企画展の入り口に向かい側にあります。
特別企画展は、「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」ちょっと長いテーマだけど、要は、今年で65年目となる国立西洋美術館のそもそもの成り立ちを振り返り、自問するというもの。この美術館では初めてとなる現代美術――すなわち、今の日本で実験的な制作活動をしていアーティストたちの作品展。
15分足らずの講話は、この企画展の意図を説明するだけのものでしたが、改めてこの美術館の成立を知って面白かった。
この美術館は、そもそも戦後にフランスから返還された「松方コレクション」を収蔵するために建てられたもの。「松方コレクション」は、松方正義の子息・幸次郎が蒐集した印象派を中心とする一連の美術品。幸次郎は、川崎造船所(現・川崎重工業)の初代社長。大恐慌で造船所が破綻したため美術品はほとんど処分されたが、国外にあったものは散逸を免れた。軍国主義の台頭と戦争によって行き場を失ったコレクションはそのまま海外に留め置かれフランス政府によって接収されたが、戦後になって寄贈返還されることになった。
幸次郎は、日本のアーティストは西洋近代美術を範としながら油絵などを描いているが、その西洋美術を目の当たりにしたことがないままにいることは不幸だと嘆き、そういう規範となる優れた西洋美術の蒐集を思い立ったという。西洋美術館を建設するにあたっては民間の寄付が募られた。その際に、大口の寄付者には見返りとして著名アーティストの作品をプレゼントしようということになった。今の「ふるさと納税」みたいなこと。
この提案に対して、当初、美術家たちは抵抗した。それを一変させてのが、洋画家の安井曾太郎の発言だったそうだ。
「このコレクションが戻ってきて、一番恩恵を受けるのは誰か。われわれ美術家ではないか」
今回の企画展は、そういう西洋美術館の成立を改めて自問するというわけです。美術館こそ、その現代に生きる美術館にとって恩恵を与える存在であったのかという反問だというわけです。
コンサートは、武満徹の作品と、彼にとって規範となった近代フランスの作曲家ドビュッシーの作品。
こういうテーマと、フルート、ハープ、ヴィオラという構成の作品をごく親密な空間で間近に接するという機会は希ですので矢も楯もたまらず足を運びました。
「海へ」は、アルトフルートとギターのために作曲され、それがオーケストラ伴奏を伴う版へと編曲され、さらに、最終的にこのハープとの二重奏版である「Ⅲ」へと改編されました。一連の「水」をテーマとした曲のひとつ。
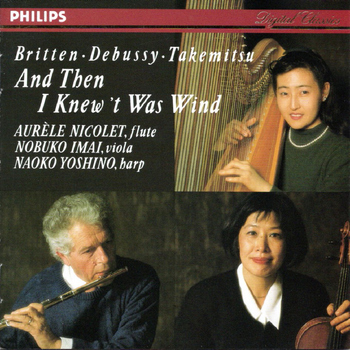
武満の葬式の弔辞で、海外友人代表のピーター・グリリは、次のように語ったそうです。
「武満こそ、西も東もない音楽の海を泳いでいた一頭の鯨ではなかったか」
二曲目の、「エア」は、武満最後の作品。武満を尊敬し、無二の親友でもあったオーレル・ニコレの70歳の誕生日プレゼントとして贈られたもの。その奏法は、フランス近代音楽の主役ともなったフルートに、日本の尺八を思わせる様々な特殊奏法を垣間見ることができました。
三曲目は、ドビュッシーのソナタ。
最後の「そして、それが風であることを知った」は、明らかにそのドビュッシーへのオマージュ。
ニコレは、武満について次のように語っています。
「…彼はフランスとの関係が強くて、はじめはドビュッシーのような作曲家だという印象を受けました。日本の能にあるような孤独な音楽を目指しておられて、そこがドビュッシーに似ているのです。」
「…“自然を大切にする”作曲家で、その点ドビュッシーが《海》や《夜想曲》を書いたのと共通しています。」
武満は、ドビュッシー、ラベル、メシアンから深い影響を受け、西洋近代音楽が崩壊する瞬間というべき《前衛》の時代に奮闘し、日本音楽への回帰と西洋音楽への揺り戻しとの間で行き交いながら、自らの「夢」の宇宙へと飛翔していった作曲家だったといえると思います。
東フィル首席の斉藤和志さんのアルト・フルート独奏の音色や、間近で聴く田原綾子さんのヴィオラの音色は出色。特に、ベテランの木村茉莉のハープには酔いしれました。ハープという楽器は、遠くのステージや、録音などではなかなかその音色と響きのバランスを体感することは難しく、こうやって2、3メートルの至近で聴くハープこそその本質なんだと痛感させられました。

ミュージアム・コンサート
「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」展 記念コンサート vol.1
2024年3月19日(火)11:00
東京・上野 国立西洋美術館 講堂
お話:新藤 淳(国立西洋美術館 主任研究員)
斎藤和志(フルート)、田原綾子(ヴィオラ)、木村茉莉(ハープ)
武満 徹:
海へⅢ
エア
ドビュッシー:
フルート、ヴィオラ、ハープのためのソナタ
武満 徹:
そして、それが風であることを知った
タグ:東京・春・音楽祭
ロマンチシズムの極み(葵トリオ@紀尾井レジデント・シリーズ) [コンサート]
音楽家あるいは室内楽グループを年1回3年にわたりじっくりと聴かせる「紀尾井レジデント・シリーズ」が新しく始まったのは3年前のコロナ禍真っ最中の3年前のこと。その先頭を切ったのが葵トリオ。シューマンの3つのピアノ・トリオを1曲ずつ配したシリーズ最終回。
ピアノ・トリオというのは、どうしても名人3人が集まってということが多く、常設のトリオというのは珍しい。一体となったアンサンブルの緻密さが持ち味のストリング・クァルテットに対して、ピアノ・トリオは、むしろ個性のぶつかり合いでスターたちのスリリングなやり取りこそ面白い。
珍しい常設のピアノトリオである葵トリオの凄味は、アンサンブルの精密さが驚異的なのにもかかわらず、三人それぞれがお互いに譲らずに個性をぶつけ合い自由に語り合う面白さ。
最終回の今回は、それがさらに進化。アンサンブルは緻密を通り越して濃密と言っても良いほど。そこに融合と対話という3人の相互作用が際立っていて音楽そのものがまばゆいばかりの光彩を放つ。その音楽的色彩感が素晴らしい。
前2回と特に違ってきたのは、リーダーシップというのか、音楽の中心が明確にヴァイオリンの小川にあること。

1曲目の、クララ・シューマンは、いかにもフェミニンで小川のヴァイオリンが優雅にしかも毅然と振る舞うのがたおやかで美しい。伊東のチェロの音色は、相変わらず滑らかで極上の艶やかさ。ピアノの秋元はいままでうってかわって優しく控えめで、そのヴァイオリンの手を添えてエスコートするかのように優しい。
2曲めのロベルト・シューマンも、家庭的な幸福感とメランコリックな憧憬にあふれていて、ここでもとびきり上等のロマンチシズムが横溢している。その夢見るような情感に酔いしれました。こちらではチェロの聴かせどころが多いのですが、ユニゾンや和声では存在が消えるほどで、そこからふっと浮かび上がるメロディの美音にうっとりさせられる。ヴァイオリンの消え際にも陶然とさせられます。
アコースティックの素晴らしさでは定評のある紀尾井ホールですが、今回座ったステージに近い左手のバルコニー席は、屋根の下にもかかわらず、そういう響きと音色の鮮度が高く、陰影のニュアンスがくっきり。音の良いホールは、どんな席でもよい音がする。紀尾井ホールは、もちろん場所によって微妙に音のバランスは違いますが、どこでもそれぞれに音が良い。室内楽には、この1階バルコニー席が最適の席かもしれません。
最後のブラームスは、そういうロマンチシズムの極地。シューマン夫妻のほとばしるような情熱が燃え上がる。頭の中が真っ白になってしまい、あっという間に時間が過ぎていく。もうこれは凄いのひと言しかありません。
このトリオは、世界でも最トップのピアノトリオかもしれません。

紀尾井レジデント・シリーズ I
葵トリオ(第3回)
2024年3月19日(火) 19:00
東京・四ッ谷 紀尾井ホール
(1階 BL1列3番)
葵トリオ
小川響子(Vn)、伊東 裕(Vc)、秋元孝介(Pf)
クララ・シューマン:ピアノ三重奏曲ト短調 op.17
ロベルト・シューマン:ピアノ三重奏曲第3番ト短調 op.110
ブラームス:ピアノ三重奏曲第1
(アンコール)
シューマン:ピアノ三重奏曲第2番ヘ長調OP80より第3楽章
ピアノ・トリオというのは、どうしても名人3人が集まってということが多く、常設のトリオというのは珍しい。一体となったアンサンブルの緻密さが持ち味のストリング・クァルテットに対して、ピアノ・トリオは、むしろ個性のぶつかり合いでスターたちのスリリングなやり取りこそ面白い。
珍しい常設のピアノトリオである葵トリオの凄味は、アンサンブルの精密さが驚異的なのにもかかわらず、三人それぞれがお互いに譲らずに個性をぶつけ合い自由に語り合う面白さ。
最終回の今回は、それがさらに進化。アンサンブルは緻密を通り越して濃密と言っても良いほど。そこに融合と対話という3人の相互作用が際立っていて音楽そのものがまばゆいばかりの光彩を放つ。その音楽的色彩感が素晴らしい。
前2回と特に違ってきたのは、リーダーシップというのか、音楽の中心が明確にヴァイオリンの小川にあること。
1曲目の、クララ・シューマンは、いかにもフェミニンで小川のヴァイオリンが優雅にしかも毅然と振る舞うのがたおやかで美しい。伊東のチェロの音色は、相変わらず滑らかで極上の艶やかさ。ピアノの秋元はいままでうってかわって優しく控えめで、そのヴァイオリンの手を添えてエスコートするかのように優しい。
2曲めのロベルト・シューマンも、家庭的な幸福感とメランコリックな憧憬にあふれていて、ここでもとびきり上等のロマンチシズムが横溢している。その夢見るような情感に酔いしれました。こちらではチェロの聴かせどころが多いのですが、ユニゾンや和声では存在が消えるほどで、そこからふっと浮かび上がるメロディの美音にうっとりさせられる。ヴァイオリンの消え際にも陶然とさせられます。
アコースティックの素晴らしさでは定評のある紀尾井ホールですが、今回座ったステージに近い左手のバルコニー席は、屋根の下にもかかわらず、そういう響きと音色の鮮度が高く、陰影のニュアンスがくっきり。音の良いホールは、どんな席でもよい音がする。紀尾井ホールは、もちろん場所によって微妙に音のバランスは違いますが、どこでもそれぞれに音が良い。室内楽には、この1階バルコニー席が最適の席かもしれません。
最後のブラームスは、そういうロマンチシズムの極地。シューマン夫妻のほとばしるような情熱が燃え上がる。頭の中が真っ白になってしまい、あっという間に時間が過ぎていく。もうこれは凄いのひと言しかありません。
このトリオは、世界でも最トップのピアノトリオかもしれません。

紀尾井レジデント・シリーズ I
葵トリオ(第3回)
2024年3月19日(火) 19:00
東京・四ッ谷 紀尾井ホール
(1階 BL1列3番)
葵トリオ
小川響子(Vn)、伊東 裕(Vc)、秋元孝介(Pf)
クララ・シューマン:ピアノ三重奏曲ト短調 op.17
ロベルト・シューマン:ピアノ三重奏曲第3番ト短調 op.110
ブラームス:ピアノ三重奏曲第1
(アンコール)
シューマン:ピアノ三重奏曲第2番ヘ長調OP80より第3楽章



