「ピュウ」(キャサリン・レイシー 著)読了 [読書]
とても新しい小説。不思議でなんともいえない無力感にとらわれる読後感だけが残される。

ピュウというのは、教会の会衆が座るベンチのような長椅子のことを言う。どこからともなく現れ、そこに寝ていた「わたし」の一人称で語られる。どこから来たのか、名前も年齢も性別すらもわからないので、人々から仮の名前としてピュウと呼ばれることになった。

そういう無意識の一人称、米国南部コミュニティというと否が応でもなくフォークナーを思い浮かべるが、この小説はさらに純粋で実体に乏しい極めて抽象的な世界。そうであっても、そこに表出される人々の欺瞞、偽善、疎外、差別、世代抑圧、あるいはコミュニティの同胞融和の圧力は、深刻で生々しくとても切羽詰まった現実感を与える。
舞台は明らかに米国の深南部の村で、そのコミュニティの様相を映し出している。一見、よそ者に対して寛容で親切で善意にあふれている。望めばその一員として受け入れる準備もある。しかしそこには底知れぬ人種意識が内在していて、ふと気がつくと遠景にはあからさまな人種隔離の境界が存在している。通りひとつで、白人と黒人の居住区が隔てられていることを知ってギョッとすることもある。
その構造は、何も南部に限らない。一見リベラルなように見える社会でも、自分がどいうコミュニティに属しているかの確認が必要だし、他人の属するコミュニティを確認する必要がある。移民国家である以上、人々は誰もが由来不明で隣人のアイデンティティは相互に監視されている。何らかの同一性を体感するためには、時には共有の儀式が求められるのかもしれない。
ピュウは、そのことを静かに穏やかに見つめていく。
もちろん、その疎外と差別は、日本のコミュニティにもある。日本社会は同一性が空気のようにあたりまえ、血縁、地縁のつながりは意識の立ち入る余地もないほどに長い時間を経ている。それだけに差別や排他意識についての自意識が希薄だ。逆に、いったん差別や排他の本能に火がつくと激しく燃えさかるし、本来内向きな同胞融和は、豹変するように攻撃的になって残虐性を帯びてしまう。
そういう内在的な自己意識、原罪意識が、読後の無力感としてどこまでも暗く尾を引いて残される。
平明で静穏だが、怖い小説だ。
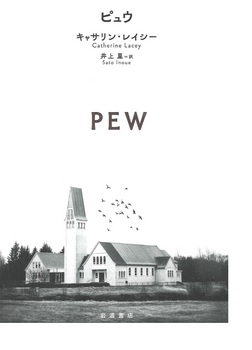
ピュウ
PEW
キャサリン・レイシー
Catherine Lacey
井上 里 訳
岩波書店
2023年8月30日 第一刷

ピュウというのは、教会の会衆が座るベンチのような長椅子のことを言う。どこからともなく現れ、そこに寝ていた「わたし」の一人称で語られる。どこから来たのか、名前も年齢も性別すらもわからないので、人々から仮の名前としてピュウと呼ばれることになった。

そういう無意識の一人称、米国南部コミュニティというと否が応でもなくフォークナーを思い浮かべるが、この小説はさらに純粋で実体に乏しい極めて抽象的な世界。そうであっても、そこに表出される人々の欺瞞、偽善、疎外、差別、世代抑圧、あるいはコミュニティの同胞融和の圧力は、深刻で生々しくとても切羽詰まった現実感を与える。
舞台は明らかに米国の深南部の村で、そのコミュニティの様相を映し出している。一見、よそ者に対して寛容で親切で善意にあふれている。望めばその一員として受け入れる準備もある。しかしそこには底知れぬ人種意識が内在していて、ふと気がつくと遠景にはあからさまな人種隔離の境界が存在している。通りひとつで、白人と黒人の居住区が隔てられていることを知ってギョッとすることもある。
その構造は、何も南部に限らない。一見リベラルなように見える社会でも、自分がどいうコミュニティに属しているかの確認が必要だし、他人の属するコミュニティを確認する必要がある。移民国家である以上、人々は誰もが由来不明で隣人のアイデンティティは相互に監視されている。何らかの同一性を体感するためには、時には共有の儀式が求められるのかもしれない。
ピュウは、そのことを静かに穏やかに見つめていく。
もちろん、その疎外と差別は、日本のコミュニティにもある。日本社会は同一性が空気のようにあたりまえ、血縁、地縁のつながりは意識の立ち入る余地もないほどに長い時間を経ている。それだけに差別や排他意識についての自意識が希薄だ。逆に、いったん差別や排他の本能に火がつくと激しく燃えさかるし、本来内向きな同胞融和は、豹変するように攻撃的になって残虐性を帯びてしまう。
そういう内在的な自己意識、原罪意識が、読後の無力感としてどこまでも暗く尾を引いて残される。
平明で静穏だが、怖い小説だ。
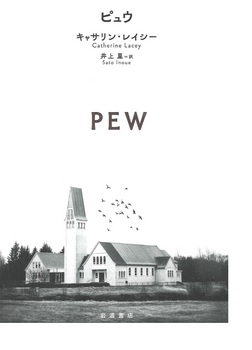
ピュウ
PEW
キャサリン・レイシー
Catherine Lacey
井上 里 訳
岩波書店
2023年8月30日 第一刷
「ごまかさないクラシック音楽」(岡田暁生 片山杜秀 共著)読了 [読書]
標題の「ごまかさない」とはどういう意味だろうか?
対談のひとり、岡田暁生氏は『はじめに』でこう語っています。
――興味を持ち始めたころ抱いた疑問は、後から振り返ってもしばしばことの核心をついている。だが納得できる答えを誰も与えてくれない――
クラシック音楽にまつわる、こうした5歳のチコちゃんの疑問を「ごまかさず」に真正面から向かい合って、本音で話し合おうというのがこの対談の趣旨であるというわけだ。

岡田氏は、これからの音楽のあり方に懐疑的な音楽史学者。一方の片山氏は、現代音楽や現代聴衆の社会政治的背景の虚実を追求してきた政治学者。互いに、クラシック音楽と呼ばれるジャンルを熱烈に愛しながらも、かなりシニカルな言辞を投げつける音楽評論家…ということでは共通しています。
一方で、バッハ、ベートーヴェンを核心とする《クラシック》の本流から、それ以前の時代の源流へとその根源をアカデミックに探訪しようとする岡田氏と、むしろ下流側の現代へと、記憶の生々しい社会事象や個人的体験に結びつけてマニアックに問いかけるクラヲタの片山氏とは、まるで音楽的嗜好も思想的志向も違っていて対立的。
前半は、その上流の音楽史であって岡田氏が主導する。とはいえ、そもそも《クラシック音楽》というものは、大正・昭和の教養主義、スノッビズムであろうと、平成・令和の軽薄短小の同調主義であろうと、その愛好家が安易に考えているような「音楽は世界の共通語」「人類みな兄弟」的なお花畑ではない…ということで妙に二人の平仄は合ってしまう。

がぜん面白くなるのは、近現代に話題が下ってくる後半。主導権は次第に片山氏へと移るわけだが、二人とも、近代資本主義や二十世紀の全体主義、戦後の冷戦時代の現実が芸術全体に落としたどす黒い影は熟知しているから、クラシック音楽の背景に潜んでいる自由主義と全体主義という政治イデオロギー対立ということでは一致する。そうした後ろ暗い陰の世界を暴き立ててばっさりと裁ち切るところで意気投合するところが面白い。
今や、自由主義的民主主義も行き詰まっていているから、さすがにクラシック音楽好きといえども、西洋正統音楽こそが唯一にして純真無垢な正義の哲人であって、グローバルな世界の善良なる文化だとは、素直に信じ切れなくなっているはずだ。
「クラシック音楽は死んだ("Musik ist tot")」
そんなところが二人の意気投合の帰結であるように思う。
だから、本書は決して《入門書》ではない。「5歳…(実はン十歳)の疑問」に答えるということでは、相当のクラシック上級者向け。
読者のほうこそ、果たしてどこまで、自分をごまかさないで受け入れることができるか?

ごまかさないクラシック音楽
岡田 暁生 (著), 片山 杜秀 (著)
新潮選書
2023/5/25 発刊
対談のひとり、岡田暁生氏は『はじめに』でこう語っています。
――興味を持ち始めたころ抱いた疑問は、後から振り返ってもしばしばことの核心をついている。だが納得できる答えを誰も与えてくれない――
クラシック音楽にまつわる、こうした5歳のチコちゃんの疑問を「ごまかさず」に真正面から向かい合って、本音で話し合おうというのがこの対談の趣旨であるというわけだ。

岡田氏は、これからの音楽のあり方に懐疑的な音楽史学者。一方の片山氏は、現代音楽や現代聴衆の社会政治的背景の虚実を追求してきた政治学者。互いに、クラシック音楽と呼ばれるジャンルを熱烈に愛しながらも、かなりシニカルな言辞を投げつける音楽評論家…ということでは共通しています。
一方で、バッハ、ベートーヴェンを核心とする《クラシック》の本流から、それ以前の時代の源流へとその根源をアカデミックに探訪しようとする岡田氏と、むしろ下流側の現代へと、記憶の生々しい社会事象や個人的体験に結びつけてマニアックに問いかけるクラヲタの片山氏とは、まるで音楽的嗜好も思想的志向も違っていて対立的。
前半は、その上流の音楽史であって岡田氏が主導する。とはいえ、そもそも《クラシック音楽》というものは、大正・昭和の教養主義、スノッビズムであろうと、平成・令和の軽薄短小の同調主義であろうと、その愛好家が安易に考えているような「音楽は世界の共通語」「人類みな兄弟」的なお花畑ではない…ということで妙に二人の平仄は合ってしまう。

がぜん面白くなるのは、近現代に話題が下ってくる後半。主導権は次第に片山氏へと移るわけだが、二人とも、近代資本主義や二十世紀の全体主義、戦後の冷戦時代の現実が芸術全体に落としたどす黒い影は熟知しているから、クラシック音楽の背景に潜んでいる自由主義と全体主義という政治イデオロギー対立ということでは一致する。そうした後ろ暗い陰の世界を暴き立ててばっさりと裁ち切るところで意気投合するところが面白い。
今や、自由主義的民主主義も行き詰まっていているから、さすがにクラシック音楽好きといえども、西洋正統音楽こそが唯一にして純真無垢な正義の哲人であって、グローバルな世界の善良なる文化だとは、素直に信じ切れなくなっているはずだ。
「クラシック音楽は死んだ("Musik ist tot")」
そんなところが二人の意気投合の帰結であるように思う。
だから、本書は決して《入門書》ではない。「5歳…(実はン十歳)の疑問」に答えるということでは、相当のクラシック上級者向け。
読者のほうこそ、果たしてどこまで、自分をごまかさないで受け入れることができるか?

ごまかさないクラシック音楽
岡田 暁生 (著), 片山 杜秀 (著)
新潮選書
2023/5/25 発刊
「アルツハイマー病研究、失敗の構造」(カール・ヘラップ 著)読了 [読書]
エーザイのアルツハイマー病の新薬「レカネマブ(商品名レケンビ)」が保険適用となり、認知症治療薬として投与が開始されたことが大きなニュースととなっている。
果たしてそれは《認知症》の治療や予防に決定的なものなのか?
高齢社会では膨大な数の認知症の要介護者を抱えている。高額な薬価への保険適用は、医療保険の財政の破綻を招かないのか?。介護支援と医療保険とどう折り合いをつけるのか?そうした懸念や疑問、批判の声が各方面から上がっている。保険適用は、社会全体から見れば、決してめでたいことではない。
本書は、アルツハイマー病研究を失敗だと断じ、その裏の事情を暴露し痛烈に批判している。
そもそも「レカネマブ」は万能の特効薬ではない。そのためにこれまで膨大な人材と研究資源が消尽され、その開発のために莫大な資金がつぎ込まれてきた。――それはなぜか?
「アルツハイマー病」とは、そもそもどんな病気か?
皆さんは、「アルツハイマー」と聞いて、すぐに思い浮かべる病状はどんなものだろうか。おおよそ次の3つから選んでみて下さい。(別に正解を問うテストではないのでお気軽にお答えください)
1.時間をかけて徐々に記憶力の障害が進行し、知的能力が損なわれ人格さえ変わってしまう恐ろしい脳の奇病。
2.脳に異常な物質が徐々に蓄積していき、脳組織が破壊されていくことによって引き起こされる重度の進行性認知障害。
3.高齢化によって認知障害が進み、痴ほう化が現れ、生活や家族関係など各方面に深刻な支障を生ずる、重度の老人性痴呆症。
さて、皆さんの答えはいかがでしょうか?おそらくほとんどの方が3.だと思われているのではないでしょうか。実際、かつての「痴呆症」とか「老人ボケ」といった言葉を「アルツハイマー」と冗談半分にせよ言い換えてしまうことは今やごくごく日常的なことになっていると思う。
私の世代では、2.だと思い込んでいる人も多い。私が「アルツハイマー」のことを知ったのは90年代初めごろ。当時、それが盛んに話題となったのは原因不明のこの認知障害の病の原因が解明されたと報じられたから。《異常な物質》とは、タンパク質の一種で「アミロイド(β)」と呼ばれるもの。それがなぜ蓄積されるかについては諸説あって、まだまだ謎だった。
歴史的には、1.が正しい。病名は、この新しい疾患を発見したドイツ人医師の名前にちなむ。アルツハイマーは、精神科医だが脳の解剖学研究にも興味を持ち、ひとりの患者の脳組織を顕微鏡で観察しその特異な病巣を発見した。長年、あくまでも「奇病」であって、希にしか発生しない病状だと見なされていた。
「アルツハイマー病」研究が拡がるのは、むしろ戦後のこと。寿命が延び、高齢化社会が進展するにつれ、身体的には頑健であっても認知の点で問題のある老人が増えてきた。有吉佐和子の『恍惚の人』がベストセラーになったのは1972年のことだった。その老人性認知症の症状は、「アルツハイマー病」とほとんど同じだった。かくて「アルツハイマー病」はまれに見る悲惨な奇病からありふれた認知症へと変貌する。3.が、現在の一般的な受け止めだと言ってよい。
つまり、1.も2.も3.も全て正解ということになる。時とともに「奇病」は、希に見る病気から、遺伝性も疑われる多発性の病気となり、今や誰もが避けることのできない老齢化に伴う症状として世の人々の恐怖心を煽っている。
しかし、「奇病」のそもそもの特異性とされた脳細胞構造の病巣にみられた異物がやがて脳病理学の進展によって「アミロイドβ」と特定されたことは画期的であったし、それが画像診断の進化によって老人性認知症患者にも共通して見られることもわかってきた。やがてこれがあたかも全ての痴呆症の病因であるかのような前提が学会に蔓延する。すなわち「アミロイドの蓄積がアルツハイマー型認知症を発症させる」という、いわゆる「アミロイドカスケード」仮説である。
著者によれば、実際のところはアミロイドが溜まるから認知症になるかどうかはわからないという。蓄積しても認知症になっていない人はいくらでもいるし、蓄積は80歳を超えると3分の1か、それ以上の半分近くにもなる。つまり、蓄積は老化の結果であって、それは認知症の原因とは見なされない。認知症が老化の結果なら、そのメカニズムは複雑で何が根本的な原因なのかは不明なのだ。
しかし、医学界も大学などの公的研究機関も、やがて「アミロイドカスケード」仮説に邁進することになる。アミロイド以外に病理を求める基礎研究はことごとく排除され研究費がつかない。製薬会社は、アミロイドを抑制する抗アミロイド薬の開発に躍起になる。その裏付けを構築するために、化学者ばかりでなく統計学者も動員され、複雑で怪しげな統計学的・疫学的見解がまかり通ることになる。
抗アミロイド薬によってアミロイド蓄積が抑制されても、認知症が治るわけではない。期待できるのは、最大限、その進行が止まることである。しかも、「アミロイド」原因説が仮説である以上、進行がとまるかどうかもわからない。最低限、患者にアミロイド蓄積があると診断されない限りは、投与することさえ意味がない。
一方で、高齢化による介護ニーズは高まるばかり。患者自身ばかりだけでなく家族の不安も高まる一方だ。《期待の新薬》に殺到するのは医者だけではない。誰だって、何とかしたいとすがりつきたくなる。
その費用は人・年あたり3百万円を超えるという。不可逆的な進行性の病気だから投与は死ぬまで続く。製薬会社の株価は高騰するかもしれないが、保険財政は破綻するかもしれない。その前に介護費用の負担との取り合いも問題になる。アミロイド蓄積が所見されることを前提にしてある程度の壁を設けるにしても、それ自体に時間と費用がかかることになる。
著者は、「では、ここからどうする?」としていくつもの提言を述べている。正直言って、医学界や基礎研究体制などの政治的裏事情はわからない。だから著者の主張はなかなかに読み取ることが難しい。要するに、「アミロイドカスケード」仮説一本やりはやめろということなんだろう。老人性認知症の研究は、時間をかけてじっくり取り組むべきだということ。
私たちは、老人性認知症に対して医学的医療だけに過度に頼ろうとせずに、社会全体で向き合うべきなんだと思う。
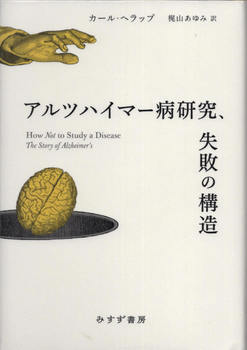
アルツハイマー病研究、失敗の構造
カール・ヘラップ (著)
梶山あゆみ (翻訳)
みすず書房
2023年8月初刊 2023年11月20日第3刷
果たしてそれは《認知症》の治療や予防に決定的なものなのか?
高齢社会では膨大な数の認知症の要介護者を抱えている。高額な薬価への保険適用は、医療保険の財政の破綻を招かないのか?。介護支援と医療保険とどう折り合いをつけるのか?そうした懸念や疑問、批判の声が各方面から上がっている。保険適用は、社会全体から見れば、決してめでたいことではない。
本書は、アルツハイマー病研究を失敗だと断じ、その裏の事情を暴露し痛烈に批判している。
そもそも「レカネマブ」は万能の特効薬ではない。そのためにこれまで膨大な人材と研究資源が消尽され、その開発のために莫大な資金がつぎ込まれてきた。――それはなぜか?
「アルツハイマー病」とは、そもそもどんな病気か?
皆さんは、「アルツハイマー」と聞いて、すぐに思い浮かべる病状はどんなものだろうか。おおよそ次の3つから選んでみて下さい。(別に正解を問うテストではないのでお気軽にお答えください)
1.時間をかけて徐々に記憶力の障害が進行し、知的能力が損なわれ人格さえ変わってしまう恐ろしい脳の奇病。
2.脳に異常な物質が徐々に蓄積していき、脳組織が破壊されていくことによって引き起こされる重度の進行性認知障害。
3.高齢化によって認知障害が進み、痴ほう化が現れ、生活や家族関係など各方面に深刻な支障を生ずる、重度の老人性痴呆症。
さて、皆さんの答えはいかがでしょうか?おそらくほとんどの方が3.だと思われているのではないでしょうか。実際、かつての「痴呆症」とか「老人ボケ」といった言葉を「アルツハイマー」と冗談半分にせよ言い換えてしまうことは今やごくごく日常的なことになっていると思う。
私の世代では、2.だと思い込んでいる人も多い。私が「アルツハイマー」のことを知ったのは90年代初めごろ。当時、それが盛んに話題となったのは原因不明のこの認知障害の病の原因が解明されたと報じられたから。《異常な物質》とは、タンパク質の一種で「アミロイド(β)」と呼ばれるもの。それがなぜ蓄積されるかについては諸説あって、まだまだ謎だった。
歴史的には、1.が正しい。病名は、この新しい疾患を発見したドイツ人医師の名前にちなむ。アルツハイマーは、精神科医だが脳の解剖学研究にも興味を持ち、ひとりの患者の脳組織を顕微鏡で観察しその特異な病巣を発見した。長年、あくまでも「奇病」であって、希にしか発生しない病状だと見なされていた。
「アルツハイマー病」研究が拡がるのは、むしろ戦後のこと。寿命が延び、高齢化社会が進展するにつれ、身体的には頑健であっても認知の点で問題のある老人が増えてきた。有吉佐和子の『恍惚の人』がベストセラーになったのは1972年のことだった。その老人性認知症の症状は、「アルツハイマー病」とほとんど同じだった。かくて「アルツハイマー病」はまれに見る悲惨な奇病からありふれた認知症へと変貌する。3.が、現在の一般的な受け止めだと言ってよい。
つまり、1.も2.も3.も全て正解ということになる。時とともに「奇病」は、希に見る病気から、遺伝性も疑われる多発性の病気となり、今や誰もが避けることのできない老齢化に伴う症状として世の人々の恐怖心を煽っている。
しかし、「奇病」のそもそもの特異性とされた脳細胞構造の病巣にみられた異物がやがて脳病理学の進展によって「アミロイドβ」と特定されたことは画期的であったし、それが画像診断の進化によって老人性認知症患者にも共通して見られることもわかってきた。やがてこれがあたかも全ての痴呆症の病因であるかのような前提が学会に蔓延する。すなわち「アミロイドの蓄積がアルツハイマー型認知症を発症させる」という、いわゆる「アミロイドカスケード」仮説である。
著者によれば、実際のところはアミロイドが溜まるから認知症になるかどうかはわからないという。蓄積しても認知症になっていない人はいくらでもいるし、蓄積は80歳を超えると3分の1か、それ以上の半分近くにもなる。つまり、蓄積は老化の結果であって、それは認知症の原因とは見なされない。認知症が老化の結果なら、そのメカニズムは複雑で何が根本的な原因なのかは不明なのだ。
しかし、医学界も大学などの公的研究機関も、やがて「アミロイドカスケード」仮説に邁進することになる。アミロイド以外に病理を求める基礎研究はことごとく排除され研究費がつかない。製薬会社は、アミロイドを抑制する抗アミロイド薬の開発に躍起になる。その裏付けを構築するために、化学者ばかりでなく統計学者も動員され、複雑で怪しげな統計学的・疫学的見解がまかり通ることになる。
抗アミロイド薬によってアミロイド蓄積が抑制されても、認知症が治るわけではない。期待できるのは、最大限、その進行が止まることである。しかも、「アミロイド」原因説が仮説である以上、進行がとまるかどうかもわからない。最低限、患者にアミロイド蓄積があると診断されない限りは、投与することさえ意味がない。
一方で、高齢化による介護ニーズは高まるばかり。患者自身ばかりだけでなく家族の不安も高まる一方だ。《期待の新薬》に殺到するのは医者だけではない。誰だって、何とかしたいとすがりつきたくなる。
その費用は人・年あたり3百万円を超えるという。不可逆的な進行性の病気だから投与は死ぬまで続く。製薬会社の株価は高騰するかもしれないが、保険財政は破綻するかもしれない。その前に介護費用の負担との取り合いも問題になる。アミロイド蓄積が所見されることを前提にしてある程度の壁を設けるにしても、それ自体に時間と費用がかかることになる。
著者は、「では、ここからどうする?」としていくつもの提言を述べている。正直言って、医学界や基礎研究体制などの政治的裏事情はわからない。だから著者の主張はなかなかに読み取ることが難しい。要するに、「アミロイドカスケード」仮説一本やりはやめろということなんだろう。老人性認知症の研究は、時間をかけてじっくり取り組むべきだということ。
私たちは、老人性認知症に対して医学的医療だけに過度に頼ろうとせずに、社会全体で向き合うべきなんだと思う。
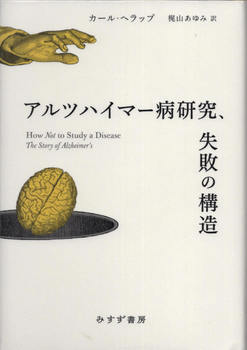
アルツハイマー病研究、失敗の構造
カール・ヘラップ (著)
梶山あゆみ (翻訳)
みすず書房
2023年8月初刊 2023年11月20日第3刷
「ヒトラー馬を奪還せよ」(アルテュール・ブラント 著)読了 [読書]
ヒトラー総統の官邸前に威容を誇っていた高さ3メートルを超える一対の馬の巨大なブロンズ像。爆撃で徹底的に破壊されたと信じられていたこのブロンズ像が現存し、しかもネオナチがらみの闇市場で取引されてた。
2015年に、このブロンズ像が当局によって奪還されて世間をあっと言わせた。
この奪還に実際に関わった著者が、いわばミステリー仕立てでその経緯の詳細を語ったドキュメンタリー。全てが実話。
なかなか興味をそそられる話しなのだけど、残念ながらさほど面白くなかったというのが本音。
そもそも、私たち日本人にとって「ヒトラーの馬」と言われても、ありがたくもなんともない。70年近く経ってそれが突然見つかったといっても、そんなものがあったことすらも知らない。

写真を見ても、いかにも悪趣味。むしろヒトラーとスターリンの嗜好があまりにも似ていることに驚き、嫌悪すら感じる。美術品として無価値だとまでは思わないが、戦後自由主義の時代に育った私たちにとっては、ナチスに退廃芸術として弾圧されたモダニズム芸術や建築の方がはるかに親しみがある。

問題は、そういう親ナチ芸術をいまでも信奉し秘匿して愛玩している人々がいて、高額な価値で闇取引されているという気味の悪さだ。こうした美術品の多くがソ連軍によって東側に持ち去られ、冷戦の間、東ドイツの外貨獲得のために西側のナチの残党やネオナチに売りさばかれていたという。そこにKGBや東ドイツの秘密警察が暗躍し仲介していた。戦後の追求を免れた親ナチで稼いだ大富豪。ネオナチが闇取引の対価として共産主義者に巨額の金銭を渡していた。そういう不正義の臭いみたいなものがほのかに香りながら話しは進む。

著者は、盗品や贋作美術を内偵・摘発する「美術探偵」なんだそうだ。一人称で語られるミステリーは、さながら小説を読んでいるようだが、あくまでもノンフィクション。だから、かえってミステリー性が中途半端。確かにどこか間抜けな探偵風でもあり、だましだまされながらたどり着くのは手先の小物ばかりで、巨悪が暴かれるわけでもない。事実は、しょせん小説ほどにはドラマチックではないのだ。
肝心の奪還の現場や所有者の正体などについても尻切れとんぼ。民間人で外国人の著者は現場に居合わせなかったからだろうが、あまりに正直過ぎる。読後のカタルシスは皆無。
まあ、ガッカリ本とまでは言わないが、ダン・ブラウンの小説のようだとかいった帯書きに踊らされない方が良い。

ヒトラーの馬を奪還せよ
――美術探偵、ナチ地下世界を往く
アルテュール・ブラント (著), 安原 和見 (訳)
筑摩書房
2023年7月30日初版
De paarden van Hitler
(オランダ語原著の英訳本よりの翻訳)
2015年に、このブロンズ像が当局によって奪還されて世間をあっと言わせた。
この奪還に実際に関わった著者が、いわばミステリー仕立てでその経緯の詳細を語ったドキュメンタリー。全てが実話。
なかなか興味をそそられる話しなのだけど、残念ながらさほど面白くなかったというのが本音。
そもそも、私たち日本人にとって「ヒトラーの馬」と言われても、ありがたくもなんともない。70年近く経ってそれが突然見つかったといっても、そんなものがあったことすらも知らない。

写真を見ても、いかにも悪趣味。むしろヒトラーとスターリンの嗜好があまりにも似ていることに驚き、嫌悪すら感じる。美術品として無価値だとまでは思わないが、戦後自由主義の時代に育った私たちにとっては、ナチスに退廃芸術として弾圧されたモダニズム芸術や建築の方がはるかに親しみがある。

問題は、そういう親ナチ芸術をいまでも信奉し秘匿して愛玩している人々がいて、高額な価値で闇取引されているという気味の悪さだ。こうした美術品の多くがソ連軍によって東側に持ち去られ、冷戦の間、東ドイツの外貨獲得のために西側のナチの残党やネオナチに売りさばかれていたという。そこにKGBや東ドイツの秘密警察が暗躍し仲介していた。戦後の追求を免れた親ナチで稼いだ大富豪。ネオナチが闇取引の対価として共産主義者に巨額の金銭を渡していた。そういう不正義の臭いみたいなものがほのかに香りながら話しは進む。

著者は、盗品や贋作美術を内偵・摘発する「美術探偵」なんだそうだ。一人称で語られるミステリーは、さながら小説を読んでいるようだが、あくまでもノンフィクション。だから、かえってミステリー性が中途半端。確かにどこか間抜けな探偵風でもあり、だましだまされながらたどり着くのは手先の小物ばかりで、巨悪が暴かれるわけでもない。事実は、しょせん小説ほどにはドラマチックではないのだ。
肝心の奪還の現場や所有者の正体などについても尻切れとんぼ。民間人で外国人の著者は現場に居合わせなかったからだろうが、あまりに正直過ぎる。読後のカタルシスは皆無。
まあ、ガッカリ本とまでは言わないが、ダン・ブラウンの小説のようだとかいった帯書きに踊らされない方が良い。

ヒトラーの馬を奪還せよ
――美術探偵、ナチ地下世界を往く
アルテュール・ブラント (著), 安原 和見 (訳)
筑摩書房
2023年7月30日初版
De paarden van Hitler
(オランダ語原著の英訳本よりの翻訳)
「言語の本質」(今井むつみ、秋田喜美 共著)読了 [読書]
学術的なテーマにもかかわらず18万部を突破する大ヒット。各方面からも絶賛の声があがっている注目の書。
言語というのは、誰にも身近な事象だけに関心を集めやすい。本書もオノマトペと幼児語、語学学習という身近で日常的な問題を取り上げていています。、しかも女性学者らしいその平易で語り口と丁寧な説明がとてもわかりやすく、親しみが持てます。異例のベストセラーとなった秘訣だと思います。
オノマトペとは、音声を模倣した擬声語のこと。
単語の形をしたシンボルマークやアイコンとも受け取られる。日本語は、このオノマトペがとても豊富。このことは欧米人もびっくり。言語が専門の人々からもうらやましがられるのだそうです。マンガ文化のおかげかと思いきや、万葉集などの古い和語にも頻繁に現れるのだそうです。
このオノマトペという赤ちゃん語が、子育てには欠かせない。子どもの言葉の発達にとても大事と言われれば、誰もがウンウンとうなずいてしまいます。でも、それは本当なの?なぜ?どうして?――ボーッと生きてる場合じゃありません。
ここから著者は、私たちを本格的な言語学の世界、その深く大きな謎へと導いてくれます。優しい顔つきながら、実はとても本気なのです。
まず最初に、オノマトペは、ほんとうに言葉(=言語)と言えるのか?と問いかけます。オノマトペとは、単なる擬声(音声の模倣)、あるいはトイレの男女マークのようなシンボル(=アイコン)に過ぎないのか?その検証のために「言語の十大原則」というものがあるそうです。著者は、そのひとつひとつを検証していく。いよいよ言語学の世界に突入します。そしてその検証の結果には、ちょっと驚いてしまいます。オノマトペは、(幼さはあっても)立派な言葉だと言えるのだそうです。
では、ほんとうに子どもが言葉をおぼえていく上で重要なのか?これが次の問題です。確かにオノマトペは、子どもの注意を引きやすいし、わかりやすい。赤ちゃんには「イヌ」とは言わずに「ワンワン」と言ったほうがわかりやすい。これはオノマトペの「アイコン」性のおかげですが、子どもが成長するにつれて「イヌ」「犬」、「犬ころ」「飼い犬」「走狗」…と果てしない豊穣の知識の世界へと展開していく。これこそ言葉の奇跡ともいうべき世界です。
ここで、いきなり人工知能の話しが登場します。ChatGTPとか生成AIの話題は、いままさに議論沸騰中。え?オノマトペと生成AI??
「記号接地問題」。
90年代から提唱されてきたAIの未解決の大問題。この名称を唱えたハルナッドというひとは、「記号から記号への漂流」とも言っています。『機械が辞書の定義だけでことばの意味を「理解」しようとするのは、一度も地面に接地することなく、「記号から記号への漂流」を続けるメリーゴーランドに乗っているようなもの』だとも。機械には実体に触れる機会も学習する方法もないので、実は言葉が示す実体を知らないのです。生成AIといえども、人間が構築した巨大なデータベースを徘徊し、単語と単語の前後の並べ方を学習し文章を構築しているに過ぎない…。
その「接地」の役割を果たすのがオノマトペだと言うのです。幼子の言い間違いは可愛い。でもそこに「接地問題」が隠されている。赤ん坊は、最初は「ワンワン」が吠えることなのか、毛並みの色のことなのか、四つ足動物のことなのか、いったいどれのことなのかはわかっていない。犬という実体と抽象性を持った言葉の意味を対応させていくことが発達の最初のステップ。この「接地」された知識ベースは驚くほどの自走性を持っていて目覚ましい拡大深化を始めるというのです。
もうひとつの視点は、自分で自分の言葉を成長させていく子どものたくましさ。教えたわけではないのに、子どもはいつの間にか新しい言葉を憶えていて、え?と驚くほど適切な場面でその大人びた言い回しを発して親をあきれさせるということがあります。そういう言葉の成長に欠かせないのが「推論」という認知科学的な問題。
ここに「アブダクション推論」という聞き慣れない言葉が登場します。
「アブダクション推論」とは、論理を対称的に推論するバイアス(=傾向・性癖)のこと。「AならばB」なら「BならばA」であると推論するのは間違っています。それは私たちが中学生の頃に散々習ったこと。いわゆる「逆はまた真ならず」という論理学のイロハです。ところが、人間はもともとそういう誤って推論するバイアスを持っていて、実は、そのことで言語習得が可能になっているというのです。このバイアスは、チンパンジーなどとの比較実験をしてみると、人間にしか見られない性癖なのだそうです。
誤った推論なのですから、子どもの勘違いはしばしばあって、それがまた可愛い。でもそれがあるからこそ言葉や知恵の目を瞠るような成長があるわけです。私たちが子どもの言い間違いや勘違いに思わず目を細めてしまうのはそのせいでしょうか。
本書は、単に堅苦しい学術的啓蒙書ではない…というにとどまらず、言語学の本質やそれが抱える謎(未解決問題)へと私たちを誘ってくれる。そうした問題は、比較文化、英語などの外国語学習や手話学習、子どもの発達障害や学習障害といった身近で切実な問題へのアプローチを示しているだけでなく、人工知能や認知科学のさらに大きい世界にも広がりを持っています。
これは、なるほどすごい本です。
オノマトペ?言語学?そんなのカンケーねぇなどと言わずにぜひ手に取って読んでほしい。知的冒険の世界が拓けます。

言語の本質
――ことばはどう生まれ、進化したか
今井 むつみ、秋田 喜美 (共著)
中公新書 2756
2023年5月 新刊
■本書の目次■
はじめに
第1章 オノマトペとは何か
第2章 アイコン性――形式と意味の類似性
第3章 オノマトペは言語か
第4章 子どもの言語習得1――オノマトペ篇
第5章 言語の進化
第6章 子どもの言語習得2――アブダクション推論篇
第7章 ヒトと動物を分かつもの――推論と思考バイアス
終 章 言語の本質
あとがき/参考文献
言語というのは、誰にも身近な事象だけに関心を集めやすい。本書もオノマトペと幼児語、語学学習という身近で日常的な問題を取り上げていています。、しかも女性学者らしいその平易で語り口と丁寧な説明がとてもわかりやすく、親しみが持てます。異例のベストセラーとなった秘訣だと思います。
オノマトペとは、音声を模倣した擬声語のこと。
単語の形をしたシンボルマークやアイコンとも受け取られる。日本語は、このオノマトペがとても豊富。このことは欧米人もびっくり。言語が専門の人々からもうらやましがられるのだそうです。マンガ文化のおかげかと思いきや、万葉集などの古い和語にも頻繁に現れるのだそうです。
このオノマトペという赤ちゃん語が、子育てには欠かせない。子どもの言葉の発達にとても大事と言われれば、誰もがウンウンとうなずいてしまいます。でも、それは本当なの?なぜ?どうして?――ボーッと生きてる場合じゃありません。
ここから著者は、私たちを本格的な言語学の世界、その深く大きな謎へと導いてくれます。優しい顔つきながら、実はとても本気なのです。
まず最初に、オノマトペは、ほんとうに言葉(=言語)と言えるのか?と問いかけます。オノマトペとは、単なる擬声(音声の模倣)、あるいはトイレの男女マークのようなシンボル(=アイコン)に過ぎないのか?その検証のために「言語の十大原則」というものがあるそうです。著者は、そのひとつひとつを検証していく。いよいよ言語学の世界に突入します。そしてその検証の結果には、ちょっと驚いてしまいます。オノマトペは、(幼さはあっても)立派な言葉だと言えるのだそうです。
では、ほんとうに子どもが言葉をおぼえていく上で重要なのか?これが次の問題です。確かにオノマトペは、子どもの注意を引きやすいし、わかりやすい。赤ちゃんには「イヌ」とは言わずに「ワンワン」と言ったほうがわかりやすい。これはオノマトペの「アイコン」性のおかげですが、子どもが成長するにつれて「イヌ」「犬」、「犬ころ」「飼い犬」「走狗」…と果てしない豊穣の知識の世界へと展開していく。これこそ言葉の奇跡ともいうべき世界です。
ここで、いきなり人工知能の話しが登場します。ChatGTPとか生成AIの話題は、いままさに議論沸騰中。え?オノマトペと生成AI??
「記号接地問題」。
90年代から提唱されてきたAIの未解決の大問題。この名称を唱えたハルナッドというひとは、「記号から記号への漂流」とも言っています。『機械が辞書の定義だけでことばの意味を「理解」しようとするのは、一度も地面に接地することなく、「記号から記号への漂流」を続けるメリーゴーランドに乗っているようなもの』だとも。機械には実体に触れる機会も学習する方法もないので、実は言葉が示す実体を知らないのです。生成AIといえども、人間が構築した巨大なデータベースを徘徊し、単語と単語の前後の並べ方を学習し文章を構築しているに過ぎない…。
その「接地」の役割を果たすのがオノマトペだと言うのです。幼子の言い間違いは可愛い。でもそこに「接地問題」が隠されている。赤ん坊は、最初は「ワンワン」が吠えることなのか、毛並みの色のことなのか、四つ足動物のことなのか、いったいどれのことなのかはわかっていない。犬という実体と抽象性を持った言葉の意味を対応させていくことが発達の最初のステップ。この「接地」された知識ベースは驚くほどの自走性を持っていて目覚ましい拡大深化を始めるというのです。
もうひとつの視点は、自分で自分の言葉を成長させていく子どものたくましさ。教えたわけではないのに、子どもはいつの間にか新しい言葉を憶えていて、え?と驚くほど適切な場面でその大人びた言い回しを発して親をあきれさせるということがあります。そういう言葉の成長に欠かせないのが「推論」という認知科学的な問題。
ここに「アブダクション推論」という聞き慣れない言葉が登場します。
「アブダクション推論」とは、論理を対称的に推論するバイアス(=傾向・性癖)のこと。「AならばB」なら「BならばA」であると推論するのは間違っています。それは私たちが中学生の頃に散々習ったこと。いわゆる「逆はまた真ならず」という論理学のイロハです。ところが、人間はもともとそういう誤って推論するバイアスを持っていて、実は、そのことで言語習得が可能になっているというのです。このバイアスは、チンパンジーなどとの比較実験をしてみると、人間にしか見られない性癖なのだそうです。
誤った推論なのですから、子どもの勘違いはしばしばあって、それがまた可愛い。でもそれがあるからこそ言葉や知恵の目を瞠るような成長があるわけです。私たちが子どもの言い間違いや勘違いに思わず目を細めてしまうのはそのせいでしょうか。
本書は、単に堅苦しい学術的啓蒙書ではない…というにとどまらず、言語学の本質やそれが抱える謎(未解決問題)へと私たちを誘ってくれる。そうした問題は、比較文化、英語などの外国語学習や手話学習、子どもの発達障害や学習障害といった身近で切実な問題へのアプローチを示しているだけでなく、人工知能や認知科学のさらに大きい世界にも広がりを持っています。
これは、なるほどすごい本です。
オノマトペ?言語学?そんなのカンケーねぇなどと言わずにぜひ手に取って読んでほしい。知的冒険の世界が拓けます。

言語の本質
――ことばはどう生まれ、進化したか
今井 むつみ、秋田 喜美 (共著)
中公新書 2756
2023年5月 新刊
■本書の目次■
はじめに
第1章 オノマトペとは何か
第2章 アイコン性――形式と意味の類似性
第3章 オノマトペは言語か
第4章 子どもの言語習得1――オノマトペ篇
第5章 言語の進化
第6章 子どもの言語習得2――アブダクション推論篇
第7章 ヒトと動物を分かつもの――推論と思考バイアス
終 章 言語の本質
あとがき/参考文献
将軍の世紀 下巻(山内 昌之 著) 読了 [読書]
下巻は、ほぼすべてが幕末に費やされている。
今までの幕末維新の歴史観はすべて倒幕側からのもの。本書はあくまでも標題の通りで将軍、すなわち江戸幕府側からの視点で書かれている。そのことが本書の独創的なところで、とても面白い。
下巻を読み通して、つくづく思うのは江戸幕府は内側から自壊したのだということ。滅ぼしたのは徳川御三家。その源泉であり中核となったのが水戸藩の斉昭。その実子である一橋慶喜が「大政奉還」という形で幕を引くことになる。
水戸が伝統的に背負っていたのは、藩主血統の正統性とその自戒から生まれた「水戸学」。その真髄は、儒学的な日本の社会秩序の精神的な権力体系。皇統に絶対的支配の頂点を求める「尊皇」思想のこと。この水戸学を狂信的な「攘夷」と結びつけたのが斉昭だった。
それは、第12代家斉の時代から始まった幕藩体制の弛緩とロシアなどの外国船の度重なる侵犯という社会背景によって、熱烈な反幕運動となって日本国中に浸透していくことになる。その否定の論理は過激化し、同時に強烈な保守の抵抗勢力を生み、互いに相容れない対立・分裂の危機を深めていく精神構造を胚胎していた。
家斉時代の反動としての家慶時代は、天保改革で幕を開ける。それは苛烈な緊縮・禁制に終始し、結局は幕府内部の改革には結びつかず挫折する。それほど幕内の既得権益は岩盤だった。そこに登場したのが「逆説の政治家」斉昭。
しかし「賢君」と期待された斉昭は、世間一般では人気が高かったが、その声望にふさわしい内実がともなわない。自らの「尊皇攘夷」が、将軍の人格を否定しその大権を干犯することに気がつかない。幕閣やその中核を成す親藩・譜代の大名たちは、斉昭の空疎なアジテーションを嫌いぬいた。幕政が混迷を深めるその一方で、足元の水戸藩も泥沼の派閥抗争に陥っていく。
こうした「尊皇攘夷」の狂気がもたらす対立・分裂の構造は、何も徳川幕府に限らない。薩長を中心とする外様の国持大名でも同じことになった。幕府も有力外様も、こうした血で血を洗う内部抗争で人材を消耗していく。幕府内の抗争はついに「安政の大獄」を生み、「桜田門外の変」で大局を喪失する。井伊直弼を闇討ちにしたのは水戸藩の脱藩浪士だった。幕府内に残されたのは、政治のリアリズムと実務には長けた人材だけで、大局を動かす人材は消失した。慶喜は斉昭の実子として生まれついたゆえに嫌われ続け、その不運が一生つきまとうことになる。
「攘夷」や「公武合体」を旗印に慶喜の周辺に輪を成した、会津の容保、桑名の定敬の兄弟も水戸徳川家の直系であり、彼らが頼みにした尾張藩慶勝も母方を通じて水戸につながっている。その血は、すなわち、そのまま水戸学「尊皇攘夷」のシンパということになる。こうした御三家、親藩譜代たちも、慶喜の醒めたリアリズムの足かせになるばかりで、結局は、薩摩のマキャベリズムの前に屈することになる。
本当に最後の将軍と言えるのは第14代の家茂だったのかもしれない。吉宗以来の紀伊徳川血統による血の入れ替えを図ったわけだが、何しろ家茂は若すぎた。心身ともに健全で見識もあり世情にも明るい青年政治家で幕閣からの敬愛も深かったが、結局は、その誠実な真情も幕末の政治的混沌には抗しきれない。長州征討の途上で虚しく夭折したのは政治に翻弄され続けた精神的抑圧がもたらした悲劇というしかない。
実際、家茂には「攘夷」論の愚を明瞭に見通す眼力があった。「世界の大勢は、和親を結び互いに富強を図る習いに変わったのに、日本だけは一向に外交に関わらないというのでは『卑怯退縮』であり、国のかたちも威信もかえって立たない」と喝破していた。孝明天皇が、一貫して佐幕の立場を貫いたのはこうした家茂の誠実さだった。孝明天皇は暗愚ではなかったが、あまりに世間知らずで朝廷をめぐる陰謀を統御できなかった。その「攘夷」は、むしろ無知ゆえの「ゼノフォビア(外国人恐怖)」であって、終始、家茂を悩ませた。「攘夷」の狂気がさっぱりと消え失せたのは孝明天皇崩御の瞬間だったいえる。日本国中がようやく冷静を取り戻すことになる。
「大政奉還」を果断に実行したのは慶喜の功績といえるが、「将軍辞職」は何も最後の土壇場に浮上したわけではないという。家茂も深刻に考えていた。表明寸前で幕閣に抵抗されて挫折している。薩摩の武力倒幕論に対して、建白による平和革命を説いたのが土佐藩だった。大政奉還の建白を思いついたのは、高知の漢方医・今井順青だったそうだ。それを坂本龍馬が後藤象二郎に伝え、山内容堂が諒承する。著者は、容堂の律儀さを称賛してやまない。慶喜の名誉は、容堂によって与えられたものであり、滅びゆく武家社会最後の道徳観の発露だったとさえ言う。
とにかく長大な幕末史を語って倦むことがない「下巻」だが、慶喜の時代はそのほんのわずかな紙数に過ぎない。実際、慶喜が将軍職にあったのは1年にわずかに満たない。この間、江戸城にすらも入ったことがない。しかし、一橋慶喜とその行動は家茂時代にはむしろ家茂以上に言及されている。なんといっても徳川幕府終焉をもたらしたのは、水戸の副将軍・斉昭とその子・慶喜だったのだから。
著者によれば、慶喜の犯した取り返しのつかない錯誤は、薩長の挑発に乗って鳥羽伏見の戦端を開いたことだという。薩長の武力倒幕は幕末維新の最大の汚点だが、それは島津久光の病による統制喪失のせいもあったという。せっかくの大政奉還にもかかわらず、慶喜がかえって戦乱を招いたことになっのは不幸なことだったと著者は惜しむ。
いずれにせよ、もはや将軍の世紀は終わっていて、戊辰戦争以後は章外のこととなる。
壮大かつ詳細を究める幕末史として「下巻」だけでも大変に読み応えがあった。
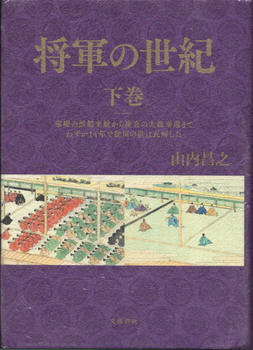
将軍の世紀 下巻
パクス・トクガワナを築いた家康の戦略から遊王・家斉の爛熟まで
山内 昌之 (著)
文藝春秋
2023年4月新刊
今までの幕末維新の歴史観はすべて倒幕側からのもの。本書はあくまでも標題の通りで将軍、すなわち江戸幕府側からの視点で書かれている。そのことが本書の独創的なところで、とても面白い。
下巻を読み通して、つくづく思うのは江戸幕府は内側から自壊したのだということ。滅ぼしたのは徳川御三家。その源泉であり中核となったのが水戸藩の斉昭。その実子である一橋慶喜が「大政奉還」という形で幕を引くことになる。
水戸が伝統的に背負っていたのは、藩主血統の正統性とその自戒から生まれた「水戸学」。その真髄は、儒学的な日本の社会秩序の精神的な権力体系。皇統に絶対的支配の頂点を求める「尊皇」思想のこと。この水戸学を狂信的な「攘夷」と結びつけたのが斉昭だった。
それは、第12代家斉の時代から始まった幕藩体制の弛緩とロシアなどの外国船の度重なる侵犯という社会背景によって、熱烈な反幕運動となって日本国中に浸透していくことになる。その否定の論理は過激化し、同時に強烈な保守の抵抗勢力を生み、互いに相容れない対立・分裂の危機を深めていく精神構造を胚胎していた。
家斉時代の反動としての家慶時代は、天保改革で幕を開ける。それは苛烈な緊縮・禁制に終始し、結局は幕府内部の改革には結びつかず挫折する。それほど幕内の既得権益は岩盤だった。そこに登場したのが「逆説の政治家」斉昭。
しかし「賢君」と期待された斉昭は、世間一般では人気が高かったが、その声望にふさわしい内実がともなわない。自らの「尊皇攘夷」が、将軍の人格を否定しその大権を干犯することに気がつかない。幕閣やその中核を成す親藩・譜代の大名たちは、斉昭の空疎なアジテーションを嫌いぬいた。幕政が混迷を深めるその一方で、足元の水戸藩も泥沼の派閥抗争に陥っていく。
こうした「尊皇攘夷」の狂気がもたらす対立・分裂の構造は、何も徳川幕府に限らない。薩長を中心とする外様の国持大名でも同じことになった。幕府も有力外様も、こうした血で血を洗う内部抗争で人材を消耗していく。幕府内の抗争はついに「安政の大獄」を生み、「桜田門外の変」で大局を喪失する。井伊直弼を闇討ちにしたのは水戸藩の脱藩浪士だった。幕府内に残されたのは、政治のリアリズムと実務には長けた人材だけで、大局を動かす人材は消失した。慶喜は斉昭の実子として生まれついたゆえに嫌われ続け、その不運が一生つきまとうことになる。
「攘夷」や「公武合体」を旗印に慶喜の周辺に輪を成した、会津の容保、桑名の定敬の兄弟も水戸徳川家の直系であり、彼らが頼みにした尾張藩慶勝も母方を通じて水戸につながっている。その血は、すなわち、そのまま水戸学「尊皇攘夷」のシンパということになる。こうした御三家、親藩譜代たちも、慶喜の醒めたリアリズムの足かせになるばかりで、結局は、薩摩のマキャベリズムの前に屈することになる。
本当に最後の将軍と言えるのは第14代の家茂だったのかもしれない。吉宗以来の紀伊徳川血統による血の入れ替えを図ったわけだが、何しろ家茂は若すぎた。心身ともに健全で見識もあり世情にも明るい青年政治家で幕閣からの敬愛も深かったが、結局は、その誠実な真情も幕末の政治的混沌には抗しきれない。長州征討の途上で虚しく夭折したのは政治に翻弄され続けた精神的抑圧がもたらした悲劇というしかない。
実際、家茂には「攘夷」論の愚を明瞭に見通す眼力があった。「世界の大勢は、和親を結び互いに富強を図る習いに変わったのに、日本だけは一向に外交に関わらないというのでは『卑怯退縮』であり、国のかたちも威信もかえって立たない」と喝破していた。孝明天皇が、一貫して佐幕の立場を貫いたのはこうした家茂の誠実さだった。孝明天皇は暗愚ではなかったが、あまりに世間知らずで朝廷をめぐる陰謀を統御できなかった。その「攘夷」は、むしろ無知ゆえの「ゼノフォビア(外国人恐怖)」であって、終始、家茂を悩ませた。「攘夷」の狂気がさっぱりと消え失せたのは孝明天皇崩御の瞬間だったいえる。日本国中がようやく冷静を取り戻すことになる。
「大政奉還」を果断に実行したのは慶喜の功績といえるが、「将軍辞職」は何も最後の土壇場に浮上したわけではないという。家茂も深刻に考えていた。表明寸前で幕閣に抵抗されて挫折している。薩摩の武力倒幕論に対して、建白による平和革命を説いたのが土佐藩だった。大政奉還の建白を思いついたのは、高知の漢方医・今井順青だったそうだ。それを坂本龍馬が後藤象二郎に伝え、山内容堂が諒承する。著者は、容堂の律儀さを称賛してやまない。慶喜の名誉は、容堂によって与えられたものであり、滅びゆく武家社会最後の道徳観の発露だったとさえ言う。
とにかく長大な幕末史を語って倦むことがない「下巻」だが、慶喜の時代はそのほんのわずかな紙数に過ぎない。実際、慶喜が将軍職にあったのは1年にわずかに満たない。この間、江戸城にすらも入ったことがない。しかし、一橋慶喜とその行動は家茂時代にはむしろ家茂以上に言及されている。なんといっても徳川幕府終焉をもたらしたのは、水戸の副将軍・斉昭とその子・慶喜だったのだから。
著者によれば、慶喜の犯した取り返しのつかない錯誤は、薩長の挑発に乗って鳥羽伏見の戦端を開いたことだという。薩長の武力倒幕は幕末維新の最大の汚点だが、それは島津久光の病による統制喪失のせいもあったという。せっかくの大政奉還にもかかわらず、慶喜がかえって戦乱を招いたことになっのは不幸なことだったと著者は惜しむ。
いずれにせよ、もはや将軍の世紀は終わっていて、戊辰戦争以後は章外のこととなる。
壮大かつ詳細を究める幕末史として「下巻」だけでも大変に読み応えがあった。
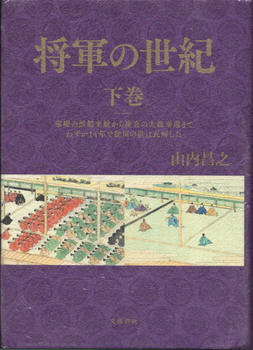
将軍の世紀 下巻
パクス・トクガワナを築いた家康の戦略から遊王・家斉の爛熟まで
山内 昌之 (著)
文藝春秋
2023年4月新刊
「藩邸差配役日日控」(砂原 浩太朗 著)読了 [読書]
連作ものの形を取っていて1章ごとに話しは完結するのですが、全体としては一貫したストーリーがあるので、1章の区切りにほどよい余韻があって、また、次の章が読みたくなる…だから一気読み。楽しかった。
主人公の里村五郎兵衛は、神宮寺藩江戸藩邸差配役を務めている。「なんでも屋」と陰口を言われ、本人も自嘲気味にそれを承知している。藩邸内の雑事や揉め事の対応に振り回される毎日。
サラリーマン的には「総務課」「庶務課」といったところでしょうか。会社の組織規程なんかには、その管掌業務は「その他、他の部署の職掌に属さざること」なんて書いてあったりする。だから訳のわからない仕事を押しつけられやすい。いかにも雑務屋だけれど、組織上は筆頭部署だったりして偉かったりする。経営中枢に最も近く、直接、役員とか社長とかに対面することも多い。
そのちょっと滑稽で皮肉な立場をうまく使って、ユーモラスな場面や人物描写と、時代劇お定まりの派閥対立とか世継ぎをめぐるお家騒動というシリアスなストーリーを、軽重のリズムよく描いていく。読みやすくしかも《侍もの》としての格調もあって、その筆致は絶妙。
主人公の五郎兵衛の飄々としていて動じぬ風格もよいけれど、部下の頭の硬いベテランと軟弱な若侍のやり取りも軽妙で、家にしきりに出入りする亡妻の妹、その叔母を慕う性格の対照的な二人の娘という女性キャラクターもとても魅力的。
最後の最後にどんでん返しを用意しているところも、さすが数々の章を受賞した手練れの時代劇小説作家。でも、このどんでん返しはちょっとやり過ぎかも?
読者としては、シリーズものとして魅力的脇役陣が活躍する続編を期待したいところですが、このどんでん返しのせいでそれが難しくなったかな…?

藩邸差配役日日控
砂原 浩太朗 (著)
文藝春秋社
2023年4月30日初刊
2023年7月20日第三刷
主人公の里村五郎兵衛は、神宮寺藩江戸藩邸差配役を務めている。「なんでも屋」と陰口を言われ、本人も自嘲気味にそれを承知している。藩邸内の雑事や揉め事の対応に振り回される毎日。
サラリーマン的には「総務課」「庶務課」といったところでしょうか。会社の組織規程なんかには、その管掌業務は「その他、他の部署の職掌に属さざること」なんて書いてあったりする。だから訳のわからない仕事を押しつけられやすい。いかにも雑務屋だけれど、組織上は筆頭部署だったりして偉かったりする。経営中枢に最も近く、直接、役員とか社長とかに対面することも多い。
そのちょっと滑稽で皮肉な立場をうまく使って、ユーモラスな場面や人物描写と、時代劇お定まりの派閥対立とか世継ぎをめぐるお家騒動というシリアスなストーリーを、軽重のリズムよく描いていく。読みやすくしかも《侍もの》としての格調もあって、その筆致は絶妙。
主人公の五郎兵衛の飄々としていて動じぬ風格もよいけれど、部下の頭の硬いベテランと軟弱な若侍のやり取りも軽妙で、家にしきりに出入りする亡妻の妹、その叔母を慕う性格の対照的な二人の娘という女性キャラクターもとても魅力的。
最後の最後にどんでん返しを用意しているところも、さすが数々の章を受賞した手練れの時代劇小説作家。でも、このどんでん返しはちょっとやり過ぎかも?
読者としては、シリーズものとして魅力的脇役陣が活躍する続編を期待したいところですが、このどんでん返しのせいでそれが難しくなったかな…?

藩邸差配役日日控
砂原 浩太朗 (著)
文藝春秋社
2023年4月30日初刊
2023年7月20日第三刷
タグ:砂原 浩太朗
「重力のからくり」(山田 克哉 著)読了 [読書]
高校生の頃、こういう科学本が好きでよく読んでいました。
家にあったアイザック・アシモフの相対性理論の入門書とか、リチャード・ファインマンの回顧録『ご冗談でしょう、ファインマンさん』とかがきっかけでした。あの頃は、やっぱりアインシュタインの相対性理論や量子力学の解説本が大流行で各出版社もシリーズものを競っていました。わかった気になって同級生と得意げに話しをしたところで、肝心の物理や数学の成績はさっぱりでした。
その当時から不思議でならなかったのが「重力」のこと。
重さ(重力質量)と慣性質量とは、別物だといいます。それがモノの質量として一致するということ。あのガリレオ・ガリレイがピサの斜塔から二つの球体を落下させた、アレです。それは等価原理と呼ばれますが、あくまで「原理」であってなぜ一致するのかは、結局は説明できないそうです。
その「原理」を原理であるということから生まれたのがアインシュタインの一般相対性理論なんだとか。ははあ?そうだったのかと今さらながら知りました。
しかしながらほぼ同時代に登場したのが量子論の世界です。
こちらは様々な面で、万有引力とは違うものでした。まず、ごくごく弱い力の万有引力と違って電磁力や素粒子相互の力は強い。万有引力は互いに引き合う力だけですが、電磁力や素粒子相互の力は、引力も排斥力もある対称性の世界です。こうした量子論の世界も、ニュートンの動力学に続けて丁寧に説明してくれます。
その行き着くところは、「相対論」と「量子論」を統一的に説明ができる理論があるのか?ということ。今のところはまったく解決の途が開けない。それでも科学者はそういう未知の世界に挑み続けているというわけです。
なぜ相容れないのか??
それは、「相対論」は連続の世界であり、極小のゼロを想定しているのに対して、「量子論」は不連続の世界であり、極小には値があってゼロではないからです。そのことを示したのがハイゼンベルクの「不確定性原理」。それは素粒子的微小の世界では、「位置」と「運動量」が互いに対になっていること。同様に「エネルギー」と「時間」も対になっている。一方を正確に測定しようとすればするほど、もう一方の値はあやふやで不正確になってしまう。それはミクロの世界では「粒子と波動との二重性」が存在するからです。そういう対のものの「あやふやさ」の幅の積は、極めてゼロに近いながら一定の値を持っているということになります。
まあ、個人的な勝手な例えですが、アナログとデジタルとの対立みたいなものです。オーディオマニアの間には、アナログ派とデジタル派が二分していて双方の主張はなかなか相容れません。…そういうことかな?(笑)
読んでみて、また相対性理論とか量子力学のことを知り直してみたいと思いました。著者は、このブルーバックスにいくつもの著書があります。『読者に必ず理解してもらう』という意欲にあふれた熱い筆致で人気の著者のひとりなのだとか。他の著書も読んでみたくなりました。

重力のからくり
相対論と量子論はなぜ「相容れない」のか
山田 克哉 (著)
ブルーバックス
講談社
2023年8月20日 初版
家にあったアイザック・アシモフの相対性理論の入門書とか、リチャード・ファインマンの回顧録『ご冗談でしょう、ファインマンさん』とかがきっかけでした。あの頃は、やっぱりアインシュタインの相対性理論や量子力学の解説本が大流行で各出版社もシリーズものを競っていました。わかった気になって同級生と得意げに話しをしたところで、肝心の物理や数学の成績はさっぱりでした。
その当時から不思議でならなかったのが「重力」のこと。
重さ(重力質量)と慣性質量とは、別物だといいます。それがモノの質量として一致するということ。あのガリレオ・ガリレイがピサの斜塔から二つの球体を落下させた、アレです。それは等価原理と呼ばれますが、あくまで「原理」であってなぜ一致するのかは、結局は説明できないそうです。
その「原理」を原理であるということから生まれたのがアインシュタインの一般相対性理論なんだとか。ははあ?そうだったのかと今さらながら知りました。
しかしながらほぼ同時代に登場したのが量子論の世界です。
こちらは様々な面で、万有引力とは違うものでした。まず、ごくごく弱い力の万有引力と違って電磁力や素粒子相互の力は強い。万有引力は互いに引き合う力だけですが、電磁力や素粒子相互の力は、引力も排斥力もある対称性の世界です。こうした量子論の世界も、ニュートンの動力学に続けて丁寧に説明してくれます。
その行き着くところは、「相対論」と「量子論」を統一的に説明ができる理論があるのか?ということ。今のところはまったく解決の途が開けない。それでも科学者はそういう未知の世界に挑み続けているというわけです。
なぜ相容れないのか??
それは、「相対論」は連続の世界であり、極小のゼロを想定しているのに対して、「量子論」は不連続の世界であり、極小には値があってゼロではないからです。そのことを示したのがハイゼンベルクの「不確定性原理」。それは素粒子的微小の世界では、「位置」と「運動量」が互いに対になっていること。同様に「エネルギー」と「時間」も対になっている。一方を正確に測定しようとすればするほど、もう一方の値はあやふやで不正確になってしまう。それはミクロの世界では「粒子と波動との二重性」が存在するからです。そういう対のものの「あやふやさ」の幅の積は、極めてゼロに近いながら一定の値を持っているということになります。
まあ、個人的な勝手な例えですが、アナログとデジタルとの対立みたいなものです。オーディオマニアの間には、アナログ派とデジタル派が二分していて双方の主張はなかなか相容れません。…そういうことかな?(笑)
読んでみて、また相対性理論とか量子力学のことを知り直してみたいと思いました。著者は、このブルーバックスにいくつもの著書があります。『読者に必ず理解してもらう』という意欲にあふれた熱い筆致で人気の著者のひとりなのだとか。他の著書も読んでみたくなりました。

重力のからくり
相対論と量子論はなぜ「相容れない」のか
山田 克哉 (著)
ブルーバックス
講談社
2023年8月20日 初版
「二十世紀のクラシック音楽を取り戻す」(ジョン・マウチェリ 著)読了 [読書]
私たちクラシック音楽ファンは、21世紀の今を生きています。
ところが聴いている音楽のほとんどが19世紀以前の音楽です。クラシック音楽というのはそういうものなのでしょうか?20世紀のある時点で、巨大隕石の落下で突然滅んだ恐竜のように、クラシック音楽の伝統は途絶えてしまったのでしょうか?
1999年、20世紀最後の年、アバドが指揮するベルリン・フィルのニューイヤーズイヴ・コンサートでは、1911年以降に書かれた曲はいっさい取り上げられませんでした。
本書は、20世紀にクラシック音楽と呼ばれるヨーロッパ正統音楽に何が起こったのか?、なぜそれは消滅したのか?という謎を解き明かし、改めてこの世紀の正統音楽――いわゆる「現代音楽」と呼ばれる音楽――の探索へと私たちを誘ってくれます。
その大きなカギとなるのは世界中を巻き込んだ二つの大戦のことです。
ナチスドイツが席巻したヨーロッパから幾多の将来を嘱望されていた音楽家が命を落とし、国を追われました。そのほとんどがユダヤ系の人々だった。国を失ったそうした音楽家のほとんどがアメリカへ逃れ、そこで余生を送った。
そういうことは今までも言われてきました。著者は、戦争はそこで終わっていないといいます。「冷戦」の勃発のことです。東西対立のなかで、音楽は国家の威信をかけた政治の道具と化したのです。
冷戦によって、欧米各国を東西に二分して対立した。スターリンの国家は、ナチと同じようにいわゆる「前衛音楽」を退廃音楽として嫌い弾圧し続けました。ソ連で奨励されたのは調性音楽で、大衆に理解しやすい聴きやすい音楽。一方で、これに対立するように西側の欧米各国では前衛音楽ばかりが生き残った。ファシズムに与しなかったという免罪符も手にしていた前衛音楽家たちは、本来の反体制・反主流から、一転して体制お墨付きの主流となって音楽界に君臨し、調性音楽を旧体制の反動的芸術として排撃する。ミラノのスカラ座の演目からは、ムッソリーニが政権掌握した1921年以後のイタリアオペラ作品は抹消されてしまいました。ファシズム時代の直前に病死して、そういう災禍を免れたプッチーニの絶筆「トゥランドット」以後の作品は再演されることがないのです。
こうして西側では大衆の支持を得ない「前衛」ばかりがはびこって廃品の山を築く。
20世紀の音楽史として、もうひとつの画期的な事件は、トーキー映画が誕生し巨大産業へと成長していったことです。
ウィーン楽界で神童ともてはやされたコルンゴルトは、ナチのオーストリー併合によりアメリカに逃れます。彼は、その後、ハリウッドで映画音楽の創生と輝かしい発展に貢献しますが、正統音楽からは抹殺されてしまう。実は、ハリウウドの映画音楽界こそ、シェーンベルクやヒンデミットなどを師と仰ぐ俊才たちの活躍の場となったのです。
劇中の人物や事象を象徴するライトモチーフ、劇中の人物の動作や表情と同期する音楽が、劇の進行に伴って際限なく続いていく。――そういう音楽こそがワーグナーの楽劇の本質であって、それを受け継いだのがコルンゴルトであり、ハリウッドの俊英たちだった。それを正統の「現代音楽」と認めず、無視したのは東西対立の政治的芸術観であり、ファシズム時代を生き抜いた「前衛音楽家」や気位の高い批評家たちだったというわけです。
二十世紀最後のニューイヤーズイヴから23年の時を経た、2022年のコンサートを指揮したのは、キリル・ペトレンコ。ゲストは人気絶頂のテノール、ヨナス・カウフマンでした。そこで演奏されたのは、映画音楽の大家ニーノ・ロータ。映画「道」をもとにした組曲の演奏に続いて、カウフマンは映画「ゴッドファーザー」の「愛のテーマ」をイタリア語で絶唱しました。
ウィーン・フィルも、90歳を超えた大家ジョン・ウィリアムズを迎えて「スターウォーズ」からの名曲コンサートで大いに盛り上がっています。クラシック音楽正統の「現代音楽」は、著者のいう通りにその失地を回復しつつあるのです。
本書で標的になっているの「前衛の旗手」ピエール・ブーレーズだけではありません。え?と驚くような暴言・失言もいろいろ暴露されていてちょっと危ないところもありますが、クラシック音楽通にとってはたまらないエピソードも満載。
音楽ファンにはぜひ読んでもらいたい一冊です。
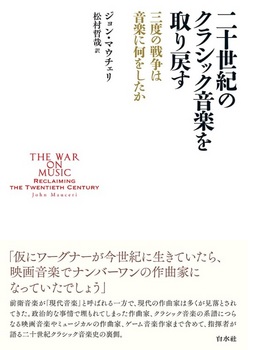
二十世紀のクラシック音楽を取り戻す
三度の戦争は音楽に何をしたか
ジョン・マウチェリ (著), 松村 哲哉 (翻訳)
白水社
2023/8/10 初刊
原題:The War on Music: Reclaiming the Twentieth Century
ところが聴いている音楽のほとんどが19世紀以前の音楽です。クラシック音楽というのはそういうものなのでしょうか?20世紀のある時点で、巨大隕石の落下で突然滅んだ恐竜のように、クラシック音楽の伝統は途絶えてしまったのでしょうか?
1999年、20世紀最後の年、アバドが指揮するベルリン・フィルのニューイヤーズイヴ・コンサートでは、1911年以降に書かれた曲はいっさい取り上げられませんでした。
本書は、20世紀にクラシック音楽と呼ばれるヨーロッパ正統音楽に何が起こったのか?、なぜそれは消滅したのか?という謎を解き明かし、改めてこの世紀の正統音楽――いわゆる「現代音楽」と呼ばれる音楽――の探索へと私たちを誘ってくれます。
その大きなカギとなるのは世界中を巻き込んだ二つの大戦のことです。
ナチスドイツが席巻したヨーロッパから幾多の将来を嘱望されていた音楽家が命を落とし、国を追われました。そのほとんどがユダヤ系の人々だった。国を失ったそうした音楽家のほとんどがアメリカへ逃れ、そこで余生を送った。
そういうことは今までも言われてきました。著者は、戦争はそこで終わっていないといいます。「冷戦」の勃発のことです。東西対立のなかで、音楽は国家の威信をかけた政治の道具と化したのです。
冷戦によって、欧米各国を東西に二分して対立した。スターリンの国家は、ナチと同じようにいわゆる「前衛音楽」を退廃音楽として嫌い弾圧し続けました。ソ連で奨励されたのは調性音楽で、大衆に理解しやすい聴きやすい音楽。一方で、これに対立するように西側の欧米各国では前衛音楽ばかりが生き残った。ファシズムに与しなかったという免罪符も手にしていた前衛音楽家たちは、本来の反体制・反主流から、一転して体制お墨付きの主流となって音楽界に君臨し、調性音楽を旧体制の反動的芸術として排撃する。ミラノのスカラ座の演目からは、ムッソリーニが政権掌握した1921年以後のイタリアオペラ作品は抹消されてしまいました。ファシズム時代の直前に病死して、そういう災禍を免れたプッチーニの絶筆「トゥランドット」以後の作品は再演されることがないのです。
こうして西側では大衆の支持を得ない「前衛」ばかりがはびこって廃品の山を築く。
20世紀の音楽史として、もうひとつの画期的な事件は、トーキー映画が誕生し巨大産業へと成長していったことです。
ウィーン楽界で神童ともてはやされたコルンゴルトは、ナチのオーストリー併合によりアメリカに逃れます。彼は、その後、ハリウッドで映画音楽の創生と輝かしい発展に貢献しますが、正統音楽からは抹殺されてしまう。実は、ハリウウドの映画音楽界こそ、シェーンベルクやヒンデミットなどを師と仰ぐ俊才たちの活躍の場となったのです。
劇中の人物や事象を象徴するライトモチーフ、劇中の人物の動作や表情と同期する音楽が、劇の進行に伴って際限なく続いていく。――そういう音楽こそがワーグナーの楽劇の本質であって、それを受け継いだのがコルンゴルトであり、ハリウッドの俊英たちだった。それを正統の「現代音楽」と認めず、無視したのは東西対立の政治的芸術観であり、ファシズム時代を生き抜いた「前衛音楽家」や気位の高い批評家たちだったというわけです。
二十世紀最後のニューイヤーズイヴから23年の時を経た、2022年のコンサートを指揮したのは、キリル・ペトレンコ。ゲストは人気絶頂のテノール、ヨナス・カウフマンでした。そこで演奏されたのは、映画音楽の大家ニーノ・ロータ。映画「道」をもとにした組曲の演奏に続いて、カウフマンは映画「ゴッドファーザー」の「愛のテーマ」をイタリア語で絶唱しました。
ウィーン・フィルも、90歳を超えた大家ジョン・ウィリアムズを迎えて「スターウォーズ」からの名曲コンサートで大いに盛り上がっています。クラシック音楽正統の「現代音楽」は、著者のいう通りにその失地を回復しつつあるのです。
本書で標的になっているの「前衛の旗手」ピエール・ブーレーズだけではありません。え?と驚くような暴言・失言もいろいろ暴露されていてちょっと危ないところもありますが、クラシック音楽通にとってはたまらないエピソードも満載。
音楽ファンにはぜひ読んでもらいたい一冊です。
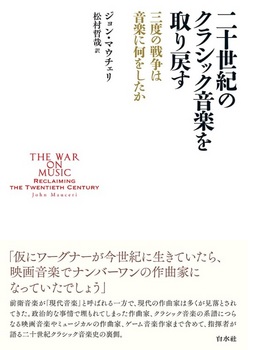
二十世紀のクラシック音楽を取り戻す
三度の戦争は音楽に何をしたか
ジョン・マウチェリ (著), 松村 哲哉 (翻訳)
白水社
2023/8/10 初刊
原題:The War on Music: Reclaiming the Twentieth Century
タグ:現代音楽
「パシヨン」(川越 宗一 著)読了 [読書]
日本の最後のキリシタン司祭であったマンショ小西が主人公。
マンショは、小西マリアの子。母のマリアは、キリシタン大名として知られる小西行長の娘。行長が関ヶ原の戦いで石田三成の盟友として西軍の主力を担ったことから斬首、対馬藩主・宗義智に嫁いでいたマリアも離縁された。その子マンショは長崎で育つ。
慶長19年(1614年)のキリシタン追放令でマカオに追放された後、ゴアに渡るが、受け入れられず、海路アフリカ喜望峰を経てポルトガルに到着。現地で学んだ後、ローマへ渡り、元和10年(1624年)イエズス会に入会、寛永4年(1627年)司祭の位を得た。寛永9年(1632年)に日本に帰国し、畿内で布教活動を行った。正保元年(1644年)に捕縛処刑され殉教した。
かつては「隠れキリシタン」と呼んでいたが、近年は「潜伏キリシタン」という呼び方をすることが多い。
「潜伏キリシタン」とは、キリスト教を棄却したと見せかけた人々のことをいう。この小説は、遠藤周作の「沈黙」に代表されるように悲惨な宗教迫害と転向の挫折を描いたものではない。遠藤の「沈黙」でも賛否が大きかった「転び」の心中にある信仰の真実といった深遠さよりも、心中に信仰を秘めることにこそ“自由”があると正面きって謳い、信教の自由と唱えている。
とはいえ、弾圧を省みずに祖国のクリスチャンのために帰国した勇気あふれるマンショ、あるいは、飄然としていて深刻ぶらない、『夕刻に家に帰る子どものよう』に平然と帰国したマンショという人物像を描こうとして成功したとは言えないと思う。
描かれたマンショ像は、どうにも軽く浅く、その口調や性格描写が平俗に過ぎる。過酷で悲惨な迫害にあって受難し、あるいは棄教という大きな挫折を味わった歴史上の人々を描くには、その筆致があまりに卑俗で厚みに欠ける。むしろ、小身から惣目付にまで出世し、宗門改役として幕府のキリシタン禁教政策の中心人物となった井上政重の人物像にかえって新鮮さを感じた。いわば真っ向からの敵役なのだが、その信条の矛盾と懊悩には小説としてのリアリティがある。
それにしても、フィクションの虚構のなかに、あまりの多くの史実や歴史上の人物を登場させ過ぎる。あえて旅行会社の「キリシタン」ツアーの企画に例えれば、天草・島原から長崎まで、まんべんなく足早に手軽な価格で一巡りするバスツアーというところだろうか。

パシヨン
Passion
川越 宗一 著
PHP研究所
2023年7月7日 初刊
マンショは、小西マリアの子。母のマリアは、キリシタン大名として知られる小西行長の娘。行長が関ヶ原の戦いで石田三成の盟友として西軍の主力を担ったことから斬首、対馬藩主・宗義智に嫁いでいたマリアも離縁された。その子マンショは長崎で育つ。
慶長19年(1614年)のキリシタン追放令でマカオに追放された後、ゴアに渡るが、受け入れられず、海路アフリカ喜望峰を経てポルトガルに到着。現地で学んだ後、ローマへ渡り、元和10年(1624年)イエズス会に入会、寛永4年(1627年)司祭の位を得た。寛永9年(1632年)に日本に帰国し、畿内で布教活動を行った。正保元年(1644年)に捕縛処刑され殉教した。
かつては「隠れキリシタン」と呼んでいたが、近年は「潜伏キリシタン」という呼び方をすることが多い。
「潜伏キリシタン」とは、キリスト教を棄却したと見せかけた人々のことをいう。この小説は、遠藤周作の「沈黙」に代表されるように悲惨な宗教迫害と転向の挫折を描いたものではない。遠藤の「沈黙」でも賛否が大きかった「転び」の心中にある信仰の真実といった深遠さよりも、心中に信仰を秘めることにこそ“自由”があると正面きって謳い、信教の自由と唱えている。
とはいえ、弾圧を省みずに祖国のクリスチャンのために帰国した勇気あふれるマンショ、あるいは、飄然としていて深刻ぶらない、『夕刻に家に帰る子どものよう』に平然と帰国したマンショという人物像を描こうとして成功したとは言えないと思う。
描かれたマンショ像は、どうにも軽く浅く、その口調や性格描写が平俗に過ぎる。過酷で悲惨な迫害にあって受難し、あるいは棄教という大きな挫折を味わった歴史上の人々を描くには、その筆致があまりに卑俗で厚みに欠ける。むしろ、小身から惣目付にまで出世し、宗門改役として幕府のキリシタン禁教政策の中心人物となった井上政重の人物像にかえって新鮮さを感じた。いわば真っ向からの敵役なのだが、その信条の矛盾と懊悩には小説としてのリアリティがある。
それにしても、フィクションの虚構のなかに、あまりの多くの史実や歴史上の人物を登場させ過ぎる。あえて旅行会社の「キリシタン」ツアーの企画に例えれば、天草・島原から長崎まで、まんべんなく足早に手軽な価格で一巡りするバスツアーというところだろうか。

パシヨン
Passion
川越 宗一 著
PHP研究所
2023年7月7日 初刊
タグ:川越 宗一



