KEIRIN(ジャスティン・マッカリー 著)読了 [読書]
在日30年の英国人記者による、競輪をテーマにした日本文化論。
まずもって、競輪は、競艇・競馬・オートレースと並ぶ公営ギャンブルの一角をなす。自転車競技のトラックレースに《ケイリン》があるので紛らわしいが、《競輪》は断じてスポーツではない。
その一方で、ギャンブルのなかでは、唯一、身体的能力を競い肉体と肉体が闘う競技であり異色の魅力を持つことも事実。《ケイリン》は、別物であっても《競輪》をもとにしたトラック競技であり、そのきっかけは競輪のレジェンド中野浩一が世界選手権スプリントで10連覇を成し遂げたことがきっかけになったことも事実。
その競輪は、戦後まもない日本の地方財政を助け、戦災復興や公共施設の建設などに貢献した。自転車競技法という法に基づいていて、主催者は地方自治体。。監督官庁は経済産業省で、運営統括は公益財団法人JKAという経産官僚の天下り先。『公営ギャンブル』たるゆえんである。
ルールは、硬直的でいまだに旧態依然としたまま。八百長などの不正防止のために選手は缶詰状態に置かれ、プロ資格取得のための養成所では軍隊か刑務所のような管理と精神教育が行われる。車体も相も変わらぬ鉄製(クロームモリブデン鋼)のフレームが使用されるのは、JKAが定める規格が厳格で固定的だからだ。競技の駆け引きには「ライン」と呼ばれる出身地方毎のグループや先輩後輩などの年齢序列の世界が強く存在する。そのために、あたかも時が止まったようで昭和の香りがぷんぷんと漂う。
競輪というものの実相や、魅力、歴史、社会的な課題や将来性なには、語り尽くせないものがある。著者は「ガーディアン」の日本駐在特派員というジャーナリストであるだけにその取材は広範囲であり膨大な資料探索とインタビューを積み上げているのはさすが。けれども、散漫な記述は何が言いたいのか、何を伝えたいのかがわからない。
一方で、ロンドン大学の日本研究の修士卒というインテリだけに、文化比較論的な日本紹介書になっている。むしろ、競輪の啓蒙書というよりは、競輪という日本独特のギャンブルをネタに外国人の日本異文化論をくすぐるガイジンによるガイジンのための書。だから、日本人がまともに読もうとすると冗長で持って回った表現が鼻につき、視点が散漫でいったい何が言いたいのかわからなくなる。競輪の後進性や閉鎖性を、日本文化論に転化されてはたまらない。
訳文は、そういう原文に忠実なのだろうが、英国人が書いた日本紹介を日本人向けに翻訳するのならもっと工夫があってしかるべきだったのではないだろうか。原著者が日本にいるのだから、思い切ったゴーストライター的な書き下ろしがあってもよかったような気がする。
競輪を知ろうという人には隔靴掻痒だし、ある程度競輪を知った人にはもどかしい。
ジャーナリスティックな取材記事としてはさすがと思わせるところも多い。拾い読みするとすれば、中野浩一へのインタビューやフレームビルダーの話しなど部分的にはたまらなく面白いところもある。
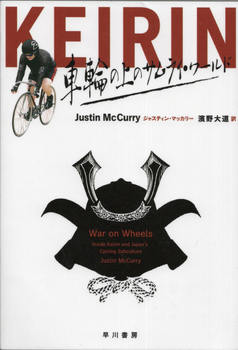
KEIRIN
車輪の上のサムライ・ワールド
ジャスティン・マッカリー (著)
濱野 大道 (翻訳)
早川書房
2023/7/19 新刊
まずもって、競輪は、競艇・競馬・オートレースと並ぶ公営ギャンブルの一角をなす。自転車競技のトラックレースに《ケイリン》があるので紛らわしいが、《競輪》は断じてスポーツではない。
その一方で、ギャンブルのなかでは、唯一、身体的能力を競い肉体と肉体が闘う競技であり異色の魅力を持つことも事実。《ケイリン》は、別物であっても《競輪》をもとにしたトラック競技であり、そのきっかけは競輪のレジェンド中野浩一が世界選手権スプリントで10連覇を成し遂げたことがきっかけになったことも事実。
その競輪は、戦後まもない日本の地方財政を助け、戦災復興や公共施設の建設などに貢献した。自転車競技法という法に基づいていて、主催者は地方自治体。。監督官庁は経済産業省で、運営統括は公益財団法人JKAという経産官僚の天下り先。『公営ギャンブル』たるゆえんである。
ルールは、硬直的でいまだに旧態依然としたまま。八百長などの不正防止のために選手は缶詰状態に置かれ、プロ資格取得のための養成所では軍隊か刑務所のような管理と精神教育が行われる。車体も相も変わらぬ鉄製(クロームモリブデン鋼)のフレームが使用されるのは、JKAが定める規格が厳格で固定的だからだ。競技の駆け引きには「ライン」と呼ばれる出身地方毎のグループや先輩後輩などの年齢序列の世界が強く存在する。そのために、あたかも時が止まったようで昭和の香りがぷんぷんと漂う。
競輪というものの実相や、魅力、歴史、社会的な課題や将来性なには、語り尽くせないものがある。著者は「ガーディアン」の日本駐在特派員というジャーナリストであるだけにその取材は広範囲であり膨大な資料探索とインタビューを積み上げているのはさすが。けれども、散漫な記述は何が言いたいのか、何を伝えたいのかがわからない。
一方で、ロンドン大学の日本研究の修士卒というインテリだけに、文化比較論的な日本紹介書になっている。むしろ、競輪の啓蒙書というよりは、競輪という日本独特のギャンブルをネタに外国人の日本異文化論をくすぐるガイジンによるガイジンのための書。だから、日本人がまともに読もうとすると冗長で持って回った表現が鼻につき、視点が散漫でいったい何が言いたいのかわからなくなる。競輪の後進性や閉鎖性を、日本文化論に転化されてはたまらない。
訳文は、そういう原文に忠実なのだろうが、英国人が書いた日本紹介を日本人向けに翻訳するのならもっと工夫があってしかるべきだったのではないだろうか。原著者が日本にいるのだから、思い切ったゴーストライター的な書き下ろしがあってもよかったような気がする。
競輪を知ろうという人には隔靴掻痒だし、ある程度競輪を知った人にはもどかしい。
ジャーナリスティックな取材記事としてはさすがと思わせるところも多い。拾い読みするとすれば、中野浩一へのインタビューやフレームビルダーの話しなど部分的にはたまらなく面白いところもある。
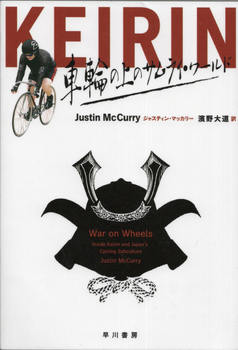
KEIRIN
車輪の上のサムライ・ワールド
ジャスティン・マッカリー (著)
濱野 大道 (翻訳)
早川書房
2023/7/19 新刊
「沈黙の勇者たち」(岡 典子 著)読了 [読書]
ナチス政権下、ユダヤ人差別はやがて迫害へ、そしてそれは大量殺戮のホロコーストへと極限化していった。
第二次世界大戦勃発の1939年当時までに数十万人のユダヤ人がドイツ国外に逃れたが、41年にユダヤ人国外移住が禁止された時点で約17万人のユダヤ人がドイツ国内に取り残された。彼らは片っ端から摘発されてドイツ占領地の強制収容所へと送り込まれた。
しかし、移送を逃れた1万~1万2千人が潜伏した。
こうした潜伏した1万人のうち、およそ5千人が生き延びて終戦を迎えることとなる。あの苛烈を極めたユダヤ人狩りのなかで約半分が生き残ったというのは驚異的だ。そういうユダヤ人を救おうと手を差し伸べた名も無きドイツ市民は、今なお不明だが、最近の研究によると2万人以上にのぼると言われているそうだ。
「沈黙の勇者」たちは、その多くがごく平凡な「普通の人びと」だった。
男性も女性もいて、職業もさまざま。医師、教師、聖職者、労働者、農夫、主婦も娼婦もいた。老人も青年も子どももいたし、障害者や末期のがん患者もいたという。圧倒的多数のドイツ国民がユダヤ人迫害に加担し、死の強制収容所へ移送されるのを「見て見ぬふり」をしていた時代であり、ナチスが奨励した密告により、隣人ばかりか身内や家族までに裏切られるような社会のなかで、彼らは自身や家族を危険にさらされてまで、ユダヤ人を匿い、逃避行を助け、違法な身分証明書偽造に手を出した。
こうした「沈黙の勇者たち」は、近年まで知られることがなかった。
長い間、ホロコーストはナチスが独裁政治のなかで秘密裡に遂行した政策であり、多くの国民は知らなかったとされていた。「国民は知らなかった」とすることで、責任をすべてナチスに負わせて一般市民の免責をはかる戦後の総括が進められてきたからだ。多くの一般市民がユダヤ人救援に関与したと認めることは、市民は知らなかった、ナチスに欺されていた、という前提を覆すことにもなる。
一方で、ユダヤ人の側もまた多くを語りたがらなかったという。
あまりに凄絶で重すぎる体験だったからである。自分だけが生き延びたことへの負い目もあった。救われたユダヤ人の生々しい体験が語られるということは、見て見ぬふりをした市民や密告者の告発でもあり、いつまでも過去にとらわれ、自分たちを繰り返し非難し続ける不快な話題だと感じさせるからだ。
こうした体験証言は、多岐にわたる。ほんの人間的な同情心から怯えながら手を貸した事例もあるし、深い信仰心や反ナチの確信を貫こうとした人々もあれば、潜伏者も巻き込んだ大がかりな証明書偽造組織まであって、多種多様に及ぶ。
本書は、近年の成果である膨大な資料から、何人かの潜伏者の体験を取り上げて、そういう名も無き市民たちの実相をドラマチックに語っている。
ページをめくる手が止まらず一気読みした。
終戦の数ヶ月前に摘発された身内の自白から瓦解した偽造組織や、わずか二ヶ月前に偶然鉢合わせになった旧知のドイツ人友人の密告により捕らえられた若者、それを見過ごせないと自首した姉の話しなど、涙無くしては字を追うことができない。
分断と経済格差の拡大、ポピュリズムの勢力拡大、同調圧力を強めるネット社会、難民・移民、テロと戦争…そういうさまざまな問題に直面している現代社会。そのなかで、この「市民的勇気」の原像が問いかけることは様々だ。
多くの人に読んで欲しい名著だと思う。

沈黙の勇者たち
ユダヤ人を救ったドイツ市民の戦い
岡 典子 著
新潮選書
第二次世界大戦勃発の1939年当時までに数十万人のユダヤ人がドイツ国外に逃れたが、41年にユダヤ人国外移住が禁止された時点で約17万人のユダヤ人がドイツ国内に取り残された。彼らは片っ端から摘発されてドイツ占領地の強制収容所へと送り込まれた。
しかし、移送を逃れた1万~1万2千人が潜伏した。
こうした潜伏した1万人のうち、およそ5千人が生き延びて終戦を迎えることとなる。あの苛烈を極めたユダヤ人狩りのなかで約半分が生き残ったというのは驚異的だ。そういうユダヤ人を救おうと手を差し伸べた名も無きドイツ市民は、今なお不明だが、最近の研究によると2万人以上にのぼると言われているそうだ。
「沈黙の勇者」たちは、その多くがごく平凡な「普通の人びと」だった。
男性も女性もいて、職業もさまざま。医師、教師、聖職者、労働者、農夫、主婦も娼婦もいた。老人も青年も子どももいたし、障害者や末期のがん患者もいたという。圧倒的多数のドイツ国民がユダヤ人迫害に加担し、死の強制収容所へ移送されるのを「見て見ぬふり」をしていた時代であり、ナチスが奨励した密告により、隣人ばかりか身内や家族までに裏切られるような社会のなかで、彼らは自身や家族を危険にさらされてまで、ユダヤ人を匿い、逃避行を助け、違法な身分証明書偽造に手を出した。
こうした「沈黙の勇者たち」は、近年まで知られることがなかった。
長い間、ホロコーストはナチスが独裁政治のなかで秘密裡に遂行した政策であり、多くの国民は知らなかったとされていた。「国民は知らなかった」とすることで、責任をすべてナチスに負わせて一般市民の免責をはかる戦後の総括が進められてきたからだ。多くの一般市民がユダヤ人救援に関与したと認めることは、市民は知らなかった、ナチスに欺されていた、という前提を覆すことにもなる。
一方で、ユダヤ人の側もまた多くを語りたがらなかったという。
あまりに凄絶で重すぎる体験だったからである。自分だけが生き延びたことへの負い目もあった。救われたユダヤ人の生々しい体験が語られるということは、見て見ぬふりをした市民や密告者の告発でもあり、いつまでも過去にとらわれ、自分たちを繰り返し非難し続ける不快な話題だと感じさせるからだ。
こうした体験証言は、多岐にわたる。ほんの人間的な同情心から怯えながら手を貸した事例もあるし、深い信仰心や反ナチの確信を貫こうとした人々もあれば、潜伏者も巻き込んだ大がかりな証明書偽造組織まであって、多種多様に及ぶ。
本書は、近年の成果である膨大な資料から、何人かの潜伏者の体験を取り上げて、そういう名も無き市民たちの実相をドラマチックに語っている。
ページをめくる手が止まらず一気読みした。
終戦の数ヶ月前に摘発された身内の自白から瓦解した偽造組織や、わずか二ヶ月前に偶然鉢合わせになった旧知のドイツ人友人の密告により捕らえられた若者、それを見過ごせないと自首した姉の話しなど、涙無くしては字を追うことができない。
分断と経済格差の拡大、ポピュリズムの勢力拡大、同調圧力を強めるネット社会、難民・移民、テロと戦争…そういうさまざまな問題に直面している現代社会。そのなかで、この「市民的勇気」の原像が問いかけることは様々だ。
多くの人に読んで欲しい名著だと思う。

沈黙の勇者たち
ユダヤ人を救ったドイツ市民の戦い
岡 典子 著
新潮選書
タグ:ホロコースト
「亡霊の地」(陳 思宏 著)読了 [読書]
著者の陳思宏は、台湾でいま最も注目される若手作家。
著者自身が生まれ育った永靖郷を舞台とした大家族の物語。主人公・陳天宏は陳家の末っ子で、五人の姉とその末に生まれた兄弟。著者も9人姉弟の末っ子で、ベルリン在住、同性愛者であることを告知しているから、自伝小説ではないとしても自分の故郷と自分の生い立ちをモデルとしていることは間違いない。

同性愛者として故郷を追われ、台北で作家として成功するも、そうした抑圧を逃れるためにベルリンで暮らす。そこで出会ったパートナーとの暮らしは貧しく、糊口を凌ぐためにネオナチに参加したパートナーとの間が次第に捻れていき、彼を殺してしまう。刑期を終え、生まれ育った永靖に十数年ぶりに帰郷する。折しも死者の亡霊を祀る中元節。弟が戻ってきたとの知らせに陳家の姉たちが集まってくる。
物語は、天宏の母親、五人の姉、兄、そして今は亡き父親の幽霊のそれぞれが、今現在と過去の記憶とをない交ぜながら語られていく。
視点の主体と時制とが交錯しながら読み進むのは、まるでフォークナーを読むようで難渋する。しかも、80年代の台湾の片田舎の狭い地域社会と大家族のなかでの確執、社会の後進性、密接な人間関係だからこその激烈で理不尽な暴力や暴言、虐待は、息苦しいほどに重い。
だから、なかなか読み進むことができない。
まるで、それはジグソーパズルの小さなピースをはめていく作業に似ている。
現時点という、薄い映像が映し出される台紙の上に、主体も時制も雑多な細かなピースを乗せていく。その作業は、最初はあまりに漠然としていてしかもそれぞれの断片が余りに重く醜悪なので難渋する。
ところが、ピースが少しずつつながり、全体の映像が確かなものとなって徐々に立ち現れてくる。最後には、謎解きがかなったようなカタルシスが訪れる。それは、家族や故郷との何とも言い難い和解ともいうべき終結だ。
最後の最後の失われていたピースがぴたりとはまったその瞬間の衝撃、は言い知れぬほどに大きい。
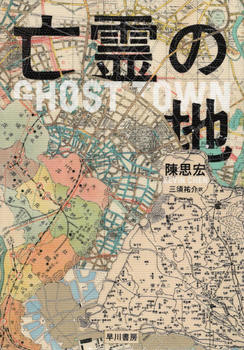
亡霊の地
陳 思宏(Kevin Chen)
三須 祐介 (翻訳)
早川書房
2023年5月23日 新刊
英訳
鬼地方(GHOST TOWN)
著者自身が生まれ育った永靖郷を舞台とした大家族の物語。主人公・陳天宏は陳家の末っ子で、五人の姉とその末に生まれた兄弟。著者も9人姉弟の末っ子で、ベルリン在住、同性愛者であることを告知しているから、自伝小説ではないとしても自分の故郷と自分の生い立ちをモデルとしていることは間違いない。

同性愛者として故郷を追われ、台北で作家として成功するも、そうした抑圧を逃れるためにベルリンで暮らす。そこで出会ったパートナーとの暮らしは貧しく、糊口を凌ぐためにネオナチに参加したパートナーとの間が次第に捻れていき、彼を殺してしまう。刑期を終え、生まれ育った永靖に十数年ぶりに帰郷する。折しも死者の亡霊を祀る中元節。弟が戻ってきたとの知らせに陳家の姉たちが集まってくる。
物語は、天宏の母親、五人の姉、兄、そして今は亡き父親の幽霊のそれぞれが、今現在と過去の記憶とをない交ぜながら語られていく。
視点の主体と時制とが交錯しながら読み進むのは、まるでフォークナーを読むようで難渋する。しかも、80年代の台湾の片田舎の狭い地域社会と大家族のなかでの確執、社会の後進性、密接な人間関係だからこその激烈で理不尽な暴力や暴言、虐待は、息苦しいほどに重い。
だから、なかなか読み進むことができない。
まるで、それはジグソーパズルの小さなピースをはめていく作業に似ている。
現時点という、薄い映像が映し出される台紙の上に、主体も時制も雑多な細かなピースを乗せていく。その作業は、最初はあまりに漠然としていてしかもそれぞれの断片が余りに重く醜悪なので難渋する。
ところが、ピースが少しずつつながり、全体の映像が確かなものとなって徐々に立ち現れてくる。最後には、謎解きがかなったようなカタルシスが訪れる。それは、家族や故郷との何とも言い難い和解ともいうべき終結だ。
最後の最後の失われていたピースがぴたりとはまったその瞬間の衝撃、は言い知れぬほどに大きい。
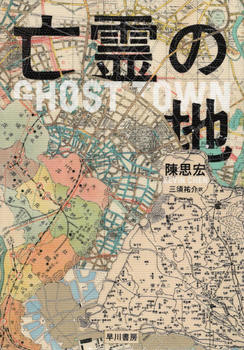
亡霊の地
陳 思宏(Kevin Chen)
三須 祐介 (翻訳)
早川書房
2023年5月23日 新刊
英訳
鬼地方(GHOST TOWN)
「終わりのない日々」(セバスチャン・バリー 著)読了 [読書]
ハードタッチの西部劇ならぬウェスタン小説。
時代は、日本で言えば幕末、ペリー来航の時代。
1845年のアイルランドの大飢饉、1859年にオレゴンが米国33番目の州に昇格、4年にわたった南北戦争が1865年に終結する。大平原での凄惨なインディアン戦争は最終局面を迎え、丸腰のシャイアン族を襲い男女、子どもの区別なくおよそ150名を殺害したサンドクリークの虐殺は、1864年のことだった。
物語は、アイルランドのジャガイモ飢饉で家族を失い食い詰めてアメリカに渡りミズーリ州に流れつき、食うために志願兵になったトマス・マクナルティの回顧録として語られていく。
トマスは、そこで生涯の伴侶であるジョン・コールと出会う。二人は食いつなぐために戦士となり、インディアンの掃討、南北内戦と、ありとあらゆる殺戮、残虐行為に加担し、飢餓や凍傷、捕虜虐待を生きながらえる。
戦役の合間に、二人の少年はミシガンの石膏鉱山町でダンス酒場で女装して男たちのダンスの相手をしたり、ひげ面の男前になってからは顔を黒く塗って演ずるブラックフェイス演劇の俳優ともなる。
言葉は不衛生で汚物、排泄、血まみれの負傷や病褥の苦痛に満ちあふれ、差別や蔑視、侮辱、卑猥な低俗な口汚さに何のはばかりもない。敵の遺体を損壊し、頭の皮を剥ぐのはインディアンばかりでなく白人兵士の習いでもあった。それが、殺伐たるリアルな描写ともなり、正義も人道も不在な戦争の空虚な実相を露わにする。下層底辺にあったアイルランド人が共に緑のシャムロックの旗を掲げて、南軍・北軍に分かれて最前線で正面対峙するというのは何とも言えぬユーモアさえ感じさせる。
そういう文面でありながら、心地よいリズムと響きがあって詩的であるとさえ言える。野蛮で野卑で美しい韻律に満ちている。アイルランドを代表する現代作家としてカズオ・イシグロらの絶賛を浴びているというのもよくわかる気がする。
トマスは女装を通じて自分のアイデンティティに目覚めていき、ジョン・コールと婚姻の契りを交わす。酋長の姪で、虐殺の現場で救い出したウィノナは、この同性の夫婦の娘となる。ウィノナは、劇場の詩人・劇作家の黒人の老人の手ほどきを受けて知的で美しい少女に育つ。同性夫婦と蛮人の養女という三人家族は、南部州のテネシーに逃れる。そこでは奴隷を解放したがために木に吊された父親の農場を引き継いだ戦友が待っていたからだ。
とにかく終始、波瀾万丈。
約束の地でのしばしの安息の日々もすぐに破られる。終末に向けてのどんでん返しの連続は、さながらスピードの落ちないジェットコースターで息もつかせず一気読みした。
すごい文学があったものだ。
翻訳もたいへんな労作。
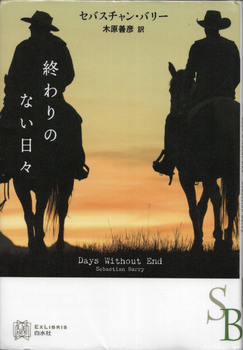
終わりのない日々
セバスチャン・バリー 著
木原善彦 訳
白水社
2023/6/2 (新刊)
DAYS WITHOUT END
Sebastian Barry
時代は、日本で言えば幕末、ペリー来航の時代。
1845年のアイルランドの大飢饉、1859年にオレゴンが米国33番目の州に昇格、4年にわたった南北戦争が1865年に終結する。大平原での凄惨なインディアン戦争は最終局面を迎え、丸腰のシャイアン族を襲い男女、子どもの区別なくおよそ150名を殺害したサンドクリークの虐殺は、1864年のことだった。
物語は、アイルランドのジャガイモ飢饉で家族を失い食い詰めてアメリカに渡りミズーリ州に流れつき、食うために志願兵になったトマス・マクナルティの回顧録として語られていく。
トマスは、そこで生涯の伴侶であるジョン・コールと出会う。二人は食いつなぐために戦士となり、インディアンの掃討、南北内戦と、ありとあらゆる殺戮、残虐行為に加担し、飢餓や凍傷、捕虜虐待を生きながらえる。
戦役の合間に、二人の少年はミシガンの石膏鉱山町でダンス酒場で女装して男たちのダンスの相手をしたり、ひげ面の男前になってからは顔を黒く塗って演ずるブラックフェイス演劇の俳優ともなる。
言葉は不衛生で汚物、排泄、血まみれの負傷や病褥の苦痛に満ちあふれ、差別や蔑視、侮辱、卑猥な低俗な口汚さに何のはばかりもない。敵の遺体を損壊し、頭の皮を剥ぐのはインディアンばかりでなく白人兵士の習いでもあった。それが、殺伐たるリアルな描写ともなり、正義も人道も不在な戦争の空虚な実相を露わにする。下層底辺にあったアイルランド人が共に緑のシャムロックの旗を掲げて、南軍・北軍に分かれて最前線で正面対峙するというのは何とも言えぬユーモアさえ感じさせる。
そういう文面でありながら、心地よいリズムと響きがあって詩的であるとさえ言える。野蛮で野卑で美しい韻律に満ちている。アイルランドを代表する現代作家としてカズオ・イシグロらの絶賛を浴びているというのもよくわかる気がする。
トマスは女装を通じて自分のアイデンティティに目覚めていき、ジョン・コールと婚姻の契りを交わす。酋長の姪で、虐殺の現場で救い出したウィノナは、この同性の夫婦の娘となる。ウィノナは、劇場の詩人・劇作家の黒人の老人の手ほどきを受けて知的で美しい少女に育つ。同性夫婦と蛮人の養女という三人家族は、南部州のテネシーに逃れる。そこでは奴隷を解放したがために木に吊された父親の農場を引き継いだ戦友が待っていたからだ。
とにかく終始、波瀾万丈。
約束の地でのしばしの安息の日々もすぐに破られる。終末に向けてのどんでん返しの連続は、さながらスピードの落ちないジェットコースターで息もつかせず一気読みした。
すごい文学があったものだ。
翻訳もたいへんな労作。
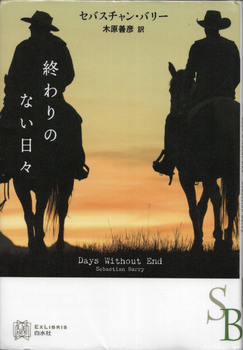
終わりのない日々
セバスチャン・バリー 著
木原善彦 訳
白水社
2023/6/2 (新刊)
DAYS WITHOUT END
Sebastian Barry
「白鶴亮翔」(多和田葉子 著)読了 [読書]
ドイツで一人暮らす日本人女性の何気ない身の回りの隣人たちとの日常の交流を綴ったエッセイ風の私小説。

作者の多和田葉子さんは、大学を卒業後、およそ40年にわたってベルリンで暮らしていて、日本語とドイツ語の二つの言語で小説の執筆を行っていて、作品は多くの言語に翻訳され紹介されている。だから、よけいにそのように見える。
…が、読み進めるほどに、そうではないとわかる。軽快なさりげない文章は、それでいて実に巧みで読みやすく、しかもリアルで含蓄や示唆に富んでいる。
主人公・美砂は、ふとしたことから太極拳スクールに参加します。ベルリンで東北(旧・満州)出身の中国人に習う。生徒たちは、南アメリカ人のカップル、ロシア人、イギリスの大学を出たフィリピン人と出自は様々。
美砂は、ドイツ文学研究の夫の留学に伴ってドイツに来たけれども、夫の帰国には従わずドイツに残る。ベルリンに定住している美砂の周囲の登場人物もほとんどがドイツ人以外の異国人。
ドイツ人と言えるのは、女友達のスージーと隣人のMさんぐらいのもの。そのMさんも、戦後に東プロイセンから移住してきた故郷追放者。Mさんというのは、最初の自己紹介で名前を聞き取りそびれ、かろうじて聞こえたイニシャルで呼んでいる。ドイツ人といっても微妙で希薄。
Mさんとの会話を重ねていくうちに、そういう異邦人たちがそれぞれに抱えるものが次第ににじみ出てくる。主人公が手すさびに翻訳するクライストの短編「ロカルノの女乞食」や、映画「楢山節考」や谷崎潤一郎などの古典的名作が、無理解や差別、分断や復しゅうの暗喩となって不吉さを醸し出す。一見、軽やかに進む文章の生地をこういう縦横の糸がびっしりと裏打ちして揺るがない。
過去の歴史や体験を背負う異邦の男女は、分断よりも互いに関わり合うことで優しく温和になれる。別れた夫は、美砂がドイツで見違えるように活発になって社交の場に溶け込むことをよく思わなかった。「発音だけはいいね」とそういう妻をくさすようなことを口にする。自分は壁に重たく張り付いているくせに、家に帰るとあれこれと饒舌になる。
白鶴亮翅(はっかくりょうし)とは、太極拳の型のひとつ。前後に両腕を真っ直ぐに広げる姿態が、翼を広げる鶴のようになる。太極拳は、呼吸を整え身体的なバランスと健康を得るものだが、基本は武術であるという。白鶴亮翅は、前方だけでなく後方からの敵にも即座に反応できる形だという。
この白鶴亮翔が、ドストエフスキー「罪と罰」と結びつき、見事なまでのエンディングとなる。
ロシア人女性アリョーシャは、成金未亡人で若いベンチャーに投資している。金を貸し与えている若い燕に不意に背後から襲われるが、習い憶えた白鶴亮翔のおかげで襲撃をとっさに避けることができた。「罪と罰」は、青年ラスコーリニコフが殺人の罪を犯すところから始まる。殺した高利貸しの老婆の名前がアリョーシャだったのです。この小説では、青年の罪を未然に防ぐことで終結となるというわけです。
もともとは朝日新聞に連載されたもの。その連載開始がロシアによるウクライナ侵攻と同時だったというのは決して偶然ではないだろうと思います。そこに作者の並々ならぬ洞察力を改めて感じるのです。
村上春樹にノーベル賞を期待する向きには気の毒だけれど、いずれは、多くの人がこの人の作品を慌てて読むことになるかもしれません。そうならないためにも、この最新作をおすすめします。

白鶴亮翅(はっかくりょうし)
多和田葉子 著
朝日新聞出版
2023/5/8 新刊

作者の多和田葉子さんは、大学を卒業後、およそ40年にわたってベルリンで暮らしていて、日本語とドイツ語の二つの言語で小説の執筆を行っていて、作品は多くの言語に翻訳され紹介されている。だから、よけいにそのように見える。
…が、読み進めるほどに、そうではないとわかる。軽快なさりげない文章は、それでいて実に巧みで読みやすく、しかもリアルで含蓄や示唆に富んでいる。
主人公・美砂は、ふとしたことから太極拳スクールに参加します。ベルリンで東北(旧・満州)出身の中国人に習う。生徒たちは、南アメリカ人のカップル、ロシア人、イギリスの大学を出たフィリピン人と出自は様々。
美砂は、ドイツ文学研究の夫の留学に伴ってドイツに来たけれども、夫の帰国には従わずドイツに残る。ベルリンに定住している美砂の周囲の登場人物もほとんどがドイツ人以外の異国人。
ドイツ人と言えるのは、女友達のスージーと隣人のMさんぐらいのもの。そのMさんも、戦後に東プロイセンから移住してきた故郷追放者。Mさんというのは、最初の自己紹介で名前を聞き取りそびれ、かろうじて聞こえたイニシャルで呼んでいる。ドイツ人といっても微妙で希薄。
Mさんとの会話を重ねていくうちに、そういう異邦人たちがそれぞれに抱えるものが次第ににじみ出てくる。主人公が手すさびに翻訳するクライストの短編「ロカルノの女乞食」や、映画「楢山節考」や谷崎潤一郎などの古典的名作が、無理解や差別、分断や復しゅうの暗喩となって不吉さを醸し出す。一見、軽やかに進む文章の生地をこういう縦横の糸がびっしりと裏打ちして揺るがない。
過去の歴史や体験を背負う異邦の男女は、分断よりも互いに関わり合うことで優しく温和になれる。別れた夫は、美砂がドイツで見違えるように活発になって社交の場に溶け込むことをよく思わなかった。「発音だけはいいね」とそういう妻をくさすようなことを口にする。自分は壁に重たく張り付いているくせに、家に帰るとあれこれと饒舌になる。
白鶴亮翅(はっかくりょうし)とは、太極拳の型のひとつ。前後に両腕を真っ直ぐに広げる姿態が、翼を広げる鶴のようになる。太極拳は、呼吸を整え身体的なバランスと健康を得るものだが、基本は武術であるという。白鶴亮翅は、前方だけでなく後方からの敵にも即座に反応できる形だという。
この白鶴亮翔が、ドストエフスキー「罪と罰」と結びつき、見事なまでのエンディングとなる。
ロシア人女性アリョーシャは、成金未亡人で若いベンチャーに投資している。金を貸し与えている若い燕に不意に背後から襲われるが、習い憶えた白鶴亮翔のおかげで襲撃をとっさに避けることができた。「罪と罰」は、青年ラスコーリニコフが殺人の罪を犯すところから始まる。殺した高利貸しの老婆の名前がアリョーシャだったのです。この小説では、青年の罪を未然に防ぐことで終結となるというわけです。
もともとは朝日新聞に連載されたもの。その連載開始がロシアによるウクライナ侵攻と同時だったというのは決して偶然ではないだろうと思います。そこに作者の並々ならぬ洞察力を改めて感じるのです。
村上春樹にノーベル賞を期待する向きには気の毒だけれど、いずれは、多くの人がこの人の作品を慌てて読むことになるかもしれません。そうならないためにも、この最新作をおすすめします。

白鶴亮翅(はっかくりょうし)
多和田葉子 著
朝日新聞出版
2023/5/8 新刊
タグ:多和田葉子
「蘇我氏四代」(遠山美都男 著)読了 [読書]
私たちの世代までは、蘇我氏は専横のままに政治を壟断し王権を簒奪しようとした極悪人で、大化の改新で中大兄皇子と中臣鎌足に誅せられたのも当然というように教えられてきた。
著者は、そういう蘇我氏四代に不当に課せられた汚名の虚偽を暴き、えん罪を晴らしていく。曰く、蘇我氏は葛城氏の正統を受け継ぐ群臣筆頭の家柄であり、蝦夷も入鹿も王権の意に忠実に従い為政に精励した忠臣だったと説く。
蘇我氏の歴史的評価見直しが、古代史研究の大きな転機であったことは間違いなさそうだ。王位というものが有力豪族の間でどのような位置づけだったのか、後継指名のあり方をめぐっての争いを通じて古代王権の確立に至った経緯が近年ずいぶんと明らかになってきた。王の在所、政権の執政所は、背景となる有力豪族によって左右されていたが、集権の象徴としての王都建設が政策の主眼となって争点ともなっていく。
「書紀」や「古事記」などのテキストを批判的に解読し、その記述の齟齬や矛盾を丹念に読み解いていく手法はとても丁寧だが、読者にとってはいささか退屈で難渋の連続。
文献学的な手法で読み解いても、正史というものは編纂にあたっては政治的な価値観に左右されているわけだから、本来は、後世の私たちがそれをどのようなバイアスで読み取ったかとかいったことが問題であって、必ずしも歴史的な事実の探求たり得ない。えん罪を晴らしたところで真犯人や新事実は現れてこない。本書にはそういうもどかしさがある。
「臣、罪を知らず」というのは、入鹿の断末魔の叫びだったが、では、入鹿は誰かにはめられたのか。それにしても、大王面前の公式行事の最中の血生臭いクーデターはあまりにも異様である。その犯人と真の動機が解明されないのでは、それまで耐えて読んできた長文が何だったのかという欲求不満がつのる。
結末の欲求不満に加えて、厩戸皇子(聖徳太子)の血統がなぜにこれほどまでに排除されたのかという謎も深まるばかり。
歴史に勧善懲悪はあり得ないというのはあたりまえの時代。そのことを定着させたことに著者は貢献したことは間違いないが、その先がほしい。古代史には、まだまだ謎が多い。

蘇我氏四代 臣、罪を知らず
遠山美都男 (著)
ミネルヴァ書房 (ミネルヴァ日本評伝選)
2006年初版
著者は、そういう蘇我氏四代に不当に課せられた汚名の虚偽を暴き、えん罪を晴らしていく。曰く、蘇我氏は葛城氏の正統を受け継ぐ群臣筆頭の家柄であり、蝦夷も入鹿も王権の意に忠実に従い為政に精励した忠臣だったと説く。
蘇我氏の歴史的評価見直しが、古代史研究の大きな転機であったことは間違いなさそうだ。王位というものが有力豪族の間でどのような位置づけだったのか、後継指名のあり方をめぐっての争いを通じて古代王権の確立に至った経緯が近年ずいぶんと明らかになってきた。王の在所、政権の執政所は、背景となる有力豪族によって左右されていたが、集権の象徴としての王都建設が政策の主眼となって争点ともなっていく。
「書紀」や「古事記」などのテキストを批判的に解読し、その記述の齟齬や矛盾を丹念に読み解いていく手法はとても丁寧だが、読者にとってはいささか退屈で難渋の連続。
文献学的な手法で読み解いても、正史というものは編纂にあたっては政治的な価値観に左右されているわけだから、本来は、後世の私たちがそれをどのようなバイアスで読み取ったかとかいったことが問題であって、必ずしも歴史的な事実の探求たり得ない。えん罪を晴らしたところで真犯人や新事実は現れてこない。本書にはそういうもどかしさがある。
「臣、罪を知らず」というのは、入鹿の断末魔の叫びだったが、では、入鹿は誰かにはめられたのか。それにしても、大王面前の公式行事の最中の血生臭いクーデターはあまりにも異様である。その犯人と真の動機が解明されないのでは、それまで耐えて読んできた長文が何だったのかという欲求不満がつのる。
結末の欲求不満に加えて、厩戸皇子(聖徳太子)の血統がなぜにこれほどまでに排除されたのかという謎も深まるばかり。
歴史に勧善懲悪はあり得ないというのはあたりまえの時代。そのことを定着させたことに著者は貢献したことは間違いないが、その先がほしい。古代史には、まだまだ謎が多い。

蘇我氏四代 臣、罪を知らず
遠山美都男 (著)
ミネルヴァ書房 (ミネルヴァ日本評伝選)
2006年初版
タグ:蘇我氏四代
「ウクライナ戦争」(小泉 悠 著)読了 [読書]
著者も述べている通り、終わりの見えない現在進行中のこの戦争を追っている限りでは限界もある。けれども、もはやあり得ないと言われていた国家対国家の大戦争が現実には起こっているという衝撃は大きく、誰しもが「なぜ?」という疑問を持っているはず。本書は、そういう衝撃的疑問に十分答えている。
まずは開戦に至るまでの経緯と開戦前夜を第1章と第2章で解き明かす。続いて第3章と第4章では開戦直後から、戦争が長期化の様相を確実にした昨年の夏頃までの経過をつぶさに追っていく。ここらあたりはとても読み応えがある。
プーチンは、国家対国家の大戦争を起こす意図はなかったし、今でもそういう戦争
をしているという自覚もないのではないか。この点で、ウクライナ侵攻がKGB出身のプーチン好みの、内通者とごく一部の精鋭で数日のうちにゼレンスキー政権を転覆する計画だったということを活写する。それがあっけなく挫折し、同時に侵攻したウクライナ南部と東部でやむなく地域紛争の形で継続せざるを得ない状況に陥っているという分析は鋭い。
プーチンの誤算は、謀略の内実があまりにもずさんだったこと。
しかもゼレンスキー政権が思わぬ抵抗力を見せた。ウクライナは、誰もが予想しないほどに果敢に抵抗し、緒戦の反撃に成功した。ゼレンスキーが背中を見せなかったことで戦争遂行について国民の絶大な支持を受け、古典的な国民戦争の様相を現したことだ。その挫折は、現代的な情報戦やハイテク戦力の底が知れていたことを露呈し、結局は、戦闘員だけでなく市民をも無差別に巻き込む死屍累々たる残虐な古典的大戦争の軍隊の本質がむき出しになってしまう。
しかし、それでもプーチンは国家対国家の戦争になっていることを認めない。
自分たちの失敗を糊塗し、地位を守ろうとする将軍たちは、他に戦いようがないからある限りの古典的な重火器を動員して物量でウクライナを押しに押そうとするが、それはもはや前進は放棄した侵攻地域確保の戦いに過ぎない。ミサイルや無人機攻撃などは、平時の地図情報のみだから大型インフラや市街地の攻撃しかできない。緒戦の失敗で近代化の表層が剥がれ落ちたら、第二次世界大戦以来のロシア国軍の古い地層しか残っていなかったということがであって、プーチンの政治的意図と戦争遂行のメカニズムとの間には、第三者からは憶測のしようがないギャップがある。
今後の問題は、核の行使とNATO軍との直接の交戦といった戦争のエスカレーションだ。
このことに著者は、どちらかといえば楽観的だ。核は使えないということで、米欧露は共通しているというのだ。たとえ戦術核であっても使ったら最後、人類誰もが予想もつかない様相にまで一気にエスカレートしていく。そういう恐怖を共有する。核は使えないから抑止力として機能する。
しかし、そういう核兵器観もまさに冷戦時代までの古典的思考ではないのか?
本書は、昨年9月時点での著述であることを断っている。ドイツやアメリカが主力戦車の供与を表明したのは今年2023年に入ってから。その後は、主力戦闘機や長射程ミサイルの供与などウクライナ支援の武器供与姿勢はどんどんと高度化していっている。
6月末のいまのこの瞬間まで、こうして供与された主力戦力が本来の戦闘力を発揮したとの兆候は薄い。やはり、こうした供与武器はゲームチェンジャーたり得ないのか?あるいはオペレーターの訓練等準備不足で本格的反抗が始まっていないのか。世界は固唾をのんでいるわけだが、この本ではそういう点で著者本来の軍事オタクとしての分析が及んでいない。
そこがとてももどかしい。
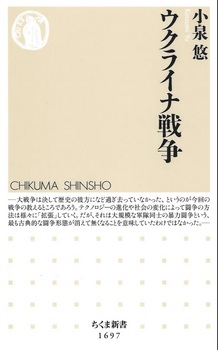
ウクライナ戦争
小泉 悠
ちくま新書(1967)
筑摩書房
2022年12月10日新刊
まずは開戦に至るまでの経緯と開戦前夜を第1章と第2章で解き明かす。続いて第3章と第4章では開戦直後から、戦争が長期化の様相を確実にした昨年の夏頃までの経過をつぶさに追っていく。ここらあたりはとても読み応えがある。
プーチンは、国家対国家の大戦争を起こす意図はなかったし、今でもそういう戦争
をしているという自覚もないのではないか。この点で、ウクライナ侵攻がKGB出身のプーチン好みの、内通者とごく一部の精鋭で数日のうちにゼレンスキー政権を転覆する計画だったということを活写する。それがあっけなく挫折し、同時に侵攻したウクライナ南部と東部でやむなく地域紛争の形で継続せざるを得ない状況に陥っているという分析は鋭い。
プーチンの誤算は、謀略の内実があまりにもずさんだったこと。
しかもゼレンスキー政権が思わぬ抵抗力を見せた。ウクライナは、誰もが予想しないほどに果敢に抵抗し、緒戦の反撃に成功した。ゼレンスキーが背中を見せなかったことで戦争遂行について国民の絶大な支持を受け、古典的な国民戦争の様相を現したことだ。その挫折は、現代的な情報戦やハイテク戦力の底が知れていたことを露呈し、結局は、戦闘員だけでなく市民をも無差別に巻き込む死屍累々たる残虐な古典的大戦争の軍隊の本質がむき出しになってしまう。
しかし、それでもプーチンは国家対国家の戦争になっていることを認めない。
自分たちの失敗を糊塗し、地位を守ろうとする将軍たちは、他に戦いようがないからある限りの古典的な重火器を動員して物量でウクライナを押しに押そうとするが、それはもはや前進は放棄した侵攻地域確保の戦いに過ぎない。ミサイルや無人機攻撃などは、平時の地図情報のみだから大型インフラや市街地の攻撃しかできない。緒戦の失敗で近代化の表層が剥がれ落ちたら、第二次世界大戦以来のロシア国軍の古い地層しか残っていなかったということがであって、プーチンの政治的意図と戦争遂行のメカニズムとの間には、第三者からは憶測のしようがないギャップがある。
今後の問題は、核の行使とNATO軍との直接の交戦といった戦争のエスカレーションだ。
このことに著者は、どちらかといえば楽観的だ。核は使えないということで、米欧露は共通しているというのだ。たとえ戦術核であっても使ったら最後、人類誰もが予想もつかない様相にまで一気にエスカレートしていく。そういう恐怖を共有する。核は使えないから抑止力として機能する。
しかし、そういう核兵器観もまさに冷戦時代までの古典的思考ではないのか?
本書は、昨年9月時点での著述であることを断っている。ドイツやアメリカが主力戦車の供与を表明したのは今年2023年に入ってから。その後は、主力戦闘機や長射程ミサイルの供与などウクライナ支援の武器供与姿勢はどんどんと高度化していっている。
6月末のいまのこの瞬間まで、こうして供与された主力戦力が本来の戦闘力を発揮したとの兆候は薄い。やはり、こうした供与武器はゲームチェンジャーたり得ないのか?あるいはオペレーターの訓練等準備不足で本格的反抗が始まっていないのか。世界は固唾をのんでいるわけだが、この本ではそういう点で著者本来の軍事オタクとしての分析が及んでいない。
そこがとてももどかしい。
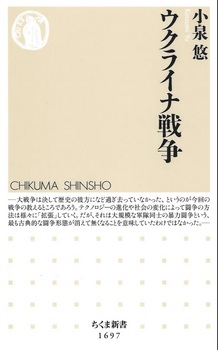
ウクライナ戦争
小泉 悠
ちくま新書(1967)
筑摩書房
2022年12月10日新刊
「長い物語のためのいくつかの短いお話」(ロジェ・グルニエ 著・宮下志朗 訳)読了 [読書]
訳者によるとロジェ・グルニエは、メジャーな作家ではないが、フランス現代作家のなかでも邦訳されている著書が多く、日本にもコアな読者が確実に存在するという作家だという。大戦中にレジスタンスに参加し、戦後、カミュの知己も得たという。本作は、2017年に物故した著者の最後の作品。
もし《老人文学》というジャンルがあるとしたら、これはまさにその金字塔と言うべき短編小説集なのかも知れない。
グルニエ自身が「記憶そのものがすでにして、一個の小説家といえる。…記憶を創作するということは、記憶に忠実であることよりも、作家にとっては役に立つ。」と言っている。「記憶」を創作の出発点として、これを作り替え、置き換えるようにして物語をふくらませていく。
老いるということは、記憶に埋もれることでもある。悔恨、失意、希望、憧憬、友情、夫婦愛…そうした置き去りにされてしまった感情のフィルターによって老人の記憶は作り替えられ、転倒され、欠損と付加が施され、色づけされていく。それはほろ苦く、ときには残酷にも思えるような結末に苛まれることでもある。記憶の変成による虚構は、真実以上に、老いの心情を映し出し苦い夢想へと沈めていく。
もともとグルニエは、エッセイも含めてその作品間には微妙な重なり合いが存在するという。ひとつの主題が、作品やジャンルをまたがって反復・変奏されていく。そういう「記憶」の連鎖や変容のなかを彷徨うのだと。
長い人生の終末である「老い」を主題とするやるせないショートショートは、老人にありがちな記憶の錯乱をそのままに創作に変えてしまう記憶の変奏曲であって、高齢者となった読み手にとっては、そのひとつひとつに身につまされ、切ない思いにさせられるに違いない。

長い物語のためのいくつかの短いお話
ロジェ・グルニエ (著)
宮下志朗 (翻訳)
白水社
2023年4月10日新刊
もし《老人文学》というジャンルがあるとしたら、これはまさにその金字塔と言うべき短編小説集なのかも知れない。
グルニエ自身が「記憶そのものがすでにして、一個の小説家といえる。…記憶を創作するということは、記憶に忠実であることよりも、作家にとっては役に立つ。」と言っている。「記憶」を創作の出発点として、これを作り替え、置き換えるようにして物語をふくらませていく。
老いるということは、記憶に埋もれることでもある。悔恨、失意、希望、憧憬、友情、夫婦愛…そうした置き去りにされてしまった感情のフィルターによって老人の記憶は作り替えられ、転倒され、欠損と付加が施され、色づけされていく。それはほろ苦く、ときには残酷にも思えるような結末に苛まれることでもある。記憶の変成による虚構は、真実以上に、老いの心情を映し出し苦い夢想へと沈めていく。
もともとグルニエは、エッセイも含めてその作品間には微妙な重なり合いが存在するという。ひとつの主題が、作品やジャンルをまたがって反復・変奏されていく。そういう「記憶」の連鎖や変容のなかを彷徨うのだと。
長い人生の終末である「老い」を主題とするやるせないショートショートは、老人にありがちな記憶の錯乱をそのままに創作に変えてしまう記憶の変奏曲であって、高齢者となった読み手にとっては、そのひとつひとつに身につまされ、切ない思いにさせられるに違いない。

長い物語のためのいくつかの短いお話
ロジェ・グルニエ (著)
宮下志朗 (翻訳)
白水社
2023年4月10日新刊
「グルーヴ!」(山田陽一 編)読了 [読書]
クラシック音楽にも「グルーヴ(groove)」はあるのか?
10人のクラシック音楽演奏家に、それを問いかけ、クラシック演奏における繊細で研ぎ澄まされた感覚と途方もなく微細で緻密な音楽造形の秘技を明らかにしていく。クラシック音楽にも、それをグルーヴと呼ぶのか、あるいはそういう意識が明確にあるのかはともかくも、確かに共通する高揚感や快感があって、演奏家はそのことを常に意識して技を磨いている。
「グルーヴ(groove)」は、ジャズやロック音楽でよく使われる。「グルーヴィ(
groovy)」とは、「かっこいい」「ノリのいい」というような意味合いで使われているがその意味は曖昧だ。「グルーヴ感がある」というとは「高揚感」ということとほぼ同義に使われる。あるいは、そういう高揚感をもたらす、ある種の揺らぎやズレのことを言うことが多い。本来の規則的な拍子から意図的に遅らせたり、一瞬の間を入れたり、押したり引いたり、ズラしたり。民族音楽によく見られるように、変拍子やポリリズムそのものの変則的で複雑なリズムにもそういう効果がある。
10人のクラシック音楽家の反応は十人十色。そこがまた面白い。
同じヴァイオリニストでも、ソリストと大オーケストラのコンサートマスターとは考えがまるで違う。
堀米ゆず子は、「練習による造り込み」をことさらに強調する。堀米にとっては、フレージングやアゴーギグなどある種の修辞法あるいは語法のようなものが音楽に生命力を与えると考えるのだろう。
一方、矢部達哉は、方向性とか空間の一体感といったアンサンブル感覚に徹している。むしろ拍節や小節の枠から少しずつはみ出す遊びとか自由があってこそのアンサンブルだと言う。そのせめぎ合いから一体感へと登りつめるところにスポーツ選手がよく言う「ゾーン」(絶頂状態)が生まれるとも言う。そのことは指揮者の下野竜也も同じで、遊びやズレなどは尊重して、楽器の音量、音色、発声の違いの組み合わせを微妙にコントロールすることに指揮者の存在意義を見いだす。あるいは、ソリストの遊びや自由のままに自分はイン・テンポな振りに徹することもある。
そういうことを強烈に意識しているのは、ベース音を支えるコントラバスや打楽器などのリズムセクション。
「みんな、ぼくの手のひらで踊っている」とコントラバスの池松宏は豪語するが、クラシックの低音楽器はピッチカートなどのリズムだけでなくアルコ(弓引き)の持続音で響きも作り上げる。ティンパニの岡田全弘も、リズムよりも「響き」を作ることの大切さに言葉を尽くす。トロンボーンの池上亘は「響き」を作ることにおける「遊び」「ずれ」の役割を徹底的に語る。
リズムのキレとハーモニーの厚み、テクスチャーのようなものを両面で使い分けるヴィオラの鈴木学の話しは、クラシック音楽においてはとても重要な「内声」のことについて余すところなく語っている。ちょっと意外だったのはファゴット奏者・吉田將のバロック音楽への博覧強記ぶり。しきりに様々な楽曲の具体例を引いて、アンサンブルの妙味について語っている。バロック音楽こそグルーヴの宝庫であるように思えてくる。そういえばファゴットは管楽器のなかでももっとも古い歴史がある。
こういう演奏家の秘儀に触れるということだけでも、本書の魅力は存分にあると思う。
さて…
クラシック音楽に「グルーヴ」はあるのか?
あるとしたらそれはどのようなものなのか?という問いかけに対しては、ジャズ/クラシック兼業ピアニストの小曽根真が感覚的に実に見事に多くを語っている。杓子定規に思えるクラシック音楽だが、そうではないことは小曽根の次の言に集約される。
『…自分の台詞だけを覚えてる役者っていうのは碌な役者じゃない…。』
『いい役者っていうのは、ちゃんと物語を把握して、相手の台詞も全部わかってて…相手がどういう球を投げてくるかを聞いて、それに対して自分の台詞の言いかたも変えられるということ…それはすごく音楽と似てるし、特に台詞があるということに関しては、クラシックとすごく似てますよね』
全体を通して思い当たるのは、ジャズが主にリズムなのに対して、クラシック音楽は、より「響き」「ハーモニー」にグルーヴを見いだす音楽だということのようだ。
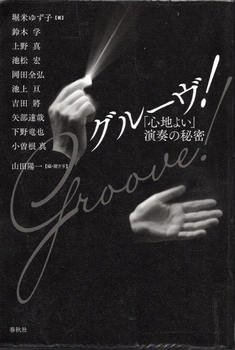
グルーヴ! : 「心地よい」演奏の秘密
編・聞き手:山田陽一
堀米ゆず子(ヴァイオリン)
鈴木 学(ヴィオラ:東京都交響楽団ソロ首席)
上野 真(ピアノ)
池松 宏(コントラバス:東京都交響楽団首席)
岡田全弘(ティンパニ:読売日本交響楽団首席)
池上 亘(トロンボーン:NHK交響楽団)
吉田 將(ファゴット:読売日本交響楽団首席)
矢部達哉(ヴァイオリン:東京都高級楽団ソロ・コンサートマスター)
下野竜也(指揮)
小曽根 真(ピアノ)
春秋社
10人のクラシック音楽演奏家に、それを問いかけ、クラシック演奏における繊細で研ぎ澄まされた感覚と途方もなく微細で緻密な音楽造形の秘技を明らかにしていく。クラシック音楽にも、それをグルーヴと呼ぶのか、あるいはそういう意識が明確にあるのかはともかくも、確かに共通する高揚感や快感があって、演奏家はそのことを常に意識して技を磨いている。
「グルーヴ(groove)」は、ジャズやロック音楽でよく使われる。「グルーヴィ(
groovy)」とは、「かっこいい」「ノリのいい」というような意味合いで使われているがその意味は曖昧だ。「グルーヴ感がある」というとは「高揚感」ということとほぼ同義に使われる。あるいは、そういう高揚感をもたらす、ある種の揺らぎやズレのことを言うことが多い。本来の規則的な拍子から意図的に遅らせたり、一瞬の間を入れたり、押したり引いたり、ズラしたり。民族音楽によく見られるように、変拍子やポリリズムそのものの変則的で複雑なリズムにもそういう効果がある。
10人のクラシック音楽家の反応は十人十色。そこがまた面白い。
同じヴァイオリニストでも、ソリストと大オーケストラのコンサートマスターとは考えがまるで違う。
堀米ゆず子は、「練習による造り込み」をことさらに強調する。堀米にとっては、フレージングやアゴーギグなどある種の修辞法あるいは語法のようなものが音楽に生命力を与えると考えるのだろう。
一方、矢部達哉は、方向性とか空間の一体感といったアンサンブル感覚に徹している。むしろ拍節や小節の枠から少しずつはみ出す遊びとか自由があってこそのアンサンブルだと言う。そのせめぎ合いから一体感へと登りつめるところにスポーツ選手がよく言う「ゾーン」(絶頂状態)が生まれるとも言う。そのことは指揮者の下野竜也も同じで、遊びやズレなどは尊重して、楽器の音量、音色、発声の違いの組み合わせを微妙にコントロールすることに指揮者の存在意義を見いだす。あるいは、ソリストの遊びや自由のままに自分はイン・テンポな振りに徹することもある。
そういうことを強烈に意識しているのは、ベース音を支えるコントラバスや打楽器などのリズムセクション。
「みんな、ぼくの手のひらで踊っている」とコントラバスの池松宏は豪語するが、クラシックの低音楽器はピッチカートなどのリズムだけでなくアルコ(弓引き)の持続音で響きも作り上げる。ティンパニの岡田全弘も、リズムよりも「響き」を作ることの大切さに言葉を尽くす。トロンボーンの池上亘は「響き」を作ることにおける「遊び」「ずれ」の役割を徹底的に語る。
リズムのキレとハーモニーの厚み、テクスチャーのようなものを両面で使い分けるヴィオラの鈴木学の話しは、クラシック音楽においてはとても重要な「内声」のことについて余すところなく語っている。ちょっと意外だったのはファゴット奏者・吉田將のバロック音楽への博覧強記ぶり。しきりに様々な楽曲の具体例を引いて、アンサンブルの妙味について語っている。バロック音楽こそグルーヴの宝庫であるように思えてくる。そういえばファゴットは管楽器のなかでももっとも古い歴史がある。
こういう演奏家の秘儀に触れるということだけでも、本書の魅力は存分にあると思う。
さて…
クラシック音楽に「グルーヴ」はあるのか?
あるとしたらそれはどのようなものなのか?という問いかけに対しては、ジャズ/クラシック兼業ピアニストの小曽根真が感覚的に実に見事に多くを語っている。杓子定規に思えるクラシック音楽だが、そうではないことは小曽根の次の言に集約される。
『…自分の台詞だけを覚えてる役者っていうのは碌な役者じゃない…。』
『いい役者っていうのは、ちゃんと物語を把握して、相手の台詞も全部わかってて…相手がどういう球を投げてくるかを聞いて、それに対して自分の台詞の言いかたも変えられるということ…それはすごく音楽と似てるし、特に台詞があるということに関しては、クラシックとすごく似てますよね』
全体を通して思い当たるのは、ジャズが主にリズムなのに対して、クラシック音楽は、より「響き」「ハーモニー」にグルーヴを見いだす音楽だということのようだ。
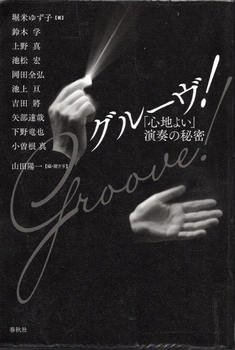
グルーヴ! : 「心地よい」演奏の秘密
編・聞き手:山田陽一
堀米ゆず子(ヴァイオリン)
鈴木 学(ヴィオラ:東京都交響楽団ソロ首席)
上野 真(ピアノ)
池松 宏(コントラバス:東京都交響楽団首席)
岡田全弘(ティンパニ:読売日本交響楽団首席)
池上 亘(トロンボーン:NHK交響楽団)
吉田 將(ファゴット:読売日本交響楽団首席)
矢部達哉(ヴァイオリン:東京都高級楽団ソロ・コンサートマスター)
下野竜也(指揮)
小曽根 真(ピアノ)
春秋社
「奇跡のフォント」(高田裕美 著)読了 [読書]
著者は、まさにフォントマニア!

デジタル時代の今日、ふだんから何気なくその恩恵にあずかっている様々なデザインの字体。それがこんなに奥深いものだとは知らなかった。さらには識字障害ということに様々なものがあって、字体デザインによってそのバリアが取り除かれることになるなんてなおのこと知りませんでした。
UDデジタル教科書体開発の奮闘は、《プロジェクトX》的な熱い物語。そのなかに様々な《奇跡》のような人との出会い(別れも!)がいっぱいあって読むものの胸を打ちます。
グラフィックデザイン、工業デザイナー、デジタル印刷、ビジネス人脈形成、識字障害、働く女性の壁、多様性社会……読者の視点や興味は様々でしょうが、とにかく面白く、しかも熱い!
そもそも《フォント》とは何でしょうか?
印刷の歴史を振り返れば、私自身が本になじみはじめた頃は活版印刷が主流で、金属製の《活字》を職人さんが一字一字拾っていくというイメージがありました。その活字には、字体と大きさがあってそのひとそろいのセットが、《フォント》に当たるわけです。行書体とか楷書体とか明朝体、ゴシック体、太字とか字体にも種類があり、大きさは、何ポイントとか言っていました。
著者が、美術短大を卒業してこの世界に飛び込んだ時は、写植だったそうです。活版印刷よりもデザインの自由度が高い写真技術を使って版下を造る写真植字。その写植機に使用する字体デザインに明け暮れる毎日。
すぐにコンピューターの導入があり、ワードプロセッサーの急速な普及とともにデジタル技術を使った《ビットマップフォント》の時代になります。
《ビットマッピング》とは、たくさんのマス目を白黒で塗りつぶして字体(画像)を描いていくこと。当時は、「スペースインベーダー」などのゲーム機が大流行。あのギザギザのキャラを思い浮かべればピンとくるはずです。私自身も会社で《OA(Office Automation)》の嵐の中でワープロと格闘。会社の社名が古くさく、公式の契約書をワープロ化するには社名の正式な字体がなくて、ワープロ付属のフォントソフトでそういう古くさい旧字体を作ったことを覚えています。
この《ビットマップフォント》は、拡大するとギザギザが避けられず、すぐに《アウトラインフォント》に置き換わっていきます。《アウトラインフォント》とは、定点を基準にそれを結ぶ曲線を計算し輪郭で描いていくフォント。年賀状などの字体を自在に斜めにしたり拡大したりできるようになったのは、なるほどこれだったのかと気がつきました。この技術で、フォントデザインはその自由度を飛躍的に増して、その対応力を高めていきます。

フォントデザインの重要な要素として「読みやすさ」「誤読させない」ということがあります。実際のところ字を習得する真っ最中の子供たちは、書き方(書き順、画数)と違う明朝体やゴシック体の字にしばしば戸惑います。だから、運筆に沿った字体(教科書体)が教科書には採用されている。それを追求していく過程で、著者は、教育の現場、さらには識字障害の子供たちと出会うことになります。それが本書の最大のテーマである「UDデジタル教科書体」の開発につながっていく。
とてもスリリングなストーリー。何度も挫折を味わうことになりますが、そのたびに読んでいてつい「頑張れ!」と言いたくなります。字が読みにくい《識字障害》のために勉強のできない子、努力の足りない子と決めつけられてしまった子供たちとの出会いは感動的。識字障害は、その様相も程度もとても多様。コツコツと地道にデータを集め、識字バリアを取り払うことに取り組んでいる研究者との出会いはもっと感動的。開発の七転び八起きは、まさにそうした奇跡の連続なんです。まさにそうした奇跡が生んだのが「UDデジタル教科書体」なのです。
こんな世界があったのだ…という発見もあるし、多様化社会づくりという私たちの社会の底力に勇気ももらえる本です。
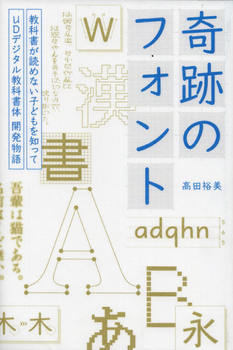
奇跡のフォント
教科書が読めない子どもを知って
UDデジタル教科書体 開発物語
高田裕美 著
時事通信社
2023年4月6日 初刊

デジタル時代の今日、ふだんから何気なくその恩恵にあずかっている様々なデザインの字体。それがこんなに奥深いものだとは知らなかった。さらには識字障害ということに様々なものがあって、字体デザインによってそのバリアが取り除かれることになるなんてなおのこと知りませんでした。
UDデジタル教科書体開発の奮闘は、《プロジェクトX》的な熱い物語。そのなかに様々な《奇跡》のような人との出会い(別れも!)がいっぱいあって読むものの胸を打ちます。
グラフィックデザイン、工業デザイナー、デジタル印刷、ビジネス人脈形成、識字障害、働く女性の壁、多様性社会……読者の視点や興味は様々でしょうが、とにかく面白く、しかも熱い!
そもそも《フォント》とは何でしょうか?
印刷の歴史を振り返れば、私自身が本になじみはじめた頃は活版印刷が主流で、金属製の《活字》を職人さんが一字一字拾っていくというイメージがありました。その活字には、字体と大きさがあってそのひとそろいのセットが、《フォント》に当たるわけです。行書体とか楷書体とか明朝体、ゴシック体、太字とか字体にも種類があり、大きさは、何ポイントとか言っていました。
著者が、美術短大を卒業してこの世界に飛び込んだ時は、写植だったそうです。活版印刷よりもデザインの自由度が高い写真技術を使って版下を造る写真植字。その写植機に使用する字体デザインに明け暮れる毎日。
すぐにコンピューターの導入があり、ワードプロセッサーの急速な普及とともにデジタル技術を使った《ビットマップフォント》の時代になります。
《ビットマッピング》とは、たくさんのマス目を白黒で塗りつぶして字体(画像)を描いていくこと。当時は、「スペースインベーダー」などのゲーム機が大流行。あのギザギザのキャラを思い浮かべればピンとくるはずです。私自身も会社で《OA(Office Automation)》の嵐の中でワープロと格闘。会社の社名が古くさく、公式の契約書をワープロ化するには社名の正式な字体がなくて、ワープロ付属のフォントソフトでそういう古くさい旧字体を作ったことを覚えています。
この《ビットマップフォント》は、拡大するとギザギザが避けられず、すぐに《アウトラインフォント》に置き換わっていきます。《アウトラインフォント》とは、定点を基準にそれを結ぶ曲線を計算し輪郭で描いていくフォント。年賀状などの字体を自在に斜めにしたり拡大したりできるようになったのは、なるほどこれだったのかと気がつきました。この技術で、フォントデザインはその自由度を飛躍的に増して、その対応力を高めていきます。

フォントデザインの重要な要素として「読みやすさ」「誤読させない」ということがあります。実際のところ字を習得する真っ最中の子供たちは、書き方(書き順、画数)と違う明朝体やゴシック体の字にしばしば戸惑います。だから、運筆に沿った字体(教科書体)が教科書には採用されている。それを追求していく過程で、著者は、教育の現場、さらには識字障害の子供たちと出会うことになります。それが本書の最大のテーマである「UDデジタル教科書体」の開発につながっていく。
とてもスリリングなストーリー。何度も挫折を味わうことになりますが、そのたびに読んでいてつい「頑張れ!」と言いたくなります。字が読みにくい《識字障害》のために勉強のできない子、努力の足りない子と決めつけられてしまった子供たちとの出会いは感動的。識字障害は、その様相も程度もとても多様。コツコツと地道にデータを集め、識字バリアを取り払うことに取り組んでいる研究者との出会いはもっと感動的。開発の七転び八起きは、まさにそうした奇跡の連続なんです。まさにそうした奇跡が生んだのが「UDデジタル教科書体」なのです。
こんな世界があったのだ…という発見もあるし、多様化社会づくりという私たちの社会の底力に勇気ももらえる本です。
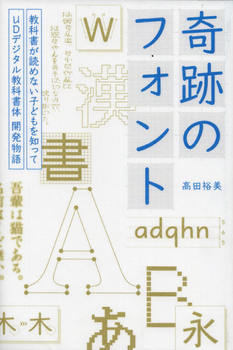
奇跡のフォント
教科書が読めない子どもを知って
UDデジタル教科書体 開発物語
高田裕美 著
時事通信社
2023年4月6日 初刊



