KEIRIN(ジャスティン・マッカリー 著)読了 [読書]
在日30年の英国人記者による、競輪をテーマにした日本文化論。
まずもって、競輪は、競艇・競馬・オートレースと並ぶ公営ギャンブルの一角をなす。自転車競技のトラックレースに《ケイリン》があるので紛らわしいが、《競輪》は断じてスポーツではない。
その一方で、ギャンブルのなかでは、唯一、身体的能力を競い肉体と肉体が闘う競技であり異色の魅力を持つことも事実。《ケイリン》は、別物であっても《競輪》をもとにしたトラック競技であり、そのきっかけは競輪のレジェンド中野浩一が世界選手権スプリントで10連覇を成し遂げたことがきっかけになったことも事実。
その競輪は、戦後まもない日本の地方財政を助け、戦災復興や公共施設の建設などに貢献した。自転車競技法という法に基づいていて、主催者は地方自治体。。監督官庁は経済産業省で、運営統括は公益財団法人JKAという経産官僚の天下り先。『公営ギャンブル』たるゆえんである。
ルールは、硬直的でいまだに旧態依然としたまま。八百長などの不正防止のために選手は缶詰状態に置かれ、プロ資格取得のための養成所では軍隊か刑務所のような管理と精神教育が行われる。車体も相も変わらぬ鉄製(クロームモリブデン鋼)のフレームが使用されるのは、JKAが定める規格が厳格で固定的だからだ。競技の駆け引きには「ライン」と呼ばれる出身地方毎のグループや先輩後輩などの年齢序列の世界が強く存在する。そのために、あたかも時が止まったようで昭和の香りがぷんぷんと漂う。
競輪というものの実相や、魅力、歴史、社会的な課題や将来性なには、語り尽くせないものがある。著者は「ガーディアン」の日本駐在特派員というジャーナリストであるだけにその取材は広範囲であり膨大な資料探索とインタビューを積み上げているのはさすが。けれども、散漫な記述は何が言いたいのか、何を伝えたいのかがわからない。
一方で、ロンドン大学の日本研究の修士卒というインテリだけに、文化比較論的な日本紹介書になっている。むしろ、競輪の啓蒙書というよりは、競輪という日本独特のギャンブルをネタに外国人の日本異文化論をくすぐるガイジンによるガイジンのための書。だから、日本人がまともに読もうとすると冗長で持って回った表現が鼻につき、視点が散漫でいったい何が言いたいのかわからなくなる。競輪の後進性や閉鎖性を、日本文化論に転化されてはたまらない。
訳文は、そういう原文に忠実なのだろうが、英国人が書いた日本紹介を日本人向けに翻訳するのならもっと工夫があってしかるべきだったのではないだろうか。原著者が日本にいるのだから、思い切ったゴーストライター的な書き下ろしがあってもよかったような気がする。
競輪を知ろうという人には隔靴掻痒だし、ある程度競輪を知った人にはもどかしい。
ジャーナリスティックな取材記事としてはさすがと思わせるところも多い。拾い読みするとすれば、中野浩一へのインタビューやフレームビルダーの話しなど部分的にはたまらなく面白いところもある。
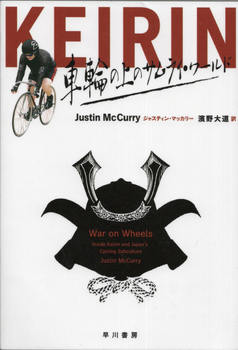
KEIRIN
車輪の上のサムライ・ワールド
ジャスティン・マッカリー (著)
濱野 大道 (翻訳)
早川書房
2023/7/19 新刊
まずもって、競輪は、競艇・競馬・オートレースと並ぶ公営ギャンブルの一角をなす。自転車競技のトラックレースに《ケイリン》があるので紛らわしいが、《競輪》は断じてスポーツではない。
その一方で、ギャンブルのなかでは、唯一、身体的能力を競い肉体と肉体が闘う競技であり異色の魅力を持つことも事実。《ケイリン》は、別物であっても《競輪》をもとにしたトラック競技であり、そのきっかけは競輪のレジェンド中野浩一が世界選手権スプリントで10連覇を成し遂げたことがきっかけになったことも事実。
その競輪は、戦後まもない日本の地方財政を助け、戦災復興や公共施設の建設などに貢献した。自転車競技法という法に基づいていて、主催者は地方自治体。。監督官庁は経済産業省で、運営統括は公益財団法人JKAという経産官僚の天下り先。『公営ギャンブル』たるゆえんである。
ルールは、硬直的でいまだに旧態依然としたまま。八百長などの不正防止のために選手は缶詰状態に置かれ、プロ資格取得のための養成所では軍隊か刑務所のような管理と精神教育が行われる。車体も相も変わらぬ鉄製(クロームモリブデン鋼)のフレームが使用されるのは、JKAが定める規格が厳格で固定的だからだ。競技の駆け引きには「ライン」と呼ばれる出身地方毎のグループや先輩後輩などの年齢序列の世界が強く存在する。そのために、あたかも時が止まったようで昭和の香りがぷんぷんと漂う。
競輪というものの実相や、魅力、歴史、社会的な課題や将来性なには、語り尽くせないものがある。著者は「ガーディアン」の日本駐在特派員というジャーナリストであるだけにその取材は広範囲であり膨大な資料探索とインタビューを積み上げているのはさすが。けれども、散漫な記述は何が言いたいのか、何を伝えたいのかがわからない。
一方で、ロンドン大学の日本研究の修士卒というインテリだけに、文化比較論的な日本紹介書になっている。むしろ、競輪の啓蒙書というよりは、競輪という日本独特のギャンブルをネタに外国人の日本異文化論をくすぐるガイジンによるガイジンのための書。だから、日本人がまともに読もうとすると冗長で持って回った表現が鼻につき、視点が散漫でいったい何が言いたいのかわからなくなる。競輪の後進性や閉鎖性を、日本文化論に転化されてはたまらない。
訳文は、そういう原文に忠実なのだろうが、英国人が書いた日本紹介を日本人向けに翻訳するのならもっと工夫があってしかるべきだったのではないだろうか。原著者が日本にいるのだから、思い切ったゴーストライター的な書き下ろしがあってもよかったような気がする。
競輪を知ろうという人には隔靴掻痒だし、ある程度競輪を知った人にはもどかしい。
ジャーナリスティックな取材記事としてはさすがと思わせるところも多い。拾い読みするとすれば、中野浩一へのインタビューやフレームビルダーの話しなど部分的にはたまらなく面白いところもある。
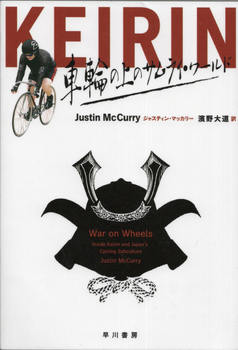
KEIRIN
車輪の上のサムライ・ワールド
ジャスティン・マッカリー (著)
濱野 大道 (翻訳)
早川書房
2023/7/19 新刊
リチャード・トネッティ&オーストラリア室内管弦楽団 [コンサート]
一度は聴いてみたいと思っていました。プログラムが編曲ものだけなので、ちょっと躊躇しましたが思い切って足を運びました。そのプログラムがかえって面白くとてもよい体験になりました。
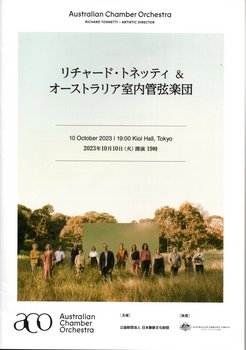
《室内管弦楽団》(“Chamber Orchestra”)と称していますが、正規団員は17人。すべて弦楽器奏者です。演目は弦楽合奏に限っているわけではありませんが、実際はストリングオーケストラというのに近い。
少人数の固定メンバーということもあってその結束力は親密で固い。それがアンサンブルの自由で開放的な雰囲気に現れているような気がします。個人の極めて高い音楽性と技術が、一段高いところにある音楽的統一性のもとに自発的なアンサンブルを形成している。リチャード・トネッティという卓抜した才能が率いているものの、個々の団員は対等であり指揮者は置いていません。

そのメンバーがプログラムに紹介してあります。
顔写真とともに、それぞれの楽器がクレジットされている。いずれも古今の名器ぞろい。楽器名をこうやって明記しているところにこのアンサンブルのプライドを感じさせます。
プログラムを一貫するテーマは《クロイツェル・ソナタ》。
一曲目のヤナーチェクの弦楽四重奏曲からの編曲。正直言って、これは当初の懸念が当たったかな…と思いました。原曲は飛びきりの名曲で、聴く機会も多い。特に近年、若く勢いのある四重奏団がこぞって取り上げる曲。むしろ、一本一本の個の筋が透徹している音色や響きが失われる合奏では不満が残ります。
二曲目は、そのヤナーチェクに学んだハース。同じように弦楽四重奏曲からの編曲なのですが、これは面白かった。初めて聴くので原曲を知らないということもあるのでしょうか。演奏からは、これが四声からの編曲だとは信じられないような多彩で変化と機知に富んだ曲となっています。モラヴィアという出自にとどまらず、様々な中欧の自然の息吹とともに新大陸の都会のさざめきや近現代の人工物の模倣的擬音がラプソディ的に自由に展開する――楽しいひとときでした。
ハースの悲劇は、プログラムを読んで知りましたが、若い頃に作曲されたこの曲にはそんなものは微塵も感じられません。ナチズムの台頭と戦争が突然にこの作曲家の運命を一変させたのです。国外に逃れようとしましたがそれを阻まれて強制収容所へ送られガス室で命を落とすことになります。このコスモポリタンな曲に秘められた悲劇を知ることは大事な側面だと思います。

休憩後の《クロイツェル・ソナタ》。
トネッティの編曲は、2000年にイヴリー・ギトリスを客演に迎えた際に初演されたもの。ヴァイオリンとピアノが丁々発止と渡り合う原曲を、ヴァイオリン協奏曲風にアレンジしています。今回、ソロを演じるのはもちろんトネッティ自身です。
ピアノを弦楽オーケストラに置き換えるわけですが、そのアンサンブルには巧妙な彫たくが施され、ソロあり、弦楽四重奏ありで変幻自在。古典的な弦五部でもなく、もちろんバロックの合奏協奏曲でもない独特の響きから生まれる独創的なソロ・コンチェルト。とにもかくにも、この弦楽オーケストラの自発的で才気渙発なこと。ピアノではなく同質の音色によるオーケストラだからこそ現れる、モチーフのフレッシュなやり取りや、ソロに押しては引き、泡立ち渦巻くように呑み込んでいく波のような音響の動きに煽られること煽られること。
どこから湧いて出てきたのだろうというほどに押しかけた外国人の英語でいっぱいの客席が沸きに沸いていました。アンコール曲が秀逸で、やはり弦楽四重奏曲からの編曲なのですが、バーバーの「アダージョ」のように弦楽アンサンブルの蠱惑的な響きの模範的な演奏へと見事に回帰していました。

リチャード・トネッティ&オーストラリア室内管弦楽団
2023年10月10日(火)19:00
東京・四ッ谷 紀尾井ホール
リチャード・トネッティ(リードヴァイオリン)
オーストラリア室内管弦楽団
ヤナーチェク:
弦楽四重奏曲第1番ホ短調《クロイツェル・ソナタ》
(トネッティ編 弦楽オーケストラ版)
ハース:
弦楽四重奏曲第2番《オピチ・ホリから》op.7(トネッティ編 弦楽オーケストラ版)
ベートーヴェン:
ヴァイオリン・ソナタ第9番イ長調 op.47《クロイツェル》(トネッティ編 弦楽オーケストラ版)
(アンコール)
トーマス・アデス:
弦楽四重奏曲《アルカディアーナ》op.12より
第6楽章〈O Albion オ・アルビオン〉(弦楽オーケストラ版)
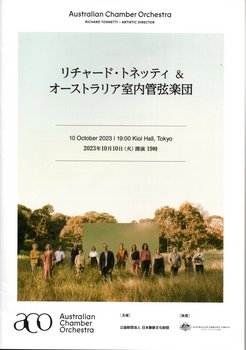
《室内管弦楽団》(“Chamber Orchestra”)と称していますが、正規団員は17人。すべて弦楽器奏者です。演目は弦楽合奏に限っているわけではありませんが、実際はストリングオーケストラというのに近い。
少人数の固定メンバーということもあってその結束力は親密で固い。それがアンサンブルの自由で開放的な雰囲気に現れているような気がします。個人の極めて高い音楽性と技術が、一段高いところにある音楽的統一性のもとに自発的なアンサンブルを形成している。リチャード・トネッティという卓抜した才能が率いているものの、個々の団員は対等であり指揮者は置いていません。

そのメンバーがプログラムに紹介してあります。
顔写真とともに、それぞれの楽器がクレジットされている。いずれも古今の名器ぞろい。楽器名をこうやって明記しているところにこのアンサンブルのプライドを感じさせます。
プログラムを一貫するテーマは《クロイツェル・ソナタ》。
一曲目のヤナーチェクの弦楽四重奏曲からの編曲。正直言って、これは当初の懸念が当たったかな…と思いました。原曲は飛びきりの名曲で、聴く機会も多い。特に近年、若く勢いのある四重奏団がこぞって取り上げる曲。むしろ、一本一本の個の筋が透徹している音色や響きが失われる合奏では不満が残ります。
二曲目は、そのヤナーチェクに学んだハース。同じように弦楽四重奏曲からの編曲なのですが、これは面白かった。初めて聴くので原曲を知らないということもあるのでしょうか。演奏からは、これが四声からの編曲だとは信じられないような多彩で変化と機知に富んだ曲となっています。モラヴィアという出自にとどまらず、様々な中欧の自然の息吹とともに新大陸の都会のさざめきや近現代の人工物の模倣的擬音がラプソディ的に自由に展開する――楽しいひとときでした。
ハースの悲劇は、プログラムを読んで知りましたが、若い頃に作曲されたこの曲にはそんなものは微塵も感じられません。ナチズムの台頭と戦争が突然にこの作曲家の運命を一変させたのです。国外に逃れようとしましたがそれを阻まれて強制収容所へ送られガス室で命を落とすことになります。このコスモポリタンな曲に秘められた悲劇を知ることは大事な側面だと思います。
休憩後の《クロイツェル・ソナタ》。
トネッティの編曲は、2000年にイヴリー・ギトリスを客演に迎えた際に初演されたもの。ヴァイオリンとピアノが丁々発止と渡り合う原曲を、ヴァイオリン協奏曲風にアレンジしています。今回、ソロを演じるのはもちろんトネッティ自身です。
ピアノを弦楽オーケストラに置き換えるわけですが、そのアンサンブルには巧妙な彫たくが施され、ソロあり、弦楽四重奏ありで変幻自在。古典的な弦五部でもなく、もちろんバロックの合奏協奏曲でもない独特の響きから生まれる独創的なソロ・コンチェルト。とにもかくにも、この弦楽オーケストラの自発的で才気渙発なこと。ピアノではなく同質の音色によるオーケストラだからこそ現れる、モチーフのフレッシュなやり取りや、ソロに押しては引き、泡立ち渦巻くように呑み込んでいく波のような音響の動きに煽られること煽られること。
どこから湧いて出てきたのだろうというほどに押しかけた外国人の英語でいっぱいの客席が沸きに沸いていました。アンコール曲が秀逸で、やはり弦楽四重奏曲からの編曲なのですが、バーバーの「アダージョ」のように弦楽アンサンブルの蠱惑的な響きの模範的な演奏へと見事に回帰していました。

リチャード・トネッティ&オーストラリア室内管弦楽団
2023年10月10日(火)19:00
東京・四ッ谷 紀尾井ホール
リチャード・トネッティ(リードヴァイオリン)
オーストラリア室内管弦楽団
ヤナーチェク:
弦楽四重奏曲第1番ホ短調《クロイツェル・ソナタ》
(トネッティ編 弦楽オーケストラ版)
ハース:
弦楽四重奏曲第2番《オピチ・ホリから》op.7(トネッティ編 弦楽オーケストラ版)
ベートーヴェン:
ヴァイオリン・ソナタ第9番イ長調 op.47《クロイツェル》(トネッティ編 弦楽オーケストラ版)
(アンコール)
トーマス・アデス:
弦楽四重奏曲《アルカディアーナ》op.12より
第6楽章〈O Albion オ・アルビオン〉(弦楽オーケストラ版)



