「重力のからくり」(山田 克哉 著)読了 [読書]
高校生の頃、こういう科学本が好きでよく読んでいました。
家にあったアイザック・アシモフの相対性理論の入門書とか、リチャード・ファインマンの回顧録『ご冗談でしょう、ファインマンさん』とかがきっかけでした。あの頃は、やっぱりアインシュタインの相対性理論や量子力学の解説本が大流行で各出版社もシリーズものを競っていました。わかった気になって同級生と得意げに話しをしたところで、肝心の物理や数学の成績はさっぱりでした。
その当時から不思議でならなかったのが「重力」のこと。
重さ(重力質量)と慣性質量とは、別物だといいます。それがモノの質量として一致するということ。あのガリレオ・ガリレイがピサの斜塔から二つの球体を落下させた、アレです。それは等価原理と呼ばれますが、あくまで「原理」であってなぜ一致するのかは、結局は説明できないそうです。
その「原理」を原理であるということから生まれたのがアインシュタインの一般相対性理論なんだとか。ははあ?そうだったのかと今さらながら知りました。
しかしながらほぼ同時代に登場したのが量子論の世界です。
こちらは様々な面で、万有引力とは違うものでした。まず、ごくごく弱い力の万有引力と違って電磁力や素粒子相互の力は強い。万有引力は互いに引き合う力だけですが、電磁力や素粒子相互の力は、引力も排斥力もある対称性の世界です。こうした量子論の世界も、ニュートンの動力学に続けて丁寧に説明してくれます。
その行き着くところは、「相対論」と「量子論」を統一的に説明ができる理論があるのか?ということ。今のところはまったく解決の途が開けない。それでも科学者はそういう未知の世界に挑み続けているというわけです。
なぜ相容れないのか??
それは、「相対論」は連続の世界であり、極小のゼロを想定しているのに対して、「量子論」は不連続の世界であり、極小には値があってゼロではないからです。そのことを示したのがハイゼンベルクの「不確定性原理」。それは素粒子的微小の世界では、「位置」と「運動量」が互いに対になっていること。同様に「エネルギー」と「時間」も対になっている。一方を正確に測定しようとすればするほど、もう一方の値はあやふやで不正確になってしまう。それはミクロの世界では「粒子と波動との二重性」が存在するからです。そういう対のものの「あやふやさ」の幅の積は、極めてゼロに近いながら一定の値を持っているということになります。
まあ、個人的な勝手な例えですが、アナログとデジタルとの対立みたいなものです。オーディオマニアの間には、アナログ派とデジタル派が二分していて双方の主張はなかなか相容れません。…そういうことかな?(笑)
読んでみて、また相対性理論とか量子力学のことを知り直してみたいと思いました。著者は、このブルーバックスにいくつもの著書があります。『読者に必ず理解してもらう』という意欲にあふれた熱い筆致で人気の著者のひとりなのだとか。他の著書も読んでみたくなりました。

重力のからくり
相対論と量子論はなぜ「相容れない」のか
山田 克哉 (著)
ブルーバックス
講談社
2023年8月20日 初版
家にあったアイザック・アシモフの相対性理論の入門書とか、リチャード・ファインマンの回顧録『ご冗談でしょう、ファインマンさん』とかがきっかけでした。あの頃は、やっぱりアインシュタインの相対性理論や量子力学の解説本が大流行で各出版社もシリーズものを競っていました。わかった気になって同級生と得意げに話しをしたところで、肝心の物理や数学の成績はさっぱりでした。
その当時から不思議でならなかったのが「重力」のこと。
重さ(重力質量)と慣性質量とは、別物だといいます。それがモノの質量として一致するということ。あのガリレオ・ガリレイがピサの斜塔から二つの球体を落下させた、アレです。それは等価原理と呼ばれますが、あくまで「原理」であってなぜ一致するのかは、結局は説明できないそうです。
その「原理」を原理であるということから生まれたのがアインシュタインの一般相対性理論なんだとか。ははあ?そうだったのかと今さらながら知りました。
しかしながらほぼ同時代に登場したのが量子論の世界です。
こちらは様々な面で、万有引力とは違うものでした。まず、ごくごく弱い力の万有引力と違って電磁力や素粒子相互の力は強い。万有引力は互いに引き合う力だけですが、電磁力や素粒子相互の力は、引力も排斥力もある対称性の世界です。こうした量子論の世界も、ニュートンの動力学に続けて丁寧に説明してくれます。
その行き着くところは、「相対論」と「量子論」を統一的に説明ができる理論があるのか?ということ。今のところはまったく解決の途が開けない。それでも科学者はそういう未知の世界に挑み続けているというわけです。
なぜ相容れないのか??
それは、「相対論」は連続の世界であり、極小のゼロを想定しているのに対して、「量子論」は不連続の世界であり、極小には値があってゼロではないからです。そのことを示したのがハイゼンベルクの「不確定性原理」。それは素粒子的微小の世界では、「位置」と「運動量」が互いに対になっていること。同様に「エネルギー」と「時間」も対になっている。一方を正確に測定しようとすればするほど、もう一方の値はあやふやで不正確になってしまう。それはミクロの世界では「粒子と波動との二重性」が存在するからです。そういう対のものの「あやふやさ」の幅の積は、極めてゼロに近いながら一定の値を持っているということになります。
まあ、個人的な勝手な例えですが、アナログとデジタルとの対立みたいなものです。オーディオマニアの間には、アナログ派とデジタル派が二分していて双方の主張はなかなか相容れません。…そういうことかな?(笑)
読んでみて、また相対性理論とか量子力学のことを知り直してみたいと思いました。著者は、このブルーバックスにいくつもの著書があります。『読者に必ず理解してもらう』という意欲にあふれた熱い筆致で人気の著者のひとりなのだとか。他の著書も読んでみたくなりました。

重力のからくり
相対論と量子論はなぜ「相容れない」のか
山田 克哉 (著)
ブルーバックス
講談社
2023年8月20日 初版
「二十世紀のクラシック音楽を取り戻す」(ジョン・マウチェリ 著)読了 [読書]
私たちクラシック音楽ファンは、21世紀の今を生きています。
ところが聴いている音楽のほとんどが19世紀以前の音楽です。クラシック音楽というのはそういうものなのでしょうか?20世紀のある時点で、巨大隕石の落下で突然滅んだ恐竜のように、クラシック音楽の伝統は途絶えてしまったのでしょうか?
1999年、20世紀最後の年、アバドが指揮するベルリン・フィルのニューイヤーズイヴ・コンサートでは、1911年以降に書かれた曲はいっさい取り上げられませんでした。
本書は、20世紀にクラシック音楽と呼ばれるヨーロッパ正統音楽に何が起こったのか?、なぜそれは消滅したのか?という謎を解き明かし、改めてこの世紀の正統音楽――いわゆる「現代音楽」と呼ばれる音楽――の探索へと私たちを誘ってくれます。
その大きなカギとなるのは世界中を巻き込んだ二つの大戦のことです。
ナチスドイツが席巻したヨーロッパから幾多の将来を嘱望されていた音楽家が命を落とし、国を追われました。そのほとんどがユダヤ系の人々だった。国を失ったそうした音楽家のほとんどがアメリカへ逃れ、そこで余生を送った。
そういうことは今までも言われてきました。著者は、戦争はそこで終わっていないといいます。「冷戦」の勃発のことです。東西対立のなかで、音楽は国家の威信をかけた政治の道具と化したのです。
冷戦によって、欧米各国を東西に二分して対立した。スターリンの国家は、ナチと同じようにいわゆる「前衛音楽」を退廃音楽として嫌い弾圧し続けました。ソ連で奨励されたのは調性音楽で、大衆に理解しやすい聴きやすい音楽。一方で、これに対立するように西側の欧米各国では前衛音楽ばかりが生き残った。ファシズムに与しなかったという免罪符も手にしていた前衛音楽家たちは、本来の反体制・反主流から、一転して体制お墨付きの主流となって音楽界に君臨し、調性音楽を旧体制の反動的芸術として排撃する。ミラノのスカラ座の演目からは、ムッソリーニが政権掌握した1921年以後のイタリアオペラ作品は抹消されてしまいました。ファシズム時代の直前に病死して、そういう災禍を免れたプッチーニの絶筆「トゥランドット」以後の作品は再演されることがないのです。
こうして西側では大衆の支持を得ない「前衛」ばかりがはびこって廃品の山を築く。
20世紀の音楽史として、もうひとつの画期的な事件は、トーキー映画が誕生し巨大産業へと成長していったことです。
ウィーン楽界で神童ともてはやされたコルンゴルトは、ナチのオーストリー併合によりアメリカに逃れます。彼は、その後、ハリウッドで映画音楽の創生と輝かしい発展に貢献しますが、正統音楽からは抹殺されてしまう。実は、ハリウウドの映画音楽界こそ、シェーンベルクやヒンデミットなどを師と仰ぐ俊才たちの活躍の場となったのです。
劇中の人物や事象を象徴するライトモチーフ、劇中の人物の動作や表情と同期する音楽が、劇の進行に伴って際限なく続いていく。――そういう音楽こそがワーグナーの楽劇の本質であって、それを受け継いだのがコルンゴルトであり、ハリウッドの俊英たちだった。それを正統の「現代音楽」と認めず、無視したのは東西対立の政治的芸術観であり、ファシズム時代を生き抜いた「前衛音楽家」や気位の高い批評家たちだったというわけです。
二十世紀最後のニューイヤーズイヴから23年の時を経た、2022年のコンサートを指揮したのは、キリル・ペトレンコ。ゲストは人気絶頂のテノール、ヨナス・カウフマンでした。そこで演奏されたのは、映画音楽の大家ニーノ・ロータ。映画「道」をもとにした組曲の演奏に続いて、カウフマンは映画「ゴッドファーザー」の「愛のテーマ」をイタリア語で絶唱しました。
ウィーン・フィルも、90歳を超えた大家ジョン・ウィリアムズを迎えて「スターウォーズ」からの名曲コンサートで大いに盛り上がっています。クラシック音楽正統の「現代音楽」は、著者のいう通りにその失地を回復しつつあるのです。
本書で標的になっているの「前衛の旗手」ピエール・ブーレーズだけではありません。え?と驚くような暴言・失言もいろいろ暴露されていてちょっと危ないところもありますが、クラシック音楽通にとってはたまらないエピソードも満載。
音楽ファンにはぜひ読んでもらいたい一冊です。
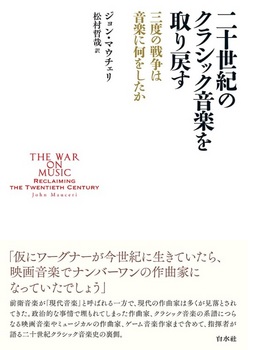
二十世紀のクラシック音楽を取り戻す
三度の戦争は音楽に何をしたか
ジョン・マウチェリ (著), 松村 哲哉 (翻訳)
白水社
2023/8/10 初刊
原題:The War on Music: Reclaiming the Twentieth Century
ところが聴いている音楽のほとんどが19世紀以前の音楽です。クラシック音楽というのはそういうものなのでしょうか?20世紀のある時点で、巨大隕石の落下で突然滅んだ恐竜のように、クラシック音楽の伝統は途絶えてしまったのでしょうか?
1999年、20世紀最後の年、アバドが指揮するベルリン・フィルのニューイヤーズイヴ・コンサートでは、1911年以降に書かれた曲はいっさい取り上げられませんでした。
本書は、20世紀にクラシック音楽と呼ばれるヨーロッパ正統音楽に何が起こったのか?、なぜそれは消滅したのか?という謎を解き明かし、改めてこの世紀の正統音楽――いわゆる「現代音楽」と呼ばれる音楽――の探索へと私たちを誘ってくれます。
その大きなカギとなるのは世界中を巻き込んだ二つの大戦のことです。
ナチスドイツが席巻したヨーロッパから幾多の将来を嘱望されていた音楽家が命を落とし、国を追われました。そのほとんどがユダヤ系の人々だった。国を失ったそうした音楽家のほとんどがアメリカへ逃れ、そこで余生を送った。
そういうことは今までも言われてきました。著者は、戦争はそこで終わっていないといいます。「冷戦」の勃発のことです。東西対立のなかで、音楽は国家の威信をかけた政治の道具と化したのです。
冷戦によって、欧米各国を東西に二分して対立した。スターリンの国家は、ナチと同じようにいわゆる「前衛音楽」を退廃音楽として嫌い弾圧し続けました。ソ連で奨励されたのは調性音楽で、大衆に理解しやすい聴きやすい音楽。一方で、これに対立するように西側の欧米各国では前衛音楽ばかりが生き残った。ファシズムに与しなかったという免罪符も手にしていた前衛音楽家たちは、本来の反体制・反主流から、一転して体制お墨付きの主流となって音楽界に君臨し、調性音楽を旧体制の反動的芸術として排撃する。ミラノのスカラ座の演目からは、ムッソリーニが政権掌握した1921年以後のイタリアオペラ作品は抹消されてしまいました。ファシズム時代の直前に病死して、そういう災禍を免れたプッチーニの絶筆「トゥランドット」以後の作品は再演されることがないのです。
こうして西側では大衆の支持を得ない「前衛」ばかりがはびこって廃品の山を築く。
20世紀の音楽史として、もうひとつの画期的な事件は、トーキー映画が誕生し巨大産業へと成長していったことです。
ウィーン楽界で神童ともてはやされたコルンゴルトは、ナチのオーストリー併合によりアメリカに逃れます。彼は、その後、ハリウッドで映画音楽の創生と輝かしい発展に貢献しますが、正統音楽からは抹殺されてしまう。実は、ハリウウドの映画音楽界こそ、シェーンベルクやヒンデミットなどを師と仰ぐ俊才たちの活躍の場となったのです。
劇中の人物や事象を象徴するライトモチーフ、劇中の人物の動作や表情と同期する音楽が、劇の進行に伴って際限なく続いていく。――そういう音楽こそがワーグナーの楽劇の本質であって、それを受け継いだのがコルンゴルトであり、ハリウッドの俊英たちだった。それを正統の「現代音楽」と認めず、無視したのは東西対立の政治的芸術観であり、ファシズム時代を生き抜いた「前衛音楽家」や気位の高い批評家たちだったというわけです。
二十世紀最後のニューイヤーズイヴから23年の時を経た、2022年のコンサートを指揮したのは、キリル・ペトレンコ。ゲストは人気絶頂のテノール、ヨナス・カウフマンでした。そこで演奏されたのは、映画音楽の大家ニーノ・ロータ。映画「道」をもとにした組曲の演奏に続いて、カウフマンは映画「ゴッドファーザー」の「愛のテーマ」をイタリア語で絶唱しました。
ウィーン・フィルも、90歳を超えた大家ジョン・ウィリアムズを迎えて「スターウォーズ」からの名曲コンサートで大いに盛り上がっています。クラシック音楽正統の「現代音楽」は、著者のいう通りにその失地を回復しつつあるのです。
本書で標的になっているの「前衛の旗手」ピエール・ブーレーズだけではありません。え?と驚くような暴言・失言もいろいろ暴露されていてちょっと危ないところもありますが、クラシック音楽通にとってはたまらないエピソードも満載。
音楽ファンにはぜひ読んでもらいたい一冊です。
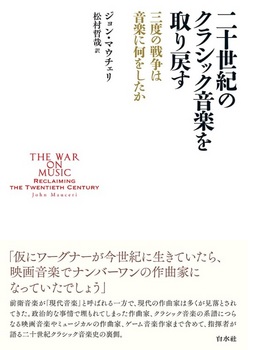
二十世紀のクラシック音楽を取り戻す
三度の戦争は音楽に何をしたか
ジョン・マウチェリ (著), 松村 哲哉 (翻訳)
白水社
2023/8/10 初刊
原題:The War on Music: Reclaiming the Twentieth Century
タグ:現代音楽



