「ペレアスとメリザンド」 (新国立劇場) [コンサート]
五感が融合し統合された「意識」のオペラ。
音楽と演劇、美術が見事に協調し、人間の知覚知能や思考の多層的な深部に分け入っていく。そこから得られる幻想は、どこに真実があるのかも不明で多義的。そのことにオペラという五感の芸術の醍醐味、楽しさを感じさせてくれます。

ドビュッシーの音楽とメーテルリンクの言語には、もともとそういう神秘世界があったのだと思います。そこに演出のケイティ・ミッチェルがさっそうと踏み込んでいく。
オペラ全体は、メリザンドの夢だと想定されています。ウェディングドレスのメリザンドがホテルの一室に登場しくつろぐ。そのメリザンドが夢想する。そこから始まり、終幕にはまたその場面に戻る。まさに一炊の夢。《夢》とは、人間の意識内のあたかも現実の経験であるかのように感じる、一連の幻影。それが夢だとは、夢を見ているうちは気づきませんが、醒めてみると自分が自分を見ていたような、劇中劇――《入れ子》の世界です。
黙り役という別のメリザンドも登場します。
岩波文庫の「対訳 ペレアスとメリザンド」の訳者・杉本秀太郎氏は、解説で『…舞台にかかっているとき、その舞台をしげしげと見守っているペレアス、そしてメリザンドが、客席に紛れている。』『かれらが声もなく坐り、私と同じ方向に視線を放っている。』――そんな情景が見えてくると書いています。
この一致には驚きました。これは偶然でしょうか。この演出では、もう一人のメリザンドはステージ上に限られますが、ペレアスやゴローも本来登場しない場面にもいつの間にか現れてじっと見つめていたり、あるいはメリザンドと絡んだりしたりさえします。そういう「意識」世界の人格の多重性、裏切りとも思えるほどの意識人格の投影反射の繰り返しがメーテルリンクの台本には確かに存在します。
黙り役としては、他にも二人の侍女が登場します。
こちらは、メリザンドの着替え役。棒のように無人格になったメリザンドから衣装をするりと脱がし、下着姿にしてから再びするすると新しい別の衣装を着せる。無人格なメリザンドを操る、黒衣や後見のような役どころは、これも夢という無自覚で他動的な意識の遷移・転移を象徴しています。
歌舞伎の《だんまり》のようにスローモーションになる場面もあります。意識世界における時間軸の伸縮と相対性を現す効果もあり、同時にドビュッシーの音楽の時間軸との同調もあって見事。ケイティ・ミッチェルの音楽の深い読み込みがあればこそ。これも、オペラとして斬新な演出です。
音楽が素晴らしい。
ドビュッシーの音楽は、アリアだとかバレー音楽だとか聴衆におもねった分断がない。ずっと舞台の進行に寄り添って間断なく続いていく。ともすれば無形式なつかみどころのない音楽になりがち。あるいは、いっそ演奏会形式で舞台や演技に向けられる視覚をカットさせないと音楽に集中できない。そういう難しさのあるこの作品が、この演出では見事に視覚と相乗作用を起こす。その音楽の綾の蠱惑的なこと。
ことに《水》のイメージが素晴らしく、庭園の泉(この演出では室内プール)の清新な水のゆらめきと濃緑色に沈む奥底、湿潤な空気感など、音楽を通じて視覚・聴覚以外の五感までもが励起される。
舞台上の水は控えめ。プールの水面は一階席から見えないがさざなみのゆらめきが壁面に映り込む。指環が不意に水に落ちても、あくまでもその雰囲気は音楽にある。繊細で緻密な演出が音楽と協調する。洞窟(演出では地下室)の場面など、「海(“la mer”)」という言葉が発せられるとオーケストラからはあの聴き慣れた交響詩の響きが現れる。それがそう確かに聞こえることに感動を覚えました。
塔の場面も、極めて官能的。現実として長い髪がみるみる伸びて塔の下まで届くというのはあり得ず、あくまでも暗喩だ。「暗闇に、薔薇が見える」「ずっと低いところ」「薔薇なんかじゃない…ちょっと見てこよう」――卑猥な戯れ歌とも取られかねないかもしれないが、それを言葉のままに映像化すればもっと陳腐になる。ドビュッシーの官能性は凄みがありました。
ペレアスとメリザンドが睦み合っているところに、誰かに見られているという不吉な予感の響きがどこからともなく湧き上がる。プールの破れた窓から突然現れるゴローはまるで、ホラー映画『リング』の貞子みたいで震え上がるが、その時に音楽の不吉さは絶頂を迎える。

大野和士は、素晴らしい創造性とリーダーシップで東フィルからそういうドビュッシーの音楽を引き出していた。間断なく続く音楽だからこそ、幕間の転換を待つ沈黙の間合いが活きている。ここにもステージ上の映像とピットの音楽との見事な相乗作用があります。それは、そもそも冒頭の花嫁とホテルの一室の場面で、じっと沈黙して待っていた大野の姿に象徴されています。そういう余白にも神経が行き届いていました。
舞台もよく出来ていた。

全体は二部に分けての上演ですが、場や幕の転換もなめらかで、しかも、夢幻的。箱型の部分ステージを黒い横幕で開閉して、移動転換するというアイデアは初めて見ました。横や上下の移動も視覚意識の遷移にぴったりとはまっています。何よりも音響的にも実によく配慮されたステージです。左手にしばしば登場するらせん階段の縦長のステアケースもよく考えられたアイデア。
何よりも称えたいのは歌手陣。
主役級の3人はいずれもこの役を得意としアクサンプロヴァンスの初演や、その後のこのプロダクションの公演に参加経験があると聞いています。素晴らしい歌唱とともにとてつもなくタフに見える演技を、最後まで緊張感を切らさずに信じられないほど緻密にやりきっている。

性格演技という面では、ゴロー役のローラン・ナウリが出色。粗暴などという表面的なものではなく、深層感情の制御を失った自意識の悲劇を演じて凄みを感じます。日本人歌手がオペラ全体によくはまり、外国人歌手と対等に渡り合っていたことも特筆したいと思います。ベテランの妻屋秀和のアルケルはさすが。イニョルドの九嶋香奈枝は、メゾであれボーイソプラノであれ演技・歌唱がはまりにくいこの役から、オペラ全体のキーとなるメッセージを発しきるところまで到達していて強い印象を受けました。

これだけ完成度の高いプロダクションは、新国立劇場でも久々だと思います。演出補のジル・リコの献身ぶりが大きかったのではないかと思います。コロナ禍を乗り切ったシーズンの掉尾にふさわしい。

新国立劇場
クロード・ドビュッシー 「ペレアスとメリザンド」
2022年7月9日 14:00
東京・初台 新国立劇場 オペラハウス
(1階5列10番)
【指 揮】大野和士
【演 出】ケイティ・ミッチェル
【美 術】リジー・クラッチャン
【衣 裳】クロエ・ランフォード
【照 明】ジェイムズ・ファーンコム
【振 付】ジョセフ・アルフォード
【演出補】ジル・リコ
【舞台監督】髙橋尚史
【ペレアス】ベルナール・リヒター
【メリザンド】カレン・ヴルシュ
【ゴロー】ロラン・ナウリ
【アルケル】妻屋秀和
【ジュヌヴィエーヴ】浜田理恵
【イニョルド】九嶋香奈枝
【医師】河野鉄平
【合唱指揮】冨平恭平
【合 唱】新国立劇場合唱団
【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団
音楽と演劇、美術が見事に協調し、人間の知覚知能や思考の多層的な深部に分け入っていく。そこから得られる幻想は、どこに真実があるのかも不明で多義的。そのことにオペラという五感の芸術の醍醐味、楽しさを感じさせてくれます。
ドビュッシーの音楽とメーテルリンクの言語には、もともとそういう神秘世界があったのだと思います。そこに演出のケイティ・ミッチェルがさっそうと踏み込んでいく。
オペラ全体は、メリザンドの夢だと想定されています。ウェディングドレスのメリザンドがホテルの一室に登場しくつろぐ。そのメリザンドが夢想する。そこから始まり、終幕にはまたその場面に戻る。まさに一炊の夢。《夢》とは、人間の意識内のあたかも現実の経験であるかのように感じる、一連の幻影。それが夢だとは、夢を見ているうちは気づきませんが、醒めてみると自分が自分を見ていたような、劇中劇――《入れ子》の世界です。
黙り役という別のメリザンドも登場します。
岩波文庫の「対訳 ペレアスとメリザンド」の訳者・杉本秀太郎氏は、解説で『…舞台にかかっているとき、その舞台をしげしげと見守っているペレアス、そしてメリザンドが、客席に紛れている。』『かれらが声もなく坐り、私と同じ方向に視線を放っている。』――そんな情景が見えてくると書いています。
この一致には驚きました。これは偶然でしょうか。この演出では、もう一人のメリザンドはステージ上に限られますが、ペレアスやゴローも本来登場しない場面にもいつの間にか現れてじっと見つめていたり、あるいはメリザンドと絡んだりしたりさえします。そういう「意識」世界の人格の多重性、裏切りとも思えるほどの意識人格の投影反射の繰り返しがメーテルリンクの台本には確かに存在します。
黙り役としては、他にも二人の侍女が登場します。
こちらは、メリザンドの着替え役。棒のように無人格になったメリザンドから衣装をするりと脱がし、下着姿にしてから再びするすると新しい別の衣装を着せる。無人格なメリザンドを操る、黒衣や後見のような役どころは、これも夢という無自覚で他動的な意識の遷移・転移を象徴しています。
歌舞伎の《だんまり》のようにスローモーションになる場面もあります。意識世界における時間軸の伸縮と相対性を現す効果もあり、同時にドビュッシーの音楽の時間軸との同調もあって見事。ケイティ・ミッチェルの音楽の深い読み込みがあればこそ。これも、オペラとして斬新な演出です。
音楽が素晴らしい。
ドビュッシーの音楽は、アリアだとかバレー音楽だとか聴衆におもねった分断がない。ずっと舞台の進行に寄り添って間断なく続いていく。ともすれば無形式なつかみどころのない音楽になりがち。あるいは、いっそ演奏会形式で舞台や演技に向けられる視覚をカットさせないと音楽に集中できない。そういう難しさのあるこの作品が、この演出では見事に視覚と相乗作用を起こす。その音楽の綾の蠱惑的なこと。
ことに《水》のイメージが素晴らしく、庭園の泉(この演出では室内プール)の清新な水のゆらめきと濃緑色に沈む奥底、湿潤な空気感など、音楽を通じて視覚・聴覚以外の五感までもが励起される。
舞台上の水は控えめ。プールの水面は一階席から見えないがさざなみのゆらめきが壁面に映り込む。指環が不意に水に落ちても、あくまでもその雰囲気は音楽にある。繊細で緻密な演出が音楽と協調する。洞窟(演出では地下室)の場面など、「海(“la mer”)」という言葉が発せられるとオーケストラからはあの聴き慣れた交響詩の響きが現れる。それがそう確かに聞こえることに感動を覚えました。
塔の場面も、極めて官能的。現実として長い髪がみるみる伸びて塔の下まで届くというのはあり得ず、あくまでも暗喩だ。「暗闇に、薔薇が見える」「ずっと低いところ」「薔薇なんかじゃない…ちょっと見てこよう」――卑猥な戯れ歌とも取られかねないかもしれないが、それを言葉のままに映像化すればもっと陳腐になる。ドビュッシーの官能性は凄みがありました。
ペレアスとメリザンドが睦み合っているところに、誰かに見られているという不吉な予感の響きがどこからともなく湧き上がる。プールの破れた窓から突然現れるゴローはまるで、ホラー映画『リング』の貞子みたいで震え上がるが、その時に音楽の不吉さは絶頂を迎える。
大野和士は、素晴らしい創造性とリーダーシップで東フィルからそういうドビュッシーの音楽を引き出していた。間断なく続く音楽だからこそ、幕間の転換を待つ沈黙の間合いが活きている。ここにもステージ上の映像とピットの音楽との見事な相乗作用があります。それは、そもそも冒頭の花嫁とホテルの一室の場面で、じっと沈黙して待っていた大野の姿に象徴されています。そういう余白にも神経が行き届いていました。
舞台もよく出来ていた。

全体は二部に分けての上演ですが、場や幕の転換もなめらかで、しかも、夢幻的。箱型の部分ステージを黒い横幕で開閉して、移動転換するというアイデアは初めて見ました。横や上下の移動も視覚意識の遷移にぴったりとはまっています。何よりも音響的にも実によく配慮されたステージです。左手にしばしば登場するらせん階段の縦長のステアケースもよく考えられたアイデア。
何よりも称えたいのは歌手陣。
主役級の3人はいずれもこの役を得意としアクサンプロヴァンスの初演や、その後のこのプロダクションの公演に参加経験があると聞いています。素晴らしい歌唱とともにとてつもなくタフに見える演技を、最後まで緊張感を切らさずに信じられないほど緻密にやりきっている。

性格演技という面では、ゴロー役のローラン・ナウリが出色。粗暴などという表面的なものではなく、深層感情の制御を失った自意識の悲劇を演じて凄みを感じます。日本人歌手がオペラ全体によくはまり、外国人歌手と対等に渡り合っていたことも特筆したいと思います。ベテランの妻屋秀和のアルケルはさすが。イニョルドの九嶋香奈枝は、メゾであれボーイソプラノであれ演技・歌唱がはまりにくいこの役から、オペラ全体のキーとなるメッセージを発しきるところまで到達していて強い印象を受けました。

これだけ完成度の高いプロダクションは、新国立劇場でも久々だと思います。演出補のジル・リコの献身ぶりが大きかったのではないかと思います。コロナ禍を乗り切ったシーズンの掉尾にふさわしい。

新国立劇場
クロード・ドビュッシー 「ペレアスとメリザンド」
2022年7月9日 14:00
東京・初台 新国立劇場 オペラハウス
(1階5列10番)
【指 揮】大野和士
【演 出】ケイティ・ミッチェル
【美 術】リジー・クラッチャン
【衣 裳】クロエ・ランフォード
【照 明】ジェイムズ・ファーンコム
【振 付】ジョセフ・アルフォード
【演出補】ジル・リコ
【舞台監督】髙橋尚史
【ペレアス】ベルナール・リヒター
【メリザンド】カレン・ヴルシュ
【ゴロー】ロラン・ナウリ
【アルケル】妻屋秀和
【ジュヌヴィエーヴ】浜田理恵
【イニョルド】九嶋香奈枝
【医師】河野鉄平
【合唱指揮】冨平恭平
【合 唱】新国立劇場合唱団
【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団
バベルの塔 (Harubaru邸訪問記) [オーディオ]
Harubaruさんのお宅を訪問しました。 そこで目にしたのは…  天にも届く神の領域にまで手を伸ばそうという、あのバベルの塔。 いや、神話のことではなく、ジークレフ音響から新たに登場した「バベル」のこと。
天にも届く神の領域にまで手を伸ばそうという、あのバベルの塔。 いや、神話のことではなく、ジークレフ音響から新たに登場した「バベル」のこと。  「吊り構造」を4層多段、3基点、小型ウェルフロートメカを12機(3機 ×4層)内蔵しているというとんでもない代物。
「吊り構造」を4層多段、3基点、小型ウェルフロートメカを12機(3機 ×4層)内蔵しているというとんでもない代物。  その多段振り子のメカは、重力波の検出にも用いられているとのことで、分子レベルまでの振動を制御するとか。ウェルフロートシリーズの究極のモデル。もはや、インシュレーターとかアクセサリーというジャンルの次元を超えた音響製品です。 訪問前日に前触れのようにあげられた日記では、Harubaruさんはその効果に驚喜、あっという間にお買い上げになったのだとか。 それを、Esoteric K-01にあてがい、そのお披露目の比較試聴という栄誉に浴することになったというわけです。 実際のところ、まさに驚異的なパフォーマンスでした。 比較は、以下のように行われました。 1)Esoteric K-01(+Babel) ディスク再生 2)Esoteric K-01(+Babel) トランスポート → Asoyaji DAC 3)MFPC/FormulaPC(Roon) → Asoyaji DAC
その多段振り子のメカは、重力波の検出にも用いられているとのことで、分子レベルまでの振動を制御するとか。ウェルフロートシリーズの究極のモデル。もはや、インシュレーターとかアクセサリーというジャンルの次元を超えた音響製品です。 訪問前日に前触れのようにあげられた日記では、Harubaruさんはその効果に驚喜、あっという間にお買い上げになったのだとか。 それを、Esoteric K-01にあてがい、そのお披露目の比較試聴という栄誉に浴することになったというわけです。 実際のところ、まさに驚異的なパフォーマンスでした。 比較は、以下のように行われました。 1)Esoteric K-01(+Babel) ディスク再生 2)Esoteric K-01(+Babel) トランスポート → Asoyaji DAC 3)MFPC/FormulaPC(Roon) → Asoyaji DAC  まず最初に一通り1)での試聴です。 以前は、Harubaru邸の基準となっていたK-01です。それは、Asoyaji DACの導入、MFPCの導入からクァッドへの導入進化があっても、その位置づけは変わらなかったのですが、昨年末にお伺いした時に聴かせていただいた時には、MFPC/Asoyaji DACでのファイル再生とはだいぶ差が開いてしまい、もはや聴く気がしなくなったと仰っていたのです。 実際に聴かせていただいた私の印象でも、比較してしまうと薄く平板な印象が否めませんでした。 ところが… 今回はのっけからノックアウト。音が厚く濃くなって印象が一変しました。
まず最初に一通り1)での試聴です。 以前は、Harubaru邸の基準となっていたK-01です。それは、Asoyaji DACの導入、MFPCの導入からクァッドへの導入進化があっても、その位置づけは変わらなかったのですが、昨年末にお伺いした時に聴かせていただいた時には、MFPC/Asoyaji DACでのファイル再生とはだいぶ差が開いてしまい、もはや聴く気がしなくなったと仰っていたのです。 実際に聴かせていただいた私の印象でも、比較してしまうと薄く平板な印象が否めませんでした。 ところが… 今回はのっけからノックアウト。音が厚く濃くなって印象が一変しました。  古い録音(アナログ)のリマスタリングですが、バリトンサックスの太い音が実にリアル。熱気がこちらに伝わってくる。 中音域の厚みとか低音などが一変したというのも大げさではないほどに感じます。Harubaruさんも、「低音が難しい。最も違いがでる。」と。このことはMFPCを聴いたことのある人は共通して仰っています。それは大型のB&W 800D3でも同じ。むしろ、だからこそ、よくわかると言えるのでしょう。 しかも今回は、CDプレーヤーという上流のデジタル機器へのBabelの効果――振動対策の飛躍――がもたらしたものなのです。
古い録音(アナログ)のリマスタリングですが、バリトンサックスの太い音が実にリアル。熱気がこちらに伝わってくる。 中音域の厚みとか低音などが一変したというのも大げさではないほどに感じます。Harubaruさんも、「低音が難しい。最も違いがでる。」と。このことはMFPCを聴いたことのある人は共通して仰っています。それは大型のB&W 800D3でも同じ。むしろ、だからこそ、よくわかると言えるのでしょう。 しかも今回は、CDプレーヤーという上流のデジタル機器へのBabelの効果――振動対策の飛躍――がもたらしたものなのです。  これも同じアナログ音源ですが、クラリネットの音色が鮮度高くとらえられていて、それが焦点ピタリと再生されると胸がすくような爽快感があります。
これも同じアナログ音源ですが、クラリネットの音色が鮮度高くとらえられていて、それが焦点ピタリと再生されると胸がすくような爽快感があります。  パワーアンプは、出川式電源の出川氏とアンプビルダーのN氏とのコラボ。前回訪問でその素晴らしさに感服したアンプです。今回はチョークや手巻抵抗などの電源強化があったそうですが、バベル効果があまりに大きくてよくわかりません(汗)。
パワーアンプは、出川式電源の出川氏とアンプビルダーのN氏とのコラボ。前回訪問でその素晴らしさに感服したアンプです。今回はチョークや手巻抵抗などの電源強化があったそうですが、バベル効果があまりに大きくてよくわかりません(汗)。  2)に切り替えました。 音は明らかに違います。でも… どちらが良いかどうかはなかなか判断がつきません。この違いはDACチップのキャラクターの違いなのでしょうか。 K-01は、かつてのフラッグシップ機ですがもはやディスコン。使用しているのは旭化成 AK4399 という32bit第二世代のチップです。それに対してAsoyaji DACは、最新の4499を搭載。Harubaruさんは、もともとの4495を4497に変更し、最終的には電流出力の4499にまで改造アップグレードされています。Asoyajiさんの大変な労作、まさに遺作と言えるもの。 AK4399(K-01)はとても素直で聴きやすい。対するAK4499(Asoyaji DAC)は、輪郭がはっきりしていてコントラストが明瞭で音像がしっかりしていて、ディテールがよく見えます。そういうDACチップの違いだけが聞こえるというのが実感です。
2)に切り替えました。 音は明らかに違います。でも… どちらが良いかどうかはなかなか判断がつきません。この違いはDACチップのキャラクターの違いなのでしょうか。 K-01は、かつてのフラッグシップ機ですがもはやディスコン。使用しているのは旭化成 AK4399 という32bit第二世代のチップです。それに対してAsoyaji DACは、最新の4499を搭載。Harubaruさんは、もともとの4495を4497に変更し、最終的には電流出力の4499にまで改造アップグレードされています。Asoyajiさんの大変な労作、まさに遺作と言えるもの。 AK4399(K-01)はとても素直で聴きやすい。対するAK4499(Asoyaji DAC)は、輪郭がはっきりしていてコントラストが明瞭で音像がしっかりしていて、ディテールがよく見えます。そういうDACチップの違いだけが聞こえるというのが実感です。  3)に切り替えると… ここでは、やはり2)ではあまり感じなかった情報量の違いを感じます。 K-01の光学読み取りのトランスポートと、MFPC/FormulaPCによるオールデジタルの送り出しの違いが感じ取れるのです。けれども、半年前のように勝負あったというような単純な印象ではありません。K-01なりの良さも感じてしまうのです。Harubaruさんは「ふだんのリラックスして聴くのはK-01に戻ってしまいディスクを聴くことが多くなった」という言葉にも思わずうなずいてしまいます。
3)に切り替えると… ここでは、やはり2)ではあまり感じなかった情報量の違いを感じます。 K-01の光学読み取りのトランスポートと、MFPC/FormulaPCによるオールデジタルの送り出しの違いが感じ取れるのです。けれども、半年前のように勝負あったというような単純な印象ではありません。K-01なりの良さも感じてしまうのです。Harubaruさんは「ふだんのリラックスして聴くのはK-01に戻ってしまいディスクを聴くことが多くなった」という言葉にも思わずうなずいてしまいます。 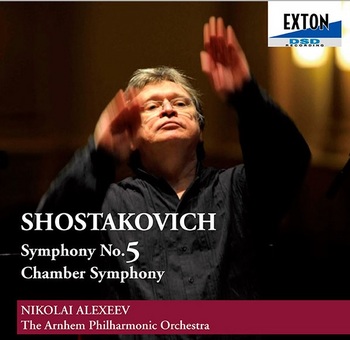 聴かせていただいたものでは、ショスタコーヴィチの5番が印象的でした。 編成規模の小さめの室内オーケストラであることがリアルに体感できる。小さいのにパワフルで音楽的パトスが際立ち、楽器の細やかな質感がリアルで美しい。とても現代的な演奏でありながら、かつてのロシア的演奏の肌合いがけっして失われていない。
聴かせていただいたものでは、ショスタコーヴィチの5番が印象的でした。 編成規模の小さめの室内オーケストラであることがリアルに体感できる。小さいのにパワフルで音楽的パトスが際立ち、楽器の細やかな質感がリアルで美しい。とても現代的な演奏でありながら、かつてのロシア的演奏の肌合いがけっして失われていない。  面白かったのは、ベートーヴェン。 ヴァイオリンを左右に配置する、対抗両翼型で低音弦は中央右手配置。まるでスコアを見るように各パートを浮き立たせていて、それだけに聴き手もそちらのほうに耳立ててしまう。一方で、和声の響きの融和とか深みが感じ取りにくくなってしまう。長らくアニメ音楽などポピュラー音楽的な録音現場とその発想になじんでいる指揮者の注文なのでしょう。かえってそういう録音の作為が見えてしまって音楽が素直に伝わらない。
面白かったのは、ベートーヴェン。 ヴァイオリンを左右に配置する、対抗両翼型で低音弦は中央右手配置。まるでスコアを見るように各パートを浮き立たせていて、それだけに聴き手もそちらのほうに耳立ててしまう。一方で、和声の響きの融和とか深みが感じ取りにくくなってしまう。長らくアニメ音楽などポピュラー音楽的な録音現場とその発想になじんでいる指揮者の注文なのでしょう。かえってそういう録音の作為が見えてしまって音楽が素直に伝わらない。  同じことは、モーツァルトのヴァイオリン・ソナタでも起こりました。 素敵なヴァイオリンなのですが、ピアノも素晴らしい。ところが録音は明らかにヴァイオリンが主役としてクローズアップして、ピアノは背景に遠目にとらえます。思わず「ピアノの音も素敵なのにもったいない…」とつぶやいてしまいました。そういう録音の作為が聞こえてしまいます。
同じことは、モーツァルトのヴァイオリン・ソナタでも起こりました。 素敵なヴァイオリンなのですが、ピアノも素晴らしい。ところが録音は明らかにヴァイオリンが主役としてクローズアップして、ピアノは背景に遠目にとらえます。思わず「ピアノの音も素敵なのにもったいない…」とつぶやいてしまいました。そういう録音の作為が聞こえてしまいます。 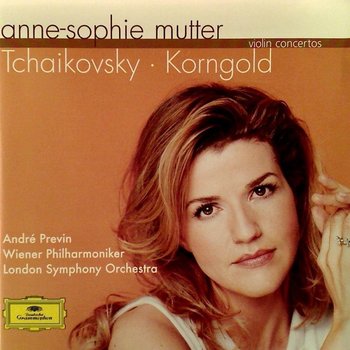 これも聴いてみましょう…と、最後に1)と3)の共通音源でのガチ勝負。 まず3)で聴くと、つい先日、我が家で味わったウィーン・フィルの圧倒的なステージ感と、繊細極まりないムターの美音と豊穣な技巧が目の前に拡がります。 1)にすると、やはり3)に比べるとステージが小さめになります。そのことは我が家の体験でも同じ。ところが気になったのは、3)ではムターのヴァイオリンの線がややぼやっと膨らんでいたこと。1)では、筋が通り音の芯が出ています。そこがまるで別のマスタリングじゃないかと思えるほど。確認すると同じディスクからのリッピングとのこと。 Harubaruさんは、Asoyaji DACにもバベルを当てないと、比較としては公平じゃないのかもしれないと笑っています。どうやら心中には、すでに2台目の塔を思い描いておられるようです。
これも聴いてみましょう…と、最後に1)と3)の共通音源でのガチ勝負。 まず3)で聴くと、つい先日、我が家で味わったウィーン・フィルの圧倒的なステージ感と、繊細極まりないムターの美音と豊穣な技巧が目の前に拡がります。 1)にすると、やはり3)に比べるとステージが小さめになります。そのことは我が家の体験でも同じ。ところが気になったのは、3)ではムターのヴァイオリンの線がややぼやっと膨らんでいたこと。1)では、筋が通り音の芯が出ています。そこがまるで別のマスタリングじゃないかと思えるほど。確認すると同じディスクからのリッピングとのこと。 Harubaruさんは、Asoyaji DACにもバベルを当てないと、比較としては公平じゃないのかもしれないと笑っています。どうやら心中には、すでに2台目の塔を思い描いておられるようです。
 「吊り構造」を4層多段、3基点、小型ウェルフロートメカを12機(3機 ×4層)内蔵しているというとんでもない代物。
「吊り構造」を4層多段、3基点、小型ウェルフロートメカを12機(3機 ×4層)内蔵しているというとんでもない代物。  その多段振り子のメカは、重力波の検出にも用いられているとのことで、分子レベルまでの振動を制御するとか。ウェルフロートシリーズの究極のモデル。もはや、インシュレーターとかアクセサリーというジャンルの次元を超えた音響製品です。 訪問前日に前触れのようにあげられた日記では、Harubaruさんはその効果に驚喜、あっという間にお買い上げになったのだとか。 それを、Esoteric K-01にあてがい、そのお披露目の比較試聴という栄誉に浴することになったというわけです。 実際のところ、まさに驚異的なパフォーマンスでした。 比較は、以下のように行われました。 1)Esoteric K-01(+Babel) ディスク再生 2)Esoteric K-01(+Babel) トランスポート → Asoyaji DAC 3)MFPC/FormulaPC(Roon) → Asoyaji DAC
その多段振り子のメカは、重力波の検出にも用いられているとのことで、分子レベルまでの振動を制御するとか。ウェルフロートシリーズの究極のモデル。もはや、インシュレーターとかアクセサリーというジャンルの次元を超えた音響製品です。 訪問前日に前触れのようにあげられた日記では、Harubaruさんはその効果に驚喜、あっという間にお買い上げになったのだとか。 それを、Esoteric K-01にあてがい、そのお披露目の比較試聴という栄誉に浴することになったというわけです。 実際のところ、まさに驚異的なパフォーマンスでした。 比較は、以下のように行われました。 1)Esoteric K-01(+Babel) ディスク再生 2)Esoteric K-01(+Babel) トランスポート → Asoyaji DAC 3)MFPC/FormulaPC(Roon) → Asoyaji DAC  これも同じアナログ音源ですが、クラリネットの音色が鮮度高くとらえられていて、それが焦点ピタリと再生されると胸がすくような爽快感があります。
これも同じアナログ音源ですが、クラリネットの音色が鮮度高くとらえられていて、それが焦点ピタリと再生されると胸がすくような爽快感があります。 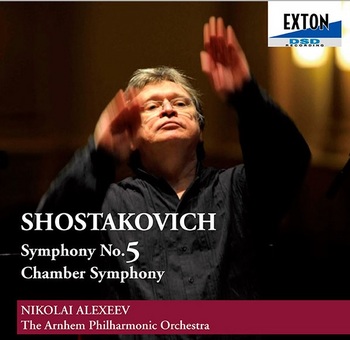 聴かせていただいたものでは、ショスタコーヴィチの5番が印象的でした。 編成規模の小さめの室内オーケストラであることがリアルに体感できる。小さいのにパワフルで音楽的パトスが際立ち、楽器の細やかな質感がリアルで美しい。とても現代的な演奏でありながら、かつてのロシア的演奏の肌合いがけっして失われていない。
聴かせていただいたものでは、ショスタコーヴィチの5番が印象的でした。 編成規模の小さめの室内オーケストラであることがリアルに体感できる。小さいのにパワフルで音楽的パトスが際立ち、楽器の細やかな質感がリアルで美しい。とても現代的な演奏でありながら、かつてのロシア的演奏の肌合いがけっして失われていない。  面白かったのは、ベートーヴェン。 ヴァイオリンを左右に配置する、対抗両翼型で低音弦は中央右手配置。まるでスコアを見るように各パートを浮き立たせていて、それだけに聴き手もそちらのほうに耳立ててしまう。一方で、和声の響きの融和とか深みが感じ取りにくくなってしまう。長らくアニメ音楽などポピュラー音楽的な録音現場とその発想になじんでいる指揮者の注文なのでしょう。かえってそういう録音の作為が見えてしまって音楽が素直に伝わらない。
面白かったのは、ベートーヴェン。 ヴァイオリンを左右に配置する、対抗両翼型で低音弦は中央右手配置。まるでスコアを見るように各パートを浮き立たせていて、それだけに聴き手もそちらのほうに耳立ててしまう。一方で、和声の響きの融和とか深みが感じ取りにくくなってしまう。長らくアニメ音楽などポピュラー音楽的な録音現場とその発想になじんでいる指揮者の注文なのでしょう。かえってそういう録音の作為が見えてしまって音楽が素直に伝わらない。  同じことは、モーツァルトのヴァイオリン・ソナタでも起こりました。 素敵なヴァイオリンなのですが、ピアノも素晴らしい。ところが録音は明らかにヴァイオリンが主役としてクローズアップして、ピアノは背景に遠目にとらえます。思わず「ピアノの音も素敵なのにもったいない…」とつぶやいてしまいました。そういう録音の作為が聞こえてしまいます。
同じことは、モーツァルトのヴァイオリン・ソナタでも起こりました。 素敵なヴァイオリンなのですが、ピアノも素晴らしい。ところが録音は明らかにヴァイオリンが主役としてクローズアップして、ピアノは背景に遠目にとらえます。思わず「ピアノの音も素敵なのにもったいない…」とつぶやいてしまいました。そういう録音の作為が聞こえてしまいます。 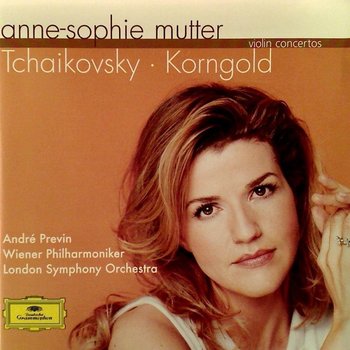 これも聴いてみましょう…と、最後に1)と3)の共通音源でのガチ勝負。 まず3)で聴くと、つい先日、我が家で味わったウィーン・フィルの圧倒的なステージ感と、繊細極まりないムターの美音と豊穣な技巧が目の前に拡がります。 1)にすると、やはり3)に比べるとステージが小さめになります。そのことは我が家の体験でも同じ。ところが気になったのは、3)ではムターのヴァイオリンの線がややぼやっと膨らんでいたこと。1)では、筋が通り音の芯が出ています。そこがまるで別のマスタリングじゃないかと思えるほど。確認すると同じディスクからのリッピングとのこと。 Harubaruさんは、Asoyaji DACにもバベルを当てないと、比較としては公平じゃないのかもしれないと笑っています。どうやら心中には、すでに2台目の塔を思い描いておられるようです。
これも聴いてみましょう…と、最後に1)と3)の共通音源でのガチ勝負。 まず3)で聴くと、つい先日、我が家で味わったウィーン・フィルの圧倒的なステージ感と、繊細極まりないムターの美音と豊穣な技巧が目の前に拡がります。 1)にすると、やはり3)に比べるとステージが小さめになります。そのことは我が家の体験でも同じ。ところが気になったのは、3)ではムターのヴァイオリンの線がややぼやっと膨らんでいたこと。1)では、筋が通り音の芯が出ています。そこがまるで別のマスタリングじゃないかと思えるほど。確認すると同じディスクからのリッピングとのこと。 Harubaruさんは、Asoyaji DACにもバベルを当てないと、比較としては公平じゃないのかもしれないと笑っています。どうやら心中には、すでに2台目の塔を思い描いておられるようです。第一次大戦と音楽 (佐藤俊介 小菅優 デュオ・リサイタル) [コンサート]
佐藤俊介と小菅優のデュオ。

大ファンである二人のデュオということで、どうしても聴きたいリサイタル公演でした。
もともとはベートーヴェンイヤーにナチュラルホルンのトゥーニス・ファン・デァ・ズヴァールトとのトリオを予定していたものが、コロナ禍の入国規制で中止に追い込まれてしまったことのリベンジなんだそうです。
おそらく水戸での新ダヴィッド同盟の流れで、二人のスケジュールをうまく合わせることができたのでしょう。このデュオは、7月6日に東京・銀座ヤマハホールでも予定されています。

東京在住なのに、あえてこのホールまで足を運んだのは、先日のプラジャーク・クァルテットとのセット券だからでした。このひまわりの郷は、駅ビルの最上階にある区の文化施設で、その音楽ホール。380席ほどの小さめのホールで室内楽向きのとてもよい雰囲気の音楽専用ホールです。
音楽専用ホールといっても客席の一部やステージ後部が可動式になっていて、オーケストラピットも可能で演劇や講演会など多目的ホールとしても使用可能。

そういうことで予算制約もあったのか、けっこう安普請。ホール壁面は、下半分こそ木張りになっていますが、上半分の灰色の部分はよく見てみたら何と鋼矢板。矢板というのは港湾・河川の土木工事に使う杭打ち型の土留め板のこと。拳で叩くとやはり鉄板の響きがします。バルコニー席の手すりも一般的なステンレスパイプ。
それなのに音響は、意外なほどバランスがよい。ライブなアコースティックですが、空間容量が小さめでステージが近く壁面一次反射が短いので、演奏者の直接音がしっかりと聞こえホールの間接音とのバランスがとてもよいのです。けっこう気に入っています。
プログラムは、いかにも佐藤さんらしい時代観を基軸においたもので、「第一次大戦と音楽」というメッセージ性が高い構成。
確かに、第一次大戦は、ヨーロッパの音楽家に大きな心理的な影響を与えましたし、対戦前のモダニズムに大きな変質的作用ともたらしたのだと感じました。後に前衛とナチズム、双方からの批判にさらされたヒンデミットが従軍中に作曲されたソナタは、のっけから緊張と厳粛な慨嘆に満ちています。
この日は、ちょっとした演出が。
古い録音を会場に流して、それを引き継ぐという形で演奏を始めます。イザイの「子どもの夢」を取り上げたのは、おそらく、このイザイ自身による録音が1913年という対戦直前のものだったからでしょう。
この趣向は、後半のクライスラーでも繰り返されます。アメリカに移住したクライスラーも大戦に従軍し母国オーストリーと戦うことになります。戦後、ヨーロッパ楽壇に復帰しますが、ユダヤ系ゆえにナチス台頭でドイツを去ることになるなど戦争に翻弄された音楽家でもあります。そのことはコルンゴルトも同じ。
それにしても、SP時代の録音とぴたりとピッチを合わせて引き継ぐところは見事でした。ピッチを自在に調整できるデジタル再生ならではの演出なのでしょう。
同じように第一次大戦の時代に生きた作曲家といっても、その技法や様式は様々。ロマン派の終末、モダニズムの台頭、古典への回帰…と、様々な芸術志向が交錯した時代。そういう多様な音楽を躊躇なく取り上げて弾き分ける佐藤の力量はさすが。それ以上に、どんな難曲であれ、技巧様式の転換であれぱきぱきと弾きこなす木島にもいつもながら感嘆してしまいます。本当にこのピアニストはアンサンブルの名手です。
前半はいささか戦争を間近に感じさせる哀切と緊張のプログラムでしたが、その最後、プログラムの中核となったドビュッシーが、そういう二人の名演でした。病気が進行し困窮していたドビュッシーにとって、その晩年は大戦による物資不足が追い打ちをかけ暖炉の燃料にも事欠く絶望的な冬を過ごしたとか。そのドビュッシーの白鳥の歌。
佐藤のヴァイオリンから、これほど艶やかであでやかな音色が聴けることは意外でさえあったのですが、小菅の見事なタッチと雄弁なまでのアーティキュレーションも相まって、フランス没落の哀感と切実なまでの亡滅の美意識にさいなまれるドビュッシーの傑作に感動しました。レコードやCDも含めて、いままで聴いたドビュッシーのソナタのなかでも白眉でした。

ひまわりの郷コンサート・シリーズ
佐藤俊介 小菅優 デュオ・リサイタル
第一次大戦と音楽 ~作曲家に想いを馳せて~
2022年7月3日(日)14:00
(2階L列-24)
佐藤俊介 Vn
小菅優 Pf
ヒンデミット:ヴァイオリン・ソナタ 変ホ長調 作品11-1
イザイ:子どもの夢 作品14
ラヴェル:クープランの墓~フーガ/フォルラーヌ (ピアノ・ソロ)
ドビュッシー:ヴァイオリン・ソナタ
コルンゴルト:空騒ぎ 作品11 ~ドグベリーとヴァージェス(夜警の行進)
グラナドス(クライスラー編):スペイン舞曲集 作品37 ~アンダルーサ(祈り)
エルガー:ヴァイオリン・ソナタ ホ短調 作品82
(アンコール)
ファリャ:7つのスペイン民謡より
ホタ
ナナ(子守唄)

大ファンである二人のデュオということで、どうしても聴きたいリサイタル公演でした。
もともとはベートーヴェンイヤーにナチュラルホルンのトゥーニス・ファン・デァ・ズヴァールトとのトリオを予定していたものが、コロナ禍の入国規制で中止に追い込まれてしまったことのリベンジなんだそうです。
おそらく水戸での新ダヴィッド同盟の流れで、二人のスケジュールをうまく合わせることができたのでしょう。このデュオは、7月6日に東京・銀座ヤマハホールでも予定されています。
東京在住なのに、あえてこのホールまで足を運んだのは、先日のプラジャーク・クァルテットとのセット券だからでした。このひまわりの郷は、駅ビルの最上階にある区の文化施設で、その音楽ホール。380席ほどの小さめのホールで室内楽向きのとてもよい雰囲気の音楽専用ホールです。
音楽専用ホールといっても客席の一部やステージ後部が可動式になっていて、オーケストラピットも可能で演劇や講演会など多目的ホールとしても使用可能。

そういうことで予算制約もあったのか、けっこう安普請。ホール壁面は、下半分こそ木張りになっていますが、上半分の灰色の部分はよく見てみたら何と鋼矢板。矢板というのは港湾・河川の土木工事に使う杭打ち型の土留め板のこと。拳で叩くとやはり鉄板の響きがします。バルコニー席の手すりも一般的なステンレスパイプ。
それなのに音響は、意外なほどバランスがよい。ライブなアコースティックですが、空間容量が小さめでステージが近く壁面一次反射が短いので、演奏者の直接音がしっかりと聞こえホールの間接音とのバランスがとてもよいのです。けっこう気に入っています。
プログラムは、いかにも佐藤さんらしい時代観を基軸においたもので、「第一次大戦と音楽」というメッセージ性が高い構成。
確かに、第一次大戦は、ヨーロッパの音楽家に大きな心理的な影響を与えましたし、対戦前のモダニズムに大きな変質的作用ともたらしたのだと感じました。後に前衛とナチズム、双方からの批判にさらされたヒンデミットが従軍中に作曲されたソナタは、のっけから緊張と厳粛な慨嘆に満ちています。
この日は、ちょっとした演出が。
古い録音を会場に流して、それを引き継ぐという形で演奏を始めます。イザイの「子どもの夢」を取り上げたのは、おそらく、このイザイ自身による録音が1913年という対戦直前のものだったからでしょう。
この趣向は、後半のクライスラーでも繰り返されます。アメリカに移住したクライスラーも大戦に従軍し母国オーストリーと戦うことになります。戦後、ヨーロッパ楽壇に復帰しますが、ユダヤ系ゆえにナチス台頭でドイツを去ることになるなど戦争に翻弄された音楽家でもあります。そのことはコルンゴルトも同じ。
それにしても、SP時代の録音とぴたりとピッチを合わせて引き継ぐところは見事でした。ピッチを自在に調整できるデジタル再生ならではの演出なのでしょう。
同じように第一次大戦の時代に生きた作曲家といっても、その技法や様式は様々。ロマン派の終末、モダニズムの台頭、古典への回帰…と、様々な芸術志向が交錯した時代。そういう多様な音楽を躊躇なく取り上げて弾き分ける佐藤の力量はさすが。それ以上に、どんな難曲であれ、技巧様式の転換であれぱきぱきと弾きこなす木島にもいつもながら感嘆してしまいます。本当にこのピアニストはアンサンブルの名手です。
前半はいささか戦争を間近に感じさせる哀切と緊張のプログラムでしたが、その最後、プログラムの中核となったドビュッシーが、そういう二人の名演でした。病気が進行し困窮していたドビュッシーにとって、その晩年は大戦による物資不足が追い打ちをかけ暖炉の燃料にも事欠く絶望的な冬を過ごしたとか。そのドビュッシーの白鳥の歌。
佐藤のヴァイオリンから、これほど艶やかであでやかな音色が聴けることは意外でさえあったのですが、小菅の見事なタッチと雄弁なまでのアーティキュレーションも相まって、フランス没落の哀感と切実なまでの亡滅の美意識にさいなまれるドビュッシーの傑作に感動しました。レコードやCDも含めて、いままで聴いたドビュッシーのソナタのなかでも白眉でした。
ひまわりの郷コンサート・シリーズ
佐藤俊介 小菅優 デュオ・リサイタル
第一次大戦と音楽 ~作曲家に想いを馳せて~
2022年7月3日(日)14:00
(2階L列-24)
佐藤俊介 Vn
小菅優 Pf
ヒンデミット:ヴァイオリン・ソナタ 変ホ長調 作品11-1
イザイ:子どもの夢 作品14
ラヴェル:クープランの墓~フーガ/フォルラーヌ (ピアノ・ソロ)
ドビュッシー:ヴァイオリン・ソナタ
コルンゴルト:空騒ぎ 作品11 ~ドグベリーとヴァージェス(夜警の行進)
グラナドス(クライスラー編):スペイン舞曲集 作品37 ~アンダルーサ(祈り)
エルガー:ヴァイオリン・ソナタ ホ短調 作品82
(アンコール)
ファリャ:7つのスペイン民謡より
ホタ
ナナ(子守唄)
「渾沌の恋人(ラマン)」(恩田 侑布子 著) [読書]
斬新にして卓抜たる芸術評論・日本文化論。
□
□
著者は俳人。十七音の芸術表現の視点から、北斎、浮世絵、絵巻、茶の湯、能、和歌、万葉と日本の美意識の深遠を逍遙し、果ては詩経をはじめとする中国古代の詩論に踏み入った探索は、その源泉にまでに及ぶ。
筆致は、自由。だから批評とか芸術論というよりもエッセイというべきだろうか。視点は自在で、何にも囚われない。
郷里・静岡の山深い里の古民家をわび住まいとし、都内港区のマンションとを毎週のように行き来して美術館をめぐったという。そういう美意識、自然観は、書斎から発する教養ぶった評論、批評とは次元を劃している。
何より衝撃だったのは、その日本語の美しさ、豊かさ。言葉が本来持っている想起力の強さ、鋭さ。その音韻のしなやかさ、あるいは切れのすがすがしさ。著者が繰り出す語彙の豊穣は驚くばかりで、名人の一手のごとくぱしりと急所に置かれると、思わずはっと息をのむ。そういう文章は、枯れ果てた日本語の倒木から更新する若い枝葉のように清新に感じる。
穏やかなもの言いのようでいて、その舌鋒は鋭く、あっと驚くような厳しい転換がある。
劈頭の「芭蕉の恋」では、句界の大御所や審美家たちの句評「浪漫的な叙情」「艶美な恋句」「朝絵巻のひとこまのように優美」といった美辞麗句を引用して、「こんなそつのない予定調和の恋にトキメクのだろうか」と一刀両断。芭蕉の恋は、実は、女人ではなく衆道の相手である杜国であったと、あっという間もなく鋭く切り返してしまう。その途端に、この書のとんでもない重たさに気づいて凜然とする。
こういう鋭く容赦のない切り込みは、後からあとへと続く。金子兜太の「俳句はアニミズム」というキャッチをこきおろすにも何の躊躇もない。なぜ、いまごろ19世紀末の西洋的進歩史観で見下したアニミズム=未開宗教という決めつけを援用するのか、というわけだ。そういうことは、今や急速に失われようとしている日本古来の美しい自然と生活意識、そこで育まれてきた美意識…への痛切な愛惜なのだろう。
出色の「日本美」論であり、声に出して朗読したいという衝動にかられる卓筆でもある。
□
□

□
渾沌の恋人(ラマン): 北斎の波、芭蕉の興
恩田 侑布子 (著)
春秋社
□
□
著者は俳人。十七音の芸術表現の視点から、北斎、浮世絵、絵巻、茶の湯、能、和歌、万葉と日本の美意識の深遠を逍遙し、果ては詩経をはじめとする中国古代の詩論に踏み入った探索は、その源泉にまでに及ぶ。
筆致は、自由。だから批評とか芸術論というよりもエッセイというべきだろうか。視点は自在で、何にも囚われない。
郷里・静岡の山深い里の古民家をわび住まいとし、都内港区のマンションとを毎週のように行き来して美術館をめぐったという。そういう美意識、自然観は、書斎から発する教養ぶった評論、批評とは次元を劃している。
何より衝撃だったのは、その日本語の美しさ、豊かさ。言葉が本来持っている想起力の強さ、鋭さ。その音韻のしなやかさ、あるいは切れのすがすがしさ。著者が繰り出す語彙の豊穣は驚くばかりで、名人の一手のごとくぱしりと急所に置かれると、思わずはっと息をのむ。そういう文章は、枯れ果てた日本語の倒木から更新する若い枝葉のように清新に感じる。
穏やかなもの言いのようでいて、その舌鋒は鋭く、あっと驚くような厳しい転換がある。
劈頭の「芭蕉の恋」では、句界の大御所や審美家たちの句評「浪漫的な叙情」「艶美な恋句」「朝絵巻のひとこまのように優美」といった美辞麗句を引用して、「こんなそつのない予定調和の恋にトキメクのだろうか」と一刀両断。芭蕉の恋は、実は、女人ではなく衆道の相手である杜国であったと、あっという間もなく鋭く切り返してしまう。その途端に、この書のとんでもない重たさに気づいて凜然とする。
こういう鋭く容赦のない切り込みは、後からあとへと続く。金子兜太の「俳句はアニミズム」というキャッチをこきおろすにも何の躊躇もない。なぜ、いまごろ19世紀末の西洋的進歩史観で見下したアニミズム=未開宗教という決めつけを援用するのか、というわけだ。そういうことは、今や急速に失われようとしている日本古来の美しい自然と生活意識、そこで育まれてきた美意識…への痛切な愛惜なのだろう。
出色の「日本美」論であり、声に出して朗読したいという衝動にかられる卓筆でもある。
□
□

□
渾沌の恋人(ラマン): 北斎の波、芭蕉の興
恩田 侑布子 (著)
春秋社



